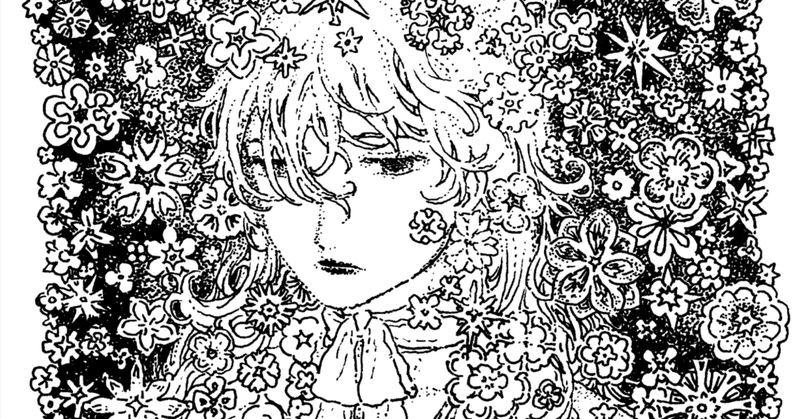
『樹洞より』4・べにの間
春の胸
春の始まりの暖かさは、きっと世界のどこであっても、胸に心地良いものなのでしょう。
遠ヶ崎の街で迎える春は、山深い巻砂のものと比べれば、幾分か知ることの難しいものです。目白の集う桜の木も、花の房をたわわに下げた小米柳も、巻砂ではありふれていたものでした。しかしこの街では、よそのお店の庭を覗いて、やっと見ることのできるものたちです。
それでも、道行く人々の表情が和らいでいること、お日様が早く顔を出し遅くに去っていくことに、私は心を暖かくせずにはいられないのです。
(今日ハ ポカポカビヨリー)
通りを行く私のそばで、おかしな声が話します。
(ポカポカビヨリニ)
(ミンナデ楽シク)
(オ買イ物ダヨー)
私のそばには、顔のついた雲の欠片――ひと月前、白い海の幻を見た日から現れた、謎のあやかしのようなもの――が、三つも浮かんでいます。
「もー、楽しいお買い物じゃないですよ。着物を繕う糸を買うのに、お小遣いを削っちゃったんですから」
私があやかしたちに話しかけると、すれ違う人々がこちらを見て訝しみます。このあやかしを見聞きするのが、どうやら自分だけであるらしいことを、私は時折忘れてしまうのでした。
あやかしたちを見聞きしないのは、「すえひろ」の皆も同じでした。私が独りでままごとをしているようで、きっと頭が足りていないのだと、荻ちゃんと清ちゃんが旦那様に告げ口していました。永さんは私を見て、時々怖がるような顔をするようになりました。
そんな皆を見れば、以前の私なら気に病んでいたでしょうが、今は気になりません。皆は昔よりよそよそしくて、なんだか遠い他人のようですし、ふとした時にこのあやかしたちが現れて、おかしな掛け合いを聞かせてくれます。
何より、この不思議なあやかしたちによって、私の生きてゆく世間は「すえひろ」の外にも広がっているのではないか――そう思わせられたのです。
(アッ 虫サンダ!)
「虫さん?」
今度は小声で、あやかしの声に応えます。蝶でも飛んでいるのかと思って通りを見ると、遠くから、こおろぎ売りが歩いて来るのが見えました。
「こおろぎ屋さんだ! いいなあ……」
こおろぎ売りのおじさんが、かごにたくさんの揚げこおろぎを盛って歩いています。
私はこおろぎの香ばしさと歯ざわりを思い出して、ついつい声をかけそうになります。しかし、節約のためには、しょっちゅうおやつを買っているわけにはいきません。
(虫サン オイシイノ?)
(ネーネー 買ワナイノ?)
「きょ、今日はいいです。買いません」
(ナンデ?)
(ナンデ ナンデ?)
「買いませんったら買いません!」
私の声は、思ったより大きくなってしまったようです。通り過ぎようとしたこおろぎ売りのおじさんが、私を見て目を丸くしています。
「お、おう、兄ちゃん。要らんのだったら、無理に買えとは言わんが……」
「わっ、ごめんなさい! ……あの、一つ買ってもいいですか?」
*
こおろぎを齧りつつ「すえひろ」に戻ると、日がだいぶ傾く頃になっていました。
今日は早めに店じまいをして、夕ご飯も済ませてしまったので、日暮れまでそれぞれが好きに過ごしていいことになっています。明日もちょうど休店日なので、いつも厳しい顔をされている旦那さまも、縁側でゆっくりとお煙草を吸われています。お庭では、荻ちゃんと清ちゃんが紙風船を叩き、遊んでいます。永さんは、いつもよりおめかしをして、ご機嫌な様子で出かけていきました。あの「イッちゃん」というお友達に会いに行くのでしょうか。
私は縁側で皆に挨拶した後、丁稚の寝室に戻りました。
丁稚の身で、一人で寝室にいられる時間は、とても貴重なものです。私は自分の行李の蓋を開けると、お財布と今日買った木綿糸をしまいました。針仕事をするには、今日はもう暗くなりすぎています。
行李の中には、お財布と針子道具、少しの筆記具の他に、着物や下着を畳んで入れてあります。私は行李の底を探って、一枚の桧扇貝を取り出しました。
台所から拝借したその貝は、気を持ち直した今でも、私の心の慰めとなっていました。
はじめはあやかしに言われるがまま、台所のものを勝手に取ってしまって、悪いことをしてしまったような心地でいました。しかし、元々使われずに煤をかぶっていた道具でしたから、「すえひろ」の誰にも気がつかれる事は無いようでした。それに、もしこの行李に持っているのを荻ちゃん達に見つかっても、巻砂から持ってきたものだと言えば、話が通りそうなのでした。
(キレイナ 貝殻ダー)
いつの間にかあやかしたちが現れて、私の周りをくるくると回っていました。ひと掴みほどの雲の欠片の中に、人の目や口のような穴が開いています。表情はうっすら微笑んでいるようにも見えますが、あまり変化はなく、読み取ることはできません。
(オメメサン コレ オ気ニ入リ?)
「……はい。これは、私のお気に入りですよ」
お目々さんというのは、私のことでした。あやかしたちは、人のことをあだ名で呼ぶようなのです。私の目はこの貝と同じ、琥珀のような黄色をしていて、それがどういうわけだか、このあやかしの気に入るところなのでした。
(オ気ニ入リハ 秘密ダネー)
(ガミガミサンニハ 秘密ダヨー)
(グウタラサンニモ 秘密ダゾー)
あやかしたちの歌に、思わず笑ってしまいます。
がみがみさんというのは旦那さまのことで、ぐうたらさんというのは永さんのことです。こんなふうにあだ名をつけるあやかしたちのおかげで、私は昔のように思い詰めることなく、この店で過ごすことができるのでした。
「あやかしのみんな、ありがとう。みんなが面白い話をしてくれるおかげで、私は元気になれたんですよ」
(エヘヘ 良カッタナー)
(アヤカシノ オカゲダッテ!)
(アヤカシ?)
(アヤカシッテ ナンダロー)
(ナンダロ ナンダロー)
あやかしたちが輪になって、何かを話し合うように集まります。彼らは、あやかしという言葉を知らないのでしょうか?
「みんな、何かのお化けなんでしょう? 人間はみんなのようなものを、あやかしと呼ぶんですよ」
(オバケ?)
(オバケカナ)
(ウーン ナンカ違ウネ?)
(ソレジャ アヤカシカナ?)
(アヤカシジャ ナクテ)
(エット エット)
(ナンダッケ?)
あやかしたちがゆらりと動き、心なしか首をかしげるような仕草を見せます。
彼らは結局、何なのでしょう。まさか、子供の亡霊であるとでも言うのでしょうか?
「あやかしでないなら、みんなは一体……」
(ア! ワルイチガ 来タゾー!)
(ワルニモ 来タゾー!)
あやかしたちが騒ぎ、湯気のように消えていきます。ワルイチとワルニというのは、それぞれ荻ちゃんと清ちゃんのことです。意地悪な人の一番目と二番目、という意味で、あやかしたちが呼んでいるのでした。
私はまた笑い出しそうになるのをこらえながら、貝を行李にしまいます。やがて、ワルイチとワルニの歩く音が、廊下から聞こえてくるのでした。
庭の友
休店日の朝、私は着物の修繕を終えると、縁側へ出ていきました。今日「すえひろ」にいるのは丁稚だけです。旦那様は観劇に行かれ、永さんは外泊をされたのか、まだ戻らないようでした。
荻ちゃんと清ちゃんは仲良し同士ですが、私とは仲が良くありません。丁稚の寝室で、二人が面子の紙を見せ合っておしゃべりを始めた時、私はこの休日を縁側で過ごすことに決めました。
妖怪の姿が描かれた、派手な色の紙面子は、二人が揃いの柄で買って自慢にしているものでした。けれどあの二人は、私が本物の妖怪と友人になっているなんて、きっと知りもしないのでしょう。
(オメメサン 笑ッテルー)
縁側に座る私のそばに、雲の欠片が現れます。
「え、そうですか? 笑ってたかなあ」
(笑ッテタヨ! 楽シソウー)
あやかしも笑っているのでしょうか、雲の端を手足のように伸ばし、ふるふると動かします。彼らに表情は無いのだと思っていましたが、よく見ると、体の形をいつも細かに変化させています。それが、彼らの顔色とでも呼ぶべきものなのでしょう。
「あやかしさんも今、笑ってたんですね」
(アヤカシ?)
雲の動きが一瞬止まりかけた後、再び白い体をもくもくと動かします。
(アヤカシ ダッケ?)
「あれ、また同じ話になってしまいましたね」
(ウーン)
「あやかしさんは、結局、何のお化けなんですか? まさか、幽霊じゃありませんよね?」
再び雲の動きが固まり、動きが鈍くなります。これは、何か考え込んでいる仕草なのかもしれません。
(エットネ エットネ)
「うんうん」
(ユーレイ カモ?)
「えっ!」
背筋がぞくりとして、思わず後ろにのけぞります。まさか目の前のものが、成仏できない死人の魂であるなんて――彼らはこう見えて、実は恐ろしい怨念を抱え込んでいるのでしょうか?
「ゆ、ゆ、幽霊だったんですね! あの、何かしたほうがいいですか? お参りとか、お供え物とか……」
(ワーイ! ナンカ クレルノ?)
「はいっ! お酒でもお花でも、なんでも……というわけにはいきませんけど、それで安らかになれるなら、用意します」
(ソレジャ オ水ガ欲シイ!)
「お水?」
(ノド 渇イタヨー)
「はい、お安い御用ですよ!」
私は台所へ走り、杯に水を注ぎます。幽霊と聞いて、つい怨霊のようなものを想像してしまいましたが、お水が欲しいだなんて、なんだか哀しいものを感じさせる幽霊です。この雲のようなものは、大昔の日照りの時に死んだ、子供の霊か何かかもしれません。
「幽霊さん、お水ですよ。はい、どうぞ!」
私は宙に浮く雲に向かって、杯を差し出します。もくもくとした雲の動きは、またさっきのように緩んで、しばし何か考えている様子を見せます。
(オ水 ココジャ 飲メナイナー)
「……あ、それもそうですね!」
私は自分のことを省みて、おかしくなってしまいました。幽霊にお供え物を直接手渡しするなんて、普通ならあり得ないことです。
「どこか、お供えする場所があるんですね? お墓とか、祠とか……」
(ウン! アノネ オ庭ニアルヨ)
「お庭ですって! うちの?」
(ソーダヨー)
私は杯を持ち、庭へ向かいます。また背筋が寒くなってきて、うちの庭に死体が埋められているのではないだろうかと、そんな恐ろしさが心を占めてきます。
(ココダヨ ココダヨ)
私を導くように飛んでいた幽霊が、一つの鉢の前で止まります。それは、去年に旦那さまがご近所さんから貰ってきた、紫陽花の鉢植えでした。
「こ、この紫陽花の下に……」
(ウン! オ水 欲シイナー)
幽霊に言われるがまま、水の入った杯を鉢のわきに添えます。幽霊は杯をじっと眺めると、私のもとへ飛んできて、大きく体を横に振ります。
(ココジャナクテ 鉢ノ中ニカケテ)
「……鉢の中に、お水をかけるんですか?」
(ウン! オ水カケテー)
「分かりました、こぼしますよ」
杯を傾け、植木鉢に水をこぼすと、幽霊は子供の笑い声のような音を立てて、体を震わせます。
この幽霊は、よほどこの紫陽花に思い入れがあるのでしょうか。これではまるで、日照りで死んだ子供の魂というよりも、水を欲する植木の心――この紫陽花の、木霊が現れたかのようです。
「……木霊?」
私の声に、雲のかけらが躍ります。
その言葉を口にするのは、巻砂を離れてから初めてのことでした。
つつじ
(オメメサンー)
(ドコ行クノー)
私は「すえひろ」を出て、通りを走っていました。
私のそばには、二つの木霊――あやかしでも、幽霊でもない彼らが、雲の体を翻しながら飛んでいます。
「街を抜けて、あの小山へ行くんです!」
私は通りのずっと先にある、小さな山を指します。
揃い始めの新緑が美しいその小山は、少し暇をもらえば行けるほどの近さでしたが、時々「すえひろ」の店先から眺めるだけで、なんとなく立ち入れずにいた場所でした。
(ドシテ ドシテ?)
「今は、そういう気分なんですよ!」
こんなに楽しく走っているのは、いつぶりでしょうか。息が切れ、お腹が痛くなっても、己の前に広がっているものを思うと、嬉しくて仕方がないのです。
(ドウイウ 気分?)
(ニコニコノ 気分!)
(ナンデ ナンデ?)
(オメメサン 木霊ノコト 好キナンダッテー!)
(キャー 好キダッテー!)
二つの木霊が、ぽこぽこと煙のような軌跡を残しながら、私についてきます。
彼らの見た目はそっくりですが、大きさにわずかな違いがあり、小さいほうは庭の紫陽花の木霊のようでした。大きい方の木霊は、通りへと出る途中に現れたもので、街道に並んで植えられている枝垂れ柳のうちの、一つかもしれません。
(オメメサン 今日ハ 元気イッパイ!)
紫陽花の木霊が、体を膨らませながら言いました。彼らのことがわかるようになったひと月前から、私の心は軽やかなものに変わっていましたが、彼らが木霊であると知った今、この胸は思わぬ熱で満たされているのでした。
「木霊の皆さん、私に声を聞かせてくれて、姿を見せてくれて、ありがとう!」
私が木霊に話しかける度に、街の人々がこちらを訝しみます。いつもなら気にしていたことですが、今ばかりは、自分の喜びの声がかき消してしまいます。
「神さま、真さま……この幸いを、感謝いたします!」
店の建ち並ぶ通りを抜けて、小山に登る道に入ります。
初めて足を踏み入れてみれば、木の根とそれを踏む人が作り上げた、かすかな土の階段がありました。そしてその階段を上りながら、私が今までこの小山に惹かれていたこと、そして、自ら近寄り難くしていたことに気づきます。
階段を上り終えて見下ろす景色は、巻砂を発った日に見たあの風景――木守さまの庵へ行く道の眺め、薮椿に飾られた島の景色に、よく似たものだったのです。
目下にある港町は、巻砂とは比べ物にならないほど大きくて、弁財船も三つ四つと止まっています。巻砂のいたるところに生えていた薮椿は見えませんが、その赤色の代わりにつつじの紅色が咲き誇り、海の青色と互いに光りあっています。
そんな違いがあってもなお、私はその眺めに、故郷の懐かしい風景を思わずにはいられませんでした。
「……母様、待っていて下さい。私の身があなたの木守となることを、神々はお許し下さいました。巻砂に戻れば、この目であなたのお姿を、きっと見ることができるでしょう」
手を合わせ、海の向こうへと祈っていると、顔の周りにやわらかな息遣いを感じます。私の周りには、この小山じゅうの木霊達がたゆたい、白い風の体をそよがせながら、肌に触れてくれているのでした。
(オメメサン 木守サンニ ナルノ?)
「はい。今はこの街で、奉公をしているけれど……故郷に戻ったら、木守になりたいんです」
(ワー!)
(ソシタラ ソシタラ)
(オメメサント チュー デキルネ!)
(キャー!)
木霊達が跳ね回り、高い音を出しながらはしゃいでいます。「ちゅー」できると聞こえましたが、「ちゅー」とは何のことなのでしょう。
ぼんやりと考えていたその時、木霊達の賑わいに、低い声が混じりました。
「……ったく、騒がしいなあ」
それは、疲れた大人のように気だるげな、それでいて子供っぽさを残したような、人の声でした。
声のした方を見ると、お兄さんが一人、つつじの茂みの向こうからやって来るところでした。歩きながら、長い髪を後ろでまとめようとしていて、こちらには気づいていないようです。
「ご、ごめんなさい! 大勢で騒いじゃって、うるさかったですよね……」
私が頭を下げると、お兄さんはぎょっとした様子でこちらを見て、やがて顔をそむけます。
「……すまんな、独り言だ。気にせんでくれ」
お兄さんは、再び髪を結う仕草に戻り、小山の道を下って行きます。首元には流行りの白い帯飾りが巻かれていて、薄い生地がはためきながら、木漏れ日の形に光っています。
都会の流行り物を身につけるような人が、こんな静かな山に入ることもあるのだと、私は意外なことに思って、そして妙に腑に落ちた心地でいました。
この遠ヶ崎は、母なる木によって出来上がった街ではありません。ここに生きる人々は、地の利を求めて周辺の郷里からやってきた、移住者の人ばかりです。このお兄さんも私のように、どこかの郷の山を恋しく思って、足を運んでしまったのかもしれませんでした。
「……ん?」
道の先で、お兄さんが声を上げて立ち止まります。
木霊達もお兄さんを気にしているようで、ふわふわと道の先へ漂っていきます。私は、木霊達がまた騒ぎ出して、怒られてしまうのではないかと心配になりました。
そして、その心配が、奇妙なものであることに気づきました。
「おい、お前さん、まさか……」
お兄さんがこちらへ振り返り、呼びかけます。すると、木霊の一つがお兄さんの方へ飛んで行き、語りかけます。
(ウイチャン 一緒ニ 遊ボウヨー)
「ウイちゃん?」
私が木霊に尋ねた言葉は、目の前の人を呼ぶものでした。
つつじ達の茂みの合間で、一人の少年が振り返り、こちらを見つめます。
その唇がつつじと同じ紅色に彩られていること、弱く小さく震えていることに、私はほんの一瞬だけ、地に落ちる前の花を思ったのです。
