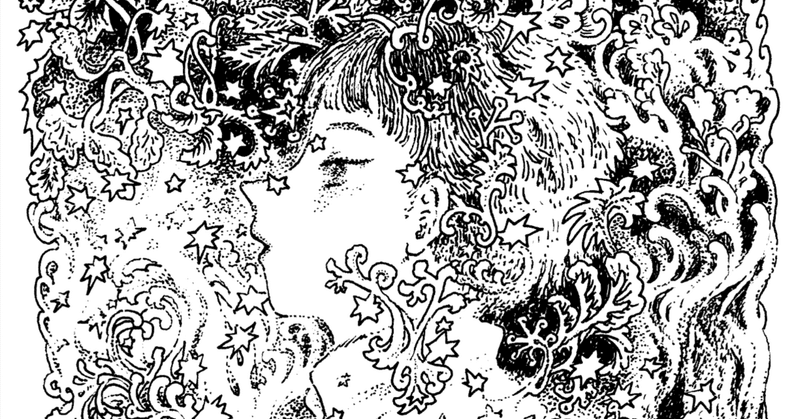
『樹洞より』 1・船の足跡
澪
澪は生まれ育った島を出る。洋品売りの商家のもとへ、丁稚奉公へ行くのだ。
巻砂という名の島の南西部、険しい山岳と磯からの風が通う盆地に、澪の住む集落はあった。斜面や崖の多い土地の、最も平坦な部分には田が造られ、荒れた土に初春の小さな芽吹きを許している。それ以外の細かな土地には、蕪や菜種、籾殻を被った甘薯の畑がひしめき、ところどころに藁葺きの小屋が点在している。
それらの田園の中に、瓦屋根の平屋の集まる一角があった。この島に生まれた子供達が暮らす、唯一の学び舎である。
学舎では、まだ日も昇りきらない頃から、慌ただしい足音が響いていた。土壁の塀の内側、六棟並んだ平屋の一棟で、人々が縁側や廊下を行き来していた。
その日は、澪たち八人の子供の門出であった。
ある者は紙問屋へ、またある者は左官の組へ行く。その各々が今、水筒に水を詰めたり、着物の綻びを繕ったり、年長者達に御守りを持たせられたりしながら、船出に遅れるまいと支度をしていた。
澪は、他の子供達の誰よりも早起きをして、荷造りをとうに済ませていた。彼は風呂敷の大荷物を背負ったままで、休まず学舎の中を巡る。小走りに合わせて、かむろに揃えたばかりの栗色の髪が、幼さの残る丸い額をぱらぱらと跳ねている。
「マツ爺、お体に気をつけて。いずれ一人前になって戻ってきますから、どうかお元気でいらしてくださいね!」
澪が縁側に座る老人の手を取り、耳元で声をかける。老人は垂れた瞼の下を潤せながら、達者でな、と呟き、丸い背中ごと何度も頷く。
澪は、学舎で世話になった年長者たちや、共に育った兄弟たちに、挨拶をして回っていた。
「タキ先生、長い間お世話になりました。紅字の書き取り、向こうでも頑張ります! あっ、あとそろばんも!」
「アツ兄ちゃん、コト兄ちゃん、いつも雉や蛇を捕ってきてくれてありがとう。また一緒に食べようね!」
あちらへ駆け、こちらへ駆け、澪は島の馴染み達に別れの挨拶をする。彼に声をかけられた者は皆、少し寂しそうに笑って、門出の言葉を贈る。
「澪や、お前は利口だから、向こうでも可愛がってもらえるよ。暮らしに慣れてきたら、便りを頂戴な」
「はあ、澪はマジメすぎて心配だよ。あのな、主人に菓子をせびれるくらい図太い方がいいんだぜ」
「澪、向こうにはぼうろとか、かすていらってのがあるんだろ? 土産には甘ーいやつを頼む!」
教師や兄貴分の少年達に肩を叩かれ、澪も笑みを返す。背の高く生まれついた彼は、年長者達に頭を撫でられることこそなかったけれども、十二の歳にして純真すぎる気質は、人々に愛でられているのであった。
そうして人々は、その無垢な子供の歩もうとしている人生に、多かれ少なかれ危うさを覚えていた。
「ミケ、待ってー」
澪は喧噪を離れ、塀の上を渡る三毛猫を立ち止まらせて、語りかける。
「こないだみたいに、蒲鉾を泥棒しちゃダメだからね。私のいない間も、いい子にしてるんだよ」
澪が撫でようと手を伸ばしたところで、猫は野良の心のままに体をすぼめ、走り去っていった。澪は伸ばした手を宙に惑わせ、追いかけようとして、やめる。
そこで彼は初めて、琥珀色の瞳に寂しさを映した。
つい先ほどまで満ちていた溌剌さが、ぷつりと途切れたようだった。兄達の賑わう声は遠くなり、晴天に昇り始めた朝日は、くすんだ仄かなものへと変わる。世間のかがやくものたちすべてが、水底から見聞きするかのように翳っていく。
澪の周りに、帳が降りていた。
――ここはどこだろう。私は、どこから来たのだろう。
澪は己に問いかける。彼が唐突にこの気分に襲われるのは、初めてのことではなかった。
――思い出せ、思い出せ……。
澪はふらつく頭の中で、覚えている限りの古い記憶に思念を巡らせた。
――自分の体温と同じなにか、肌を伝うもの……白い水。
それらは、いつもならほんの一瞬で消えてしまうはずの、胸の内をくすぐる既視感たちであった。それが今、澪の思考の中で、永劫のように引き延ばされている。
――私は、私は暗がりから、温もりからやってきた。
――暖かくて暗い、母様の胎の中から、木守さまに取り上げられて、この世に生まれた。
――そうやって今、ここにいるんだ!
そこで、帳は払われた。
澪の周りには、いつもより少しばかり騒がしい、朝の学舎の風景があった。「……あっ、いけない! 木守さまに会いに行くんだった!」
澪ははっとして背筋を伸ばし、風呂敷を背負い直した。今朝拭き上げたばかりの布靴を砂色に汚しながら、学舎の門を目指して走っていく。
「おうい、澪。船出はまだだよ、どこに行くんだい」
澪に話しかけたのは、庭木の陰で話し込む老人達だった。
「はい、ちょっと庵へ! 木守さまにお会いしたいんです」
澪は立ち止まり、老人達に小さく頭を下げた。木守さま、と聞いた老人達は、少しだけ声をひそめて話し合う。
「梗か。子供たちの見送りには来ないようだね」
「あの人、賑わいを好かないもんだから……」
澪が木守さまと呼ぶ、梗という者の陰口を老人達が始めようとしたとき、澪は足早に門の外に出たところだった。慌てて老人の一人が声をかける。
「これ、澪! その大荷物で庵まで行くのかい?」
「はい、頑張ってしょっていきます!」
「何言ってんだい、船出の前にここへ戻るだろう。一旦置いておきなさい、旅の前から疲れちゃ損だよ」
「あっ、そうですね! すみません、気が急いちゃって」
澪は照れ笑いをして、慌てて荷物を縁側に下ろす。身軽になった体で門の前に立つと、再び老人達に一礼した。
「では、行って参ります!」
「おう、船には遅れるなよう」
段々畑のあぜ道を駆け、はあい、と遠く返事をする澪を見送りながら、老人達は談義に戻る。
「ちいと心配だねえ、あの子は」
「ああ。あの齢にして利発だが、些か心の清すぎる。人となりは違えど、性は梗とおんなじよ」
「いずれ、木守を継ぐやもしれん……遠ヶ崎の地でも、気丈にやってくれるといいが」
小椎の声
澪が梗と初めて話したのは、六歳の頃だ。
夏の終わり、襟元の汗を冷やす風の吹き始めた季節であった。子供達は学舎の庭先で、幼子の有り余る力のまま駆けたり、跳ねたりしていた。
澪はあまり暴れるような遊びは好まなかったけれど、木登りは面白く思っていた。はじめは兄達に混じって、物見櫓のままごとで登っていた。おっかなびっくり辿り着いた樹上の眺めが、狭い集落の景色を面白く見せてくれたことで、澪は木登りの楽しみを知った。
やがて、体格の良く育った澪は、長い手足でうまく木の股を踏み、こぶを掴みして、歳上の兄達にも負けずに樹上へ登るようになった。時には、大人達が柿や枇杷を採るのに加勢することもあった。
そうするうち、澪は樹木のひとつひとつに愛着をもった。木々のかたち、樹皮や葉の違っていることは、それぞれの顔立ちや目髪をもつ人間のようで、面白さと親しみが感じられた。松のうねりは肩をいからせた武人に似て、百日紅の肌は白粉を塗った旅芸人を思わせた。
その晩夏の日、澪は兄弟達の鬼ごっこから抜け、独りで木登りをしに行った。登るのは学舎の炊事場の裏、一本の古い小椎だ。
澪はその木に登るのが初めてだった。炊事場の小屋の裏手には井戸があって、近くには水路も造ってあり、刈れども刈れどもどくだみに覆われる場所だった。日陰と水気を求めて蛇が来るという噂もあって、澪はあまり近寄りたがらなかった。
それでも彼がその老木のもとへ行ったのは、兄弟達に臆病さをからかわれて、へそを曲げたためだった。そして登ろうと思ったのは、小屋と塀の陰を被ったその姿に、思わず哀愁を見たためであった。
――この木のような人を、見たことがある。
小椎に登りながら、澪は考える。太い枝のひとつを選んで座ると、猿の腰掛けの固い感触が指に触れた。
――タエ爺さまだ。梅雨に亡くなって、お葬式をしたときの、あの固い肌に似てるんだ。
澪は、学舎で馴染んだひとりの保父の、静かな葬儀を思い出した。
まだ齢六つの彼の胸に、深い悲しみは残っていない。思い出すのは非日常の体感だった。棺の中の青ざめた体、花を焦がしたような線香の匂い、島の役員達の聞き慣れぬ挨拶。理法という教えのものだという異国の詩を、独り墓前で唄い続ける大人。
――あの詩を唄っていたのが、みんなの言う「木守さま」だったっけ。
――でも、爺様達には「梗」って名前で呼ばれてる。
――ちょっと、変わった名前だ。紅国や鐵国の昔話に出てきそうな……。
「澪!」
大声に呼ばれて、澪は思考を中断した。
「澪、降りなさい! その枝は、じき折れる――」
張りのある声を響かせて、炊事場の小屋の向こうから駆けてくる大人がいた。古風な長い着物と引詰めの黒髪に、澪は覚えがあった。
木守さまだ、と澪が思ったとき、彼の天地は逆さまになった。不思議に思う間もなく尻から背中が地に打たれ、咳と悲鳴の混じった声が出る。
梗は息をのみ、草むらで呻く澪のもとへ駆け寄って肩を抱いた。大丈夫か、と呼びかける梗の声は、やがて幼い泣き声にかき消された。
澪の座っていた小椎の枝は、根本から折れていた。
澪が木から落ち、大きな声で泣いたことで、学舎はいっとき騒がしくなった。しかし、座っていた枝がそう高くなく、澪に大きな怪我がなかったことが分かると、駆けつけた大人達は笑って彼の背中を撫でた。
「澪や、大ごとにならなくて良かったなあ!」
「まあしかし、こんなにこの木の腐れていたとはね。澪も不運だねえ」
まだ半べその澪の周りで、保父達が小椎の木を見ながら話している。
「澪があんまり木登りばかりするもんだから、きっと木霊も怒ったのさ。そうだろう、梗」
年輩の保父に話を振られた梗は、俯いたままで返事をしない。深い眼窩の双眸、乾いた大地のような色の眼差しは、保父も澪も木も映すことはなく、静かに宙を見据えている。
年輩の保父はしばらく返事を待ったが、やがて短く溜息をついた。
「……ふむ、木守さまは考え事か。さ、みんな戻ろう! 澪ももう弟の多い歳になったんだから、あまりべそをかくんじゃないよ」
澪は嗄れた声で返事をした。去っていく保父達を見送りながら、涙と鼻水に濡れた顔を拭く。
――木守さまは、あの枝が折れることを知っていた。私にそれを知らせて、助けようとしてくれたんだ。
――でも、私がぼんやりしていたせいで、あんなに大きな枝を折ってしまった。椎の木にはひどいことをした。
澪は梗の、未だ動かぬ横顔を覗き見る。木守とは、木の精霊の通詞を務める祈り手なのだと、学舎の教師が言っていたのを思い出す。
――今、木守さまは、木霊とお話しているのだろうか。
そう考えていると、梗が澪に向き直った。
梗の眼窩には影が落ち、その中で砂色の瞳だけが光をはらんでいる。そこに澪の伺い知れる心はない。向き合えど情動を交わせぬ眼差しに、澪は畏怖の念を覚えた。
「あの……木守さま、さっきはありがとうございました。それから、枝を折ってしまってごめんなさい。この木の木霊には、申し訳ないことをしました」
澪はついさっき聞いた、張りあげられた梗の声を思い出して、怒られるのだろうかと肩をすくめた。
しかし、梗から返ってきたのは、存外穏やかな声色だった。
「木霊に呼ばれて駆けつけたが、間に合わず申し訳ない。これからあのような古い木に登る時は、茸のつき方に注意してみなさい。あまり多いと、中が朽ちていることがある」
澪は少し拍子抜けしたけれど、梗の瞳に暖かい色が灯ったような気がして、胸をなで下ろした。
「分かりました、気をつけます。……椎の木霊さん、ごめんなさい」
澪は、枝を一つ失った小椎の老木に手を合わせて、目を瞑った。
どくだみの、青々とした香りの混じる晩夏の風が、澪と梗の首元を撫でている。
「……木守さま。木霊は今、ここにいますか」
「ああ」
梗もまた小椎の方を向き、静かな眼差しで、彼だけの知る世界を見る。
ふいに、青い香りの風が止む。午後の陽の暖かさが、二人の肩に降り注ぐ。
「木霊は、何と言っていますか」
「……私は怒ってなどいない、触れてくれて嬉しかった、と」
澪は、目を瞑ったまま微笑んだ。隣の祈り手も同じ表情であることは、見なくとも分かっていた。
瞼の裏、暖かい色の暗闇の中に、木霊の笑みを見た気がした。
母
門出にさんざめく学舎を離れて、澪はあぜ道を通り抜け、林道へと入った。
彼の生まれであるこの巻砂島は、一晩野営をとれば海岸線を一周できるほどの大きさだが、そこにつくられた集落は、島の小ささ以上にこぢんまりとしている。それは、ところどころ崖を為す険しい山が、海の目の前まで迫るような地形であるためだった。
巻砂の集落は、南端の僅かな平野部を占め、学舎はその北部に位置している。島民達は、島の所属する東海国本土へ船を渡す、古い港の周りに暮らしていた。
彼らは、幾重にも墨を塗り込めたような森の陰を畏れ、本土から南洋風情を想われる海へ向かって、島の繁栄を願っているのだった。
「この景色とも、しばらくお別れ……」
林道に入った澪は、人の歩みと木の根が作り上げた土の階段を昇ると、後ろを振り返り呟いた。
そこは、藪椿の茂りの合間から、港の景色をよく見下ろせる地点であった。椿の花はちょうど盛りのただなかで、目覚ましい赤の色が朝陽を受け、つぶらな葉と大海原の上で身を躍らせている。
澪は背伸びをして、茂みの合間から港を見た。
子供達を乗せる船は、昨晩から停泊していた。巻砂の船着場には大きすぎる弁財船を、船乗りたちが出入りしている。陸に上がる船乗りのうちの幾人かは、市場の通りへと入っていく。
「みんな、お料理屋さんへ行くのかな。いいなあ」
澪が、お料理屋さん、と呼ぶ店は、その通りから少し外れたところに屋根を見せていた。彼は、その店では毎晩祝い事のようなご馳走が出されているらしいこと、店に務める異郷の者たちの、衣装や歌声が華やかであることを知っていた。そして、そこに子供の出入りが禁じられていることを惜しく、また不可思議に思っているのだった。
この少年は、そのような店が単なる宴会の場ではなく、秘された歓楽を流浪の者たちが引き受ける場所であることを、まだ知らずにいる。
澪は道の先に向き直り、小さな峠を目指して歩みを進める。巻砂の狭い俗世から離れ、山の暗がりの奥に住む者へ、彼は別れの言葉を伝えにゆくのだ。
「木守さま、いらっしゃいますかあ」
峠を越え、下り坂となった林道を抜けて、澪は遠くへと呼びかけた。それに応える声は、まだ返ってこない。
小走りになる澪の頭上を、木々の梢が通り過ぎ、朝の空がまばゆさを露わにする。澪はその眩しさを強いまばたきで払い落とすと、この場所で別れを告げるべきもう一つの存在を、潤んだ琥珀色の瞳で見つめた。
「……母様」
己に語りかけるような声で、澪は呟く。
山地の中、異様なほど唐突に開けた野の中心に、彼が母と呼ぶもの――一本の赤榕の木が生えていた。
それは、緑多きこの島の何物にも代え難い、たったひとつの巨樹であった。
真緑の葉を付けた枝は天高く伸び、それでも足りずに外へと向かい、青い影の傘をつくっている。その下では、細い気根が幾重にも幹へ取りつき、うねった滝のような姿で、滑らかな樹皮に木漏れ日を流している。枝、幹、気根とが複雑怪奇に混ざり合うそれらは、注連縄の大輪をくぐったのち、幾筋かの束をつくって、野の下の見えぬ世界へと潜っていく。
そして、澪の目が留められているのは、その木の根本に底知れぬ暗闇をつくる、大きな樹洞であった。
――私達の母様。どうかこれからも、巻砂とその民をお守り下さい。
艶かしいまでに身を絡ませた赤榕の姿を見て、澪は合わせた手に熱を感じた。そうして、その巨樹の内、畏るべき暗闇の中に、温かな血潮の流れていることを想う。
――いつまでも、愛らしい弟達を、私達にお授け下さい。
澪が祈りを終えたとき、彼のはじめの呼びかけに応えが返ってきた。
「澪か」
森と野の境目にぽつんとつくられた、藁葺きの古い庵から、梗が姿を現した。
「郷里を離れるお前に、伝えておかねばならない話がある」
澪は梗に招かれ、庵の縁側に座っていた。改まった表情で隣に座る梗を見て、澪もまた唇と拳を結ぶ。
梗は一呼吸おいて、俯きがちに語り出す。
「我々木守というものは、この世に遍く存在する、母なる木のしもべとなる存在だ。それは、お前のゆく遠ヶ崎の街でも、東海の都や遠い西洋の国々でも変わらない」
「はい」
「木守は母なる木の樹洞に立ち入り、生まれてくる赤子を取り上げる役目を負っている。そして我々は、生まれた弟達の名を木霊達から授かり、命名をしている」
梗が始めた話は、誰もが学舎で学ぶことであり、澪もよく知ることだった。
「私の澪という名も、木守さまが……梗さまが、つけて下さったのですよね」
澪は慌てて言い直す。梗の手によって臍帯を切られたのは、澪の三つ上の兄までだ。それより年長の兄達が、梗の先代の木守に名付けられていたことを、彼は思い出したのだった。
「ああ。お前の名は、私が木霊から授かったものだ。水の通り道、という意味だな」
「はい。水のしっぽという意味で、水尾……あるいは、『船の足跡』ですね。進む船が後ろに残す、白波の跡です」
「そうだ。よく知っているな」
俯いていた梗の視線が、澪へと移る。愛想のなさを島民達に揶揄されもする、そんな彼としては珍しく優しげな表情が、そこにはあった。
それを見た澪も、顔色を明るくする。
「港で働く兄様たちが、よく言うんですよ。『お前は縁起の良い名前だ。もし船が流されたら、餅と酒を供えてやるから捜してきてくれ』って」
澪は笑い話をしたつもりだった。しかし、ひどい堅物でもある梗に、その面白味は伝わらない。
「船を捜すのは、海仕事に慣れないお前には厳しかろう。港の者達も酷な頼みをしたものだ……」
怪訝な顔をする梗に、澪は慌てて両手を振る。
「いえ、あの、これは冗談です! 兄様たちは、私を海の神さまに喩えて遊んでいるのです」
「……そうか」
二人の間に、しばしの沈黙が流れる。梗は再び俯き、澪は腿の上で着物の裾をつねった。足下の落ち葉が、風に吹かれてからからと転がっていく。
「澪は、この地を離れて奉公へ行くことを、どう考えている?」
先に語りかけたのは梗だった。
「勉強、と思っています。私は外へ出て行かねばならない、もっとこの世を知らねばならないと、そう思ったのです」
眼差しを上向かせて、澪が答えた。風が短い前髪をそよがせている。
「……なぜ、そう思う?」
「私は……泣き虫で弱っちくて、度胸がありません。兄様達は優しいけれど、私のこと、ずっと下の弟達みたいにするんです。だから、街へ出て修行して、強い心になって……そうしてまた、巻砂に戻りたい」
梗は何も返さず、隣の小さな横顔を見つめる。
澪は泣いていた。
「本当は……本当は、それも恐ろしさゆえなのです。私の身の周りには、時折、得体の知れぬ帳が現れて……この島で穏やかに過ごしていれば、何も世界を見ぬままで、その帳に呑まれてしまいそうで」
澪は涙を流しながら、しかし俯きはせずに、目を見開いていた。
「だから、私は遠ヶ崎への奉公を志願しました。強い人に……梗さまのような、世を知るお方になるのです」
「私のような?」
梗が驚く。澪は涙を袖で拭うと、梗の方へ向き直った。
「梗さまは紅国の生まれで、幼い頃は鐵国にいらっしゃったのだと、爺様方から聞きました。わけあって海を越え、巻砂の木守を継がれたのだと」
「……そうだな」
梗は一瞬、眉間をこわばらせた。しかし、澪の瞳が憧憬に輝いていることに気づいて、表情を和らげる。
「木守さま。小椎の木のもとでお話してから、今日の日まで、お世話になりました。今よりも強く立派になって、いつかまた巻砂に戻ってきます!」
縁側から立ち上がって、澪は梗にお辞儀をした。梗も立ち上がって澪の目を見据え、笑顔を見せる。
「澪、お前ならきっと、どこでも強く生きてゆける。遠ヶ崎の地で存分にものを知り、見聞を深めてきなさい」
「はい!」
澪は涙を飲み込み、朗らかな声で返事をした。
梗は独り庵の前に佇んで、澪が林の中へ去るのを見送っていた。
「……あの子に話すつもりでしたが、その必要はありませんでした」
梗は宙に語りかける。そこにいるのは、彼だけに姿を見せるものだった。
「いずれ、私を継ぐ子供は出てきます。……巻砂の母よ、あなたの願いは叶えません」
梗の眼差しは、母なる木へと向いていた。そしてその目には、ひとつの人影――白い霧の粒で象られた、美しい顔を悲壮に歪ませる霊の姿が、はっきりと映っていた。
船出
船出は正午であった。昇り切った日が、港に立つ人々の影を、足元に丸く縮こめている。
船着場の岸辺には、奉公へ行く八人の子供達と、見送りをする十数人の島民達が集っていた。子供達は肩を並べ、陸を向いて海岸に立ち並ぶ。
「巻砂の民の代表として、君達の門出を祝う」
横一列になった子供達の目前、見送りの島民達の先頭で語るのは、巻砂の首長であった。
「島の皆が、君達の勤めに期待している。どうか、これからの旅路が安らかでありますように」
頭巾を被った初老の首長は、丸まりかけている背をすっくと伸ばし、子供達の顔を一人ずつ見ながら語りかける。
やがて首長が、澪に目を合わせる。子供ゆえ政とは縁遠かった澪は、これまで、改まって首長と向き合うことはなかった。緊張するような、それでいてくすぐったいようなきまりの悪さを覚え、澪は唇を噛み締めた。
――私は本当に、これからこの島を出るんだ。なんだか今になって、信じられないことのような気がしてくる。
――首長さまはきっとこんなお別れを、何度も経験されているんだろうな。爺様達も先生達も、子供の出ていくことは、寂しくても当たり前のことだろう。
首長の後ろには、見送りに来た学舎の保父や教師達の、馴染みのある顔ぶれが並んでいる。
――みんなとは、何年かのあいだお別れになる。私は知らない街で、知らない人達の中で、新しい暮らしを始める。
――だけどみんなは、この島で変わらず、昨日までと同じ日々を送り続ける。私はその世界から抜け出して、歳をとって……いつか、大人になる。
首長が門出の挨拶を終える。船着場にひとときの静寂が訪れ、海風がぼうぼうと鳴ってそれを吹き飛ばす。
風に目を細める大人達の、乾いてささくれ立った頬、眉間に刻まれた皺は、彼らの暮らしが穏やかなことばかりではなかったことを示していた。若い澪は、大人達の全てを知ることはできなかったけれど、彼らの表情に、晴れやかさと哀しさを織り交ぜた心の宿ることを感じ取った。
「おうい、巻砂の子供衆や! ぼちぼち出ますぜ」
沖合いに停泊している弁財船から、船乗りが呼びかけた。首長が返事をして、子供達を海岸の艀へ乗るよう促す。
澪は大人達の顔を、名残惜しく愛おしむように眺め、海岸の方へと向かった。
「さよなら!」
澪の隣で、彼と同じ大荷物を背負う兄弟が、見送りの者達に向かって叫んだ。慣れ親しんだ横顔の、鼻の先が赤い。きっと海風の冷えるためだ、と澪は胸の内で唱える。そうでもしていなければ、すぐにでも同じ顔色をしてしまうに違いなかった。
「……さようなら!」
喉元に嗚咽を抑え込みながら、澪も別れの挨拶を叫んだ。声が震えてしまったかもしれないと案じるのも束の間、大人達の威勢のいい声が返ってくる。
「達者でなあ!」
「またいつか、戻ってきてくれよ!」
「寂しけりゃ、便りを寄越しなさいな!」
さようなら、達者で、と大声をかけ合いながら、子供達は仲仕と艀に乗り、岸を離れていく。澪も艀に乗り、波間に揺られながら、弁財船の舷梯を昇る。足首を濡らしていた小波の水音が遠のいて、船荷の木箱たちの擦れる音が近づいてくる。
子供達が船に乗り終えると、仲仕と船乗り達は舷梯を片付け、出港の準備を始めた。
澪たちは、船が動き出すまでの時間を、屋倉の戸の前に固まって過ごした。時々、船乗り達が屋倉を出入りして、お前達の部屋はあっちだとか、どこで誰が降りるんだとか、声をかけていった。子供達はそれにはきはきと答えて、けれども居心地悪そうに、度々海岸の大人達を振り返り、その場で狼狽えていた。
やがて、船乗りが吹子のらっぱを鳴らすのを合図に、船が動き出した。一度船体が大きく揺れて軋み、弁財船の巨躯に慣れない子供達は、ひゃあと声をあげた。
「達者でなあー!」
「達者でー!」
海岸から、再び大人達の声が投げかけられた。子供達は手を振ってそれに応える。手を振り返す大人達の姿は、小さく遠くなり、顔の皺も見えなくなっていく。やがて入江の地形が現れ、小舟に乗る漁師達も子供達へ手を振る。
澪は、遠のく彼らの一人一人を見て、それがどんどん、手の届かない過去のものへと変質していくように感じていた。切なさに唇が震え、喉の奥が痛む。これでもう終いにしよう、と思って、巻砂の港の全てを見渡す。
「……木守さま?」
潤んだ澪の瞳に映ったのは、入江の隅の林地に佇んで弁財船を見送る、梗の姿だった。
「木守さま、木守さま! さようなら!」
澪が感激して手を振ると、梗の方もそれに気付いて、片手を挙げた。
――ああ、最後に木守さまとお別れができて、よかった。
澪の瞳から、涙が溢れた。彼の視界は、巻砂の森の深い緑と、海の藍色で染め上げられる。
その二層の色彩は、この島に生まれた者達全てにとって、いずれ帰るべき心の景色であった。
「母様。木守さまのように立派な大人になって、強くなって……この島に、必ず帰ってきます」
澪は滲んだ視界の中で、母を想った。野に聳える赤榕の巨樹。その傍に佇む梗の姿と――隣に並ぶ、まだ見ることのできない、己の姿。
――私の愛しい母様。いつかきっと、あなたにお仕え致します。
涙を拭い、澪は大海原へと向き直った。快晴の薄青と藍色の狭間には、彼の向かう新しい世界が待っていた。
巻砂の島から、一隻の船が旅立っていく。あぶくでできた船の足跡が、白く長く尾を引いていた。
