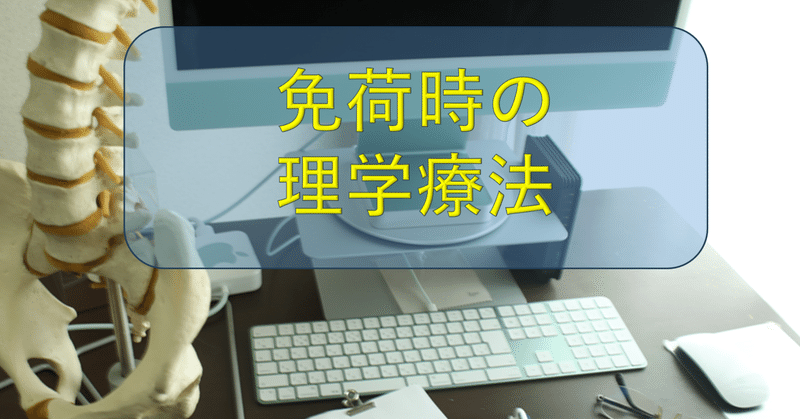
免荷時の理学療法
こんにちは、理学療法士のおかむーです。
今回は、「免荷時の理学療法」についてお話しします。
術後の免荷がしばらく続くとき、若い理学療法士から「この期間、何を行なえばよいでしょうか? 現在、術側下肢以外の筋トレと免荷での松葉杖練習を行なっているのですが。」
と質問されることがあります。
すると私は、「免荷の時の方が行なうことが多くて大変だよ。」と答えます。
理由は、荷重をかけていないので、荷重自体によるROMや筋トレが行えないからです。
その分、こちらで行なわなければなりません。
でも、歩行のように、多岐にわたるROMや筋トレは限られた時間では行えません。
そこで、ポイントを絞って実施します。
膝関節術後で膝関節固定中の方を例にお話しますと
① ROMex
まず、押さえたいのが足関節と足部です。
理由は関節が多くて小さく、固まり易いからです。
大きな筋もないのでマッスルポンプの作用が小さく、体液を心臓へ送り出す機能が低く、関節を固まらせやすくします。
「ROMは生ものだ!」と考えています。
ROMex開始時期は、できるだけ早い方がいいです。
ちなみに、中枢(片麻痺)は「筋収縮の促通が生もの」と考えています。
足のROMexですが、足関節では底屈・背屈はもちろんのこと、内がえし、外がえし、内転・外転も実施します。
関節の可動域に目が行きやすくなりますが、そこを走行する腱への伸張も重要になります。
ですので、ROMexと筋の起始・停止を考慮したストレッチです。
また、足部も同様です。
距骨下関節、ショパール関節、指節間関節すべてになります。
指節間関節では内転、外転の動きも忘れないようにします。
但し、硬くない箇所はチェック程度でよいかと。
特に重要なのが、足指の屈伸と距腿関節の外がえしです。
理由は
足指は、関節が小さく、マッスルポンプの作用が少なく、末梢に位置するので体液が関節内に溜まり、固まり易いからです。
これは手指も同じですが、手の場合は、手関節に小さな手根骨が8個もあるので、足以上に固まり易くなります。
次に距腿関節ですが、外がえしのROMexが重要なのは、下腿三頭筋が短縮しやすいからです。
下腿三頭筋は、距腿関節に影響する距骨下関節の内がえし最大作用筋です。
下腿三頭筋の短縮理由はいろいろありますが、膝関節の障害で考えた一つの例として
腓腹筋とハムストはつながりがあり、ハムストの緊張で脛骨を後方偏位させてPCLの緊張を高め、膝関節を安定させようとします。
そのハムストの緊張を促すために腓腹筋が働きます。
また、臥位では関節がズレやすい状態であり
下腿三頭筋の緊張による距骨下関節の内返しで、足部を安定化させます。
次に、股関節です。
ROMexとしては、伸展、回旋、外転です。
理由は、術後、免荷での病棟等の生活を考えると、下肢を持ち上げるために股関節では屈筋を働かせます。
また、座位はもちろん、臥位でも股関節はすべて屈曲位です。
それを想像すると、行なわないのは、伸展、回旋(特に内旋)、外転です。
内転方向は、膝関節安定化としてのハムストは股関節内転作用があり、外転を押さえるので、あまり制限は起こりません。
② 筋力増強
重要な足部や股関節で、ROM制限がある箇所の制限と逆方向の筋力が低下しやすいです。
若い人では足を中心に、高齢者は足と股関節の両方が必要かと。
ただ、筋力は後からでもつきます。
やはり、大事なのは‘生もの’であるROMです。
非障害側の筋力増強ですが、特別な事情がなければ必要ないと考えます。
生活の中では非障害側で動いているので、生活自体がROMと筋トレになります。
長い目で見た場合、左右差を減らすことが重要です。
私も、理学療法士になるきっかけの膝関節の手術を施行して、かれこれ半世紀近く経ちますが、下肢に左右差があり、二次的障害で不自由さを経験してます。
③ 術創部周辺の対応
医師より、荷重やROMの許可が出て、問題になるのがROM制限です。
この制限の要因の一つに、筋の緊張による短縮があります。
なので、術創部が確認できる状態でしたら、荷重やROMの許可が出る前から膝関節周囲筋の緊張を下げるマッサージなどが必要と考えます。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
