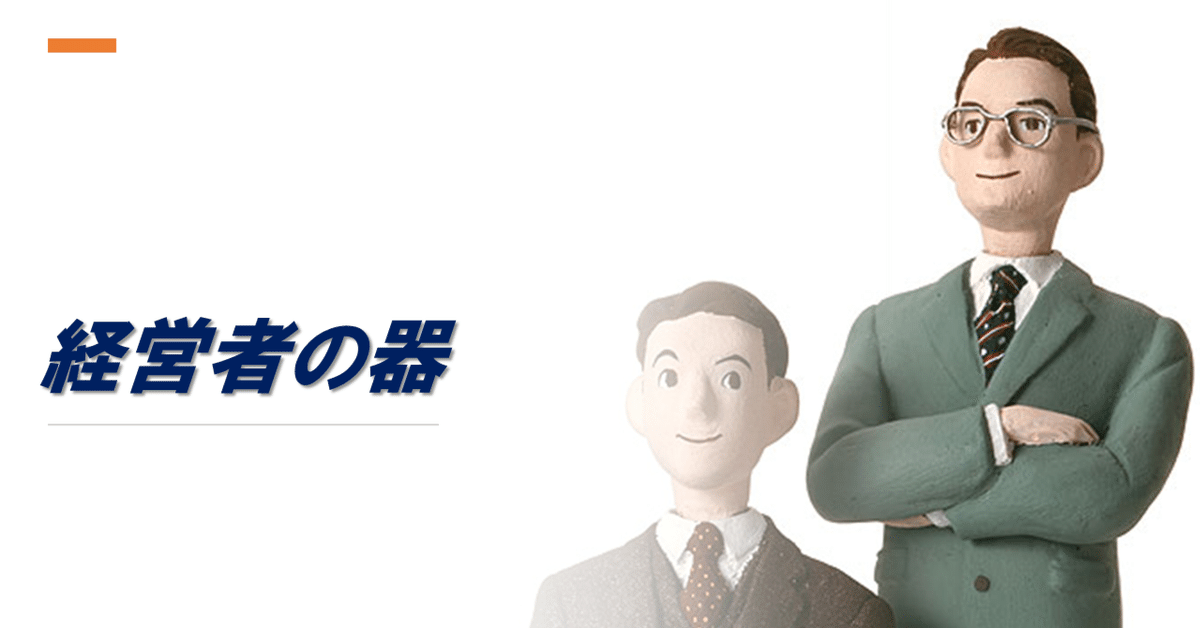
『稲盛和夫一日一言』 10月10日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 10月10日(火)は、「経営者の器」です。
ポイント:企業の規模が大きくなるにつれ、経営の舵取りがうまくいかなくなって潰れてしまったとすれば、それは、組織が大きくなっていくにつれ、経営者が自らの器を大きくすることができなかったからだ。
2001年発刊の『京セラフィロソフィを語るⅠ』(稲盛和夫著 京セラ経営研究課編/非売品)の中で、「経営はトップの器で決まる」として、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
経営はトップの器で決まります。いくら会社を立派にしていこうと思っても、会社はそのトップの人間性、器の大きさにしかなりません。
カニが自分の甲羅(こうら)に似せて穴を掘るように、自分の甲羅、つまり器量よりも大きな穴は掘れないということです。
経営というのは、組織のトップに立つ人間にかかっています。これは何も社長だけでなく、各組織の長でも同じです。組織のトップに立ち、その組織を立派にしようと思うその人が、自分の人格、人間性を磨き立派にしていかなかければなりません。それは「器が大きくなる」ということなのです。
京セラの場合で言えば、あるアメーバの長が小さなアメーバを見ているときは何とか治まっていても、その後次第にアメーバが大きくなっていったときに治めていくことができるのかということです。
そのときにはまさに、自分の器を大きくするような努力をしてきたのか、つまり自分が持っている人間性、人格、人生観、哲学、考え方というものを向上させるよう努力をしてきたかどうかが、たいへん大事になってくるわけです。
私は昔から、「経営はトップの器で決まるのだから、トップである私自身の器を磨き、大きくしていかなければならない」と思い、自分なりに努力を重ねてきました。
今日までの歩みを振り返ると、「経営の技術」を高め続けてきたわけではなく、「理念」を高め続ける日々であったと言えると思います。(要約)
京セラグループでは、「アメーバ経営」と呼ばれる独自の経営管理手法がとられています。これは、グループの企業哲学を実現していくために創り出されたもので、会社の組織をアメーバと呼ばれる小集団に分け、その集団を独立採算で運営する経営システムです。そのシステムによって培われる従業員の経営参画意識やモチベーションの向上は、京セラグループの強みのひとつとなっています。
ひとつのアメーバの構成人員は、1名から数百人までとさまざまです。アメーバ長の力量、人間性がそのまま組織の成果に現れてくるため、そのアメーバに求められる機能や目標達成までのスピード感、全体スケジュールなどに応じて、都度フレキシブルにアメーバの分割・統合が実施されます。
京セラ在籍40年の間、小さなアメーバで立派な実績を出したリーダーが、一つ上の組織を任された途端、実績を上げる間もなく心身に支障をきたして退いてしまう、といった事例をたくさん見てきました。
当然ながら、環境条件に左右される場合もあるし、誰がやっても同じ結果だったのではと見れなくもないのですが、実際のところ、任された組織を自らの器で受け止めることができなかったというのが正直なところではないでしょうか。(自身の経験も踏まえての反省です・・・)
しかし、京セラでは「チャレンジする姿勢を評価する」という風土があります。それは、「チャレンジせずに成功した人」よりも「チャレンジして失敗した人」をより高く評価しようというものです。
会社のためにあえてチャレンジした結果、もし失敗したとしても、それは会社、組織、そこで働く従業員のためによかれと思ってしたことであり、誠実な、しかも利己的でない努力の結果であれば、罰せられることなく、再チャレンジすることもできるのです。
なぜなら、チャレンジすることで数々の修羅場を経験しなければ、自らの器を大きくすることはできないからです。
無謀なものであってはなりませんが、現状よりも少しでも前に進みたいと思っている人にとって、チャレンジすることは自らの器を大きくするため、人間性を高めていくために、絶対に必要なことではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
