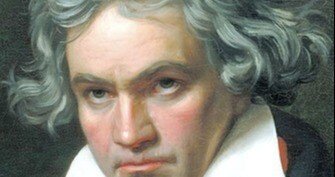#ベートーベン

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調「ハープ」作品74
In this video, we'll be playing Ludwig van Beethoven's String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 74, on the harpsichord. If you're a fan of classical music, then you'll love this video! We'll be playing the amazing String Quartet No. 10 by Ludwig van Beethoven on the harpsichord. This work is full of beautiful melody and is sure to please any classical music fan! 00:00 I. Poco adagio - Allegro 09:17 II. Adagio ma non troppo 18;47 III. Presto 24:00 IV. Allegretto con variazioni 演奏者 Borromeo String Quartet (String Quartet) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 弦楽四重奏曲第10番変ホ長調Op.74は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンによって1809年に作曲された弦楽四重奏曲である。第1楽章の随所に現れるピッツィカートの動機から、「ハープ」という愛称を持つ。ベートーヴェンは金字塔ともいえる3曲の巨大な作品群「ラズモフスキー弦楽四重奏曲」を作曲したあとは、作品の規模は縮小し、代わりにロマン的な情緒やのびのびとした感情をたたえる作風へと変化した。この曲はまさしくそのように、いくらか自由な気持ちで作曲されたものである。 曲の構成 第1楽章 Poco Adagio-Allegro 気まぐれな序奏に始まる。主部はソナタ形式で、第1主題は和音の連打によって始まるが、その後は極めて旋律的な第1主題が第1ヴァイオリンとヴィオラによって歌われる。そしてすぐに前述のピッツィカートによる推移部が現れる。但し第2主題は経過的なものである。展開部は内声はトレモロを刻み、両外声が絡み合いながら進む。再現部は定型どおりであるが、コーダは第1ヴァイオリンのアルペッジョの伴奏の下にピッツィカートであとの三つの楽器が掛け合う充実したものとなっている。 第2楽章 Adagio ma non troppo 変イ長調、ロンド形式。様々な美しい旋律群が豊かな和声や装飾に彩られている。 第3楽章 Presto-Piu presto quasi prestissimo スケルツォ、ハ短調。同じトリオが2回ある。 いわゆる「運命の動機」のようなもの(厳密には違う)によって支配されている。 トリオはハ長調。2小節単位で6/8拍子の要領で弾くという指示がある。チェロとヴィオラに現れる2本の旋律がポリフォニックに展開する。 第4楽章 Allegro con Variazioni 変奏曲。主題と6つの変奏、コーダからなる。意外にも、ベートーヴェンが弦楽四重奏曲の最終楽章に使用した変奏曲として唯一のものである。主題は同じ動機が繰り返される。ここでは晩年に見られるような主題の性格を変えていく性格変奏ではなく、装飾によるものである。 #ベートーベン #弦楽四重奏曲第10番 #ハープ #作品74 #StringQuartetNo10 #Beethoven

ベートーベン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」
In this video, we'll be taking a look at Ludwig van Beethoven's Symphony No. 3 in E♭ major, also known as the "Hero Symphony." This composition is full of epic and heroic music that will leave you captivated from start to finish. If you're a fan of symphonic music, then you need to check out this video! In addition to discussing the composition, we'll also give you a performance of the piece by the Vienna Philharmonic Orchestra. This is one symphony you won't want to miss! 00:00 I. Allegro con brio 15:11 II. Marcia funebre: Adagio assai 30:40 III. Scherzo: Allegro vivace 36:29 IV. Finale: Allegro molto - Poco andante - Presto 演奏者ページ Czech National Symphony Orchestra orchestra 公開者情報 Palo Alto: Musopen, 2012. 著作権 Creative Commons Attribution 3.0 備考 Source: Musopen lossless files also available 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第3番 変ホ長調 作品55『英雄』(こうきょうきょくだい3ばん へんホちょうちょう さくひん55 えいゆう、原題:伊: Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire d'un grand'uomo 英雄交響曲、ある偉大なる人の思い出に捧ぐ)は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1804年に完成させた交響曲。『英雄』のほか、イタリア語の原題に由来する『エロイカ』の名で呼ばれることも多い。ベートーヴェンの最も重要な作品のひとつであると同時に、器楽音楽による表現の可能性を大きく広げた画期的大作である。 概要 交響曲第3番の浄書総譜表紙(ウィーン楽友協会蔵) フランス革命後の世界情勢の中、ベートーヴェンのナポレオン・ボナパルトへの共感から、ナポレオンを讃える曲として作曲された。しかし、完成後まもなくナポレオンが皇帝に即位し、その知らせに激怒したベートーヴェンは「奴も俗物に過ぎなかったか」とナポレオンへの献辞の書かれた表紙を破り捨てた、という逸話がよく知られている。 この曲は、ハイドンやモーツァルトなどの古典派の交響曲や、自身の交響曲第1番・第2番からの飛躍が著しい。曲の長大さや、葬送行進曲やスケルツォといったそれまでの交響曲の常識からすると異質にも思えるジャンルとの本格的な融合、マーラーを先取りする「自由に歌うホルン」を取り入れたオーケストレーション、さらに英雄的で雄大な曲想などの点において革新的である。 この曲の題名のように用いられているエロイカ (eroica) は、男性単数名詞を形容する eroico という形容詞が女性単数名詞である sinfonia (交響曲)を修飾するために語尾変化したものである。sinfonia eroica を直訳すると「英雄的な交響曲」となる。したがって交響曲第6番「田園」の場合のように交響曲をもとにしてに田園の情景を描いたいわゆる標題交響曲とは異なり、「英雄を描写した交響曲」という意味は持っていない。 1817年(第9交響曲を作曲中のころ)、「自作でどれが1番出来がいいと思いますか」という詩人クリストフ・クフナーの質問に対し、ベートーヴェンは即座に「エロイカ」と答え、「第5交響曲(運命)かと思いました」と言う言葉に対しても「いいえ、いいえ、エロイカです!」と否定している。 作曲の経緯 作曲者の「無給の秘書」シンドラーが書いた伝記によると、当時ウィーン駐在のフランス公使だったベルナドット将軍(後のスウェーデン国王カール14世ヨハン)の勧めにより作曲を始めたものとされていたが、このエピソードはシンドラーの創作であるとする説が有力視されており、この交響曲の作曲に着手したきっかけはよくわかっていない。 なお、ナポレオンが皇帝に即位したという知らせを聞いたベートーヴェンが「奴もまた俗物に過ぎなかったか。これから、人々の人権を踏みにじって自分の野心のためだけに奔走し、誰よりも自分が優れていると誇示する暴君になるのだろう」と激怒し、献辞が書いてある表紙を破り取ったという、弟子フェルディナント・リースの回想に基づく有名なエピソードが伝えられている。しかし実際は、ウィーン楽友協会に現存する浄書総譜には表紙を破り取った形跡はなく、表紙に書かれた「ボナパルト」という題名とナポレオンへの献辞をペンでかき消した上に「シンフォニア・エロイカ」と改題され、「ある英雄の思い出のために」と書き加えられている。 ナポレオンへの献呈は取り止めになり、最終的な献呈先はロブコヴィツ侯爵に落ち着いた。この書き足された「ある英雄」が誰であるのかに関しては昔からいろいろ推測されてきたが、ごく最近「この「ある英雄」は、非公開の初演に立会い、1806年7月9日にイェーナの会戦で戦死したプロイセン王子ルイ・フェルディナント(フリードリヒ大王の甥で音楽的才能もあった)ではないか」という説も出てきている。 またそれゆえに、ベートーヴェンが皇帝に即位したナポレオンに激怒したという件についても、事実であるかどうか疑いが持たれている。ベートーヴェンは終始ナポレオンを尊敬しており、第2楽章が英雄の死と葬送をテーマにしているため、これではナポレオンに対して失礼であるとして、あえて曲名を変更し献呈を取り止めたという説もある。 演奏時間 20世紀中盤は第1楽章の繰り返しを含めず50分程度が多かったが(ヴィルヘルム・フルトヴェングラーなど)、20世紀終盤からは古楽の隆盛による演奏様式の史的考証の進展に伴ってベートーヴェンのメトロノーム指定を尊重する傾向が強まり、繰り返しを含めて42分から48分ほどの演奏が増えている。 曲の構成 第1楽章の巨大な展開部と第2展開部に匹敵するコーダ。第2楽章には歌曲風の楽章の代わりに葬送行進曲、第3楽章にはメヌエットの代わりにスケルツォ(ただし、これは第1番と第2番でも既に試みられている)、そして終楽章にはロンド風のフィナーレの代わりに変奏曲が配置される。 第1楽章 Allegro con brio 変ホ長調。4分の3拍子。 ソナタ形式(提示部反復指定あり)。 第2楽章 Marcia funebre: Adagio assai ハ短調。4分の2拍子。葬送行進曲。A-B-A'-C-A"の小ロンド形式。 第3楽章 Scherzo: Allegro vivace 変ホ長調。4分の3拍子。複合三部形式。 第4楽章 Finale: Allegro molto 変ホ長調。4分の2拍子。自由な変奏曲の形式。 楽譜 ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社によって旧ベートーヴェン全集が1860年代に出版されて以来、他のベートーヴェン作品同様、旧全集やその改訂版が演奏されて来たが、研究が進むにつれてベートーヴェンが関わった原稿や初版譜の点検が行われ、旧全集の譜面との差異が明らかになり、新たな楽譜を作ろうとする動きが出て来た。 ベートーヴェンの生前出版された『英雄』の楽譜はパート譜が最初で、それを元にロンドンとボンの出版社からスコアが出版された。そのため両版には食い違いがみられる。自筆スコアは失われているが、ベートーヴェンの立会った演奏で実際に用いられた筆写スコアとパート譜が残っている。 ベートーヴェン作品の新しい全集を企画したボンのベートーヴェン研究所は、バティア・チャーギン (Bathia Churgin) の校訂で第3、4番をヘンレ社から刊行すると発表した。チャーギンは筆写スコアに残るベートーヴェンが訂正した箇所が「ほぼ全ページにある」と言い、写譜師の不注意によって逆にベートーヴェンの意図を確認できることに感謝せねば、とさえ書いている。そうした新発見が多数反映される予定だった新全集は、1996年に出版の目処がついたという報が流れた。ヘンレ社は出版準備中を告知、第4番以降も印刷作業に入り、資料評価の経緯を記した校訂報告の作成が難航、という関係者の非常に現実的な証言もあったが、実際の刊行は行われなかった。ベートーヴェン研究所の資金難と版刻師の人手不足が主な原因といわれる。交響曲の他の巻も、新資料の発見による校訂のやり直しなど様々な問題を抱えている。以来交響曲の巻は10年以上出版が無く、2013年にようやく再告知、4番とともに交響曲第2巻として刊行が実現した。同年末に5・6番を収録した第3巻も刊行された。 新全集版が刊行停止している間に『英雄』の原典版は2種類刊行された。ベーレンライター社から、実演・録音で賛否両論を捲き起こした『第九』同様ジョナサン・デルマー校訂の原典版が刊行されている。この版は出版前にジョン・エリオット・ガーディナーなどの指揮者が試験的に採用しており、新発見が反映されただけでなく、演奏上の問題を考慮した楽譜という点でも画期的なものである。旧全集の出版社ブライトコプフ社も東西ドイツ統一直前にペータース社の原典版を準備していたペーター・ハウシルトの校訂で新版を出した。現在まで残る手稿、初版のパート譜・スコアなどあらゆる資料を参照して作成された批判校訂版となった。 なお、『英雄』旧全集版は当時ドレスデンの宮廷楽長でチェリスト、作曲家、指揮者として活躍していたユリウス・リーツが校訂したものである。旧全集では他に『田園』がリーツの校訂である。 楽曲が用いられた作品 テレビアニメ『ルパン三世』(第2シリーズ、日本テレビ)第89話『ドロボウ交響曲を鳴らせ』 テレビアニメ『科学忍者隊ガッチャマンF』、敵役であるエゴボスラー伯爵のサブテーマ曲になっており、劇中でしばしば本曲を聞き惚れるシーンがある。 漫画『のだめカンタービレ』 Sオケのデビュー曲に加え、千秋真一が初めて聴衆の前で指揮棒を振って演奏した曲でもある。Sオケ創設者のシュトレーゼマンが演奏予定だったものの指導を放棄した為、千秋が事実上の代役をする事に成り、新装版13巻の最終話で千秋がシュトレーゼマンに向けて、「実はあなたのエロイカ聞いていないんです」と言う顛末に成った。 映画『スパイ・ゾルゲ』作品最後、ドイツ再統一のニュースが流れる1990年のシーンに第4楽章が使用された。 映画『路上のソリスト』ではナサニエル・エアーズ役のジェイミー・フォックスがナサニエルの少年期~ジュリアード学院在籍時の練習曲として、第一楽章をチェロで弾くシーンが何回か登場する。 「銀河英雄伝説」の「我が征くは星の大海」において、ヤンが歴史ビデオを見るシーンはナポレオン時代のものであり、その時のBGMがこれである。また本編OVAにも複数回使用されている。第2話、第37話、第38話など。 特撮テレビドラマ「爆竜戦隊アバレンジャー」にこの曲をモチーフとする巨大怪物が登場する。 #ベートーベン,#Beethoven,#英雄,#交響曲第3番,#作品55

ベートーヴェン:交響曲 第2番 ニ長調, Op.36
In this Ludwig van Beethoven video, we're exploring his Symphony No. 2 in D major, Op. 36. This beautiful and powerful work was written in 1802 and is one of Beethoven's most popular symphonies. In this video, we'll look at the highlights of this Symphony and hear how it's instrumentation and composition would have sounded in the 19th century. After watching this video, you'll have a much better understanding of this amazing work and be able to enjoy it even more! 00:00 I. Adagio molto - Allegro molto 12:07 II. Larghetto 23:52 III. Scherzo 27:34 IV. Allegro molto 演奏者ページ University of Chicago Orchestra (orchestra) Barbara Schubert (conductor) 公開者情報 Chicago: University of Chicago Symphony 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 備考 Performed 30 April 2005, Mandel Hall. From archive.org 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 交響曲第2番 ニ長調 作品36 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの書いた2作目の交響曲である。 概要 断片的な着想は第1番作曲中の1800年に遡り、1801年から本格的な作曲が開始されている。1802年3月には完成されたと考えられ、1803年4月5日、ウィーン近郊アン・デア・ウィーン劇場にて、ピアノ協奏曲第3番、オラトリオ『オリーヴ山上のキリスト』とともに初演された。 この作品が作曲されたのはベートーヴェンの持病である難聴が特に悪化した時期であり、10月には「ハイリゲンシュタットの遺書」も書かれているが、作品内に苦悩の跡はほぼ見られない。形式的には未だにフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの枠組みの中にあるが、作曲技法としては第1番よりも更に進歩しており、第1楽章序奏の規模が拡大し重要性が増していること、動機労作がより緻密になり、ソナタ形式楽章におけるコーダが第二展開部としての様相を呈し始めていることなどが指摘される。楽器法の面でも、木管楽器(特にクラリネット)の活用や、チェロとコントラバスを分割して扱う手法が顕著になっていることが注目される。 初演では「奇を衒いすぎている」と評された。 なお、後に自身の手によって、ピアノ三重奏用に編曲された(1805年刊行)。これは、当時の庶民にとってオーケストラを聴くことは高価であったため、作品を手軽に家庭で楽しめるようにする必要があったためだと思われる。 曲の構成 全4楽章からなり、演奏時間は約34分(第1楽章の繰り返しを含み、スケルツォを対称形にしない場合)。随所に、後の交響曲第9番を思わせるパッセージが登場する。 第1楽章 Adagio molto ニ長調 4分の3拍子 - Allegro con brio ニ長調 4分の4拍子 序奏付きのソナタ形式(提示部反復指定あり)。序奏部は大胆な転調を含む大規模なもので、中ほどにニ短調の主和音がアルペッジョで下降するパッセージが見られ、交響曲第9番の第1楽章・第1主題を彷彿とさせる。主部は力強い第1主題と穏やかな第2主題を持つ。展開部は長く2部に分かれており、更にコーダも長く、第2展開部としての役割も果たす。 第2楽章 Larghetto イ長調 8分の3拍子 ソナタ形式。旋律の美しさによって有名で、後に何者か[1] によって歌詞が付けられて歌曲になったこともある。第1主題部は長めで弦楽部に始まり、木管で繰り返される。第2主題も第1ヴァイオリンで導かれる。コデッタの後、反復なしで第1主題を主とした展開部に入る。再現部は対位法を効果的に使ったものとなっているが、流れ自体は提示部と変わらない。 第3楽章 Scherzo Allegro ニ長調 4分の3拍子 複合三部形式。ベートーヴェンが交響曲に初めて「スケルツォ」の名称を用いた。トリオの旋律は後の交響曲第9番のスケルツォのトリオに類似している。ベートーヴェンの交響曲の舞曲楽章の中では最も規模が小さい。 第4楽章 Allegro molto ニ長調 2分の2拍子 ロンドソナタ形式。何者かに問いかけるようなユニークな動機の第1主題で開始され、その動機が楽章全体を支配している。チェロによる田園的な経過句の後、木管に第2主題が現れる。短いコデッタの後、展開部へ移行する。第6番や8番のフィナーレと同じく提示部の繰り返し記号はない。展開部は劇的な迫力を伴い、総休止を効果的に使って進行する。再現部は型どおりで、コーダは全体の3分の1を占める長大なものとなっている。 #ベートーベン,#beethoven,#交響曲第2番,#Op36,#Symphony

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第10番 ト長調 Op.96
00:00 I. Allegro moderato 09:40 II. Adagio espressivo 16:01 III. Scherzo: Allegro 17:53 IV. Poco allegretto 演奏者ページ Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ウィキポータル クラシック音楽 ポータル クラシック音楽 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第10番ト長調作品96は最終作のヴァイオリンソナタであり、後のシューマンやブラームスの作品に通じる自由な構成の作品。ベートーヴェンは壮年期までにヴァイオリンソナタ全10曲のうち9曲までを完成させており、本作は前作から9年たって作曲された創作後期の唯一のヴァイオリン曲である。 作曲年代:1812年2〜11月(ベートーヴェン41歳) 初演:1812年12月29日 出版:1816年 曲の構成 4楽章構成。自由なソナタ形式。全体に穏やかな曲想である。献呈はルドルフ大公。 第1楽章 Allegro moderato 冒頭からヴァイオリンのトリルで伸びやかな展開。下属調和音をゆったりと歌い上げる。 第2楽章 Adagio espressivo 変ホ長調。歌謡風の落ち着いた主題。アタッカで第3楽章とつなげて演奏される。 第3楽章 Scherzo. Allegro ト短調。タイを使って強調しているが、壮年期の作品(第9番など)とは違い、激しさは影をひそめている。 第4楽章 Poco Allegretto ト長調。主題と8つの変奏による変奏曲。随所に休符を入れ、柔和な演出をしている。第7変奏では後期の作品の特徴であるフーガが規模が小さいながらも使われている。 #ヴァイオリンソナタ,#beethoven,#ベートーベン,#ベートーヴェン,#第10番

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第5番 へ長調 Op.24 「スプリング」
00:00 I. Allegro 07:18 II. Adagio molto espressivo 12:53 III. Scherzo. Allegro molto -Trio 14:21 IV. Rondo. Allegro ma non troppo 演奏者ページ Wolfgang Schneiderhan (violin) Wilhelm Kempff (piano) 公開者情報 Deutsche Grammophon, 1953. 著作権 Creative Commons Zero 1.0 - Non-PD US 備考 Téléchargement Enregistrements sonores 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第5番 ヘ長調 作品24 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1800年から1801年にかけて作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 ベートーヴェンのヴァイオリンソナタの中でも非常に有名な曲であり、その、幸福感に満ちた明るい曲想から『春』や『スプリングソナタ』という愛称で親しまれている。元々、ベートーヴェンは前作の第4番 イ短調とセットで「作品23」として出版するつもりであったが、製本上の理由により、別々に出版された。 ベートーヴェン自身のヴァイオリン演奏は技術的に稚拙で自作のヴァイオリン部を公開で弾く機会はほとんどなかった。ヴァイオリンのイディオムにもピアノのそれに対するほど通じてはいなかったので、ソナタの旋律リズムはピアノのものが中心になっている。 曲の構成 第1楽章 アレグロ ヘ長調、4分の4拍子、ソナタ形式。 ピアノの伴奏に乗ってヴァイオリンで第1主題が歌われる。主題は10小節からなり、順次進行で下降したあと、跳躍を含む音型が3回繰り返されて盛り上がって終わるという、大変バランスの取れた、非常に美しい旋律である。その旋律がピアノで繰り返されたあと、推移となり第2主題が導かれるが、それは第1主題と対比して、和音連打によるものである。コデッタは連打による動機の模倣と、音階によるものからなる。展開部は第2主題が使用され、再現部は提示部と逆で、第1主題はピアノ→ヴァイオリンの順で奏される。 第2楽章 アダージョ・モルト・エスプレッシーヴォ 変ロ長調、4分の3拍子、三部形式(または変奏曲形式)。 分散和音の伴奏に乗って、美しい旋律がピアノ、ヴァイオリンの順で歌われる。推移部のあと、主題が再現する際、それは装飾的な変奏や、転調などで彩られる。 第3楽章 スケルツォ:アレグロ・モルト ヘ長調、4分の3拍子。 音階が上がったり下がったりする主部と急速なトリオからなる、短い楽章。 第4楽章 ロンド:アレグロ・マ・ノン・トロッポ ヘ長調、2分の2拍子、ロンド形式。 「A - B - A - C - A - B - A - コーダ」の構造を持つ。軽やかなAの主題は、同音が3回連打されることで印象付けられる。2部分からなり、ハ短調に陰るなど様々な要素を持つBと、3連符とシンコペーションのリズムを伴うニ短調のCを経て、Aの主題がニ長調で再現されると、さらに美しく変奏されて、喜びに満ちたまま曲は終わる。 #ベートーベン,#ヴァイオリンソナタ,#スプリング,#beethoven,#violin,#春

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第1番 ニ長調 Op.12-1
00:00 I. Allegro con brio 05:57 II. Theme and Variations: Andante con moto 13:11 III. Rondo: Allegro 演奏者ページ Corey Cerovsek (violin) Paavali Jumppanen (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヴァイオリンソナタ第1番 ニ長調 作品12-1 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1798年頃に作曲したヴァイオリンソナタ。作曲者のヴァイオリンソナタの第1作であり、第2番、第3番とともに師であるアントニオ・サリエリに献呈された。3曲とも「ヴァイオリンの助奏を伴ったクラヴィチェンバロまたはピアノ・フォルテのためのソナタ」と記されていて、ピアノに重きが置かれている。 全体的に明るい曲想であり、しばしば演奏会で取り上げられ、人気も高い。 曲の構成 全3楽章。演奏時間は約20分。 第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ ニ長調、4分の4拍子、ソナタ形式。 冒頭からヴァイオリンの重音奏法で主和音が現れる。ピアノの名手としての作者らしく、アルペッジョの急速な進行が随所に盛り込まれている。 第2楽章 主題と変奏:アンダンテ・コン・モート イ長調(第3変奏はイ短調)、4分の2拍子、変奏曲形式。 主題と4つの変奏からなる落ち着いた曲想の楽章であり、イ短調の3連符が伴う変奏で対立を際立たせている。 第3楽章 ロンド:アレグロ ニ長調、8分の6拍子、ロンド形式。 楽曲が用いられた作品 仮装集団 - 山崎豊子の長編小説。東京体育館で行われたサベーリエフのヴァイオリン演奏会の中で登場する。 #marthaargerich,#gidon kremer,#ヴァイオリン・ソナタダイ1バン - ダイ1ガクショウ,#ヴァイオリンソナタ,#ベートーベン

ベートーベン:チェロソナタ第5番 ニ長調 Op.102-2
00:00 I. Allegro con brio 07:25 II. Adagio con moto sentimento d'affetto 16:20 III. Allegro fugato 演奏者ページ Laurence Lesser (cello) Russell Sherman (piano) 公開者情報 Boston: Isabella Stewart Gardner Museum 著作権 Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 [tag/del] 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのチェロソナタ第5番作品102-2は、1815年の作。第4番作品102-1と連作であり、非常に簡潔な小品である。 曲の構成 第3番の雄大な規模と異なり、室内楽の範囲にありながらピアノソナタ第31番と同様にバッハのフーガ技法を取り入れている。ベートーヴェンのチェロソナタ5曲で唯一緩徐楽章を使用している。作曲者最後のチェロ作品として後のロマン派音楽につながる自由な創意が認められる。第2楽章と第3楽章は切れ目なく演奏される。 第1楽章 Allegro con brio ニ長調、4分の4拍子、簡潔なソナタ形式。冒頭からピアノによる16分音符のD-Fis-E-D、二分音符1.5拍によるD音の主題が繰り返される。ピアノソナタ第3番と作曲素材は類似しているが、チェロの強い音量に配慮した華やかさがあり、ピアノ独奏曲よりも更にAllegro con brioになっている。またピアノ左手のトレモロが多くこの点でも華やか。 中間部はハ長調、展開は短くト長調で主題を出した後に再現部。コーダにわずかに自由な和声が現れる。 第2楽章 Adagio con molto sentimento その名のとおり落ち着いた叙情的な楽章。4分の2拍子、ニ短調。低音の主題が美しい。 第3楽章 Allegro ニ長調、4分の3拍子。非常に巧みな4声のフーガ。 #ベートーベン #ソナタ #チェロソナタ第5番 #クラシック #theartofpablocasals #beethoven #classical music

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」 Op.47
00:00 1. Adagio sostenuto — Presto 10:22 2. Andante con Variazioni 31:25 3. Finale. Presto 演奏者 Paul Rosenthal (violin) Edward Auer (piano) 公開者情報 Pandora Records/Al Goldstein Archive 著作権 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 [tag/del] 備考 Performed 1982. Seattle: Lakeside School ヴァイオリンソナタ第9番 イ長調 作品47 は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1803年に作曲したヴァイオリンソナタ。 概要 ロドルフ・クロイツェル(クレゼール) ベートーヴェンの作曲したヴァイオリンソナタの中では、第5番『春』と並んで知名度が高く、ヴァイオリニストのロドルフ・クロイツェル(クレゼール)に捧げられたために『クロイツェル』の愛称で親しまれているが、ベートーヴェン自身のつけた題は『ほとんど協奏曲のように、相競って演奏されるヴァイオリン助奏つきのピアノソナタ』である。 ベートーヴェンは生涯で10曲のヴァイオリンソナタを書いたが、特にこのクロイツェルは規模が大きく、王者の風格をそなえており、ヴァイオリンソナタの最高傑作であるとされる。ベートーヴェン以前の古典派のヴァイオリンソナタは、あくまでも「ヴァイオリン助奏つきのピアノソナタ」であり、ピアノが主である曲が多いが、この曲はベートーヴェン自身がつけた題の通り、ヴァイオリンとピアノが対等であることが特徴的である。技術的にも高度なテクニックが要求される。 ロシアの文豪レフ・トルストイによる小説『クロイツェル・ソナタ』は、この曲に触発されて執筆された作品である。嫉妬心にかられ妻を殺してしまった夫の悲劇が描かれている。ヤナーチェクはこの小説に刺激を受けて、弦楽四重奏曲第1番『クロイツェル・ソナタ』を作曲している。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 概要 ロドルフ・クロイツェル(クレゼール) ベートーヴェンの作曲したヴァイオリンソナタの中では、第5番『春』と並んで知名度が高く、ヴァイオリニストのロドルフ・クロイツェル(クレゼール)に捧げられたために『クロイツェル』の愛称で親しまれているが、ベートーヴェン自身のつけた題は『ほとんど協奏曲のように、相競って演奏されるヴァイオリン助奏つきのピアノソナタ』である。 ベートーヴェンは生涯で10曲のヴァイオリンソナタを書いたが、特にこのクロイツェルは規模が大きく、王者の風格をそなえており、ヴァイオリンソナタの最高傑作であるとされる。ベートーヴェン以前の古典派のヴァイオリンソナタは、あくまでも「ヴァイオリン助奏つきのピアノソナタ」であり、ピアノが主である曲が多いが、この曲はベートーヴェン自身がつけた題の通り、ヴァイオリンとピアノが対等であることが特徴的である。技術的にも高度なテクニックが要求される。 ロシアの文豪レフ・トルストイによる小説『クロイツェル・ソナタ』は、この曲に触発されて執筆された作品である。嫉妬心にかられ妻を殺してしまった夫の悲劇が描かれている。ヤナーチェクはこの小説に刺激を受けて、弦楽四重奏曲第1番『クロイツェル・ソナタ』を作曲している。 作曲の経緯 この曲は、当時イギリスのプリンス・オブ・ウェールズ(のちのジョージ4世)に仕えていたジョージ・ブリッジタワーが、ウィーンで演奏会を行うにあたって急遽作曲された。作曲が間に合わず、初演の幕が開く寸前まで作曲が行われた。初演では、第1・第2楽章の一部は、大まかにだけ書かれた手書きの楽譜を元に即興的に演奏された。第3楽章は、自身のヴァイオリンソナタ第6番の終楽章であったものを転用した。 ベートーヴェンはこの曲を当初はブリッジタワーに捧げる予定だったが、実際にはクロイツェルに献呈されている。ブリッジタワーの証言によると、ある女性をめぐる対立から不仲となったため献呈者をクロイツェルに変えたという[1]。また、ベートーヴェンがこの年パリへ行く予定だったので、その前に当時フランスで著名なヴァイオリニストであったクロイツェルと親交を深めておこうとしたという事情もあった。しかし、いずれにしても、クロイツェル自身は一度もこの曲を演奏することはなかった。 初演 初演は1803年にウィーンでブリッジタワーのヴァイオリンと作曲者自身のピアノによって行われた。 曲の構成 第1楽章 アダージョ・ソステヌート - プレスト イ長調 - イ短調、4分の3拍子 - 2分の2拍子、序奏付きソナタ形式。 イ長調の重厚な和音で始まるが、すぐにイ短調に転調し緩やかな序奏が終わる。主部はイ短調のプレストで、ヴァイオリンの激しい動きだけでなく、ピアノにも豪華な役割が与えられている。展開部は第1主題を主に扱い、大きく盛り上がる。ヴァイオリンは音量が小さいのでピアノに伍するために重音を活用しているが、ピアノはユニゾンで単純抑制された役に徹している。随所にアダージョの部分を挟むことで単調さを避けている。 第2楽章 アンダンテ・コン ・ヴァリアツィオーネ ヘ長調、4分の2拍子、主題と4つの変奏曲。 穏やかな主題が提示されたあと変奏が始まる。第2変奏でヴァイオリンは高音域で存在を誇示している。第3変奏はヘ短調。 第3楽章 プレスト イ長調、8分の6拍子、ソナタ形式。 輝かしいタランテラ。終楽章にタランテラを設けるのは、ベートーヴェンの中期に多く見られる技法である。ここでも適宜拍子を変えて緩徐な部分を挿入し、変化をつけてタランテラの野卑さを抑えている。 #ベートーベン,#クロイツェル,#,#beethoven,#violin,#kreutzer,#ludwigvanbeethoven,#classicalmusic