
鈴木大拙と未分——読書会「日本の美を読む」でおなはししたこと
2022年2月23日 祝日・火曜日にミナブックフェスティバル(minagarten 広島・皆賀)のなかでおこなわれた読書会『日本の美を読む 総集編——解題としての鈴木大拙』を、今田順さんとともに担当いたしました。
当日は今田さんと中村による対談形式の進行。 ここでは中村がおはなしした部分のサマリーとスライドショーの一部を公開します。
資料
1: 読書会『日本の美を読む』鈴木大拙 略年表
2: 読書会『日本の美を読む』鈴木大拙 資料
*リンク先の外部URLよりPDFがダウンロードできます。
解題としての鈴木大拙——OSなるもの
東京・国分寺 胡桃堂喫茶店と広島・皆賀 ミナガルテンでおこなわれた『日本の美を読む』。これはブックキュレータ 今田順さんの企画・進行でおこなわれた読書会シリーズです。2017年にはじまった最初のシリーズであつかわれたのは、岡倉覚三(天心)『茶の本』、夏目漱石『草枕』、谷崎潤一郎『陰翳礼讃』、柳宗悦『民藝四十年』、和辻哲郎『風土』、岡本太郎『日本の伝統』『沖縄文化論』となりました。
当初は数名の参加者による、ラボ的なかたちになることを想像していましたが、回をかさねるごとに参加者がふえ、いつのまにか『続 日本の美を読む』として、参加者のもちこみ企画がはじまり、本編の6名にくわえ鈴木大拙『東洋的な見方』、柳田國男『遠野物語』、白州正子『かくれ里』があつかわれました。僕はこの読書会シリーズにほぼ毎回出席していた縁もあって、鈴木大拙の回を担当することになります。
その後、今田さんが広島に拠点をうつされたこともあり、2021年に再度『日本の美を読む』シリーズが広島・皆賀でオフライン・オンラインの併用形式で開催され再度、6名の人物と書物がとりあげられました。2022年2月、その最終回として『日本の美を読む 総集編——解題としての鈴木大拙』というものを開催しました。
いずれも続編、あるいは総集編というかたちで鈴木大拙をとりあげたのは、もれたものを引っ張り出すという意味ありつつ、この読書会シリーズであつかわれた内容の通奏低音として大拙のいう「東洋的な見方」あるいは「日本的霊性」なるものがあるようにみえるのが、その理由です。大拙のいう東洋的な見方あるいは禅というのは、『日本の美を読む』の根底にあるOSのようなものかもしれません。
岡倉覚三『茶の本』や谷崎潤一郎『陰翳礼讃』は、デザインや美術をまなぶなかで触れる機会のおおい書物です。自身も学生時分この二冊にであい、その内容にいろいろ腑におちたことがありました。というのも、どうしても美術造形教育というのは、近現代のものであれ、伝統的なものであれ、西洋の体系のうえで展開されることを基本としています。日本でそれをまなぶ立場にしてみれば、それは輸入されたものをうけとることになり、どこか自分たちの身体感覚が切断されるような心持ちもありました。
ですので、岡倉や谷崎のはなしは、そうした基本的なところを肯定するような感覚をおぼえたのでした。 そうするなか、こうした書物につうじる「そもそも」のことと、その根底にあるのはなにか? という念がうかぶようになりました。おもいかえせば、2011年。ちょうど震災のころでした。産学連携というかたちで、いくつか地方都市のひとたちと協働する機会にめぐまれるなか、いわゆる近代デザインの文脈ではたちゆかない場面にたびたび遭遇することになりました。
そうしたとき、モダニズムのデザインを参考にすればするほど、そこにある西洋知といえる哲学や宗教的価値観が気になってしまうのでした。大拙の書物にふれた最初はそうした時期でした。読みはじめてみれば、それまで漠然とふれていた谷崎や岡倉、あるいは柳宗悦といったひとびとのはなしに通底するなにかが、うかんできたのです。
鈴木大拙: 明治・大正・昭和。日本とアメリカで一世紀を生きたひと
鈴木大拙 鈴木貞太郎 Teitaro ‘Daisetz’ Suzuki
1870年11月11日 —— 1966年7月12日
明治3年 —— 昭和41年
鈴木大拙の形成——時代と環境がつくりだした存在
鈴木大拙は1870年にうまれ。享年が95歳と一世紀ちかく、かなり長生きをしています。和暦でいえば明治3年から昭和41年と、明治、大正、昭和と三時代をすごしたことになります。1870年11月11日(旧暦 10月18日)うまれ、そして1966年7月12日没。横浜で日本初のガス灯が点灯され、富岡製糸工場が操業した年です。同年生まれの人物としては島崎藤村、樋口一葉、ピート・モンドリアン、そして生涯の同志である西田幾多郎がいます。
いっぽう、1966年はザ・ビーチボーイズ『ペット・サウンズ』の発表にビートルズ来日。さらには『笑点』と『ウルトラマン』の放送が開始され、ソヴィエトのルナ9号が月面着陸。グリコからはポッキーが、トヨタからはカローラが発表。日本の人口が一億人を突破した年となります。2022年現在でも、ちかい過去という感覚ではないでしょうか。1983年うまれの僕にとっては、親世代が経験している時代です。
鈴木大拙。本名は鈴木貞太郎。金沢うまれ。第4高等中学(現 金沢大学)で西田幾多郎とであうことになります。その後、中学校の英語講師の職を辞し、21歳のときに上京。東京専門学校——いまの早稲田大学に入学。その後、帝国大学専科にも在籍します。このころ、北鎌倉の円覚寺に参禅をするようにもなります。ここで出会ったのが円覚寺の住職であった今北洪川です。しかし、まもなく遷化。そのあとを継いだ円覚寺住職 釈宗演にであうことが、大拙その後の人生を左右することになります。なお大拙という居士号は釈宗演によるものです。
釈宗演は当時として、かなり国際感覚のあった人物で、慶應義塾大学で福沢諭吉にまなび、そのつてでセイロンをはじめ外国をめぐっています。1893年にはシカゴ万国博覧会の一貫としておこなわれた万国宗教会議に出席したようなひとです。この宗演の英訳をおこなったのが、大拙でした。
大拙は生涯のなかでおおきく二度、アメリカに拠点をおいています。はじめは1897年から1909年。27歳から39歳にかけてのとき。ここでは釈宗演の紹介によりポール・ケラースのもとオープンコート社に編集者として勤務。この十年は、英語でかかれたおおくの宗教系論文を目にしていたといいます。
帰国後、学習院で英語講師兼寮長としてつとめることになります。当時の学習院長は乃木希典。ドイツ語を担当したのは同郷の友人 西田幾多郎です。そこでであった教え子のひとりに柳宗悦がいます。明治期の軍人が学長であり、いっぽう学生たちは白樺派の時代。近代における世代差を象徴しているようです。なお柳は生涯にわたり、大拙と関係しています。資料の年表をみれば、大拙の学習院時代と柳の白樺時代、乃木の殉死、そこからの漱石による『こころ』は縦軸でぴったりとかさなります。
大拙二度目のアメリカ生活は1949年から1958年にかけて。おどろくことに79歳から88歳のあいだです。ここでは、おもにコロンビア大学客員教授として籍をおきながら、各所で講演活動を実施しています。コロンビア大学の講演を聞き、その後、大拙本人をたずねた人物のなかには『4:33』でしられる音楽家 ジョン・ケージがいます。これにかぎらず大拙のアメリカにおける影響力はおおきようです。
鈴木大拙の代表作といえば68歳のときに書かれた『禅と日本文化』(1938, 1940 翻訳)また、もうひとつとして74歳の歳にかかれた『日本的霊性』(1944)、この二冊となるでしょう。この読書会では90歳をすぎ出版された『東洋的な見方』(1963年 / 上田閑照 編による新編は1997年)をテーマ図書としました。『日本的霊性』から20年ほどあと。二度目の渡米、異国の地で、さまざまな講演・講座を経てた洗練された内容となっています。

では鈴木大拙とはどんな人物でしょうか?。いっぱんには晩年になっての姿がしられているかとおもいます。和服やアスコットタイのもの。大拙自身は僧侶ではありませんが、まさに高僧のような風貌をしています。いっぽう、最初のアメリカ時代は洋装で髭をたくわえた姿がめだちます。まさに明治のインテリという風貌です。こうした外的変化は内的変化の賜物かもしれません。
年表をみてみれば、まさに激動の時代にいきた激動の人物という表現がうかびます。前述のように鈴木大拙95年の生涯、それは日本の近代、その一世紀とそのままかさなるものです。明治のはじまりにうまれた若者が金沢から東京にでて、大学に籍をおきながらも、北鎌倉の禅寺に参禅。そこからアメリカの宗教系出版社で編集者をつとめ、帰国後は学習院や大谷大学で教鞭をとりながら著作を執筆。高齢となっての二度目の渡米。
コロンビア大学をはじめ各国・各所での講演をおこない、90歳を目前としての帰国——金沢と東京、大学と禅寺、日本とアメリカ、日本と英語、パートナーであったビアトレス・レーンはアメリカ人であり神智学を背景にした人物です。鎌倉と京都。アカデミズムと在野。禅と真宗。禅と華厳。亡くなったのはカトリック系の病院である聖路加病院……こうして大拙の人生をみれば、不思議なほど二分されているようにもみえます。
しかし、それがいずれも対立するものでなく、溶解され、ひとつの大拙像がうきあがることも、ならではといえるでしょう。 さて、みためにかぎらず現在、ひろくイメージされる鈴木大拙像はおそらくは晩年の時期のものでしょう。そこにいたるまでの過程をさまざまな宗教・思想という視点からみたのが安藤礼仁による著書『大拙』(2018)であり、また仏教者という視点からみたのが蓮沼直慶の『鈴木大拙 その思想構造』(2020)となります。
これをはじめこの近年、鈴木大拙に関する図書はかなりふえているようにみえます。安藤や蓮沼による研究論文ともいえる内容もあれば、はじめての大拙のようなビギナーむけのものもあり、またマガジンハウス『アンドプレミアム』による2021年の読書案内でも紹介されていました。
僕がはじめてふれた2011年ごろは、岩波や角川の文庫本にて大拙自身の著作いくつかが存在する程度でしたが、このしばらくは様々な性格の大拙関連図書がおおく刊行されています(そしてはからずとも、この大拙の流行は柳宗悦=民藝のリヴァイバルとかさなっています)
大拙はひじょうに英語の堪能な人物でした。そのキャリアのはじまりは英語講師であり、その後は釈宗演の通訳という立場を得ています。1897—1909(27歳から39歳まで)にかけ、アメリカで編集者としてすごしており。帰国後は学習院で英語講師となります。人生の後半生では80歳代をむかえてコロンビア大学をはじめ海外での教育活動にたずさわります(1950—1959、79歳から88歳)ゆえに、鈴木大拙の著作には日本語でかかれたものと、英語でかかれたものが混在しています。
『禅と日本文化』は原題を『Zen and Japanese Culture』としたものの翻訳です。外国人にむけ日本人が記した書物が、翻訳され現在も発刊されているというのは、岡倉覚三『茶の本(The Book of Tea)』とも共通します。 英語につよいかた様々にたずねるかぎり、鈴木大拙は日本語と英語で文章表現が、ややことなるようです。英語は必然的にその言語構造ゆえ、主体があり定義してゆく形式となり、日本語のテキストはむしろ想像力をかきたてるような形式となっている。
両言語を同等にあつかえた人物だからこそ、その特性にあわせてつかいわけをおこなっていた……とも想像できます。それはそれぞれ対象となった読者がいたことを示唆するものですし、それぞれの読者がどのように理解をするのか? という点において把握していた編集者としての手腕なのかもしれません。
鈴木大拙——「未分」
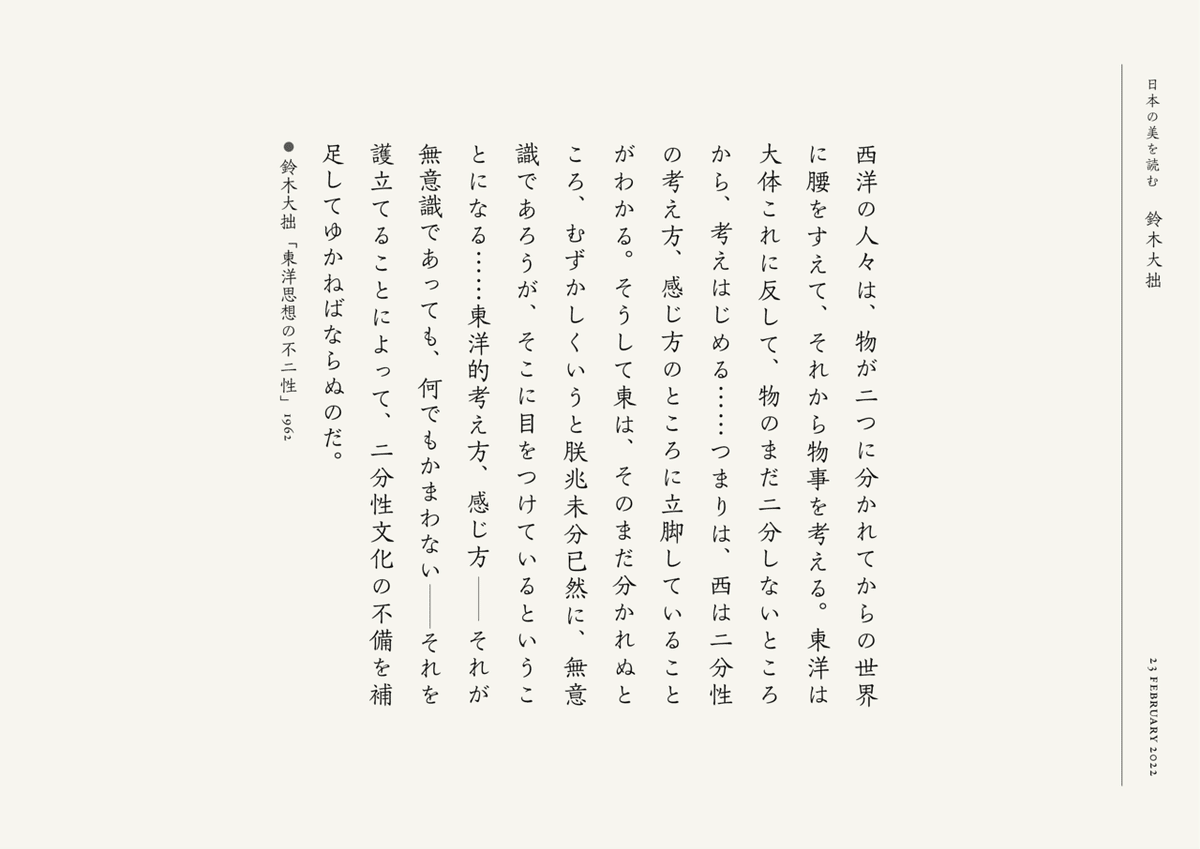
大拙のはなしをつらぬくのは「未分」といえます。二元論ではなく、般若心経にある「色即是空 空即是色」の状態。大拙が指摘するには、西洋の思想の根底には二元論——つまりYes / No、主体と客体を分別することにあるといいます。なお大拙のいう「西洋」は(かなり漠然としてはいますが)おそらくはヨーロッパとアメリカ、それからキリスト教と哲学あたりを指していると推測されます。そしてそこからの発展である科学や個人主義といった「近代」のできごとのようです。
二元論とは白黒はっきりつけるということ。つまり「これ」と「これではない」という判断の状態。判断した結果、YesはNoではないものとなり、たとえるなら白と黒が別物となる状態です。 いっぽうで未分は、それを区別しない。おなじものとなること。YesかNoか。ものごとを断定することはできても、じっさい完全にいいきることはむずかしい。こうした経験はおおくのひとがあることでしょう。つぶさにみれば「ゆらぎ」が存在するのは当然のことかもしれません。白と黒は別物ではなく、あいだに陰影——グレーの階調——を、みいだすことでおなじものとなる。
より精緻にみてゆけば、どこまでが白で、どこからが黒かわけられなくなります。その状態においてもシームレスな連続したもの、ひとつのものとみることもできるし、1, 2……と二元論的に数値化してみてゆくこともできます。あるできごとを「わけて」理解してゆくか、それともひとつとしてみるか。こうして二元論にたいし、未分という視点があることを指摘しているのが大拙のかんがえです。
こんかいの読書会では、チャート資料『読書会「日本の美を読む」資料』を進行の補助とします。こうした区別や構造化がなにより二元的であるのですが、その点はご容赦ください。これは大拙のいう「未分」から、柳や谷崎、あるいは大拙のいう「西洋的なるもの」のキーワードを抽出し、配列したものです。これを参照にしてみます。
「わかる」のもとはわけるであり、西洋知はすなわち分別知といえます。分別がつくようになれば、人間として一人前というものです。ちなみに「あいだ」をみる視点としてレンマというものも存在します。レンマが1で、ジレンマが2、トリレンマが3。ただしレンマに関しては、あいだというニュアンスもあり、それゆえ分別が前提になっているかもしれません。この点、未分とレンマは同様というより、ニアイコールという認識が適切とかんがえます。
未分は「わかれたものをひとつにみる」ということであり、どうじに「わかれる以前をみる」という性質があります。ここでは大拙の「未分」を「色即是空」とつうじるものと仮定し、さらに色即是空を実体たる「色」、メタとしての「空」として整理してみました。 いかにも分別しながらの理解のうながしとなりました。お許しください。
しかし大拙の『日本的霊性』のように、霊性そのものを明解に定義するのではなく、さまざまな要素を参照しつつ「これは霊性ではないか」「これは霊性ではない」というように、周縁をみながら霊性そのものをうきたたせようとするアプローチもあります。やや大袈裟ですが、それを参考にしつつ、こうしていくつかのキーワードをあげながら、大拙の視点をたちあがらせてみましょう。

実体としての未分——谷崎潤一郎『陰翳礼讃』を例に
まずは実態としての「未分」に触れてゆきます。ここでは谷崎潤一郎『陰翳礼讃』を引用します。

ここでは主客が溶けた状態であることがみられます。羊羹そのものが美しいのではなく、谷崎は羊羹があるその状況に着目しています。そして羊羹——漆器——空間、そこにあるさまざまな要素——ひかり——陰影——そしてそれをふくむ人物がわかれることなく、一体となったようすがうかがえます。またそれは人物にとってみれば、視覚にかぎらない経験となります。環境音楽をAmbient Musicといいますが、これはまさにアンビエントな状態といえるのではないでしょうか。

ここで、一枚の絵を参考にしてみます。長谷川等伯による『松林図屏風』。室町時代の制作であり、この読書会であつかわれる時代よりもはるかにふるいものです。しかし「未分」という状態を象徴しているひとつです。
まさに「西洋的な目」の延長である記録術たる写真でみれば、わかりづらいものですが、この『松林図屏風』をじっさいに目のあたりにすれば、不思議なリアリティをおぼえるものです。あたかも、その場にいるような湿度や温度をかんじ、絵と自分の境目が曖昧になります。さむい冬のある日の経験を想起するような感覚。そこにはインスタレーション的な情報量が存在します。
これとほぼおなじころ、西洋ではルネサンスの時代にあたります。ここで成立した遠近法や解剖学はまさに絵画や造形を科学的に構築するこころみです。レオナルド・ダヴィンチによる『最後の晩餐』やラファエロ・サンティ『アテナイの学堂』など、この時代・様式の絵画は、遠近法がもちいられ写実的な描写によるリアリティが追求されています。
しかし遠近法は、鑑賞者がその視点の中心にいなければ正確にみることができません。必然的に絵画と鑑賞者の関係をわけることになります。いっけんすれば、ルネサンス期の美術は、現代的にみてもリアリティある描写をしています。視覚的リアリティといえるものです。しかし、ぼんやりとした『松林図屏風』もまた、ことなるある種のリアリティが成立しているとみることができます。
ルネサンスのころ、レオン・バティスタ・アルベルティによる『絵画論』が発表されています。ここにある「面の上に点が置かれ、点と点を結べば線となり、それの移動が面となる」という趣旨の造形要素の分解と理解は、近代のヴァシリー・カンディンスキーによる体系と通底します。現在でも美術大学や美大受験予備校などでは、造形要素として点、線、面と、その関係性、概念をおそわることからはじまります。おなじくAdobe IllustratorやPhotoshopのような造形アプリケーションにある、レイヤー構造やベジェ曲線、それによるオブジェクトの関係性もまた、その延長にあります。
ルネサンスはコンピュータをつかわないながらも、そのアイデアにおいて非常にデジタル的です——というよりも、デジタルの根源をみてゆけば、ここにたどりつくことになるでしょう これは造形要素を二元的に因数分解してゆき、それぞれを定義しながら、関係性をたばね、構造化しているといえます。
つまりルネサンスから近代造形、そしてコンピュータによる造形は連綿とひとつの線でつながっているものです。まず「面」があり、そのうえに「点」が存在するみかた。つまり、最初の段階ですでに二元的な関係になっています。こうしてみれば、ルネサンスはなにも過去のはなしではなく、現在にも脈々とつづくそれ以降のOSたる存在といえるかもしれません。
いっぽう『松林図屏風』は水墨画です。墨が和紙に滲んでいる状態。墨自体も水とのバランスで濃淡や、にじみ、かすれがうまれます。面のうえの点というより、そもそもその関係が不可分であるのです。そこにある和紙に墨はにじむ。筆のかすれは鍛錬によりある程度コントロールできるようにはなるかもしれませんが、いずれも偶然性がおおく内包されるものです。
作者がえがいているのか、絵それ自体がえがいているのかわからない状態ともいえます。それはつくり手・つくられる側という対立構造ではなく、相互の関係のなかでできあがってゆくものです。絵画と鑑賞者ばかりでなく、それができる段階からすでに不可分なもの。
たとえば、湿度の高い日に、水滴まとわりついたうつわを手にしたとき、ふとなかの水、そのものにふれているような錯覚をおぼえたことがあります。水とうつわ、そして自分がいったいとなるような感覚。実際に湿度が高い日は外気と肌の境目が曖昧になることがある。
谷崎の『陰翳礼讃』は、光と闇ではなく、あくまでも陰影。場と時間がある。羊羹や漆、あるいは厠などなど、そこでは固有のものではなく、それがおかれるたたずまいや、時間をふくめた状況でかたられます。まさにアンビエントな状態といえるのではないでしょうか。
僕自身は、年末になるとよく北陸と京都にでかけます。そこではときおり、水墨画のような景色にであうことがあります。長谷川等伯もまた北陸にうまれ京都にうつった人物です。おそらくこうした風景をみているのではないでしょうか。そして、これを写そうとしたとき、どんな表現が適切かとかんがえれば、しぜんと和紙と墨がおもいうかぶ。水墨画よりさきに、そうした風景が存在していたのでしょう。マテリアルもまた風土に最適化される。

さて、言語や音楽においては音韻と音響の関係が存在します。音韻とは言葉の意味やドレミファソラシドというものです。これはどんな人物や楽器であれ共通する情報です。
一方、音響とはなしかたの癖やニュアンス、楽器個々の音色、それが演奏される場・環境の響きなどをふくめた情報を差します。ルネサンス絵画は音韻的、『松林図屏風』は音響的なリアリティをみてとることができます。
さて、ここで補足として、岡崎乾二郎『感覚のエデン——蛇に学ぶ』を引用します。これは歴史のなか、さまざまな画家にえがかれ、またテーマとなった「楽園追放」についての論考です。イヴに知恵の実をすすめているのが蛇であることに着目してみましょう。
エデンの国には「知恵の樹」と「生命の樹」があって、イヴとアダムは、食べてはいけないと言われた知恵の実を食べてしまう。ゆえに二人はエデンから追放される。旧約聖書の「楽園追放」のエピソードです。知恵の実を食べると直接、真理を認識できるようになる(中略)そして思い起こすべきは、この現世的な場所とは、知恵の実を食べた後に、楽園追放され辿り着いた世界だということです。
そのつど無数に感受されている感覚情報に、それぞれ同等の権利を認めるならば、それらは当然、一つの対象に収束されることもなく、同時に一つの空間や時間に、一緒にあるということもできなくなります。いわば、それらの無数の感覚の間に、真偽の違いも、真実の度合い=ヒエラルヒーもない(中略)けれど17世紀オランダの画家アルベルト・カイプが描いたこの絵をみてください(中略)動物たちがオルフェウスの弾く竪琴の音色に惹かれ近づいてくる。だが、そこにはあからさまな階層がある。彼の側にいるのは家畜たちです。野生になるにつれ動物たちは遠巻きにしている(中略)
当然のように蛇の姿はここには見えません。なぜなら蛇には耳がないから。より正確に言えば、蛇の耳に当たる器官は皮膚内部に埋もれ、蛇は鼓膜も鼓室も持たない。つまり蛇は空気中の振動は聴こえず、地面を通じて伝わる振動しか捉えることができない。だから蛇の感覚はむしろ触覚的な感覚です。さらに言えば蛇は目もよくなく、すなわち五感の分節が明瞭ではないのです。蛇は空気を媒介せず音も視覚も、触覚もすべて距たりをもった感覚としてではなく、身体で直接知るのです。イヴに知恵の実を食べることを勧めたのが蛇であることは示唆的です。
岡崎乾二郎『感覚のエデン——蛇に学ぶ』
近代、人々は視覚優先、つまりいかによく「みえるか?」という点に注力しながら進化したのかもしれません。しかしそれは必然的に「みる立場」と「みられる立場」にわけることとなります。
谷崎が『陰翳礼讃』と同時期、盲目をテーマにした『盲目物語』『春琴抄』を執筆していることは、けっして偶然ではないでしょう。谷崎の『陰翳礼讃』にあるのは、ひかりのあたる部分以外、つまり陰影をみいだしたことはもちろん、そうした視感覚以外も融解し一体化した状態、さらには自分自身と周辺もまた溶け、その場となった状態なのではないでしょうか。
ルネサンスの遠近法や解剖学は、いかにみえるか、あるいは、みえているものは、いかなる構造か?——という問いへの模索であるでしょう。テレビやスマートフォン、カメラといった目の再現たる道具の解像度は日々あがりつづけ、白熱電球から蛍光灯、LEDと人工照明はそれをささえるように光量があがりつづけています。
近年、鉄道のホームをみれば「白杖のひとがいたらサポートをお願いします」という趣旨の告知をみかけます。それは当然のことではありますが、反対にいえば、こうした公共性がつよい施設でさえ、視覚情報優先で整備されていることになるのではないでしょうか。谷崎のはなしにあるように、かつて視覚障害者はもっとちかいところにいたのかもしれません。
かんがえてみれば、視覚は五感のなか、もっとも主体性のつよい感覚かもしれません。おなじ場にいれば、においや音はおなじように共有できるけれど、視点においてはそれぞれの立場にわかれてしまう。
さて大拙は、西洋には二元論的な発想があるからこそ、数学や化学・科学が発展したと指摘しています。いわく「分けて制する」ことです。分析分類しながら体系立てることは、まさに二元的思考の面目躍如といえます。
谷崎は『陰翳礼讃』において「西洋のほうは順当な方向を巡って今日に到達したのであり、我等のほうは優秀な文明に逢着し……」という。西洋の順当な方向というのは、まさに西洋の神が「光あれ」と光と闇、神と人を分別したゆくすえであり、禁断の果実を口にしたあとの世界といえるでしょう。もちろん、これはどちらがすぐれているとか、そうしたことではなく、単純に性質の異なるものであるととらえてください。
環境——EnvironmentとAmbient
実態における未分。そこでは場、つまり環境をどうとらえるか? ということについてのかんがえる必要があります。環境問題というと、環境を保護する立場としての人間という具合になりますが、そうなると環境と人間の対立構造がみえてきます。バウハウスにまなび、その後、オトル・アイヒャーらと1953年にデザイン学校 ウルム造形大学を設立し学長職についたマックス・ビルの発言を引用します。
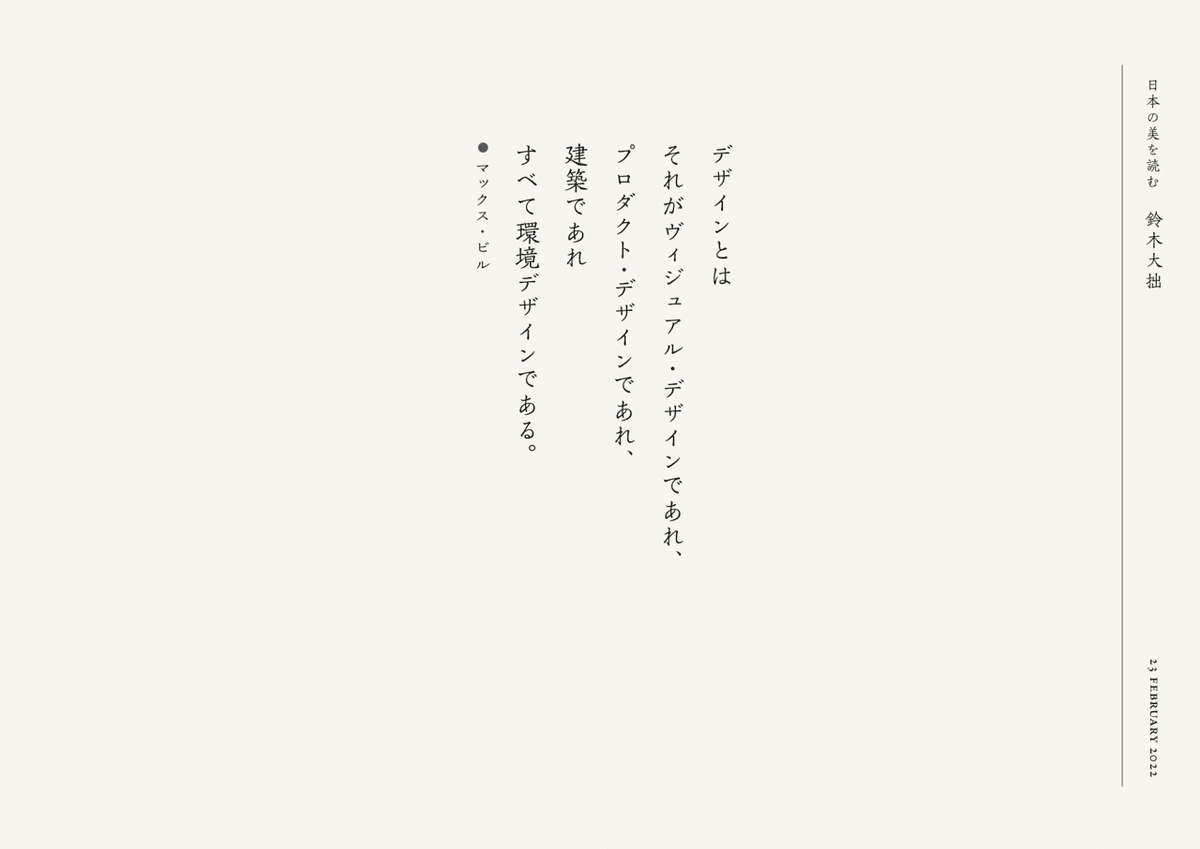
バウハウスでは、同心円状にカリキュラムがしるされ、さまざまなデザインの総合としてビルディング、つまり建築が指標とされていました。ビルのいう環境はそれをより拡張したものというみかたができます。
つまり、人間を中心としながら、家具があり、建築があり、都市がある……というような同心円状の環境です。ちょうどビルの活躍した20世紀なかば、日本をみれば丹下健三とその研究室が東京計画1960をかかげ、建築の拡張として都市をデザインの対象としていました。
近代デザインをみれば、アーツアンドクラフツによる家、バウハウスによるビルディング、そしてビル——ウルム造形大学における環境と、その対象範囲が明確に拡張しています。そして、そこでは環境をつくる立場である人間と、つくられる立場である環境という主従関係がうきぼりになります。では大拙はどのように環境をとらえていたのでしょうか。



大拙のいう環境は人間もまた環境のひとつであるというみかたです。まさに未分といえます。ビルの環境がEnvironmentであれば、大拙はAmbientと認識するのが適切かもしれません。環境問題はEnvironment Affair、環境音楽はAmbient Music。Environmentは外的環境というニュアンスがつよいものです。
それにたいしAmbientは対象化されない環境といえますし、それは『陰翳礼讃』の羊羹のくだり、あるいは『松林図屏風』の状態であり、和辻哲郎いうところの「風土」という範囲でもあるでしょう。
例えばゴスペルのように、何らかの場所を伴った音楽に一層興味がある。聞き手は、目当ての音楽を体験するためにはある場所に赴いて、そこの一部にならなくてはならないような音楽だ。そこで人は、全く異なる社会的・音響的な設定の中に入る。
その音楽を包む、完全な背景が存在する。 ちょうど光の色や雨の音が環境の一部となるように、環境の一部として音楽を聞くという方法だ。
ブライアン・イーノ
アンビエント・ミュージックのパイオニアであるブライアン・イーノのインタビューから引用しました。中心性をもち対象化された環境と、一体化した状態としての環境のちがい。イーノは音楽家ゆえ聴覚的なところからはなしがはじまりますが、『陰翳礼讃』つうじてくるのではないでしょうか。
メタとしての未分——民藝を例にして
「未分」を具現化した例が『陰翳礼讃』だとすれば、意識、つまりメタとして具現化するとどうなるか? その一例が民藝になるかもしれません。
大拙の教え子であり、生涯の交流がつづいた柳宗悦を代表するものです。民藝というと、日本民藝館所蔵の品々や濱田庄司の作陶、芹沢銈介の染色……など、具体的なものを想起するかもしれませんが、ここではその意識下に通底する民藝の姿勢についてふれます。まずは宗悦の集大成ともいえる『美の法門』から引用しましょう。
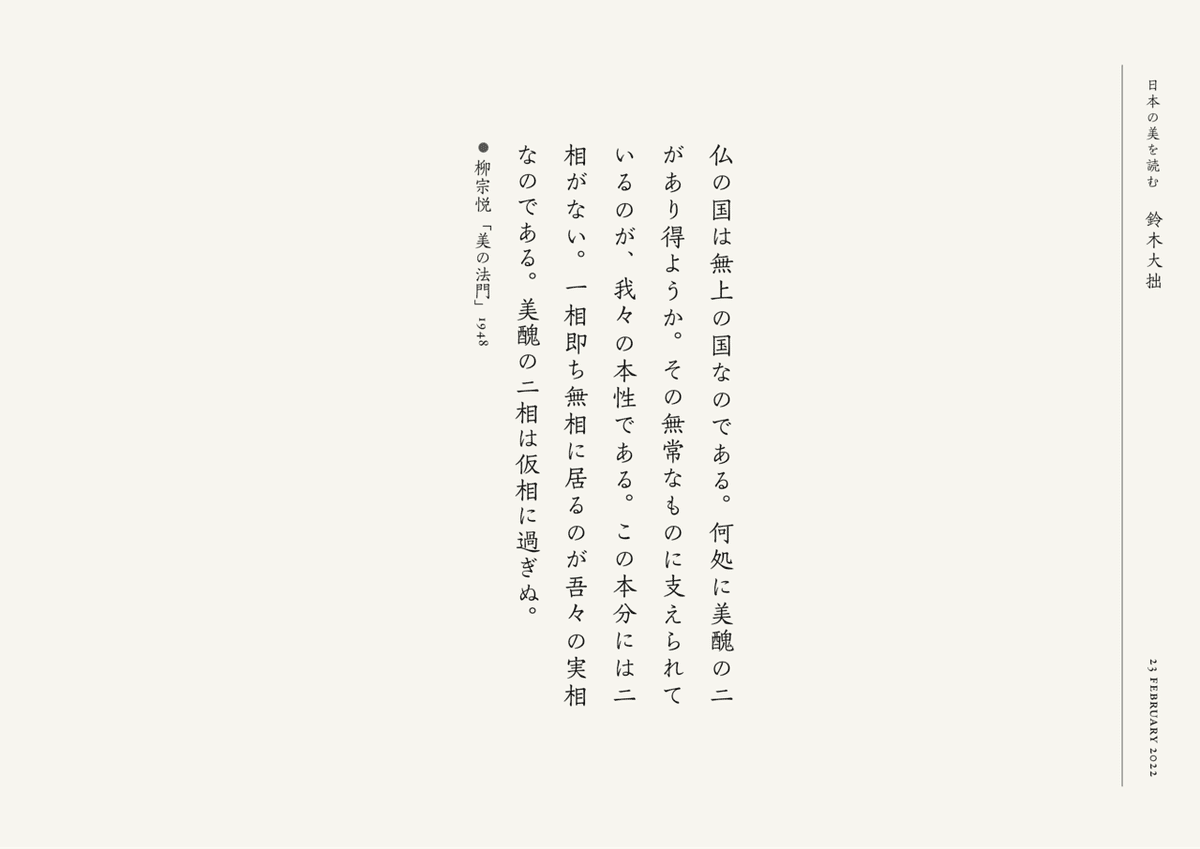
つづいて再度、大拙による『東洋思想の不二性』を引用します。
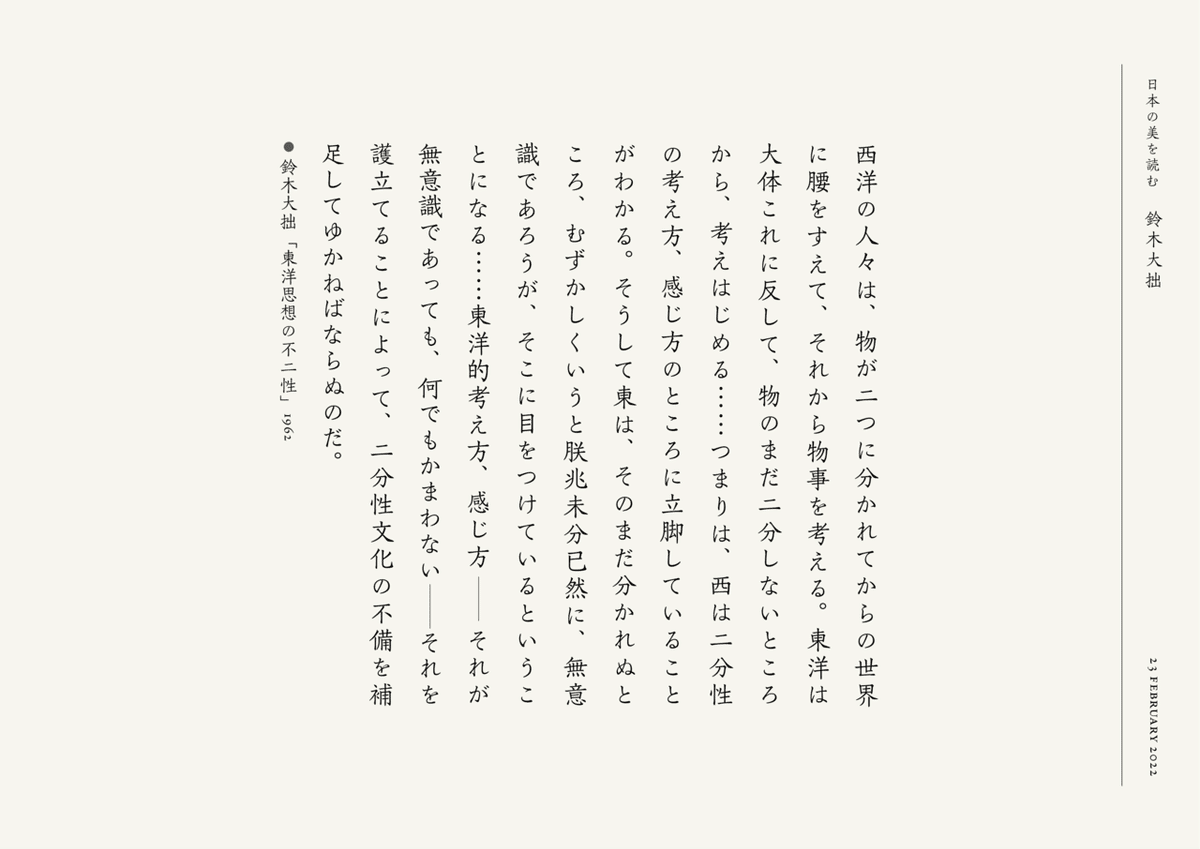
「未分」というものが、なんとなくつかめるかもしれません。柳と大拙のことばはかさなるところがおおい。ぜひ『美の法門』と『日本的霊性』をよみくらべてみてください。
民藝を象徴することばに「用即美」あります。しばしば「用の美」という言葉もみられるが、近年、指摘されるよう、その語の存在について疑問がのこるものです。じっさい「の」「即」と、接続が変化するだけで、意味がかなりかわってしまいます。 「即」というのは、仏教的な視点でみれば、ことなるふたつのものをつなぐレンマ的なものともいえるし、それらを同一視、さらには、ふたつのものがわかれる以前をみる未分ともいえます。
まさに「色即是空 空即是色」の視点です。つまり用即美であれば、「用」と「美」は不可分であるということになります。いっぽうで「用の美」となると、つかわれるものが美しい、あるいは機能的なものが美しいというように「用」と「美」の関係が二分され、そこにヒエラルキーがうまれてしまう。柳のはなしを追ってゆけば「用即美」という見方のほうが、それらしいものとかんがえられます。
日本においては近代化のなか「美術」という言葉がうまれることで、それまで存在しなかったヒエラルキーが生じることになりました。鑑賞される対象たる「美術」として、西洋画、彫刻、書、日本画が、そのつぎに鑑賞される「工芸美術」として、陶芸、木漆竹工となる。そして最下層として「工芸」日常雑器、手工品があるという図式です。
近代化のなか西洋的な芸術の概念と手法が輸入され、それ以前から日本に存在した種々の造形とともに整理する必要がうまれました。その結果として鑑賞される対象たる美術が上位にあり、ふだんづかいのものは下級のものとなる分断をうむことになりました。
しかし、鑑賞される対象としてのヒエラルキーは結果として、鑑賞物と鑑賞者の関係に分断することをより強固なものとしてしまいます。日常雑器はそのつかい手と一体化し、しだいにつかい手の身体感覚がデザインされてゆくことになる。
つまり、用と美は不可分——「即」の関係になります。つかうことと、そこに美しさを見出すこと、さらには人とものの関係を同一化する「即」というみかた。これこそ民藝を象徴することばであり、大拙のいう「未分」の状態ではないでしょうか。柳が民——民藝をみいだしたのとおなじように、大拙は妙好人という市井のひとびとの信心に日本的霊性をみいだしています。
つづいて柳による文章『工藝的なるもの』を引用します。
今仮にバスに乗ったとする。そうして車掌に行く先を告げて、どこで降りたら一番いいかを尋ねたとする。謂わば個人的な問いである。彼女は普通の言葉で私に答える。それは並の会話に過ぎない。だが一旦与えられた公の任務に戻る時、彼女は急に抑揚のある言葉遣いを始める。「お降りの方は御座いませんか」とか「曲がりますからご注意希います」とか、「次ストップ」とか韻律的に言葉を使う。
柳宗悦『工藝的なるもの』
ものとしての工芸というよりも、まさに動詞的な「工藝的なるもの」。バスの車掌をいう例はやや唐突な展開にもみえます。しかし、ここではバスの車掌にある「おおやけ」性がうかんできます。
モノマネできてしまう鉄道関係者のアナウンスにある独特の抑揚。それは個々の声ではなく、ある集団を象徴する公的な声といえます。柳はこの文章のなか、ほかに理髪屋の鋏の調子、線路工夫の掛け声、銀行員のお札の数えかたなどを例にあげています。つづきましょう。
仕事が玄人の手に渡ると、それぞれにこんな調子が出てくる。一寸考えると無駄なようだが、実はそれが一番無駄のないやり方である。かかる動作を私は「工藝的なやり方」と名づけよう。落ちつく所に落ち着いた形である。
柳宗悦『工藝的なるもの』
ある集団のなか培われ、洗練されてきた所作と、そこから生まれるリズム。結果として顕在化したものと、それをうんだ背景。そしてそこにある、ものとひととの関係——こうしてながくひろい尺度でとらえることが、民藝を咀嚼するヒントなかもしれません。
ひとりの個人ではなく、ながいながい時間のなかに存在する、ある点。僕たちが存在するのは、そうした場です。 ほかの人物を引用してみよう。昨年出版された内藤廣『建築の難問 新しい凡庸さのために』からです。
たとえば知事さんでも市長でもいいですが、どこかの政治家がやりたいと言ったからといっても、ほんとうのクライアントは目の前にいる人ではなく、背後にいるその政治家を選んだ人たち、さらに過去、現代、未来のわたしと会っていない人たちです。 (中略) 大切な何かを決めるときには「その会議に死者を召喚しなくてはならない。
内藤廣『建築の難問 新しい凡庸さのために』
つづけてもうひとつ引用をします。キング・クリムゾンのベーシスト トニー・レヴィンが昨年の来日公演時にしるしていたブログ記事です。
仲間たちの亡霊
今回のツアーは、バンドの最後の日本公演として発表されてますが、キング・クリムゾンの最後のツアーである可能性が高いです。そしてそれは、52年の歴史の中でバンドの音楽に影響を与えてきた、生きている人も死んでいる人も含めたプレイヤーたちの亡霊が宿っているようです。僕にとっても、このバンドに参加して40年になりますが、そこにはかつての今と異なるか、あるいはそれよりもっと今と同じような自分の亡霊もいます。そして、そこには僕より前にいたベーシストたちがいて、長年にわたって僕が関わってきた象徴的なパートを作ってくれました。彼らもここにいます。
また、別の種類の亡霊も存在します。40年前にここで一緒にツアーをした青年、ロバート・フリップは、コンサートでも旅先でも、僕の目の前で導いたり叱ったりする存在です。その存在は、現在のロバートと同じくらい鮮明です。昨晩、最後から2回目の公演で、僕のステージの向こう側にいたのは、今のロバートだったのか、それとも35歳のロバートだったのか。スツールに座り、同じように直立した姿勢で、少し違った眼鏡をかけて、演奏しながらバンドを見守り、それぞれの曲に新しい命を吹き込み、少しでも新しい方向に持っていこうと努力していたのです。あるいは、ステージ上にはその2人のプレーヤーがいて、若い彼が方向性を示し、年配の彼が経験の知恵を加えているのでしょうか。
トニー・レヴィン
大拙を把握するために、柳に民藝、岡倉、内藤廣、そしてプログレまで引用することとなりました。死者や亡霊とことばにすれば、どうしても胡散くさくなってしまうが、しかしいわんとせんことは明確になるとおもいます。
ひとの痕跡というのは脈々とつがれてゆくものであり、みずからもまたおおいなる過去のひとつとなりながら、またつぎの時代にのこってゆく。まさに「工藝的なるもの」あるいは「即」であり、大拙のいう「未分」や「妙」「不二」というものにつうじてゆく。すこし事例をあげながら整理します。
「かた」と「うつし」——脈々とつづく文脈
ある「かた」があり、その「うつし」が脈々とつづきながら、ながい時間と時代のなかで、最適化されてゆくこと。たとえば音楽教育であれば——それがクラシックなら、バッハやブラームスなど古典とされるものが、演奏家同士においては演奏経験が共有され、作曲家であれば基礎となる研究対象として、その「かた」を咀嚼していることでしょう。
あるいはジャズであればチャーリー・パーカーにマイルス・ディヴィス……というように世代ごと、あるいは楽器ごとにその対象があります。それは料理においてもおなじでしょうし、ほかさまざまな芸事においても共通します。自明なる「かた」が存在し、それは集団や領域を象徴する記号となってゆきます。初学者はそれをインストールしながら、ある種の同一化をしてゆき、そしてまたつぎの世代へとひきついでゆきます。
文字に内包される「声」
たとえば活字書体、そしてそれをあつかう技藝たるタイポグラフィを例にみてみましょう。現在はPCにインストールされたデジタルフォントをもちいるが、そこにある活字書体、そして組みかたの作法は、いずれもそれ以前の写真植字、さらには金属活字の時代から脈々と培われたものでです。
そして、文字のかたちそのものは手書きの時代にまでさかのぼります——石や木に刻まれたもの、ペンで書かれたもの、あるいは筆で書かれたもの——こんにちの活字書体のかたち、ひとつひとつにさまざまな時間と習慣が内包されているのです。

最初のタイポグラフィであったグーテンベルク聖書が、それまでの写本聖書の模倣であったというのは示唆的です。ほかにもエミール・ルーダーの主著『Typographie——A Manual of Design』をみれば主要なローマン体であれ、イギリスのCaslon、フランスのGaramond、イタリアのBodoniでは、それぞれの生まれた言語のもつリズムに最適化されていることがわかります。
もちろん、なにも伝統や地域、風土に固執することが目的である必要はありません。しかしそれらは、必然的に結果をつかさどる巨大なものであることも、また事実なのです。文字や活字書体であれば——ある特定の時代や地域、あるいは集団の「声」を内包し可視化したものといえるでしょう。
こうした「かた」に込められた時間と公性は、まさに「工藝的なるもの」であり、それはそれぞれが「即」となり「未分」となった状態といえます。

河井寛次郎のこの言葉は、まさにそうした状態を適切に表現しているかもしれません。 さて、大拙は芭蕉とアルフレッド・テニスンを比較しながら、そうした一体性について説明をしてみます。すこし引用してみましょう。
よく見れば 薺花咲く 垣根かな
松尾芭蕉
壁の割れ目に花咲けり
割れ目より汝を引き抜きて
われはここに、汝の根ぐるみすべてを
わが手のうちにぞ持つ
おお小さなる花よ
もしわれ、汝のなんたるかを
根ぐるみも何もかも、一切すべてを 知り得し時こそ
われ神と人のなんたるかを知らん
アルフレッド・テニスン
テニスンが花を引き抜いて、彼の手のうちに握って、おそらく意識しながらそれをじっと見つめて、お前の ‘根とすべてをわしは握っている’ と言う。彼にもちょうど芭蕉が道ばたの垣根の薺の花を目にとめた時の感興と大いににたようなものがあったようにも見える。しかしこの二人の詩人には次のような相違がある。芭蕉は花を引き抜きはしなかった。ジッとよく見ているだけ。彼は考えにふけった。彼のこころは言うに言えぬ何かを感得するけれども、それを言葉には出さない。ただ一個の詠嘆詩 ‘かな’ に自己のいっさいの感慨を投入して、これにすべてを語らしめる。彼は言うべき言葉を知らぬのである。
知らぬというのは、彼の感があまりにきわまって、深くてしかも深いということさえも覚えぬほどだから、これを概念に盛り上げようというような気持ちすら起こらぬのである。テニスンのほうはどうかと言うと、これは行動的で、分析的であると言える。彼はまず花をその生えている場所から抜き取る。……花にとっては大切な土からその花を引き離してしまう。これは東洋の詩人とはまったく別の行き方といえよう。
鈴木大拙
自他の「未分」、その範囲や状態というのがなんとなくおわかりいただけるかもしれません。ほかの事例をみてみましょう。
消費的に「ピカソの絵っていいよね」と終わる前に、ピカソの人生を追っていったら、四次元思考の話に行くし、当時の数学によって空間の捉え方が変わったこともわかる。(中略)ピカソを知ろうとするだけで、めちゃくちゃ教養が必要になってしまう。 好きなものを外側から見て消費するんじゃなくて、まずは自分の内側にピカソを取り入れて、自分がピカソになる。それだけで身体が複雑になっていかざるをえない。そのプロセスさえ始まっちゃえば、どんどん自分が変化していく。
上妻世海インタビュー『制作的身体のためのエクササイズ』
おもわず西田——柳——大拙のはなしがうかんできます。はなしの前半で大拙の年表を参照にしましたが、大拙自身もまた時代のなか、時代や環境にとけ、またさまざまな人物のかんがえが一体化しながら、みなのしる大拙の姿となっていったことがわかります。
大拙がその思想をしるした書物の刊行をつづけるのは、西田が没してからというのは象徴的です。ほか、教え子である柳宗悦もまた大拙のなかに一体化しているでしょうし、かずかずの哲学者や歴代の仏教者や宗教者、そして妙好人まで、さまざまなひとが溶け、大拙ができあがってゆく。つまりなにより、大拙自身が「未分」であり「即」を体現したひとなのではないでしょうか。
モダンデザインの人物が岡倉覚三『茶の本』を引用したり、アメリカではビートニクが禅を参照したり、あるいはグレン・グールドが『草枕』をよんだり、ジョン・ケージが大拙の講義をうけたり、ジャン・ヌーヴェルが『陰翳礼讃』からの影響を公言したり——と。方面はことなれども、こうしたいわゆるモダニストのつくり手たちが、こうした界隈に惹かれていたのは不思議です。日本の近代化は西洋化でありましたが、一部の西洋にとっての近代化は東洋化であったのかもしれません。
シュタイナーやベルクソン、あるいはブレイクなどにあった超人間的な視点の下地があったことがおおきく、しだいにそれらが内包するある種のカルト性が希薄な——つまり西洋的視点でみれば宗教ではなく哲学にみえるであろう——東洋の思想に着地したのではないか?とも想像することができます。そして、この構図は大拙や柳悦の思想の変遷ともかさなるところがあります。
興味ぶかいのは西洋のモダニストたちにある、そうした東洋的な視点の影響が、わりあい可視化されるところ、つまり表現として如実にみえることです。西洋のモダニストが東洋的なるものをかたるとき「その状態をみている自分」という視点がある傾向も顕著です。
たいして、柳=民藝は形而上にそれがあることが特異点といえるでしょう。造形物でありながら、具現化する造形物は多種多様であり、そのプロポーションがみえづらい。しかし、むしろメタ的なところをみれば、そのステイトメントがうきぼりになる。
前述のように、日本国内のデザイン教育でも『茶の本』や『陰翳礼讃』は引用される機会もおおいものですが、どこか西洋のモダニズムに親和性があるもの……というとらえかたをされているようにもみえ、その解釈は逆説的に西洋知に東洋が飲みこまれている構図がうきぼりにもなります。哲学のなかに東洋哲学があるという構図ではなく、ことなるところに「東洋的な見方」が存在すること。大拙や柳がめざしたところは、そうしたもののはずです。
「未分」に象徴される大拙の思想は、まさに東洋の思想の根幹であり、さしずめOSといえるのではないでしょうか。大拙は「禅には何ら時代性なるものはない」と発言しつつ、どうじにそのどの部分が時代に適応するかは変化すると指摘しています。大拙の思想にもまた時代性はなく、それぞれの場面で響いてくるものではないでしょうか。大拙をはじめとした今回の読書会シリーズの面々、そしてその背景にあるものに今日性をみいだすことが、読書会をおえたいまたちあがってくる、これからの課題なのかもしれません。
—
23 February 2022
中村将大
於: minagarten
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
