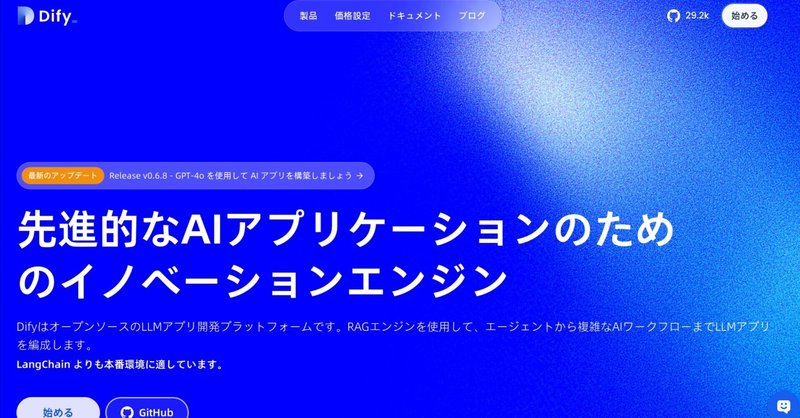
君はDifyを知っているか?ノーコードでチャットボットを作成できるDifyがアツい🔥
記事はポッドキャストでも配信しています。音声で聴きたい方はこちら。
🍎Apple Podcastで聴く↓
Difyとは?
Difyを簡単に説明すると、ノーコードでチャットボットを作成できるプラットフォームです。
ノーコードとは、プログラミングでコードを書かなくても利用できることを意味します。チャットボットとはChatGPTのような人間と会話できるものをイメージしてください。

Difyの背景と人気の理由
5月頭位から特に日本で大きな注目を集めています。
ただ、Difyは今年の5月に急に出てきたサービスではないんですよね。
2023年3月にチームが結成され、2023年5月11日に最初のバージョンがリリースされました。
面白いのが、日本での人気も公式は把握していること。日本人専用のDiscordチャンネルを開設したほどです。
Difyに関する投稿をSNS検索すると日本人の投稿が目立ちます。
運営企業と商用利用
Difyはアメリカのデラウェア州に登記されたLangGenius社によって運営されています。同社のCEOはLuyu Zhang氏、共同創業者にはRichard Yang氏が名を連ねています。
開発メンバーの多くはテンセントクラウドにいたメンバーが多数を占めるしいです。テンセントはWeChat(LINEのようなアプリ)を開発する中国企業ですね。
ちなみに、Difyは商用利用も可能です。
一部の利用条件がありますが、基本的には商用利用OK。個人プロジェクトや業務としても利用できます。
Difyの利用方法
Difyは主に2つの利用方法があります:
セルフホスティング方式:Difyはオープンソースとして提供されており、ユーザーは自分のパソコンにダウンロードして直接利用可能。
公式サイトからの利用:Difyの公式サイトにアクセスし、無料版では200メッセージまで利用が可能です。有料版の料金は月額59ドルからとなっています。
環境構築の手間を考えると、圧倒的に公式サイトからの利用が簡単ですね。
月額59ドルと聞くと個人では高いと感じてしまいます。しかし、企業がチャットボットをホストして、なおかつノーコードで作成できることを考えると月額59ドルというのは決して高い金額ではないと思います。
仮にチャットボット開発を委託しようとすると、結構な金額がかかってくると思います。
チャットボットをサイトに埋め込み可能
Difyを利用することで、例えば企業が自社のウェブサイトにカスタマーサポート用のチャットボットを簡単に組み込むことができます。
会話履歴を管理できるため、顧客対応の質を向上させることも可能です。
例えば、ユーザーがBadを付けている会話があるとします。(ユーザーは回答にGood, Badのフィードバックが可能)
こうしたケースでは、「この問い合わせに対してユーザーは不満を感じているな…よし、この案件は人間で巻き取ろう。改善しよう」という判断も出来るわけです。
Difyの活用事例
ECでの活用
例えば、あなたがオンライン特化のアパレルブランドを経営しているとします。
今までのカスタマーサポートはメールや電話による対応でしたが、Difyを用いてサイト内にチャットボットを導入する選択肢も出てきます。
カスタマー対応の第三の選択肢としてAIによるチャットボット対応も実現できるわけですね。
例えば、配送オプションや返品ポリシーに関する一般的な質問にチャットボットが自動で回答することが可能です。
実際にはRAGという仕組みを利用してAIが知らない回答にも対応できるようカスタムできます。
社内wikiとしての活用
企業内でDifyを活用する一つの方法として、社内wikiの機能を強化することがあります。
社内の様々な手続きやポリシーに関する質問に対して、チャットボットが即時に回答を提供します。
社員の時間を節約し、業務の効率を向上させることができます。
例えば、新入社員のマニュアルや領収書の手続き、年末調整などの質問はAIが対応するようにしても良いと思います。
自治体での活用
自治体がDifyを利用しても面白いと思います。
例えば、各種証明書の申請方法に関する一般的な問い合わせをチャットボットが担当することで、窓口の業務負担を大幅に軽減できるのではないでしょうか。
AIが対応できない案件は今まで通り人間が対応すると。ただ、簡単な問い合わせはAIが対応すれば利用者も自治体側も改善できるのでは?と思います。
仮に運用する場合、個人情報を入力させない範囲で巻き取るなどチューンしていく必要があると思います。
プログラミング知識のゼロでもチャットボットを作れるか?
Difyがバズった要因として非エンジニアでもチャットボットを作れる、という点が評価されたと思います。
プログラミング知識ゼロでもチャットボットを作れると。…果たして、そうでしょうか?
この点に関して、私はケースバイケースと感じています。
要約すると、プログラミング知識ゼロでも(簡単な)チャットボットを作成できる。でも、プログラミング知識があればより高度なチャットボットを作れる、と感じました。
変数、条件分岐、APIの理解、この辺は抑えておきたいところですね。
Difyを業務利用する際の注意点
業務利用する場合には個人情報や機密情報に関する取り扱いも注意する必要があります。
入力された情報を学習させないモデルの選択などですね。
ちなみにDifyではDify Premiumというサービスも用意されています。
これはAWS上でワンクリックでデプロイ(公開)できるDIfyのAWS製品です。
Dify側で業務利用を想定した受け皿も用意されているので、会社での導入を検討している人はカスタマーに問い合わせると良いと思います。
私もプライバシーポリシーに関して質問しましたが、回答まで5時間もかからず返答がありました。
企業がAIを導入する際に注意したいポイント
組織がAIを導入する際には何に注意すべきか?という点もじっくり考える必要があります。
AIを導入すれば業務効率が改善することに目を奪われがちです。
しかし、AIを導入することのリスクにも注意を払いたいところ。
日本ディープラーニング協会が発行する生成AIの利用ガイドラインを一読することをおすすめします。
生成AIの活用を考える組織がスムーズに導入できるよう利用ガイドラインの雛形を公開しています。
色々と書きましたが、1番は実際に触って試してみる。
個人(もしくは会社)で活用できそうであれば、導入を検討してみる。これに尽きますね。
Difyは無料で試せるので気になる人はチェックしてみてください✌️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
