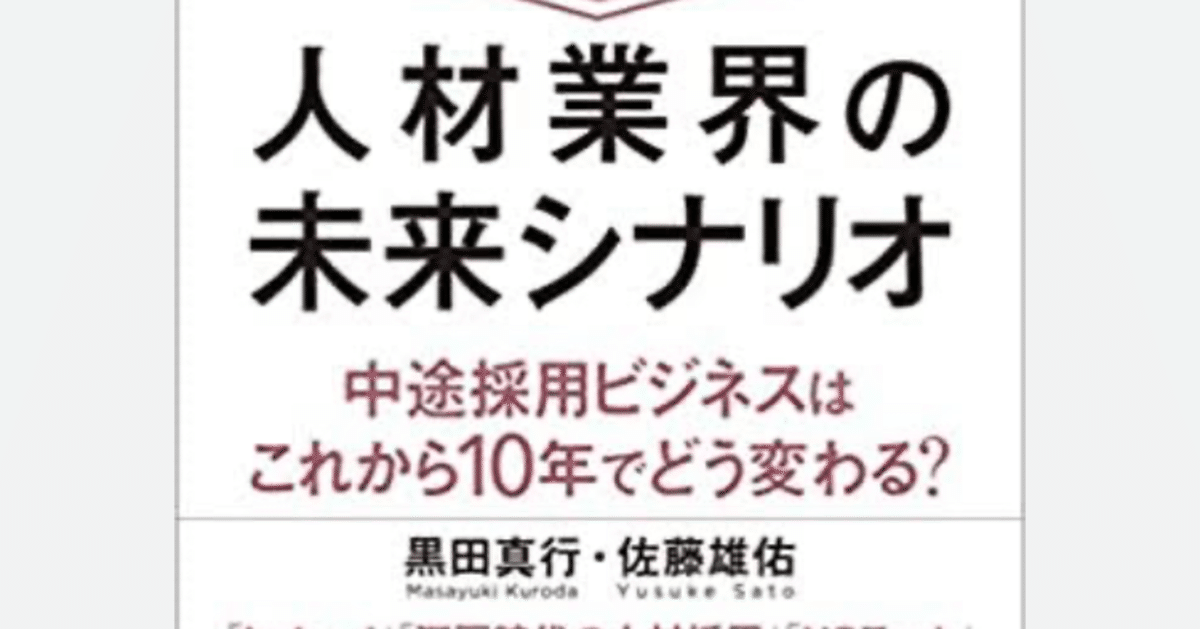
人材業界の未来シナリオ
こんにちは、Rです!今回は「採用100年史から読む人材業界の未来シナリオ」を要約しました。
人材業界の過去、現在、未来をまとめた一冊です。
著者について
黒田真行[クロダマサユキ]
1988年、リクルート入社。2006~13年まで転職サイト「リクナビNEXT」編集長。2014年ルーセントドアーズを設立、成長企業のための「社長の右腕」次世代リーダー採用支援サービスを開始。35歳からの転職支援サービス「Career Release 40」、ミドル・シニア世代のためのキャリア相談特化型サービス「CanWill」を運営している。
佐藤雄佑[サトウユウスケ]
株式会社ミライフ代表取締役。新卒でベルシステム24に入社、マーケティング業務に従事。リクルートエイブリック(現リクルートキャリア)に転職。法人営業、支社長、人事GM、エグゼクティブコンサルタントなどを歴任。MVP、MVG(グループ表彰)などの表彰を多数受賞。リクルートホールディングス体制構築時には、人事GMとしてリクルートの分社、統合プロジェクトを推進した。2016年にミライフを設立し、働き方改革事業、戦略人事コンサルティング事業などを展開している。
人材業界の100年
ざっとまとめるとこんな感じ。
1873年:明治6年。学制の施行。財閥企業の三菱が新規大学卒業者を定期採用したのが新卒採用の始まり。
1911年〜:第一次世界大戦の大戦景気で雇用が増え大人で人手を賄えなくなり小中学生の採用へ。ポテンシャル採用して社内教育するスタイルが定着。就社型・総合職採用の原型といえる。
1928年:戦後恐慌。就職難の学生が学業を疎かにして就職活動するようになったため、採用試験は卒業後にするものと規定された。新卒の一括採用の始まり。
1960年〜:オリンピック・大阪万博・バブル経済。人手の奪い合い→人材ビジネスの誕生
現在:人材ビジネス戦争期。人材紹介、人材広告、人材派遣、アグリゲーション型、SNSなど多様化。
ちなみに江戸時代は縁故採用がほとんどで、縁故がいない人は職にありつくのも難しかったそう。都市部においては、口入れ屋と呼ばれる職があり、奉公先の紹介や身元保証と交換に、給料の一部を仲介料として受け取ると言うビジネスをしていたようだ。
求人広告の誕生
1960年:江副浩正氏が東京大学の学生新聞である「東京大学新聞」の広告代理店「大学新聞広告社」(現・リクルートホールディングス)を創業。
1967年:学生援護会(現・パーソルキャリア)がアルバイト専門の求人広告として『アルバイトニュース速報』を創刊。
1975年:リクルートが正社員の中途採用求人を集めた『週刊就職情報』を創刊。正社員中途採用の広告メディアビジネスの起点
1960年以前の学生はどのように求人を探していたかというと、大学の学生課に張り出された求人票をいちいち見に行っていたらしい。そういえば、1970年代に生まれた私の母も、就活時は壁に張り出された求人票を見て電話をかけて面接のアポを取っていたと言っていたような。今ではネットが主流なのでキーワード検索などをして簡単に職探しができるが、そんな風に便利になったのも割と最近のことなんだな…
人材紹介の誕生
江戸時代:人材紹介の元となる口入れ屋という職業があった。この時点では法整備はない。
明治時代:工場化が進み労働力がさらに必要になると、人材紹介における強制労働や差別などの問題が出てくる。そこで国から法令が制定され、人材紹介の基本的なルールが設定された。
1947年:昭和。職業安定法の制定。これにより、人材紹介業に厳しい規制が課されるようになる。「職業選択の自由」「採用募集における差別禁止」「守秘義務」など、現在の人材紹介のもととなるルールが規定された。
人材派遣の誕生
1948年:アメリカで2人の弁護士が人材派遣会社、マンパワー社を創業したことから一気に広がる。日本では明治時代から人の送り込みは存在していたものの、過剰な中間搾取や劣悪な労働環境が問題視され規制がかかっていた。
1966年: マンパワーグループが日本陸上することをきっかけに法整備が進む。
1973年:国内で初めての人材会社、テンプスタッフ(現パーソルグループ)が成立。
ちなみに、高度成長期には終身雇用と年功序列が一気に広がったことで、新卒で入社した会社を一生勤め上げるのが当たり前という時代が来る。途中でやめる人は根性なしの負け犬という考え方が一般的であったことから、中途採用市場が広がりを見せられずにいた。1976年から1984年まで『就職情報』編集長を務めた元リクルートの神山陽子氏はこう語っている。
一度会社を辞めると「脱落者」のように見る社会の目を変えたいという気持ちが強かったですね。新聞の求人欄では「給与は委細面談」としか書かれていない情報の圧倒的乏しさや新卒と中途の間にある待遇格差。堂々と転職できる世の中を作ろう、「明るい転職」が当たり前にできる国にしよう、という合言葉をもとに、事業を作っていきました。
現在と2030年の働き方
黒田氏は人材業界の今後を語る上で重要な要素となるのは、少子高齢化とテクノロジーの進化だと語る。
①少子高齢化
少子化と同時に高齢化、つまり「人生100年時代」に本格的に突入していくわけですが、その時には、20歳前後で働き始め、70歳以上のリタイアまで職業寿命が50年を超える世界を迎えます。 一方で、(中略)倒産企業の平均寿命も20年程度と言われており、今後も増々短縮する可能性が高くなります。となると、人が働く職業寿命が50年に対し、企業寿命が20年程度なので、当然これまでのように終身雇用で一社でキャリアを全うすることは難しくなってくるといえます。
②テクノロジーの進化
野村総合研究所の試算によると、日本の就業者のうち49%が人工知能やロボットなどで代替可能としており、テクノロジーによって仕事がなくなるのではないかとも言われています。(中略)今の保有スキルだけでは、その先長い期間働いていくことは難しく、スキルが陳腐化しないよう、変化していくことが求められます。
この2つをふまえて、黒田氏は
・一社で長く勤めるのが美徳
・企業が会社内で従業員のキャリアを考える
と言う時代から
・いろんな会社で多様な経験を積んだひとが評価される
・個人個人が主体的にキャリア形成をする
と言う時代になると予測している。
リクルーティングビジネスの方向性
少子高齢化により求職者の母数が減っていく中で、優秀な人材を採用したいという企業のニーズに応えるには、求職者ニーズに応えて人を集めることが最重要になってくると黒田氏は言う。
これまでのビジネスモデルは、大量に採用する企業に大人数を送り込むような「B to B to C」モデルであった。
しかしこれからはそもそもの求職者のパイが減って人材獲得が難しくなり、より多様な価値観や志向を持つ求職者ニーズに応えられるビジネスモデルに変えていくことが求められる。そこで黒田氏はこれからのリクルーティングビジネスは、「B to C to B」に変わって行くと予測している。

また、採用ターゲット別におけるチャネルは下のように変化していくと予想している。
経営層やマネジメント層の採用は人材紹介メインが続く
即戦力プレイヤー・若手プレイヤーは業界再編バトルが始まる
経営層・マネジメント層が人材紹介メインのままになる理由は、この領域は求人を非公開で進めることが多くインターネット上に求人が公開されることは少ないから、採用にはスキルやカルチャーフィットなどを丁寧に把握する必要があり人が介さないと難しいからだ。
一方即戦力・若手プレイヤー領域においては、求人広告や人材紹介と、ソーシャルリクルーティング、アグリゲーション型求人検索エンジン、そして無料チャネルのリファーラルリクルーティングが、人材を取り合うことになると予想。(下の図参照)

さて、リクルーティングサービスを選ぶ際の企業のニーズは「優秀な人材」を「手間なく」「安く」採用できることだ。それを踏まえ、黒田氏は今後は以下の順でサービスが選ばれていくのではないかと推測している。
ファーストチョイス:採用単価が低く、負担の少ないアグリゲーション型求人検索エンジン経由での自社ホームページ採用
セカンドチョイス:採用単価は低いが負担は大きい、ソーシャルリクルーティングと呼ばれるSNS拡散型求人PRサイトやビジネスSNS、そして無料チャネルであるリファーラルリクルーティング
サードチョイス:ハイクラス人材などの売り手市場ターゲットは人材紹介がメインのチャネルのまま
最後のチョイス:求人広告。黒田氏は、求人広告は次の10年で、かなり厳しい環境にさらされるのではないかと予測している。理由として以下をあげている。
ファーストチョイスになっていくアグリゲーション型検索エンジンや、ソーシャルリクルーティング、リファーラルリクルーティングなど、より低価格や無料サービスが台頭してきていること、一方で、人材紹介が売り手市場向けサービスとして、より高付加価値の方向にビジネスモデルが磨かれていくと、そのど真ん中にある求人広告はプレゼンスが中途半端になり、居場所を失うことになります。
まとめ・感想
以上です!労働人口が減少する中、求職者ニーズに応えられるBto C to Bのビジネスモデルがメインになるというのは納得ですね!
またテクノロジーが進化する中ではスキルを更新していく必要があり、スキルアップやキャリア形成のための転職が当たり前、むしろ必要なものになるという話は勉強になりました。スキルがある人と、テクノロジーで置き換えられるスキルしかない人で、売り手市場、買い手市場が二極化していきそうですね。人材業界でも、そういった市場の違いによって台頭するチャネルが変わってくるということですね!
最後まで読んでくれた方ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
