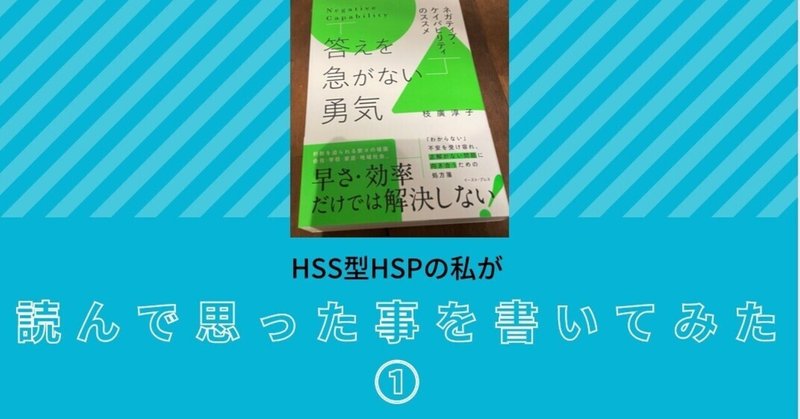
【答えを急がない勇気】日々更新中
なぜ読もうと思ったか

本屋さんでこの本を見つけた時に初めに思ったのは
『直観力とか瞬時に決めろ!って本が多いのに急ぐなってどういうこと?』
って興味本位で手に取りました。
簡単に私の思考のパターンを紹介します。
・早く行動しなきゃ!
・なんでもいいから何とかしなきゃ!
・何もしていないと周りからどう思われるだろうか・・・
など
他人の目を気にしがちな面が多いです。

『自分がどうしたいのか?』
よりも
『他人からどうみられているのか?』
の方が気になってしまう人です。
だから
『わからない』不安を受け入れ、正解がない問題に向き合うための処方箋
という帯びのキャッチコピーに惹かれました。

他人がどう思っているのかなんて分かるはずがないのに
不安に思ってしまう自分の考えを変えられるかもしれない
そんな思いから読み始めました。
ここまで読んでくれた人はもぅ分かったと思いますが
私は文章を書くことに慣れていません。
この本を読んで感銘をうけて付箋を貼ったところに関して
自分の解釈と感想を書いているだけです。
批判は絶対にしないでください。すぐに心が折れます。
そんな考え方もあるだね。くらいの気持ちで読んでいただければありがたいです。
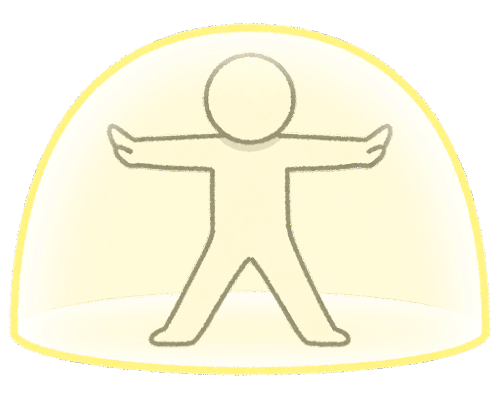
はじめに
第1章に入る前に付箋を貼りだしてしまいました。
P15~
『わかりたいと思うのは仕方ない』
『人類は進化の結果、不確実性を嫌うようになった』
『意味がわからないと、わかりたいと思うのは心の根本的な傾向です』
『意味とは、わからないものをわかるようにする働きです』
この文章に安心を与えられました。
私だけ不確実な事柄に左右されやすいのかと不安になっていましたが
人類はみんな不確実性が嫌い!
意味を求めることは悪いことではない!って
ちょっと嬉しくなりました。
第1章
P42
『洞察やより深い理解はどこで生まれるのでしょうか?それは、ここまでは知っている・わかっているというぎりぎりのところ』
『知っていることと知らないこととの端』
『自分の知らないことと向き合う』
深い理解がどこで生まれるかなんて意識したこともなかったからドキッとしました。
『わかっていること』と『わからないこと』が明確になっているかどうかが大前提みたいですよね。
今まで私は『とりあえず』で行動してきたけど何がわかっていて、何がわからないのかを明確にする作業をすっ飛ばしていたないと思い返しました。

自分が何を知らないのか。
漠然とした不安が大きかったけど、
不安の正体を自分で隠してよく見ようとしていなかったかもしれない。
P47
『ネガティブ・ケイパビリティとは人が不確実さとか不可解さとか疑惑の中にあっても、事実や理由を求めていらいらすることが少しもなくていられる状態のことだ』
ネガティブ・ケイパビリティって言葉は初めて知りました。
これは私にないものだなって事で付箋。
不確実な状況を前にすると車の前に飛び出した鹿のように固まってしまうから。
事実や理由を求めてイライラしないって
今の自分にはなかなか難しいようにも感じました。
広い心とやらが必要なのかな

P54
『精神分析医は目の前の患者のありのままの姿や状態を見ようとするのではなく、頭の中にある精神分析学の知識や理論をあてはめて理解しようとしてしまいます。』
『100%今ここにいる』ことができるためにはネガティブ・ケイパビリティが必要。
P56
『過去のセッションを思い出さないように』
手掛かりである『過去のセッション』が『今の目の前の相手』を理解するうえでの『先入観』を作り出してしまう恐れがある。
『今この瞬間に、まっさらな気持ちと頭で相手を受け容れる』ことを邪魔させてはいけない。
これはパーソナルトレーナーの私も同じことが言えるなって思いました。
お客様をみているつもりだけど頭の中はお客様が伝えてくれたことに対してどう返答しようかを考えてしまっている。
その場に100%でいるか?って言われると自信がないなぁって…
100%で今ここにいるってどんな感じなのか実感してみたいな。
お客様の身体は毎日変化しているわけだから前回のトレーニング時とは違うはず!
でも前回はこうだったなって思い返していることは多々ある‥

自分自身に対してもそう言えるかな
『私はこういう人間だ』って決めつけて生きていたら自分自身を受け容れることは難しくなってしまうかもしれない。だから忘却力って大事なのかなぁ。まっさらな気持ちと頭で相手のことも自分自身のことも受け容れたいな。
P58
『無知』の姿勢が最も重要。その理由は『知るということは、見える可能性の範囲を狭め、予期せぬこと、言葉にされなかったこと、これから言葉にされることには、耳を貸さないという傾向を強める。無知な姿勢は見えてこないものを可能にする』
この文章には耳が痛くなってしまった。
知ったつもりになってしまっていることにさえ気がついていないのかもしれない。
色々な経験をして色んな人に会ってしまっているから、ある程度のデータはあるわけで…
この人はこういう人かもしれないと当てはめてしまうと確かに視野は狭くなってしまうかぁ。
『無知』についてあまり良い印象を持ってない。
何も知らない奴って馬鹿にされたくないって思う。
これは小さなプライドのせいかな?
やっぱり『人からどう思われるか?』を気にしてしまっているんだなぁ。
正直に『分からない!』って言えるのも強さなのか。
P61
今この場で患者と自分の間で何が起きているかに注意することである。
この本では患者って言ってるけど、他人と関わるときに『何が起きているか』を常に注意し続けるって凄い集中力が必要じゃない?
それくらいしないとその場に100%いられないのか😱
これを試してみたけど、意識してないとすぐに気が散ってしまう💦
P63
色々な葛藤を持ちながら、ぐっと耐えてそれを持ち続ける。それが『おとな』なのだというのがぼくの定義なんです。
この文章には痺れました!
カッコいい!
『おとな』になりたい‼︎って😂
すぐに耐えられなくなってピーピー言っちゃうから
じっくりゆっくりでも問題と向き合っていきたい。
迷ってもいい
理解したつもりになるくらいなら分からないままの方がいい
じっくりコツコツなイメージの方がより深い理解や共感に繋がりそうかな。
人が集まってくるような温かい焚き火のような寛容さも作り出したい。

第2章
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
