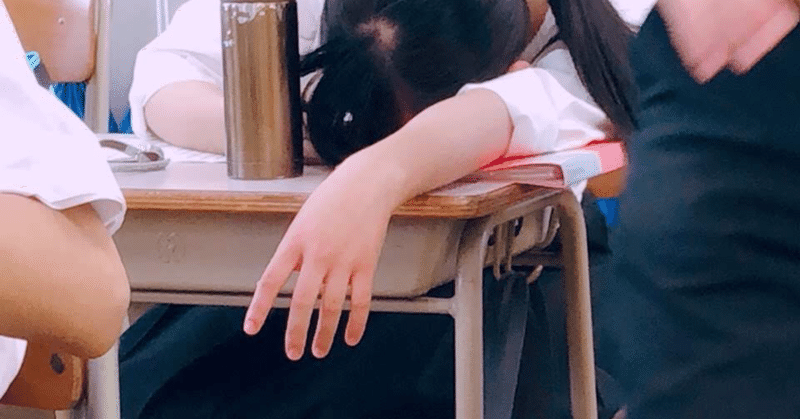
勉強の”挫折”の正しい理解
大多数の人が経験する、「勉強」での挫折
ほとんどの人は、小・中・高・大学で何かしら勉強につまずいたことがあるのではないでしょうか。
私は中学まではつまずくことを経験したことがなかったのですが、高校では勉強についていくのに大変苦しみました。
典型的なタイプだと思います。
そこで、勉強が網羅できて余裕がある状態と ついていけない状態の両方を体感し、自分なりに乗り越えた経験から学んだこと・得たことを述べたいと思います。
そしてこの記事では、
その挫折は挫折じゃない!つまずく理由を正しく知れば見方が変わる!
ということを論じ、根拠を説明し結論づけますので、どうか最後までお付き合いを。
挫折を防ぐ秘訣
さて、勉強で不必要な挫折をしないコツを一言で言うと
自分が容易に理解できるレベルの"把握"
です。
ペンで書くか、目で見るか
自分が容易に理解できるレベルは、二つに分けられます。
一つは、目で追って頭で理解できる、「読書」の形で理解できる段階です。
教科書を眺めたり読んだりしたら、その状態でもう問題を解けるという状態です。
この状態は要するに、インプットした知識をどう使えば問題が解けるかが無意識のうちに瞬時に理解できている状態です。
分かりやすい例として、算数・数学の公式を挙げます。
小・中学校で習う算数や数学の公式は比較的、一目で見てその意味が分かりやすいような、易しいものが多いのではないでしょうか。
これは塾や家庭教師のアルバイトをして感じたことですが、特に小・中学の算数・数学は、個々の学習スピードに合ったサポートがあれば誰でも容易に習得できるものなので個々の理解のレベルが分かりやすい部分だと感じます。
一度学校で習った状態ですぐに色々な問題が解ける人もいれば、マンツーマンでやり方を丁寧に教えてもらうことで解き方を理解する人もいます。
そして一回の授業ですべて理解できる人が偉いとか、そうじゃない人が落ちこぼれだとかの話ではなく、
各々習得するスピードには必ず個人差があって
それを自分で理解する必要がある
と言いたいのです。
この理解をしないまま闇雲に勉強を進めると、無条件に周りの人と比べてしまい、
「みんなは一度聞いて理解して解けているのに、自分はついていけない」
「みんなの何倍もしないと自分は出来ない人間なんだ。勉強は苦手だ」
と自分に負のレッテルを貼ってしまいます。
小中高生の年齢の時に自分に抱いた感情は、潜在意識の中に生き続けることも多いのでその後の人生における”学習”にも影響を及ぼすと思います。
映像授業に限らず、対面の授業や教科書を読むことにも共通して言えますが
映像授業を視聴して、動画を目で追うことはできるが
視聴が終わったあと頭に残っていない、
見終わった時点で問題を出されても解けない・方針も立てられない
というレベルにきたら、「自分は今後この難易度より難しいものは、違う方法で頭に入れる必要があるのだな」と思えばいいのです。
ここの見出しの言葉を借りていえば、目で見るインプットが追い付かなくなったらペンで書いて頭に入れる方向にシフトチェンジするのです。
書いて学習する利点
ペンで書いて覚えようとするときは、手から伝わる筆圧や自分の手でペンをもって手先を使う感触があり、脳もそれを認識するためより頭に入りやすくなります。
また、書くという行為はアウトプットにもなるためとても効果的です。
しかし、目でさらうだけで習得できるレベルのものを一生懸命書いて時間をかけて覚えるのは効率が悪く、時間も労力も勿体ないです。
だからこそ、自分が容易に理解できるレベルの"把握"が大事なのです。
これはよく言われる「量と質」にも関係してくると思います。
自分が目で見て理解できるレベルを見分けたり、その見分け方を見つけるには、試行錯誤しながらのある程度の勉強量が必要です。
その中で自分なりの勉強の方法をシフトチェンジする境界線を見つけたら、質を意識してより効率の良い勉強方法で勉強することが大切だと思うのです。
まとめ: 挫折は挫折じゃない
多くの人が勉強でつまずくポイントは、勉強の方法を変えるポイントであり、その時点で勉強することを諦めてほしくないと思います。
一人でも多くの人が自分に合った学習法と出会い、学ぶことの楽しさを知ることのできる世界になればなと常々思っている、大学生のいち意見、呟きでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
