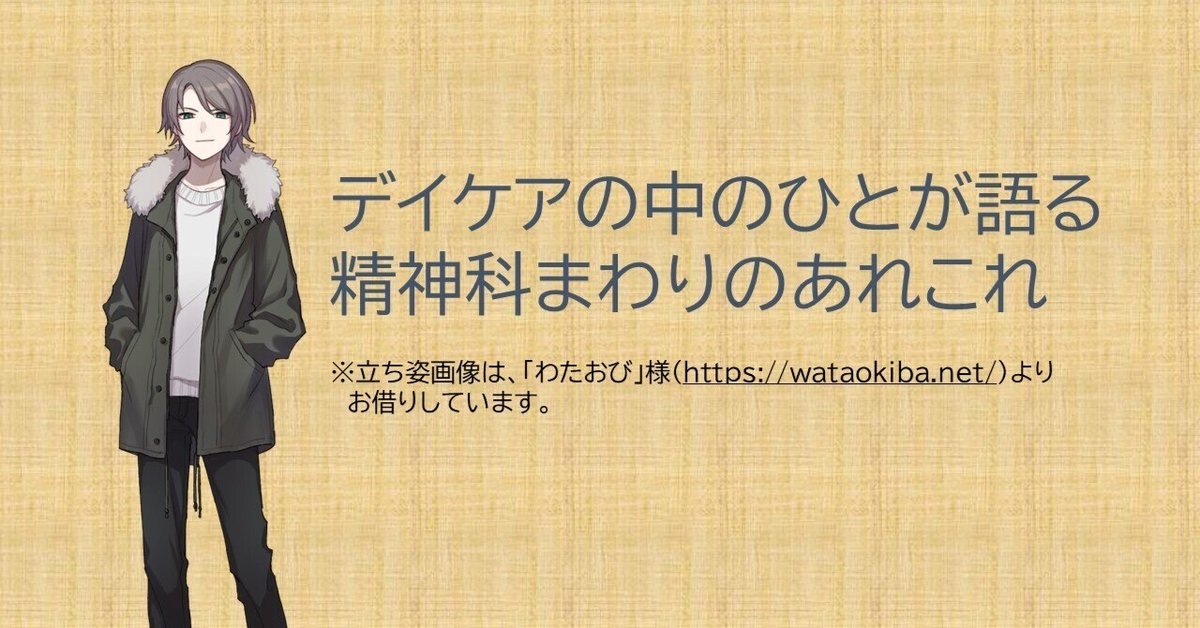
【睡眠衛生指導】睡眠のことで、悩み過ぎないほうがよい
【睡眠衛生指導】睡眠のことで、悩み過ぎないほうがよい
「デイケアの中のひとが語る、精神科まわりのあれこれ」#78
なんとなく連載になってしまった「睡眠衛生指導」についての記事。今回は、「睡眠のことで、悩み過ぎないほうがよい」ということについて。短めです。
***
睡眠・覚醒は、視交叉上核にある生物時計(体内時計)が支配する「概日リズム」によって司られています。その意味では、純粋に生理学的現象なのですが、心理社会的な様々な要因により妨げられることによって、不眠や睡眠障害が生じる場合があります。
私たちは、なにがしかの“悩み”を抱えていると、睡眠に支障が出ること(寝つけない、熟眠できない、など)がありますよね。“悩み”を抱え、考えを巡らせ続けている(心理学的には「反芻(はんすう)」といいます。牛が牧草を食べる時に“もぐもぐ”し続ける、あれです)と、不眠や睡眠障害を悪化させてしてしまう可能性があります。
ですから、睡眠衛生指導では、ストレスマネジメント(上手にリラックスする、ストレスのもととなる問題を上手に解決する、相談する、など)を重視します。また、悩み事があるのなら、眠る前に考えるのはやめて、メモを取るなどして翌日に回すようお勧めします。
***
不眠や睡眠障害を抱える方は、「うまく眠れない」こと自体が、悩みの種になっていることでしょう。不眠や睡眠障害についての悩みは、それを悩むことでますます不眠を悪化させてしまうことになりかねず、注意が必要です。
日中の眠気がひどくて生活がままならない、不眠のために持病(精神疾患など)が悪化しかねないなど、大きな支障が出ていないのであれば、「まあ、いいか」と“開き直る”姿勢も大切でしょう。「完璧な睡眠」など、ないのです。
***
睡眠衛生指導では、不眠や生活の状況に応じた、睡眠を改善するコツを、いくつかアドバイスする場合があります。ただ、これも「完璧にこなさなければ」と意気込みすぎると、それが逆に患者様のストレスになってしまうかもしれません。それでは本末転倒ですよね。気軽に取り組んでいただくことが大切です。
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
