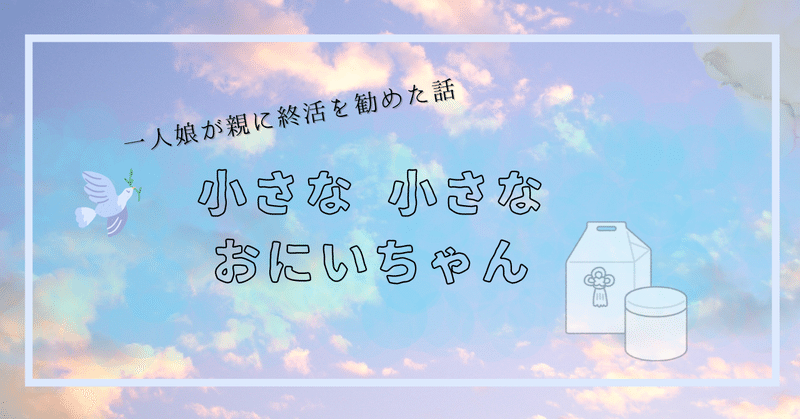
小さな小さなお兄ちゃん
私のお兄ちゃんはとっても小さい
私は一人っ子だ。
でも本当は兄が1人いる。
この世に生を受けなかった
水子という形だ。
妊娠8か月の時、
残念ながら死産となり、
2日後火葬され、
小さな小さな骨壺に入っていた。
私は物心がついたころから、
一人っ子ではなく、兄がいると
言い聞かされ、
お墓参りをしていた。
年に一度、命日近くに
遠方の寺の納骨堂にいき、
手を合わせていた。
実際にはお墓ではないのだけれど。
兄は生きていれば48歳。
当時、幼すぎる子供が
親兄弟誰もいないお墓に一人入るのは可哀そうだろうという思い、
そして、自宅にお骨を安置することは難しいという思い。
当時の若い両親の思いを察すると、
納骨堂に安置するほかなかったのだと思う。
2024年4月
48年経って、兄が実家に帰ってきた。
帰ってきたという表現が正しいのだろうか。
兄にとっては初めての自宅だ。
GW、実家帰省中に私は兄のお骨に会えたのだった。
帰省する日、
私は母の日の花と菖蒲の花1輪を持参した。
花は何でも良かった。
でもせっかく自宅に帰ってきたのだから、花を手向けたかった。
折しも、こどもの日近く。
生まれて祝ってあげられなかった
こどもの日の花、
菖蒲にしようと、ふと思いついたのだった。
私も流産を2回、
出産を2回経験したからだろうか。
自分が母となった今、
兄は色濃く、忘れられない存在になっている。
供養され続けていたものの、
48年間もの長い間、
窓のない薄暗い納骨堂で安置されていた。
そんなお骨の兄が、
実家の日差しが入る明るい角部屋、
和室にちょこんと
安置されている光景がなんとも、
不思議で
やっと、
やっと、
やっと、
帰ってきたんだねと感慨深かった。
私には息子と娘がいる。
あまりにも小さい骨壺を
見つめながら、
生まれてくることが当たり前じゃない
命の尊さを感じずにはいられなかった。
彼らはどこまで
理解していたかはわからないけれど、
「ママのお兄ちゃんなんだね」と言いながら
一緒にお線香を手向けた。
両親の終活
そもそも
なぜこのタイミングで
小さな骨壺が実家に帰ってきたかというと両親の終活だった。
両親は日頃から、
私たちのどちらからが亡くなったら、
お兄ちゃんと一緒にしてもらっていいからと言っていた。
でもその具体的な方法は提示されていない。
一緒って何?
何をどう一緒にするの?
私一人娘で、墓守できない可能性もあるから、
墓は買わないでほしいと
ずっとお願いしていた。
でも片親が亡くなるその時まで、
兄のことを寝かしておいた方がいいものなのか。
心の奥でずっと引っかかっていたのだ。
両親も終わりの処が未定という不安もあっただろう。
見つけた!最適解
それを見事に解決してくれたのが
私がお嫁に行った先の実家だ。
義父・義母両家のお墓は同じ墓所にある。
墓を立てた祖父母達も仲が良く、
墓所でお酒を酌み交わせるわねと
生前から冗談混じりに
約束をしていたという。
我が家は毎年お正月に、
お墓参りに行くが、
年始に、一度に、一気に先祖に参ることができる。
不謹慎かもしれないが、
なんとも効率的なのだ。
これは一種のカルチャーショックだった。
私の実家の墓は、
秋田県と群馬県。
遠方の為、そう参ることはできない。
私は数えるくらいしか墓所には行ったことはない。
お墓の選び方
そう、この終活を仕掛けたのは、
私だ。
仕掛けてしまう娘もどうかと思うが、
この兄の存在を
両親二人、健在のうちに
何とかしてもらわないと…
最適解を見つけた今、
いつ話そうか、
いつ話そうか、
その時を常日頃から考えていた。
私の両親と、主人の両親と
同じ寺の墓所になれば、
私たち夫婦、よくよくは子供たちも
参りやすいのではないか。
もちろん、
両親がどんな形で葬儀をしたいのか、
宗派など、こだわりは多少は考慮しつつも、
残される人間(参る人間)にどこが参りやすいか、
その視点は意外にも重要だと考えたのだ。
早速、両親に相談すると
とりあえず話だけでも聞いてみようと前向きに聞きいれてくれた。
両親にはお墓は買わないでほしいとお願いしていたので
墓を建てるつもりはなく、
合同墓地を検討していたところだった。
このお寺の合同墓地はどうかな…
主人の実家の墓所の寺を提案した。
両親は現在の実家の辺りで検討したようだが、
寺の所在地、通いやすさ、価格、宗派等も含め、
今後のことを話すと、
すんなり受け入れてくれた。
そして、
兄を先に納骨してほしいと頼んだ。
少し遠方の兄の納骨堂も、
コロナ渦で足が遠のき、
加齢に伴い、通い続けるもの難しい状況だと両親たち自身が感じ始めていた頃合いだった。
決断
結局、両親は
主人の実家の墓所がある寺の
合同墓地という決断をした。
駅から近く、現在の自宅からも通いやすい。
境内正面、右手に鎮座する合同墓地。
いつ来てもきれいな花がたくさん手向けられている。
墓石を上から見下ろすように
春にはソメイヨシノとしだれ桜の大樹が咲き乱れる。
そして、まずは兄をそこに納骨すること
を決断してくれたのだ。
正直、ほっとした。
同じくほっとしたのは母だ。
終活の話をしたがらない父と墓の話になっては喧嘩していたようだ。
私が話を切り出したおかげでここまでまとまったという事、
実際に行動に移せたことを感謝された。
またまた、私の荷も少し降りたのだった。
そして、納骨堂からお骨を移動させ、
自宅で納骨の時を待つことになった。
生と死の現場で
私が社会人になって初めて務めたのは
産婦人科専門病院だった。
そこでは毎日、命のドラマが繰り広げられていた。
独身だった私は、
お産は少し怖いものと感じていた。
あの凄まじいお産の声を聞くと
女であることを悔やんだくらいだ。
でも産後はみなさん、
かわいい赤ちゃんを抱いて
幸せいっぱいの空気が広がっていた。
誕生の場のエネルギーの高さが
手に取るようにわかり、
とてもやりがいをもって働いていた。
その仕事の中で、
今でも印象に残っているのは
お産を見守る観音様の存在だ。
病院の分娩室が並ぶフロアの一角。
人目に触れないように、
扉の奥にそっと、
でも分娩室の方をしっかりと向いて
安置されていた。
この観音様には
水子さんがいらした日、
ちいさな哺乳瓶をお供えにいく仕事もあった。
ある時、病室を訪問すると
いつもの赤ちゃん用カートの中に
ひと際小さい赤ちゃんが
お花いっぱいの中
寝かされていたのだ。
私は一目見て、
悲しみの現場だと悟り、
病室を後にしたが、のちに死産だったことを知った。
お産は生と死の間だ。
兄もあのくらいの大きさだったのだろうか。
そこにいらした患者様と母を照らしあわせて
胸が苦しくなったのを思い出す。
もっと早く…
実家に置かれた小さなお骨を見ると
もっと早く自宅に戻れなかったものか。
そんな思いも抱いた。
以前、母は
父がお骨を家に置いておくのは嫌だと言ったから、
自宅には置けないのよと言ったのを覚えている。
兄の火葬に唯一、立ち会った父としては
悲しみの象徴だろう。
そばに置いておくのは辛い。
母もまた、心の拠り所にしていて、
ことあることに、お兄ちゃんに報告…と納骨堂で手を合わせていた。
父に反対されている以上、お骨を自宅に戻せなかった。
私も実家に一緒に住んでいる時は、
小さな兄の存在は実家の守り神的な役割くらいに思っていた。
母になってこそ、
もっと早く呼び寄せるべきだったんじゃないかと思うのだろう。
終活の打ち合わせの時、
ふと母は言った。
「これで(合葬すると)お兄ちゃんは永遠にいなくなっちゃう訳じゃない?
もちろん、私たち家族は忘れないけどさ…」
ちょっと寂しさが見え隠れしていた。
48年経っても
癒しきれない悲しさ、寂しさがそこにあって、
小さな小さな存在だけど、
母の中では大きい存在のように思う。
お腹を痛めた我が子なのだから。
今回、納骨を決め、
両親が自宅にお骨を呼び寄せることができたのは、
これが最期の別れでもあるからだ。
何も言わないが、父もそんな思いがあるのかもしれない。
身近に感じていた兄
私は事あるごとに
兄が守ってくれているなと感じている。
若い頃自動車事故をした時、
車は大破したけれど、
私は奇跡的にむち打ち程度で助かった。
エアバッグとシートベルトに
絞め殺されると苦しみながらも、
頭をよぎったのは、
お兄ちゃんが守ってくれたんだなという根拠のない確信。
心の中で感謝した。
また、
私が一人目を妊娠中、
性別がわかるかわからないかの頃、
実家の両親は、
家庭菜園で採れた茄子が
男の子のシンボルのような形に実った。
その様子を見て、男の子かもねと
笑い話をしていたという。
時同じくして、
両親はそのことを私に報告しようとしていた時に
私が「男の子みたい」と電話したのだった。
私は第一子は男の子だろうなと感じていて、
男の子と判明した時はやっぱり!って思ったのだ。
さらに
茄子の話を聞いて、
ほらね、お兄ちゃんが帰ってきてたよって
両親に教えに来たなと思ったものだ。
少し兄を身近に感じた瞬間でもあった。
納骨に48年かかった話
親の終活を一緒にはじめ、
思いがけず兄への心の整理も
両親はできたのではないかと思う。
そして私も。
こうして書き残したいと思ったのは
兄への最後の供養だと思ったからだ。
水子の供養は一般的に
いつからはじめて、いつまで行うという決まりはない。
あくまでも家族の心が落ち着くまでとされているようだ。
我が家は48年かかったようだ。
この夏、
兄は両親が入る予定の合同墓地に納められる。
石碑には両親の名が
朱色で彫られるが、兄の名は刻まれない。
刻まないことを選んだのだ。
でも
両親と私の心にはいつまでも
兄がいたことが刻まれ続けることだろう。
#創作大賞2024
#エッセイ部門
#親の終活
#終活お手伝い
#お墓の選び方
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

