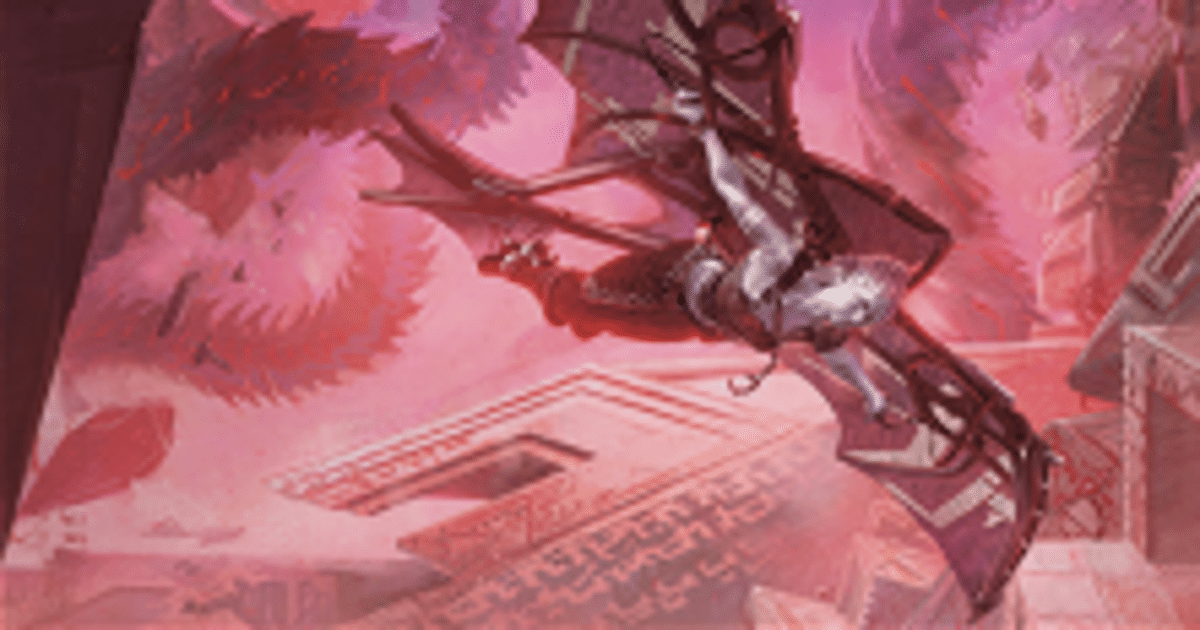
【MTG】ドラフトは統計では勝てない?
【はじめに】
カード集めも兼ねたリミテッド期間が終了し、ぼちぼち構築の方に目を向け出している今日この頃です。今回は僕がMOM環境でプレイした全19回にも及ぶドラフトの戦績と言わずと知れた17lands.comのデータを照らし合わせながら、ドラフトというゲームにおいてデータとはどれほどの価値があるものなのかということについて語っていきたいと思います。
という訳で、今回は僕個人の戦績に関する話が多くなってしまうと思うのですが、これは単なるドラフト日記ではなく、最終的には環境全体、ひいてはMTGというゲーム全体にまで及ぶ話なので、「他人の戦績なんてどうでもいい」という方にこそ読んでいただきたいです。
ちなみに、今回のリミテッド環境についての振り返りは、こちらの記事の方でやっています。
実は今回の記事はこちらの続編のようなものなので、僕の記事では珍しく前作を読むことをお勧めしております。まあ17landsのデータを含めて独自に環境全体の理解を深めているという方なら必要ないと思いますが、個人的には外部のデータをそっくりそのまま記事に乗せるのは避けたいので、今回の記事を読んで途中で気になった方はご自分で17landsの方を見ていただけると理想的です。
それでは、早速やっていきましょう。
【僕の戦績】
まずは何より自分の戦績を晒す必要がありますね。ちなみに、僕はドラフトに限らず、構築の方でも外部ツールのようなものを利用しておらず、いつもアナログな方法で勝率を記録しています。まあAIとかにも頼らず、毎度のように長文記事を書いているような奴なので、僕はとにかく機械が介入する余地を少なくしたいというマインドの持ち主なのでしょう。
ということなので、僕には外部ツールがどれだけデータを詳細に記録できるのか自体も分からないのですが、とにかく、僕のデータは片手間で記録できる範囲内の特に重要な部分だけになっていますので、その点は予めご了承下さい。
では、僕のMOM環境ドラフトの戦績を見ていきましょう。

こういうのを提示して話す経験がそこまで無いので、もしかしたら不便な点があるかもしれませんが、とりあえずこれが大元のデータです。
では次に全体としてのデータを。

全体勝率は6割、これは個人的には調子が良い方で、正直に言うと調子が悪かったら恥ずかして戦績なんて晒せません。それに、全19回のデータと言っても17landsほど膨大なデータではないため、ここから更に回数を重ねると必然的に17landsの全体勝率のように5割に近付くとは思います。
順番の方を見ると、ランク帯が上がって勝率が下がりそうな後半の方がむしろ勝率が安定しているということが分かります。ONEの最初期にドラフトをやってから一度もリミテッドをやっていなかったので、今回も当然のようにブロンズ帯からのスタートでしたが、最終的にはダイヤモンド帯まで到達したので、後半はほとんどプラチナ帯での試合になると思います。まあ同じプラチナでもリミテッド自体の経験がそこそこあるプレイヤーが多いように思いますが、その辺りになるとダイヤモンドとかミシックと当たることもあるので、割とハードな領域だったのは事実でしょう。では、何故そのような状況下で安定した勝率を出せたのか、それが重要な訳ですが、その前にまずはこちらのデータも見ていただきたいと思います。

これは大元のデータを色ごとに整理したものです。つまり、これでどの色が最も勝てるかということが分かる訳ですね。
………これは、どういうことなのでしょうか? なんと、17landsの方で最も成績が悪かった白黒の勝率が脅威の8割超えを達成してしまっているではありませんか。それだけではありません。17landsの方では特に白青と青黒の成績が良かったため、前回の記事では単色としての最強は青と結論付けたのですが、そんな青が僕の方では最も勝率が悪いのです。正直、これが5回とか10回のデータなら奇跡的な食い違いで片付けても良さそうですが、19回は個人が集められるデータとしてはそこそこの量だと思いますし、白黒に関しては3回中3回が7勝ということになっており、それを単なる奇跡と捉えるのは逆に無理があるように思います。では、何故そのような統計上の勝率が悪い色で勝ち続けることができたのか、それが今回の記事で僕が主張したいことになる訳です。
【所詮、データもカードもプレイヤー次第】
データを利用すれば、どのカードを使った時に勝てているのかという統計上の事実は簡単に分かります。しかし、実際のドラフトはそんなに単純ではありません。評価が高いカードが来ても欠乏しているマナ帯を補充するためにそれを無視することもあるでしょうし、逆に評価が低いカードであってもシナジーの関係で採用し、結果的にプラスに作用するということだってあります。その意味で言うと、データは誰でも簡単に得られるからこそ、その先にある実力による差を明確化してしまう作用すらあると言えるのではないでしょうか。
では、僕は実力のあるプレイヤーなのかと言われれば、一概にはそう断言することもできません。全体勝率6割は確かに良い方ですが、要所要所で負け越しも存在しますし、黒赤や白青などが苦手であるという事実も浮き彫りになっています。そして、このような傾向には運というこれまた忘れてはいけない要素も関係しているのです。
散々言われていることかもしれませんが、この手のゲームにおいては運を制御すること自体も実力の内であると僕は考えています。僕が白青をプレイした時に記録したメモを見返すと「ロードが来なかった」や「騎士が集まらなかった」などの言い訳が散見されるのですが、騎士デッキを追求するのなら既にロードがある状態から目指すべきですし、無いなら無いで騎士に拘らずに組むべきで、中途半端なデッキにしていたのは紛れもなく自分自身であるにも思えるのです。まあマナ関連の事故ともなると流石に回避するのは難しいと思いますが、それにもマリガンという手段はありますし、やはり全てが運ということはあり得ないと思います。つまり、白青のようなデータ上は勝てている色であっても、個々のポテンシャルや相性の問題で結果が出ないというのは幾らでもあり得ることで、それを全て「運が悪かった」で片付けることはできないという訳です。それに、データ上の結果が良い色はドラフトにおいて混む可能性も高いため、安易なデータ依存を回避するというのも立派な実力であるとも言えるのではないでしょうか。
また、これは僕自身に対する言葉でもあるのですが、有り体に言ってしまうと、データに依存するばかりで実力が伴っていないプレイヤーほど「リミテッドは運ゲー」という結論に陥りがちな気がします。実は今回の白青のような例は軽い方で、特に酷かったのはBRO環境でした。勝率自体も56%と大したことはなかったのですが、その時のメモを見返すと、やれマナフラがどうのとかやれレアが弱かったとか言い訳ばっかりでした。正直、その時と比べて自分が成長したという実感は特に無いのですが、実を言うと、その時は常に外部から得たカード評価表のようなものを傍らに置きながらプレイしていたのです。要するに、この時の僕は他人のデータに勝手に依存し、自分で思考することを放棄していたため、本来は振り返るべき反省点が見えなくなってしまっていたのです。まあそのカード評価表が自分で作ったものであったのなら、それについて反省すれば良い訳ですが、やはり他人の評価ともなると、そこから何かを得るのは難しいと思います。勿論それは17landsのような所が提示しているデータにも言えることで、それらは確かにインパクトがあるもので、頼りたくなってしまうのが人間の心理というやつなのかもしれませんが、外部の、それも数値やランクだけの評価から反省点を得るのは非常に困難です。データにおいて最も大事なのは、そんな無機質な数字の羅列ではなく、その背景にある思考や傾向の部分であって、それを読み取る能力というのも結局は個人の実力になるのでしょう。要するに、データに依存する行為は、結果的にデータを活用する能力を奪ってしまうという結果を齎すと言えるのではないでしょうか。
つまり、データ”で”リミテッドをするのではなく、データ”と”リミテッドをするというのが全てにおいて正しい姿勢であると言いたい訳です。まあ偉そうに言っていますが、僕もnoteで自分の考察を形にするようになってから初めて気付けたことで、まだまだデータに依存してしまっている側面もあるとは思うのですが、とにかく、まずは失敗を恐れずに自分の判断を信じてみるというのが長期的には自分の財産になるような気がします。
【娯楽としてのリミテッド】
しかし、データの活用というのは日々進化しています。それこそAIのようなものは、その最たる例でしょう。先に挙げたマナ帯の補充やシナジーの強化などというものも、極論を言ってしまえば、データによってパターン化することも可能ではあります。勿論、その場合は扱わなければならないデータが今までの比ではない量になりますが、では仮にそれがAIなどを活用することで可能になるのなら、それがリミテッドにおける最適解になるのかと言われれば、僕はそれは否定したいと思います。
これは構築にも言えることですが、コピーデッキやデータに依存し、自分でデッキを作らず、調整さえもせず、果てにはプレイすることすら効率を求め出したら、それは自分自身をシミュレーターにしてしまう行為なのではないでしょうか。そりゃ仕事とかの分野では効率化上等ですが、娯楽として見た場合に効率化などというものが果たして必要でしょうか。競技的にやっている人なら「それでも勝てるなら良い」と言われるかもしれませんが、まあ実際それで本人が楽しんでいるのなら問題は無いと思いますが、効率化を求めているのに「MTGは運ゲー」と批判するのは何か違うような気がしてしまいます。はっきり言って、自ら技術が介入する余地を狭めて、運を算出するシミュレーターのようになっているだから、その場合は甘んじて運ゲーを受け入れるべきなのではないでしょうか。
運ゲー批判というのは、自分の意志で運に立ち向かった人に初めて許されるものであるにも関わらず、そういう人は同時に自分の実力も俯瞰することができるため、結果として「運が全て」という結論から逸れていくという不思議な法則があるような気がします。
プロの方とかは特にそんな感じですよね。まあ僕自身は謎デッキ研究をやっていてもそんな境地に至った感覚は全くありませんので、まずは自分の実力に絶望するところから始めたいと思います。
【さいごに】
いつもより短い記事でしたが、最後まで読んでいただいて本当にありがとうございました。
まあ内容自体は凄まじくディープなものになりましたね。僕が最初に書いた記事を思い出します。こういう直球な内容だと何かと問題があるような気もするのですが、協力者の方から「当たり障りのないことばっかり書いてんじゃねぇ」という趣旨の助言をいただいたので、今回は久し振りに僕の素直な気持ちを書いてみることにしました。
勿論、ご意見ご感想などもお待ちしております。良識ある反論や批判はもっとお待ちしております。とにかく、これを読んだ方に少しでもプラスの作用があると嬉しいです。
それでは、またの記事で。
※これはファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
