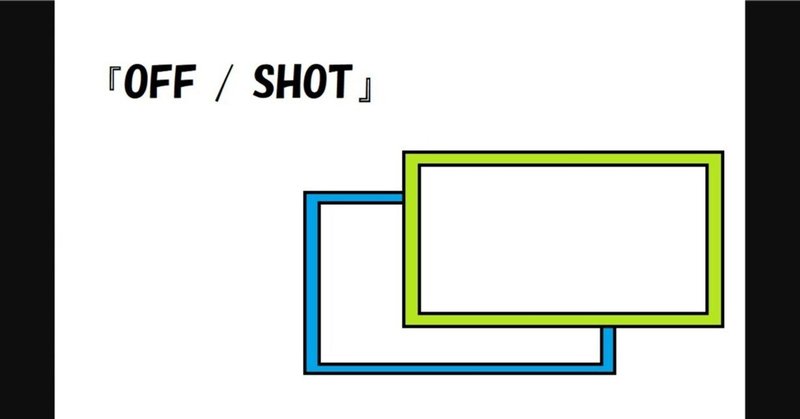
『OFF / SHOT』 6/6 《短編小説》
【文字数:約3,700文字】
お題 : #創作大賞2023 +(#イラストストーリー部門)
Back : 5/6
タチアナが桐原の腕の中で消える場面は、翠那がいない状態でも撮影するか判断が分かれたみたいだけど、画像処理の応用で対応することに決まったらしい。
実際ガチ泣きしたモニカは同じ演技をするのが難しそうだったし、カメラが遠ざかっていく締め方であれば、感情の鮮度が高いまま使うのが賢明だろう。
とにもかくにも全撮影が終了して、役者のできることはSNSでの告知や番宣映像への協力といった、表に立つ裏方仕事だけになった。
そうそう、配信前に原作者の先生からは「とても良い」と太鼓判をもらった。
配信後もおおよそ好評だったから、まさかあんなことになるなんて、想像していなかった。
何度か遊びに行ったことのあるモニカの自宅へと、翠那は早足で向かっていた。
「メッセージも未読のまま、電話にも出ないって……」
きっかけは些細な誤解だったけれど、火を消そうとして水をかけたらそれが燃料になって燃え広がった。
それまで端役を務めていた人間が、規模は小さくとも主役になり妬ましく思ったのかもしれないし、誰にだって後ろ向きな探求心は備わっている。
断片的な情報であるからこそ想像やウソの入り込む余地が生まれ、事実と異なる醜悪なものに育っていった。
エントランスにある石碑みたいなインターホンを鳴らしても、予想通り反応がない。
外出中に連絡がつかないのは行方不明みたいなものだし、在宅中であるなら状況はさらに悪い。
「こんなに心配させて風邪とかだったら、タダじゃ済まないから!」
呼び出しを続けるインターホンに向かって叫び、肩に下げたバッグから使いたくなかった最終手段を取り出す。
いくつもの溝が彫られた細長い板により、翠那は住民の1人であるかのようにエントランスを突破して、平静を装いながらエレベーターに乗りこんで目的階の数字を叩く。
合鍵の存在は翠那とモニカ・蒼瑠の双方が合意しているに過ぎない。お互いの事務所との信頼に関わるだけでなく、それこそ火種になるかもしれない危険物だ。でも今はそれに頼るしかない緊急事態だった。
「速く……速く……」
増えていく数字の遅さに苛立ちながら、このままエレベーターが止まればいいとも考える。目的の階に辿り着かなければ事実から遠ざかったまま、嫌な予感だけで済ませられる。
だけど鉄道と同じく優秀な動く箱は、故障や遅延することなく翠那の指定した階へと辿り着いた。
開きかけた扉から無理やり出ようとして肩をぶつけ、痛みを感じるのも忘れて走る。
見慣れた扉の前に立ち、祈るような気持ちで扉横のインターホンを押した。
「お願い……返事して」
1回、2回、3回と続けてからドアノブに手をかけ、一呼吸した後に引いてみる。施錠された扉は反抗的な声を出し、訪ねてきた客人の入室を拒む。
エントランスのとは別の鍵を使えばいい。だけどそれをすれば、もう後戻りできない。
マネージャーに連絡して一緒に入る、ここで引き返して忘れる、そんな選択肢が交互に浮かんでは消える幻覚に苦しみながら、どちらでもない選択を翠那は選んだ。
「……入るよ」
拒絶しかできないように思えた扉は訪問者を受け入れ、普段モニカの寝起きしている空間が外とつながる。
異なる世界を隔てる鋼鉄の板を開け放したまま、しばし翠那は立ち尽くす。外にあふれてくる空気は冷たくて、どうやらクーラーが動いているらしい。
鼻先に感じるポプリは記憶にあるのと同じだから、中に入ってもいつも通りだと期待させる。
後ろ手に扉を閉め、あえて脱いだ靴を整えてからリビングに足を進めた。照明は点いておらず、日を浴びたカーテンが遠慮がちに光っているだけだ。
「ねぇ……」
主演を務めた自分へのご褒美に、奮発して買ったという本革のソファに近づく。とても柔らかくて横になっていると眠くなるから、「人をダメにするソファ」と持ち主は呼んでいた。
幸福の象徴に向けて翠那は手を伸ばす。正しくは、その場所にいる人間に向けて。
触れると温かいと感じたのは一瞬で、すぐに体温が奪われて冷たさに手を離す。
モニカ・蒼瑠は眠っていた。
とても静かに美しく、写真のように動かない。胸に見覚えのある台本さえ抱いていなければ、きっと広告として採用されて人気が出るに違いない。
クーラーの作り出す冷風が頬を撫で、現実を認識した翠那は膝から崩れ落ちた。
◇
録画を始めたカメラの前に、2人の役者が現れる。
1人は黒髪に白い半袖セーラー服、襟と袖口それにスカートは孔雀の羽みたいな色をして、笑うと子供、キメ顔は大人の小さな悪魔。
その隣にいるのが長い金髪に青いブラウス、黒いスカートにタイツを合わせ、泣いて笑える彫刻みたいな先生あるいは医者。
「すいちゃんです!」
「もーちゃんです!」
「「ふたりあわせて~」」
左に悪魔、右に先生あるいは医者が並んで立ち、お互いの身長差を活かした動きでもって画面全体をカバーする。
「「マーダー・ガールズです!」」
西部劇で使われそうなリボルバー式拳銃の発砲音が鳴り響き、それに合わせて2人も見えない銃を撃つ。銃口から流れているかもしれない煙を吹くオマケつきだ。
「この度は『OFF / SHOT』のご購入ありがとうございます! こちらは特典映像ということで、(バキュン!)ぶりに作中の衣装を着てみました!」
「すいちゃんカワイイ!」
「もーちゃんだってカワイイよ! あたしたちが並ぶとまるで月と太陽だね!」
「それだとどっちか光ってなくない?」
「あたしは闇メイクだし太陽って感じじゃないからなー」
すると先生が長い金髪で自分の顔を隠し、「ほーらお月様」と低い声を出す。
「こわっ! もーちゃんが画面から出てきそうだよ!」
「私もーちゃん、今あなたの後ろにいるの」
「んなわけっ!」
悪魔が金髪カーテンの川を揺らせば、どんぶらこっこと美しい顔面が現れた。
「すいません、ウソです」
「もちろん分かってるよ! もーちゃんは今ここにいる1人だけだもんね!」
「そういえば私からも、この度は『OFF / SHOT』のご購入ありがとうございます」
「ありがとうございます!」
槍の入っていそうな背筋のまま先生は頭を下げ、悪魔は開いた両手をチアガールのポンポンみたいに振る。
「本作は『マーダー・バレット』の制作現場ドキュメンタリーから派生したスピンオフ作品です!」
「すいちゃん、それだと何なのか分からないよ」
「ですよねーっと、まぁそれは予想済みなので……」
悪魔はコウモリ羽のついたバッグを前に持ってきて、中からメモ用紙と冊子を取り出した。
「もーちゃんはこっち持ってて。ええとですね、人の殺人衝動を呼び起こす銃が『マーダー・バレット』には登場するわけですが、それは現実の世界にも存在するのかもしれません」
「見た目は新品っぽいけど、これって誰かの台本だよね」
「目に見えなかったはずの悪意がSNSで可視化され、弾丸となって飛び交う中で心にケガをしたり、もしくは死んでしまう人もいるかもしれなくて、本作を作ろうと思いました。以上、監督より」
「わぁ、皆さんのサイン入りだ!」
「というわけで、今もーちゃんが持っている出演者のサイン入り台本を1名様にプレゼントします!」
悪魔はさっきまで読んでいたメモ用紙を投げ捨て、先生の持つ冊子に指で作った銃口を向ける。
「欲しい方はブックレット記載のパスコードからアクセスしてね!」
「せんせー質問!」
「はい、もーちゃん」
「そうすると抽選でもらえるの?」
無垢な子供みたく首を傾げた先生に、悪魔が悪魔みたいな笑みを向ける。
「ざーんねん、抽選販売だよ!」
「わぁ、あくどい!」
「私は悪魔だからさ!」
キメ顔あるいはドヤ顔になってしばらく経つと、それまで流れていたポップな音楽からピアノソロにBGMが変わる。
真顔になった2人だけに当たるよう照明が絞られ、悪魔がゆっくりと語り出した。
「『マーダー・バレット』で主演を務めたモニカ・蒼瑠さんが亡くなり、その後を追うようにして共演者の翠那さんが亡くなりました」
「私たちは人から見られる仕事です。見られて評価されないと続けることができません」
「皆さんに質問です。評価とは何でしょうか?」
悪魔の投げかけた問いが画面の向こうに届く頃、わずかに先生は視線を上げる。
「簡単にまとめるなら褒めること、貶すことのどちらかです」
「見た人には評価する自由があります。でもすこしだけ、考えてください」
「私たちは作品の登場人物であり、役者であり、そして人間です」
視線を戻した先生は、手で銃の形を作って視聴者に狙いをつけた。
「あなたの放った弾丸は何処へ向かうのか、考えたことはありますか?」
「人間は誰もが見えない銃を持っています」
悪魔の腕が上がり、やはり手で銃の形を作る。
「「こんなふうに」」
数秒の沈黙が過ぎると照明が消され、画面が暗転した。スタッフの名前が上から下へと流れ始め、最後に黒い背景から1つの文章が浮かび上がった。
【あなたの銃が、どうか誰かを救うものとなりますように】
End.
なかまに なりたそうに こちらをみている! なかまにしますか?
