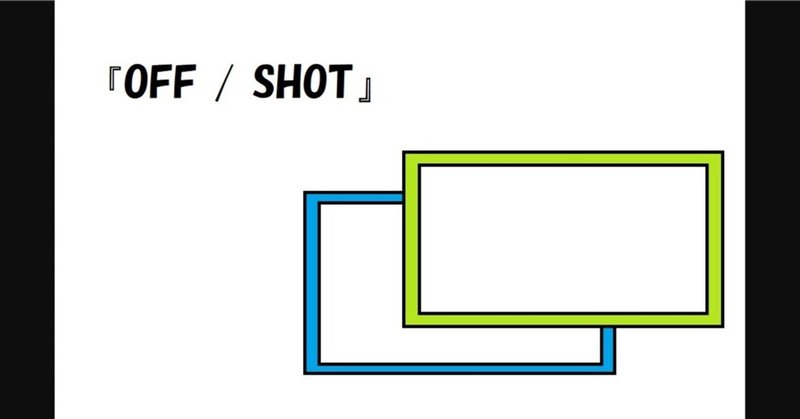
『OFF / SHOT』 5/6 《短編小説》
【文字数:約3,500文字】
お題 : #創作大賞2023 +(#イラストストーリー部門)
Back : 4/6
いよいよ最後の場面は、和やかだった教室の空気を消し去るアクションだ。
悪魔タチアナが人間の桐原を呼んだのは自分を殺してもらうためであり、もちろん桐原はそれを断る。そもそも出会うはずのない2人が一緒にいるのは異常事態で、近くにいるだけで互いの存在を削り続けるらしい。
離れずに最後までいることを提案する桐原へと、タチアナは静かに銃口を向けた。
「私は悪魔だもの。あなたを殺すなんて簡単よ」
桐原が手に入れたのと同じリボルバー式拳銃を構え、その先には抵抗の意思を示さない人間が立っていた。
「タチアナがそれを望むなら受け入れる。だけど私の願いは変わらない」
まっすぐな瞳は翠那を狙って外すことがなく、どちらが悪魔なのか迷う宣言に続いて、交渉人のように一歩、また一歩と足を踏み出す。半分くらいの距離になったところで、
「あなたがそういう人だって知ってるから、だからね──」
人ならざる悪魔が歌い、近づく者へと悪を成す。
もちろん本物の弾丸は出ないし、人間の作ったものとは仕組みが異なる設定なので、翠那は引き金を操作するだけでいい。
見えない弾丸は空中を飛び、モニカの右腹部に達して消える。
「……うぅ、ああ!!」
撃たれた人間は殺人衝動を呼び起こされ、他者を慈しむ愛情は腐り落ち、広がる毒の沼が道義心を食らい尽し、残るは突き立てられた衝動の楔のみ。
心身を内外から焼くような痛みは理性を殺し、やがて本能に宿る暴力性だけが生き残る。手近な武器を使うことには迷いがなく、今それは白衣のポケットにある狂気の孵化器に定められた。
「……! ……!」
人語に値しない発声のまま提示された凶器は、間違いなくタチアナを狙っている。
「それでいい、それですべてが終わる。あなたは自分を縛る鎖から解放される」
悪魔は愛しい人を迎え入れるように両手を広げ、残されていた距離を埋めるように、ゆっくりと桐原の元へ歩み寄る。
「私に死を与える弾丸は、あなたにとっての祝福になるでしょう」
1つの画面に2人が入る構図だけでなく、カメラに向かって翠那が歩く映像を重ねることで、近づいてくるタチアナの姿を印象づける。
銃を構えた人間から見れば的が大きくなっていくわけで、始めの笑みを維持するのはもちろん、カメラが寄るほど恐怖を感じるように努める。
「……がう、ちがう!」
急に苦しみ始めた桐原は頭を押さえ、それまでブレることのなかった銃の狙いが天井に向いた。
「私は、タチアナを……殺し、たくない!」
「抵抗すれば苦しむだけ、本能に身を委ねて」
「い、やだ! そんなこと……させ、ない!」
必死に抗おうとする桐原の命を糧にして、内側から食い破られるような痛み、という体感したことのない激痛をモニカは演じる。
想像の痛みをまるで現実かのように提示するとき、役者である翠那たちもまた見えない血を流し、その先にある死を間近に感じている。
そしてタチアナが見ているであろうものは、愛しい人の苦しむ姿に他ならない。
「もう止めて! あなたが壊れてしまう!」
人間が殺人衝動に抗えるのは始めの数分だけで、わずかに残された自我を取り戻すことはないはずだった。悪魔との接触が原因なのか、それとも別の理由によるものか分からないけれど、桐原は人間のまま死のうとしている。
ついには立っていることができず床に膝をつき、
「タチアナに……生きて、欲しい」
自らの頭に向けた銃口が、残された命を絶つ凶弾が、モニカの美しい横顔に花を咲かせようとする。
「ダメッ!」
発砲の瞬間だけが何倍にも引き伸ばされ、加速された翠那の腕が悲劇をわずかに遠ざけた。
天井に撃ち出された悪意は何も傷つけることなく消え去り、けれども人間の桐原が生み出した代償として、その体は悪魔へと引き寄せられる。
人間のすべてを失ったとき、桐原もまた消える運命にあった。
「……もうこれ以上、苦しまないで……私を1人に、しないで……」
本来の銃の持ち主であるタチアナが死ねば、桐原は失った人間の部分を取り戻すことができるらしい。ただ、上位の存在である悪魔が人間によって害されることは皆無なので、消えたら狂気の拡散者を新たに選ぶだけの話だった。
タチアナと触れているおかげで落ち着いた桐原は、まるで人間のように泣く悪魔に訊ねた。
「どうして止めるの」
「……ずっと蓮華に、会いたかった。だから……もういいの」
「さっき私を撃ったのは自分を殺させるためでしょ?」
わずかな間があって、こくりとタチアナは頷く。
「これ以上は望んじゃいけない、もう諦めないと、あなたが消えちゃう」
「……私なんかのために、そこまでしなくていいのに」
本来なら見えないはずの存在と触れている時点で、桐原は悪魔の側にかなり傾いている。
星を観測するためには彼らの光を目から取り込む必要があり、そしてごくわずかに瞳を焼かれている。強い光を受け取りたくて近づけば、焼かれる度合いもまた強まるのが道理だった。
「私は妹を助けられなくて、だから医者になった。でも結局は虚しいだけだった」
桐原が視線を下げ、長い金髪が寂しげな表情を隠す。
「担当している子に言われたの、先生は僕を見ているようで見てないって。そのとき私は言い返せなかった」
そんなときに銃を拾ったと続け、髪と同じ色をしたモニカの瞳に翠那が映る。
「これは私に対する罰だと思った。でもタチアナに呼ばれたのなら、さっき言ってたみたいに祝福なのかもね」
「……蓮華は、死んでも構わないっていうの?」
問われた桐原は否定しない。
「私にはもう生きる理由がない、ただの空っぽな人間だから」
命の器に満たされた血が枯れるとき、あるいは内側に流れる願いの川が干上がるとき、人は生涯を終えるとされる。
亡くした妹のために生きてきた桐原が、進む道を間違っていたわけではない。正しいと肯定される世界ではなかったけれど、決して無駄な道ではなかった。
それなら翠那が肯定する役目をすればいいし、タチアナはそのために存在する。
「あなたって、本当に……」
自らの理由を打ち明けて、どことなく晴れやかな桐原は無防備だった。
悪魔を殺せる唯一の武器ですら、握っているというよりも引っかけているだけとするのが適切で、その持ち主であれば容易に扱うことができた。
何者にも向いていない銃口は、白いセーラー服の胸元に狙いをつける。
「あっ!」
抵抗しようとした桐原の動きより速く、悪魔は目的を果たしていた。
人間の手で作られた銃創から、無数の枝葉が伸びるように黒い裂傷が広がっていく。
「なんてことを!」
医師としての反射神経なのか処置を試みるも、生まれる死を払いのけようとする手は成長の速さに追いつかず、みるみるうちに悪魔の体を覆い始めた。
「あなたは死なない、私の分まで生きるから」
「そんなこと言わないで!」
子供のように訴えてもタチアナの崩壊は止まらない。桐原の触れている部分とその周辺だけが陽だまりのように残されるばかりで、それすら手を離せば一瞬で消えてしまうだろう。
生きながら闇に食われていく光景を前にして、無力な医師は何もできずにいた。
「あなたが呼んだのに、タチアナこそ私を置いていく!」
「私は悪魔だもの。裏切ったり悲しませたりするのは得意なの」
笑みを浮かべた顔に生気はなく、重たそうな両目をどうにか開けている。
翠那の視界に占めるモニカの割合は減ったけれど、むしろ触れている部分の熱を強く感じてしまい、結果として息苦しさを表現するのに役立った。
「……気づいたときにはこの姿で、ずっと何でだろうって思ってた」
おぼろげな記憶を頼りにして桐原を探し、呼びかけても届かない日々を重ね、やがて悪魔として現れることにした。それが相手を苦しめると分かりながら。
いよいよ別れの場面において、聞こえるか分からないほどの小さな声で「おねえちゃん」と呼びかけるのが、モニカの話を元に追加された最後の台詞だ。
しかし翠那はそれを使わず、自分なりの言葉を紡いだ。
「大好きだよ」
桐原に伝わったのか分からないし、役に取り込まれているモニカは聞こえていないかもしれない。それでもよかった。キャラと役者のあやふやな境界で漂うのが、今はまだ安心できたから。
やがて人間の生み出す悲しみの雨が降る中で、看取られるように悪魔は死んだ。
全身に広がった傷は氷が割れるみたいに口を開けて、タチアナという存在を無へと帰す。泡が割れて後には何も残らないのと同じで、桐原の腕の中にはもう何も存在しなかった。
Next : 6/6
なかまに なりたそうに こちらをみている! なかまにしますか?
