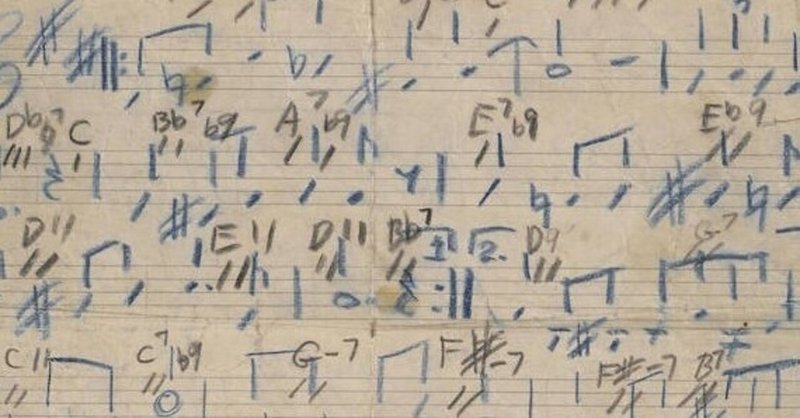
【短編小説】俺の知らない青
1
世の中には高校デビューというヤツがある。髪を染めてみたり、ピアスを開けてみたり、まぁ要するに高校入学を機にイメージチェンジをはかるというアレのことだ。俺はしなかったけれども、するヤツの気持ちはよくわかる。十五歳で、いまの自分に心から満足しているヤツなんていない。そして十五歳が自由にできるものはせいぜい自分の髪型と服装ぐらいだ。だけど、まさか、幼馴染のカズサが女装して登校するなんて思わなかった。ブレザーにチェックのスカートという女子の制服を着、新入生代表として壇上にあがったカズサがスピーチ原稿を読み始めたとき、体育館中にどよめきが走った。まぁムリもない、蜜を垂らしたようなつやつやの茶髪、白桃色の肌、モデルのように整った容姿だけ見れば、誰でもカズサのことは女だと思うだろう。そのざらついた低い声を聞かないかぎりは。ざらついた低い声で原稿を読み終えると、カズサは深々と一礼をして壇上を降りた。小雨のようなざわめきの中をカズサは悠々と歩いていたが、呆然としている俺に気づくと、悪戯っぽく微笑みながら手をひらひらさせた。
放課後。
スクールバッグを小脇にひとりで校門を出ていくカズサに俺は声をかけた。
「カズサっ!」
カズサは振り向くと俺の顔を見て足を止めた。
「あ、マキトじゃん。おつかれ」
「突然だけどよ、めっちゃつまんない質問してもいいか?」
「やだねー。つまんない質問なら今朝からもう何億回もされてるもん。するならおもしろい質問にして」
「……その格好って日替わり? たとえば明日は男子の制服で来て、明後日はシルクハットにマントで来る、的な」
「……んふっ」
カズサは吹き出すとおかしそうに笑った。
「……ふふ、何だよ、シルクハットにマントって。いまどきマジシャンでもそんな格好しねーだろ」
「まぁ、あくまでたとえだけど。どうなんだよ、そこんとこ」
「わかった、ちょっとツボったから答えるね。これは日替わりとかそういうのじゃないよ。僕は卒業するまでこの格好で登校し続けると思う」
「お前、中学までフツーに男子の制服着てたじゃん。何でまた急に……」
「そのフツーがイヤになったの。なんていうかさ、もう自分に嘘つくのやめようって思ったんだ」
「ウソ?」
「ん、今まで男の格好しててもずっと違和感があったっていうかさ、ホントの自分じゃない気がしてたんだよね。なんかこう、男っていう役割を演じてるみたいなさ。あのさ、去年の冬休み、みんなでふざけて女装したことあったじゃん」
「ああ、“全員全力で女装して誰が一番盛れるか選手権”な。みんな解ってたことだけど、ぶっちぎりでお前が優勝だったな」
「マキトは最下位だったね。でもあんときのマキト面白すぎて未だに待ち受けにしてるよ、ホラ」
「うわ、ちょ、マジでやめろや。これでも全力尽くしたんだから。人の努力を笑うな」
「んふふ、まぁアレがきっかけっていうか、引き金だったんだよ」
「マジで?」
「まじで。あのとき思ったんだよ、ホントの僕はこれかもしんないって。それからはネットで女物の服買って部屋で着るようになって、そんで外にも出るようになって、最終的にこうなったってワケ」
「……そうかァ。なるほどな。なるほどね〜〜〜〜〜〜。お前の人生は、アレで変わったのか」
「そ。わかんないもんだよね、人生を変えるできごとってさ、ものすごい大事件とかじゃなくてさ、あんがい誰にでもあるようなさりげない瞬間なんだよ」
「でも、親御さんとか学校からよくオッケー出たな」
「高校の合格発表出た日に、女子の制服で通いたいって親に話したんだ」
「うわあ。すげえ勇気いったろ、それ」
「すげえ勇気いったよ。でもさ、人からどう思われるかより、自分が自分をどう思うかの方が大事なんだよ。だから正直に、ぜんぶ話したんだ。女装して外出してることとかさ」
「どんな反応だった?」
「んー、まぁまぁやばかったね。でもさ、僕の人生は父さんのものでもないし母さんのものでもない、僕のものだから。認めてくれないなら学校も中退するし、家を出て一人で暮らすって言ったら親もようやく承知してくれてさ、学校にも掛け合ってくれたんだ」
遠い目をしながら言うカズサに、俺は思わず溜息を洩らした。
「んー、なんか、すげえな、お前……」
「すごくないよ。さっきも言った通り、もう自分に嘘をつくのをやめようって思っただけ。僕は、僕がしたい格好をする。だからもし、シルクハットにマントで学校に来たいって思ったらそうするかもしんない」
そういってカズサは笑った。四月の風がカズサの綺麗な髪を揺らしていた。
カズサと俺は幼稚園の頃からの友達だ。女の子のような見た目をしているためか、いつもイジメられていたカズサをかばってやったのが友達になったきっかけ……といったようなありがちなバックグラウンドは全くなく、気がついたら友達になっていた。明確なターニングポイントとかは覚えていない。気がついたら仲がよかったのだ。幼馴染なんてそんなもんだ。というかむしろイジメられていたのは俺の方で、カズサはそんな俺をよくかばってくれていた。度胸があって、機転が利き、面倒見も良いカズサはいつもみんなの人気者だった。
中学校に上がる頃になるとカズサは髪を伸ばし始めた。カズサの容貌がいかにスペシャルなのかを思い知ったのも大体この頃だ。一緒に街を歩いているだけで、いったい何度、街頭スナップやスカウトの類に遭遇したか解らない。それどころか無断で写真を撮るヤツさえいた。大体の場合カズサはそれを無視していたが、一度、サッカー部の親善試合の打ち上げで中華料理屋に行ったとき、カズサをこっそり盗み撮りしたオバサンの客がいて、そのときカズサは席から急に立ち上がると、ニコニコ笑いながらオバサンに近づき、その手からスマホを奪い取るとそのまま中華鍋の中に突っ込んだことがあった。何であのときに限ってカズサがあんなことをしたのかは解らない。それはまあまあな騒ぎに発展したのだけれども、カズサだけはずっと平然としていて、俺はそのとき『こいつは本物だ。何かの』と思ったのを強く覚えている。そんなヤツだったからいつか何かをやるだろうと思っていたけれども、まさか、こんなことをするとは思わなかった。
駅に着くとカズサは、それじゃまた。と言って小さく手を挙げると、俺に背を向けて歩き出そうとした。俺は追いすがるようにその後ろ姿に声をかけた。
「な、なあ、デリカシーない質問かもしんないけど、聞いていいか?」
振り向いたカズサはキョトンとした表情を浮かべたのち、口元に手を当てて笑った。
「ったくさ、マキトってホント律儀だよね。いちいち許可取りすぎでしょ」
「や、あの、こーゆーのは、その、デリケートなことだからさ……」
「いいよ、答えたくない質問だったら答えないだけだから何でも聞きなよ。僕のことでマキトがなんかわだかまりを抱えてるんなら、それは、ヤだから」
わだかまりしかねえよ、と心の中でツッコミを入れつつ、俺は恐る恐るカズサに尋ねた。
「あの、さ……なんつーかさ、お前が好きなのって、その、どっち、なんだ?」
「……どっち、って?」
「だから、その、つまり……男が好きなのか? 女が好きなのか?」
俺がそういうと、カズサは少し冷たい表情を浮かべ、低い声で返した。
「……そーゆーの、あんま聞かないほうがいいよ」
「あ、わ、悪ぃ……」
「まぁ気になるのもわかるけどね。わかるけど、好きってそーゆーことじゃないじゃん?」
「……どーゆーこと?」
「好きに理由なんかないじゃん。誰かを好きになるってことに、性別とか年齢とか国籍とか、そんなの関係ないよ」
そしてカズサは肩をすくめて笑うと、踵を返して歩き出した。俺は小さくなってゆくカズサの後ろ姿をずっと見つめていた。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
