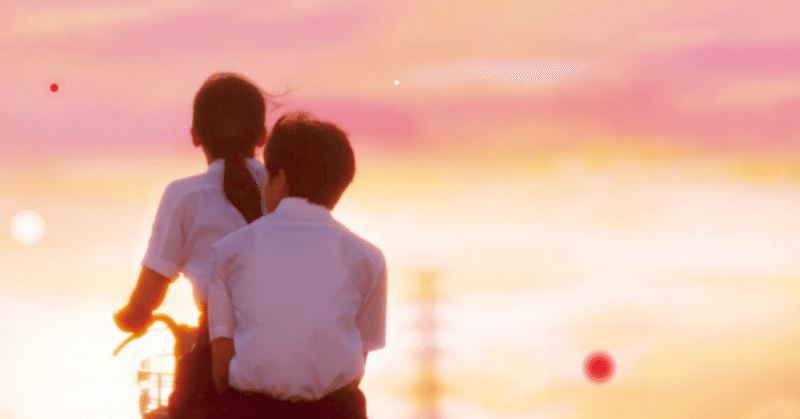
『茜色に焼かれる』石井裕也監督作品 田中良子、理不尽と闘うためのアイテムは「ルール」なのか。「ルール」って何さ?
トップの写真は、リンクした公式サイトより、拝借しました。2020年、去年の初め。中国武漢の状況から知らされることになった新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界に広がり、日本でも緊急事態宣言が出され、社会の機能が一時停止した、その頃。
「誰も助けてくれないんだ」
うちの娘がそう話した。若い彼女は、それまでは日本の国の政府や行政は、非常事態が起きたとき、弱い立場の人が困ったとき、助けてくれるものだと思っていたという。
ところが、現実に、社会が停止し、多くの業者が仕事をなくす中、国も政府も行政も、決して積極的には、助けようとはしなかった。感染の有無を調べる検査は異常なほど抑制され、感染対策は各自に任される。給付金はわずかに十万円が一回のみ。さまざまな支援金や援助制度があるというが、そのほとんどは国や自治体からの貸付金であり、要するに借金だ。仕事がなくなり、現金収入を失った人たちに借金を背負わせる。それを普通は「助ける」とは言わない。
「死ぬしかないんだね」
お金がなくなったら、死ぬしかない。20代後半、未婚、低収入の彼女の実感のようだった。
我が家は、たまたま夫がすでに年金生活で、定期的に厚生年金が支給されるし、たまたま近所にバイトが見つかり、わたしも働いているし、さらにたまたまコロナに影響されない職種ーマンションの掃除と高齢者向けの宅配弁当ーで仕事を失うこともなかった。収入は、コロナ以前と以後で変わってはいない。
しかし、こんなのは、本当にただただ「運が良かった」というしかない。パンデミックの影響下で、仕事を失い、住居を失い、命をも失った人たちは、夥しい数になる。誰にも助けられることもなく。目に見えないように。消されていくように。
映画『茜色に焼かれて』は、そんな誰にも助けられない。ただ見捨てられていく人々が、実際に、現実に生きている。この国の、今現在について、おそらくは、目に見えるように、顕になるようにと描かれた映画なのだと思う。
主人公の田中良子は、夫を交通事故で失う。7年後、加害者の葬式に出向き「いやがらせをするな」と追い返される。加害者は、元官僚で葬儀は大変に立派なものだった。彼女はなぜ、そういう行動をとるのか。
「一言も謝らなかった」
「虫けらのように扱われた」
一見して、このエピソードのモデルは「池袋暴走事故」だとわかる。「上級国民」という言葉が生まれ、加害者の老人もバッシングされたが、被害者の家族もなんら報われることのない。「一言の謝罪もない」事件だと記憶している。
具体的な事件への言及というよりも、現実の理不尽さで、一度弱い立場に置かれると、圧倒的にもうそこから逃れられなくなってしまう、今の世の中の「仕組み」について。映画の中で田中良子が、執拗に繰り返す「ルール」という言葉にも、その「仕組み」についてが、込められているのだと想像できる。
その「仕組み」の中で、母子家庭は、お金のない若い女は、結婚していない女は、虐待された子どもは、風俗に入り浸る男は、みな困窮し、ちょっとでも上の立場だと錯覚している者は、平気で他者を見下し、蹂躙する。
田中良子は、いろんな男に怒っていたが、あたしが一番頭に来たのは、風俗に出向いて「高い金を払ってるんだ、気持ちよくなかったら。お前が死ね」と若い女の子に向かって言ったハゲの男にだった。殺す…殺せるものなら、殺してやる。このチンカス野郎が!
息子の通う中学でのいじめも「売春婦が税金で暮らしてる」とか「交通事故で父親が死んだから税金で食わせてもらってる」とか、おめーらツイッターの見過ぎか? ネトウヨの親がいんのか? ほんとのバカか?とぶん殴って潰してやりたくなる。
こんな中学生がいるわけないとか思う、心優しい人たちもいるでしょうが、子どもたちがいるんでなくて、大人がいるから、こういうバカが育つんだよ。ほんとにありえないって思いたいけど、あるある過ぎるとしか思えないわたしが嫌だ。
怒りは、わたしの中にも、どろどろたごまっている。だけどこうやってネットで呟いてみたりするだけで、現実には、ただ飲み込むばかり。あるいは理不尽から逃げるばかりでしかない。だからこそ田中良子の噛み締める怒り、押さえつける感情、ブルブル震える貧乏ゆすり、「なんだかわからない」自分がどうなってるのかわからない感覚は、多分、ものすごくリアルだ。誰にとっても。
わけのわからない「ルール」に閉じ込められて。はみ出せば縁に転がり落ちれば、もう誰も助けてくれないのなら。怒りを表現して何が悪いのか?
田中良子を舐め腐った悪い男に向かって放たれた、純平の飛び蹴りは、最高に爽快だった。
映画に不満があるとしたら。
母親の無償の愛、みたいなもん。さらには、「愛しちゃった」んだと、女の情念、欲望を人間の原点回帰のごとく、生命の力のごとく、ラストに持ってきてしまったことだろうか。
映画の中の男は、13歳男性未満の純平以外、全員ダメ人間だ。上級であろうと下級であろうと、ロックミュージシャンであろうと、ただ平民だろうと、とにかく全員、男はダメ人間だという断罪は、40代男性監督の自虐なのか反省なのか、問題提起なのか、知らんけど。
あたしには、逆にそんなものは、信じることができない。あたしもまた母親であり、女だから。
なんでそこまで母に、女に、頼るの? 納得できません。
というところまで含めて、田中良子の映画なのだとしておきたい。
朝になったら、まさに映画について、一つの答えのような記事があった。母子家庭の多くの母親は、限界まで働き、生きていると。「普通の家庭」が働く夫とパートの妻なんだとして。夫が死んだり、離婚したら、多くの妻と子は貧乏になる。河野太郎の言ってることは、ただの世間知らずの坊ちゃんが甘ったれた考えを垂れ流しているだけだ。
自分がそういう立場になりえるーかもしれないという想像力が一欠片もない。だからこの世界には、映画や小説やテレビドラマや音楽や演劇や落語や様々な表現があるのに。人間は見たいものしかみないから、河野太郎も何も見てはいないのだろう。頼むからもっと勉強してくれ。人文が大事じゃないなんて、本当に間違ってる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
