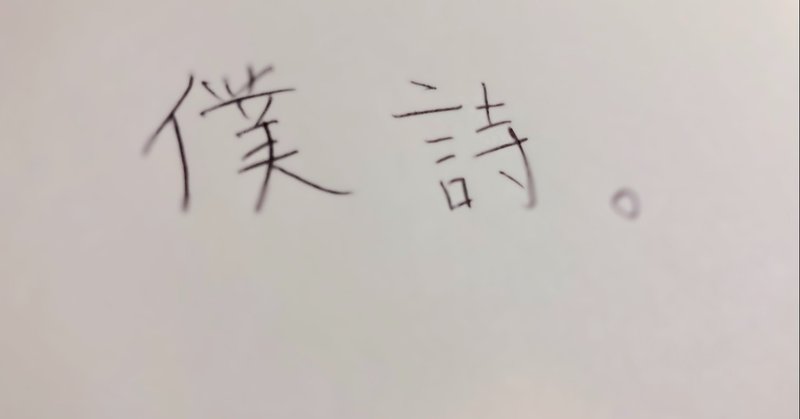
僕詩。 2.家出
聡介を乗せた電車は、がたんごとんと揺れなが進んだ。
息を切らせて、空いている車両へとうつった。座席に座り混むと、どきんどきんとうるさい胸の音が、だんだんと恐怖に変わった。
家を出てきてしまった。持っているのは財布と鍵とスマホだけだ。この急行はどこまでいくのだろう?自力で戻れる範囲だろうか?車掌のアナウンスが流れたが、よく聞き取れなかった。目を閉じて、深く呼吸をする。家を、出てきてしまった。
ポケットに入れていたスマホが振動した。取り出すと、「どこにいるの?」と母から連絡がきていた。
「今電車。今日中には帰るよ」
無事でいることがわかれば、深く聞いてはこないだろう。今日中に帰るといえば、追ってこないだろう。
聡介を乗せた電車は、日常をぐんぐん追い抜いて、非日常へと路線を変えた。今日1日くらいは「自由に」なってやる。聡介は財布を確認した。とりあえずご飯も食べられるし、帰りまでもつだろう。そうだ海に行こう。波の音がききたい。潮風をかぎたい。そこでぼーっとするんだ。なにもしないで。夕日が沈むまで。少し寒いかもしれないけれど。
乗り換え案内をみながら、電車を乗り換えた。見慣れない景色にドキドキした。本当にやっていいのだろうか。これは家出だ。でも、なにもずっと帰らないわけじゃない。
周りの人がみな、自分を見ているような気がして怖かった。なるべく目を伏せた。耳も塞ぎたかった。平然を装いながら、内心は怯えていた。
やがて聡介は駅を降りた。コンビニでおにぎりとお茶を買い、地図を見ながら海辺へ行く頃にはあたりは夕日の色に染まり始めていた。
汚い砂浜に腰をおろし、聡介はぼーっと海を見た。ここまで遠かった。実際は1時間くらいだったのだが、もっと長く感じられた。
遠くに船が見える。ざざあん、ざざあんと波音がきこえる。潮風というにはやや生臭い風が、聡介の髪を撫でていった。
ずっとここにいるわけにはいかない。
でもいまはここにいてもいいだろう。
桟橋のほうにはカップルやお年寄りや家族連れがいた。砂浜の方には聡介以外いなかった。冷たい風が頬を赤くした。
おにぎりを頬張り、お茶を飲みこんだ。聡介はそのまま、日が落ちるまで、海と一緒にゆれていた。母親から「夕飯はハンバーグ」と連絡がきているのを知ったのは、すっかり日が落ちてあたりが暗くなってからだった。
学校へいく時間なのに、聡介は布団から出ることさえできなかった。部屋のドアをノックする音。母親だろう。
「聡介、具合が悪いの?学校に電話しようか」
「うん今日は休む」
「じゃあ電話しとくから」
返事はそれだけだった。部屋を離れていく足音。理解の良い母親で良かった。昔から行きたくないと言うと「じゃあ休みなさい」と言ってくれた。テストがあってずる休みをしたこともあったけれど、基本的には真面目に学校に通っていた。どうしても、学校に行けない日がある。そういうときは休ませてくれた。そのおかげで、どれだけ呼吸が楽になっただろうか。
そうだ、今は息がくるしい。胸がくるしい。もう歩けない。起き上がれもしない。布団の中で聡介はため息をついた。倦怠感がだんだんと眠気に、そして夢の中へと聡介をひきずりこんでいった。
また夢だ。
聡介の手の中にはなぜかセラミック包丁があった。また街には人がたくさんいる。車は見当たらない。人がざらざらと歩いていく。顔はわからない。大人も子供もお年寄りも、ゆらゆら歩いていく。聡介はなぜか彼らを倒さないと次の場所に行けない気がしていた。次の場所がどこなのかはわからない。だから聡介は暗い影のような人を、手に持ったセラミック包丁で刺した。ぶすっという感触がある。だけど綿を刺したように感じられた。刃を抜いても血飛沫はなかった。安心して聡介は次々と綿人間を刺していった。次の場所に行くために、いったい何人倒せばいいのだろう。さすがに疲れてきた。刺しては抜き、抜いては刺す。息ができない。
目がさめてすぐ、時計を見た。10時7分だった。息が苦しかった。胸に鉛が埋め込まれているようだった。頭は混乱していた。夢で良かった。ああ、夢で良かった。こんな夢見たくなかった。だから眠るのは苦手なんだ。
午後になると、すぐれなかった気分が少しよくなってきた。散歩に行こうと思っていると、母親が部屋をノックした。
「聡介、ちょっといい?」
「いいよ」
母親はベッドの聡介の隣に腰掛けると、膝元に視線をおとして言った。
「学校、しんどい?」
「・・・・今はしんどい」
「父さんのこと、知りたい?」
「知りたくない」
「学校は気のすむまで休んでかまわない。でもひとりで溜め込みそうなら、そうね、ノートに詩でも書いてみたら」
「・・・詩?詩ってどうやってかくの?」
「なんでも。聡介の思ったこと。感じたこと。文章にしなくていい。自由にかけばいい。母さんもね、昔書いてたの。やっぱり学校に行けなくなった頃があってね。頑張りすぎて、しんどくなって。気が向いたらでいいのよ」
「わかった。気が向いたらそうする」
「さてと」
母親は立ち上がってのびをした。そしていたずらをする子供みたいな顔で「ゆいちゃんが心配してたわよ」と言った。
「・・・・あっそう」
「ゆいちゃんはいい子ね」
「ふーん」
じゃあね、と母親は部屋を出ていった。聡介は布団に寝転んだ。松野ゆいの顔を思い出していた。ほんのり心に明かりがともるような、少し幸せな気持ちになるような、それでも届かない月に手を伸ばすような、そんな気持ちだった。
彼女の髪はきっと花の香りがするのだろう。手はきっと小さくて温かいのだろう。唇はきっとやわらかいのだろう。ぎゅっと抱きしめたらきっと笑って困りながら「どうしたの」と言うのだろう。それとも嫌われてしまうのだろうか。
聡介はいつの間にかまた眠りに落ちていた。しかし悪夢ではなかった。どこまでも続く草原と青空のあいだを、風のように、自由に飛び回る夢を見ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
