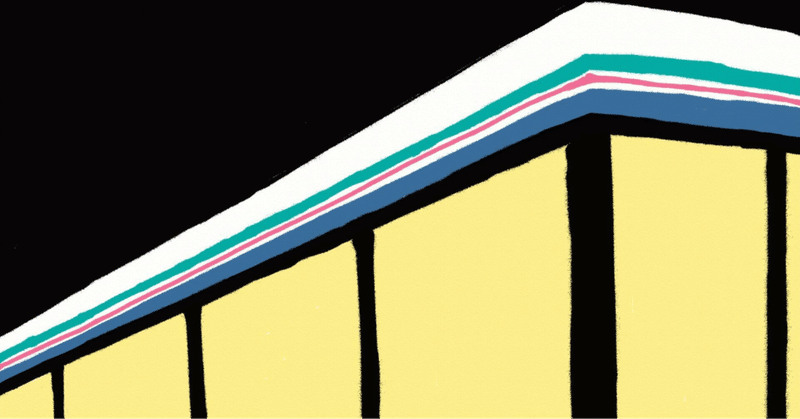
残高125円のオンナ
鞍馬はこう思った。
世の中でよく聞く、
「えー!お金無いんです⤵︎⤵︎」
とか
「今月はもうお金使えないです〜」
そんなもの全部空っぽに聞こえる。と。
本当に金のない奴が金のことを気にするなんて有り得ない。彼女はそう思っていた。
真の金が無いやつ、そして真の金持ちは自分の貯金残高なんて知らない。考えない。
相反する二者が唯一共通する点だ。
時は遡り、場所は北海道。札幌市において最強の繁華街で夜も眠らない街、ススキノ。北の歌舞伎町とでも言うべきか。そこに鞍馬と東雲はピザを食べに来ていた。
「マルゲリータマジ美味い」
「彼氏丸刈りにした。マジ怖い」
怖いのは君だ。鞍馬はそう思った。
一枚八百円で食べれるピザ屋があると聞いて2人で夜な夜なやってきた。街は週末もあるせいか人で溢れかえっていた。
ただこのピザ屋は閑散としている。
こんなにも美味しくてコスパが良いのに客は2人の他に、スーツを着たサラリーマン風の男性とカジュアルなパンツスタイルの女性しかいない。
鞍馬は入店した時こそ、その異変に気づいたが次第に気にならなくなっていった。
なんせ隣にいる人間が全てをかき消してくれるからだ。いつの間にか東雲のピザは無くなっており、2枚目を追加注文していた。
そんな時だった。
「仕事、辞めたい」
そう鞍馬は呟いた。
2枚目のマルゲリータを食べ始めていた東雲はその手を止めず、聞き返した。
「なんかあったの?」
鞍馬は、その時とある清掃会社に勤めていた。
そこの社長は、どこにでもいる情緒不安定パワハラクソジジイだった。社長の機嫌によってその日の仕事量は変わってくるし、新しく入ってきた人は皆すぐに辞めてしまう。怒鳴られるのなんて日常茶飯事。
ある時現場での作業中、何が彼の逆鱗に触れたのか全くわからないが突然怒鳴られた。
鞍馬はいつものことだなぁと思い適当に受け流していると、
ペシャッッ
冷たい感覚が鞍馬を襲う。
鞍馬は一瞬何が起きたのか分からなかった。
なんと彼は足元にあったバケツを鞍馬に投げてきたのだった。
中身は黄色のペンキ。
うそやーーーーん
驚き過ぎて声も出なかった。が、実はこれに似たことは今までにもあった。
電動丸ノコをぶん投げられたり、登ってる脚立を蹴られたりなどぶっちゃけこの行為に慣れてしまっていた。
しかしその慣れが鞍馬をより一層蝕んでいった。
ぶつぶつ文句を言って現場を去る社長。
髪の毛が黄色くなった鞍馬。
なんだこりゃ
鞍馬はもう笑うしかなかった。
東雲は話を聞いている最中ずっとピザを食べていた。話が終わると同時に彼女は2枚目のピザを完食した。
「今すぐ辞めなよ」
おしぼりで手を拭きながら東雲は粛々と言った。
「アンタの顔面でスプラトゥーンのゲームしてたの?」
東雲はいつになく厳しい表情で鞍馬に訴えている。
「その仕事続けてたってたぶん何にもならないよ、自分削ってまでやりたいことなの?スプラトゥーンって?」
スプラトゥーンから離れてほしい。心の中でツッコミを入れたが声には出さないよう鞍馬は努めた。
「その頭もまばらに黄色くなってるし、自分で染めたの?ダサいよ、目覚せ、生きろ」
違う、この頭はペンキの名残なんだ、私のセンスじゃないんだ。誤解しないでほしい。またしても鞍馬は心の中でツッコミを入れた。
ただ、彼女に言われた、
生きろ。
その一言が鞍馬の心を強く掴んでいた。
鞍馬は今まで自分のことじゃなく相手の機嫌を取ることだけ考えてきたことを今、思い知らされていた。
そうだな、もっと我儘に生きても良いんだよな。
そう思い始めていた頃にはもう頭は澄み渡っていた。
「辞めるわ、会社」
そう言ってみた途端、スッと心が軽くなった気がした。
東雲は笑いもしなければ茶化したりもせず、
「みんな大丈夫なんだよきっと。何してたって」
そう言って彼女はいつの間にか頼んでいたコーラを飲み干した。
彼女の不器用な優しさが好きだ。余計なことは何も言わない単純なのに不可解な愛情がとても好きだ。そう鞍馬は思った。
その後は二人、たわいもない会話を心ゆくまで楽しんだ。
「あ、ちょっと財布に金入ってなかったからおろしてくるわ」
会計を済ませようと財布を出した矢先、東雲は店を出て近くのコンビニに走って行った。
10分ほど待っていただろうか、東雲は帰ってこない。
痺れを切らした鞍馬は2人分の会計を済ましピザ屋を出て、東雲を探した。しかし彼女はいなかった。電話をかけようと思ったが残念なことに充電が切れてしまっていた。
食い逃げをするような奴では無いことはわかっていた。
まさか、誰かに絡まれているんじゃ?鞍馬の中に嫌な不安がよぎる。近くのコンビニを手当たり次第探し歩く。星が綺麗な夜だった。
3軒目に尋ねたコンビニの喫煙所。空を見上げて煙を吐く東雲を見つけた。
ホッと安心し、歩み寄って鞍馬も東雲の隣でタバコを吸い始めた。
「なんかあったのか」
鞍馬はゆっくりと煙を吐き出しながら問いかける。
東雲は相変わらず空を見上げている。今日は空気が澄んでいる、だから星がよく見えるのだ。つまりめちゃくちゃ寒い。
もう2人とも勝手に体が震え始めていた。
そんな東雲から出た言葉は、鞍馬の予想できるものではなかった。
「残高125円だった」
もう東雲は明後日の方向を向いていた。
それ、手数料も払えないよ、、
鞍馬はその言葉を飲み込むようにそっとタバコを吸った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
