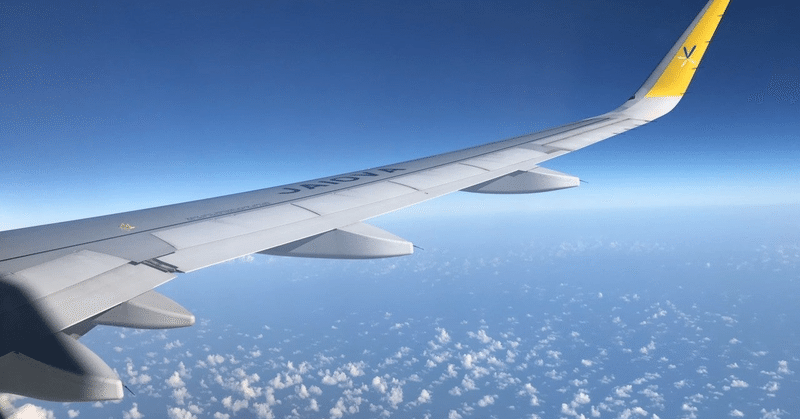
『ジャーニーシリーズ本読みの会 チーム・ジャーニー第9話「塹壕の中のプロダクトチーム」』に参加してきました。
表記イベントに参加してきたので、感想を記載します。
チームジャーニーの著者による読書会で、9話、10話について聞いてきました。前回の読書会はコチラです。
9話 塹壕の中のプロダクトチーム
9話は第2部として新しい話となります。単体のチームではなく複数のチームでプロダクトを作ることになり、チーム間の認識が合わないといった話になります。
・ユーザー、ビジネス、プロダクトに対しての価値を気にして情報(血)を回していく。加えて、マネジメントという立場で見ると「ユーザー、チーム、プロダクト」の視点で扱っていくと良い。
・チームのミッションを達成するための作戦については非常に重要。我々はいかに作戦を立てられてないか?という事の理解が必要。
<作戦についてのメモ>
・作戦とは何なのか?誰がいつ考えてどうしていくのか?
・ミッションとタスクの間には距離感が合るので、作戦が必要
・作戦は何をどうやって行くのかといったもの、スプリントゴールとバックログの積み上げだけではミッション達成は困難(特にチーム活動、組織としては必要)
・作戦自体も変えていかないといけない。(スプリント、仮説検証が進むなかで新たな事実が分かるので適用しないといけない)
・将棋で言えば「定石」。プロダクト作りでいうと『PSF.PMF』とかの「仮説」も作戦に近い
10話 チーム同士でむきあう
10話ではチーム同士牽制し合う状況から、プロジェクトの体制設計を見直して、情報の同期・可視化をし始めるという内容でした。
・大丈夫でないことがみんなで共有できることが収穫(本のストーリーより)
・情報共有の設計が重要(情報自体の内容による切り分けもいるし、チームの階層自体を意識した情報設計も重要)
・ワークショップ等では逆に「空気感」に引きずられないような一手も重要。「空気感」は良い点も悪い点もある。目的や設計が重要
感想
市谷さんも第2部から難しくなっていると話していて、面白かったです。私もこの本を最初に読んだとき、正直理解できないことが多かったのですが、未だにやはり難しいと感じます。
本日話に上がった、作戦についても重要性は理解できるものの、具体的な作戦というものが、自身で言語化ができてないという事を把握できました。この件は仕事のなかでも何回も指摘してもらっている事なのですが、未だに理解しきれてません。この作戦の感覚をしっかり持っているといいんだと思います。
何となく、作戦については『ミッション』と『依存関係』と『達成基準』みたいなものが混ざったものというような概念を持っています。市谷さんからは『仮説検証の要素』が作戦では重要と話がありました。仮説キャンバスの整合を検証して、崩して育てていく具体計画が『作戦』かなぁ?ただキャンバスもプロダクトに集中して作るので、その上位概念や下位概念もあると思うので、、、、と考えてて、混乱してきました。
今年は『作戦』を言語化する年にしたいと思いました。ありがとうございました。
また、10話で話があがった情報共有の設計については、同期の設計の話も重要ですし、チームトポロジーを読んで、チーム自体の機能目的設計が、より重要だなと思っていて、チームジャーニーを最初読んだ時より自身の理解が多少進んでいるといった、自身の進化を感じることもできました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
