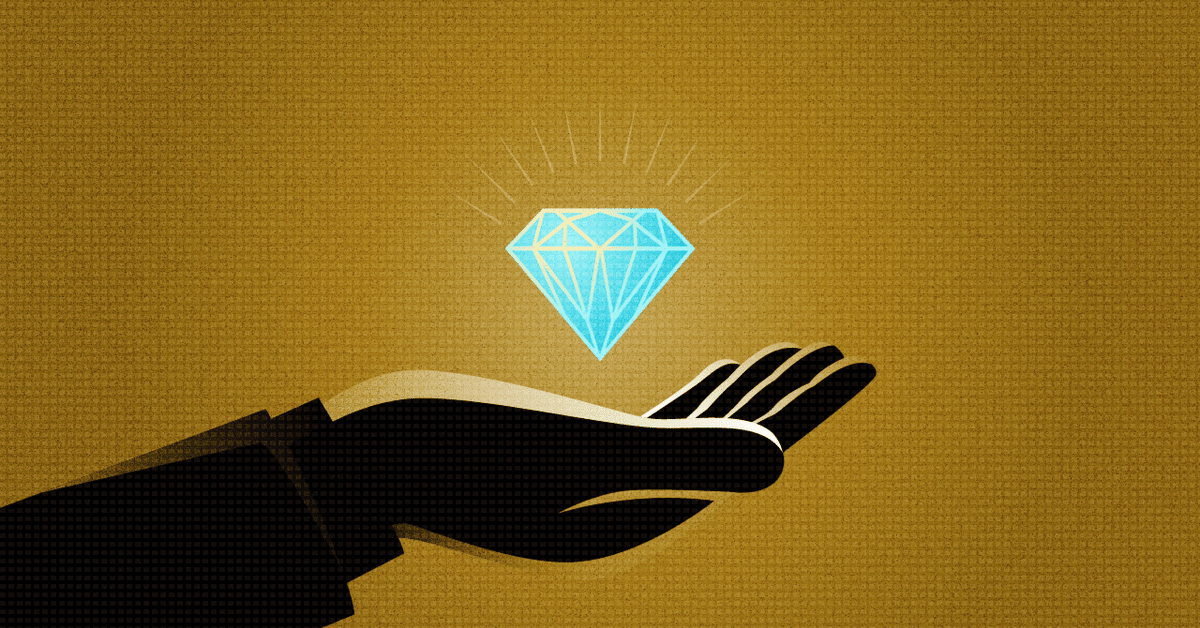
技術開発の要【その1】
特許調査は『一過性』では意味がない?
中小やベンチャーの企業様においても、
近年は新製品の開発に伴って特許を含む知財調査を行っている企業が増えてきています。
最近では、開発資金調達の一部として公的補助金などを申請した場合、
面接審査において
「知財について手当をしてあるか?」
「知財侵害の心配は無いか?」
「模倣対策はしていますか?」
などと聞かれることが多くなってきています。
これに自信をもってYESと答えるには、
もちろん事前に十分な特許調査を行っていなければなりません。
つまり、一過性でピンポイントの調査を行ったぐらいでは、新規の技術情報(論文、特許公報など)は常にアップデートされているため、十分とは言いきれないわけです。
この観点から、幣社では、知財部を持たない、または技術者が知財部を兼務しているような中小・ベンチャーの企業様に向けて、伴走型特許調査サービス『PatHelp』を提供しています。
意外と細かい?特許調査の種類
【特許調査】と一言で言っても、
その時期や内容に応じて多様な種類のものがあり、要望に沿ってカスタマイズすることもできます。
例えば、典型的な調査態様としては以下のようなものが挙げられます。
大手企業から毎月、公知文献の調査依頼を大量に受けて捌く特許調査
侵害訴訟等に使用するため、特定のテーマ(対象となる特許権など)及びその周辺を深く掘り下げる特許調査
市場動向を知財面から探るために行う特許調査
競合他社の技術動向を探るために行う特許調査
出願内容が既に定まっていて、その技術背景となる公知例を探す特許調査
上記のうち、弊社では3~5を対象に承っており、
公知資料の調査を中心に出願まで、あるいはその後のフォローを特許調査の観点から長い期間に渡って行っています。
なぜ継続的な特許調査が必要なのか
「継続的」とは
例えば半年~数年単位での調査を指しますが、
その理由はシンプルで、新製品や新技術の開発には時間が掛かるからです。
その開発過程の多くは試行錯誤の繰り返しになり、
一過性の調査をピンポイントで行っても最終製品はそれから外れてしまうことが多いのが実情。
結局のところ、首尾よく権利化できた場合でも製品さえ守れないことがあるのが特許の世界なのです。
そのような場面を多く見てきて痛感していることは、
どうしても一定期間、企業と伴走して紆余曲折が想定される開発工程に寄り添った情報収集、臨機応変の調査、アドバイスなどを双方向でタイムリーに行なう必要があるということ。
開発現場からの一方向の情報提供に頼った調査では
例えば出願前に公知にしてしまうなど、
重要なタイミングを逸失することが多くなってしまうのです。
また、特許調査を一定期間行うことによって、
技術アイデアや技術着眼点の蓄積が次の開発に役立つばかりか、場合によっては特許出願をしなくても済むことも有り得えます。
つまり、そのような知見や情報を蓄積することで、
その改善や工夫をノウハウとしてキープしておいても良いとの判断が可能になってくるのです。
(ただし内容によっては、弁理士に相談することをお勧めします)
次回、特許調査の有用性を端的に示すものとして、
少し古いですが、韓国発の2019年の新聞発表のものをご紹介します。
中小・ベンチャー企業様における技術開発のまさに要とも言える内容です。次回更新までお待ちいただけたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
