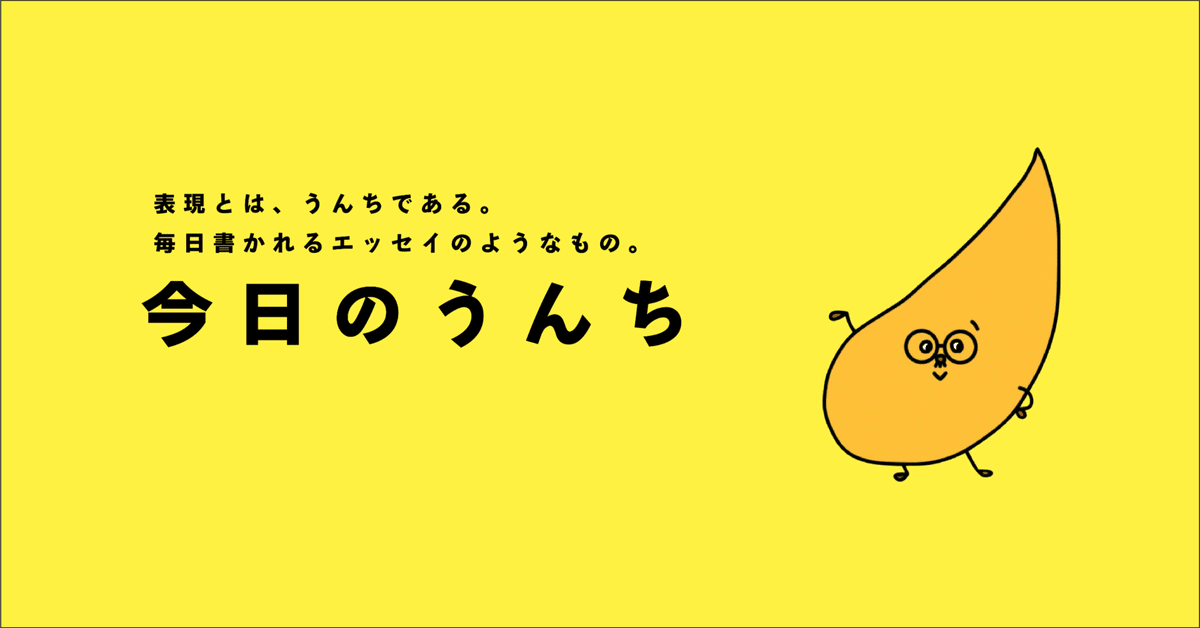
問いと答えは似たような表情をしている
*きのうは、哲学者の谷川さんとのトークイベントでした。「ネガティブ・ケイパビリティ」という、一度立ち止まって答えを保留する力についてや、スマホ時代の哲学など、現代の哲学をいろいろと研究されている谷川さんのお話は、非常におもしろかったです。何がおもしろかったって、話している内容ももちろんなんですけど、それ以上に「話し方」や「応答の仕方」がおもしろかったんだよなぁ。
特に最後の質疑応答の時間では、質問された内容、つまりクエスチョンに対してアンサーを返すのではなく、新たに問いを乗っけて返すというやり方を終始されていて、その姿勢がまさに哲学者だった。どうしても質問をすると、相手の答えを求めて、その答えに縋り付くというか、鵜呑みにしちゃいそうになるものなんだけれど、いい意味でそれをさせてくれない。自分に浮かんだ問いに対して、また新たな「?」を乗っけてくれるので、ずっとボールで遊んでられるような感覚がある。
今日話した内容の中でも「答えと問いは、似たような顔をしている」という谷川さんの言葉がすごかったなぁ。何かしっくりこない答えが出たりしたときは、答えが合っているとか間違っているとかではなくて、「問い」のほうがあまり良くないものなんだと。答えがしっくりこないときは、その答えを引き出している問いかけの方が実はしっくりきていないというのは、よく考えたら本当にその通りで、わかりやすい例えだった。
そうだ、「答え」がアウトプットだとしたら、「問い」はインプットのようなものだ。いい答えが出ないとき、アウトプットがうまくいかないとき、どうしてもアウトプットのやり方を変えようとしたりしてしまうのだけれど、本当に大切なのは、その手前にある「インプット」の方なのだ。冷蔵庫が空になっているのに、料理のしようがない、という感じだね。きちんと仕入れに行って、いい素材を揃えて、初めて料理ができる。気付いたら簡単なことなんだけれど、忘れがちなんだよなぁ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
