
令和6年6月19日(水) 赤口 甲寅
起床時間 午前5時40分
血圧 111-67
脈拍 52

読んでから観るか、観てから読むか。これは映画とその原作本の順序の問題。あまり映画を観てこなかった人生なので、これについて考える機会が少なかったが、最近は映画に触れる機会が増えてきたので、少し振り返ってみる。

「鉄道員」(浅田次郎)。これは、読んでから観て、そしてまた読んだもの。他の作品も面白かったし、DVDまで買ってしまった。人気作家なのに、出会うのが遅かったかも。

「終わった人」(内舘牧子)、「総理の夫」(浜田マハ)。これは、読んでから観たもの。原作の方に軍配・・・かな。ちなみに、「総理の夫」は、小生のアマゾンプライムビデオ・デビュー作品。
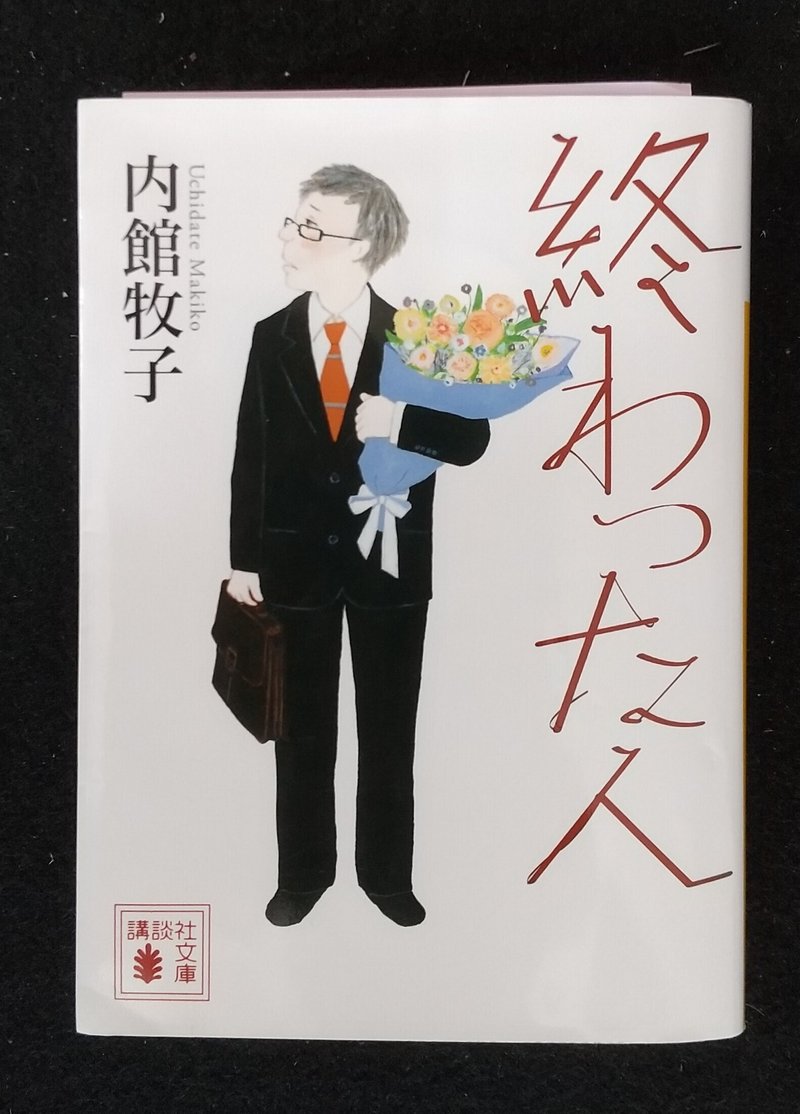

「海の見える理髪店」(荻原浩)。これは観てから読んだもの。原作も映画(テレビドラマだったかな)も、文句なく面白かった。ただ、高校生の頃には、もう頭のつむじが無くなっていた小生には、辛い場面があった。
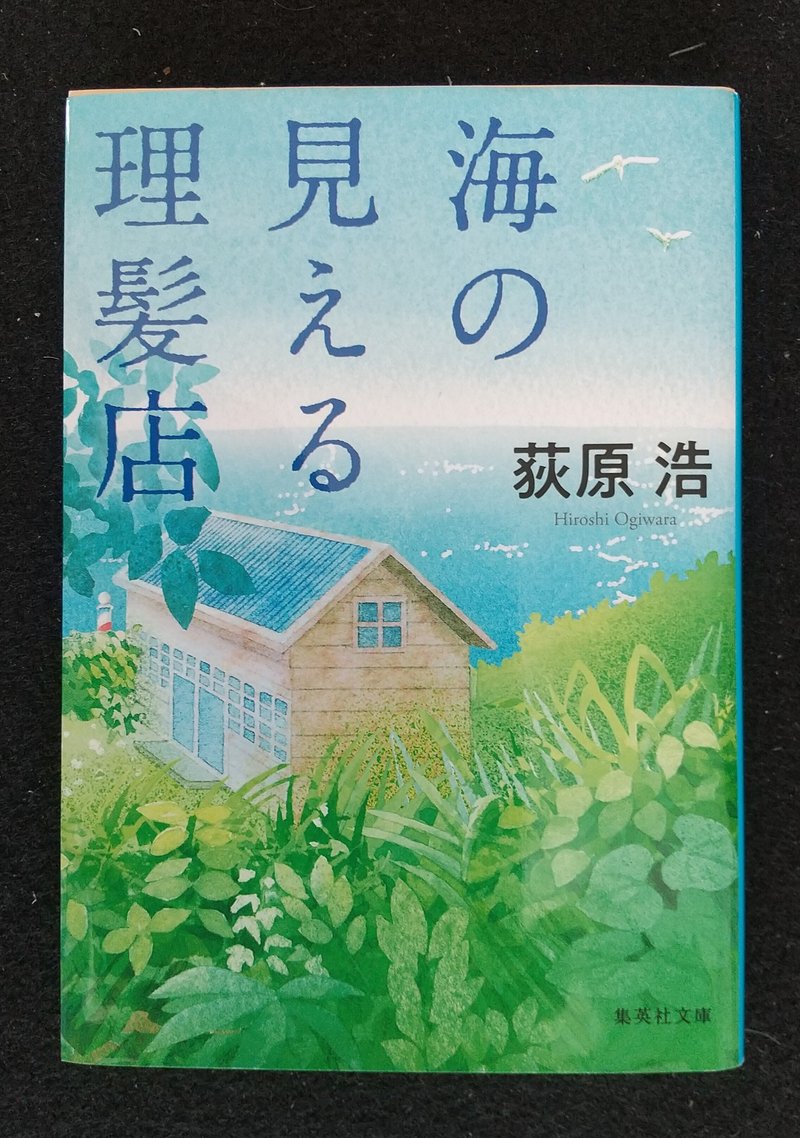
さて、日本経済新聞の春秋を読んでいて、「十二人の怒れる男」という有名な映画があるのを知った。
場所はニューヨーク、12人の陪審員が集まって・・・と聞いただけで、映画好きの方ならシドニー・ルメット監督の名作「十二人の怒れる男」(1957年)を思い出したことだろう。(中略)同州では陪審員全員の意見が一致しなければ決着しない。作品の見どころはまさにそこで、ただひとり被告の無罪の可能性に賭ける陪審員(ヘンリー・フォンダ)が、次々と他の11人の主張を覆していく。
観たことがない映画だし、ヘンリー・フォンダが誰だかも知らないので、アマゾンプライムビデオで慌てて観た。映画好きが思い出すほどの名作とあって、他の11人の主張を覆していく過程は確かに面白かったし、何よりも英語の勉強にもなった。
We have nothing to gain or lose by our verdict.
This is one of the reasons why we are strong.
No jury can declare a man guilty unless it's sure.
民主主義と公正な裁判のあり方を語る、象徴的な台詞だった。

そして春秋は語る。
出自も職業も価値観も異なる人々が、徹底的に考えを述べ、結論に至れば完全に同意できなくても従う。その合理的なプロセス自体を尊重する。
この映画を観た隠居にとって、古き良き民主主義を懐かしむ日となった。

【きょうの英単語】
shore up
analogous
boon
iodine
lose out to
plaque
rampant

【株式市場】
日経平均 38,570.76(+88.65)
NYダウ 休場
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
