
FACT FULNESS 世界の教養 by エシモの備忘録
ファクトフルネスとは、常識の中に隠れた思い込みに気づくこと。
どうも、エシモです!今回はハンス・ロリング著「FACT FULNESS 世界の教養」のまとめを共有します。この本が訴えている内容を一言で言えば「世界はゆっくりと良くなっている」です。しかし、私たちは「世界は悪くなっている」と思いがち。そう思ってしまうのは人間の本能だから。ハンス先生はその本能から解放してくれます。
それでは参りましょう、レッツ備忘録!
◆ファクトフルネスの10個のルール
⒈分断本能を押さえよ
極端な数字の比較に注意せよ。人や国のグループには必ず、最上位層と最下位層が存在する。大半の人や国はその中間の、上でも下でもないところにいる。アフリカの紛争地域と一部の東アジア諸国を含めて8億人が井戸水を使い、靴も買えず、炭火で調理し、地べたで寝ている。この極度の貧困と言われる生活を送る人の割合は1800年代からどんどん減少していて、私たちが生きている間には、誰もが水道を使えて、ガスで火を付け、ベッドで寝られる生活が実現されるだろう。世界は良くなっているんだ。
⒉ネガティブ本能を抑えよ
世の中に溢れるのは大抵ネガティブなニュースだ。それはネガティブなニュースの方が、圧倒的に耳に入りやすいからだ。商業メディアは人々の注目を集めなくてはならない。だから悪いニュースを広めることに注力しているんだ。本当は悪いニュースと良いニュースは両立していることを覚えておこう。

●ニュースの特徴
・良いニュースは流れない
・ゆっくりとした進歩はニュースにならない
・悪いニュースが増えても、悪い出来事が増えたとは限らない
・人々はいつも過去を美化したがる
⒊直線本能を抑えよ
世界の人口はひたすら増え続けると言う思い込みをなくそう。ワクチンが普及し、避妊方法が広まり、子供の生存率が高まればどの国でも生まれた子供はちゃんと大人になれる確率がほぼ100%になる。だから必要以上に子供を産まなくなるのが自然だ。世界の人口は2100年頃から100億人から120億人で安定するとみられている。

グラフはまっすぐになるだろうと言う思い込みに気づこう。なんでもかんでも直線のグラフを当てはめないようにしよう。多くの場合データは直線ではなく、S字カーブ、滑り台の形、コブの形、あるいは倍増する曲線の方が当てはまる。
⒋恐怖本能を抑えよ
人は誰しも身体的な危害、拘束、毒(ウイルスなども含む)を恐れているが、それがリスクの過大評価につながっている。リスクを正しく計算しよう。

リスク算出の公式
リスク=危険度(質)×頻度(量)
恐怖でパニックになっているときに、大事な決断をするのは避けよ。
⒌過大視本能を抑えよ
ただ1つの数字が、とても重要であるかのように勘違いしてしまうことに気づこう。常に比較対象を見つけて、割合を導き出そう。
●比較のポイント
・この数字は、どの数字と比べるべきか
・この数字は、1年前や10年前と比べたらどうなっているか
・この数字は、似たような国や地域のものと比べたらどうなるか
・この数字は、どの数字で割るべきか
・この数字は、合計するとどうなるのか
・この数字は、一人当たりだとどうなるのか
●80:20の法則
項目が並んでいたら、まずは最も大きな項目だけに注目しよう。多くの場合、小さな項目は無視しても差し支えない。
●割り算をしよう。
割合を見ると、量を見た場合とは全く違う結論にたどり着くことがある。大抵の場合、割合の方が役に立つ。国や地域を比較するときは、一人当たりの数値に注目しよう。
⒍パターン化本能を抑えよ
1つの集団パターンを根拠に物事が説明されていたら、それを疑おう。パターン化は間違いを生み出しやすい。
過半数に気をつけよう。
強烈なイメージに注意しよう。ほとんどの場合、それは例外かもしれない。
自分以外はアホだと決めつけないようにしよう。変だと思うことがあったら、好奇心を持ち、謙虚になって考えてみよう。
⒎宿命本能を抑えよ
すべてのものは変わらないように見えて、ゆっくりと変化している。
常に知識をアップデートしよう。テクノロジー、国、社会、文化、宗教は刻々と変わり続ける。

おじいちゃんやおばあちゃんの話を聞こう。価値観がどれほど変わるかを改めて確認できる。
⒏単純化本能を抑えよ
1つの視点だけで世界を理解しようとしないこと。
自分の考えを検証しよう。知ったかぶりはやめよう。数字の裏の背景を想像しよう。単純なものの見方と単純な答えには警戒しよう。世の中は複雑なバランスで成り立っている。
⒐犯人探し本能を抑えよ
何かが起こると、人は誰かを犯人にして安心したがる。誰かが見せしめとばかりに責められていたら、それに気づこう。犯人ではなく、原因を探そう。ヒーローではなく、社会を機能させている仕組みに目を向けよう。
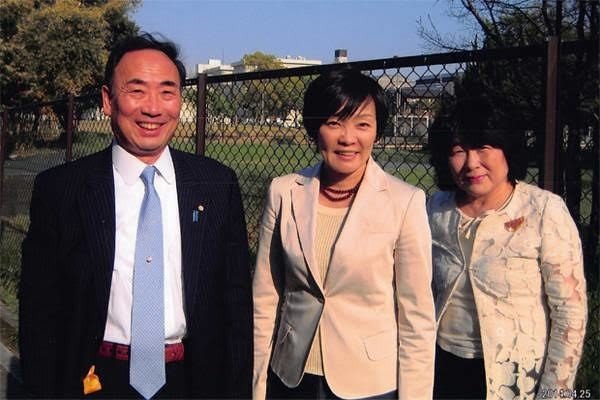
⒑焦り本能を抑えよ
今すぐに決めなければならないと感じたら、自分の焦りに気づこう。小さな1歩を重ねることが大事だ。深呼吸しよう。緊急で重要なことならなおさら、データを見るべきだ。正確で重要なデータだけを取り入れよう。未来についての予測は、いつも不確かなものだ。過激な対策には必ず副作用があることを知っておこう。
◆心配すべき5つのグローバルなリスク
⒈感染症の世界的な流行
第一次世界大戦では戦争で失った兵士よりも、スペイン風で失った兵士の方が多かった。感染力が強くどんな対策も効かないウィルスからあらゆる手で自分たちを守る事は、より一層重要になるだろう。
⒉金融危機
世界で最も優秀な経済学者でさえ、先の金融危機を予測することはできない。金融システムが複雑すぎて正確な予測ができない。金融システムがもっと単純なら、危機を救えるかもしれない。
⒊第三次世界大戦
力にものを言わせてきたプライドの高い国家が、市場での支配力が弱まった時に他国を攻撃する可能性はいくらでもある。常に新たな道を探すことを忘れてはならない。

⒋地球温暖化

地球温暖化を批判する人々は大抵豊かな国に住んでいる人々だ。そして、その豊かな国が1番二酸化炭素を排出していることを知っておこう。私たちがまず率先して排出量を減らした方が良い。
⒌極度の貧困
今この世界で極度の貧困に苦しんでいる人々の数8億人だ。彼らを救うには平和、学校教育、全ての人への基本的な保健医療、電気、清潔な水、トイレ、避妊具、そして市場経済に参加するためのクレジットが必要だ。貧困の撲滅にイノベーションは必要ない。他の場所で効果のあった対策を、極度の貧困にある人たちに届ければ良い。後は最後の一歩を詰めるだけだ。人類の極度の貧困との戦いは、1800年から続く、マラソンのような長距離レースだ。2020年代の世代はゴールテープを切るチャンスがある。共に戦おう。
◆エシモの所感
私たちは何でもかんでも分断しがちで、ネガティブなことに過剰に反応し、直線的に予測し、恐怖を前にすると思考停止し、過大視しがちで、なんでもパターン化させて、宿命として諦めがちで、単純化が大好きで、犯人探しで無駄な時間を過ごし、常に焦っている。でもそれは、ただ本能に踊らされているだけで、自分で情報を集めてデータを読みさえすれば事実と異なる思い込みに過ぎないことが分かる。この本が売れたということは、人々はいかに自分で調べないかを物語っている証拠でもある。次の世代の私たちはデジタルネイティブ世代だ。「自分で調べる冷静さ」を持とう。そんな読後感でした。
以上です。みなさんはどう思いましたか?また次回お会いしましょう!
◆エシモからのご紹介
エシモブックスより死ぬまでに知っておきたいラブの知識として、スマホで読める電子書籍「ラブのある暮らし」を販売中です。恋愛や仕事、人生の悩みに対する一言アドバイスに、イラストを加えた、ユーモアたっぷりな作品になっております。Amazonプライム会員の方は無料、そうでない方もワンコインで購入できるので、ぜひ、お立ち寄りください😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

