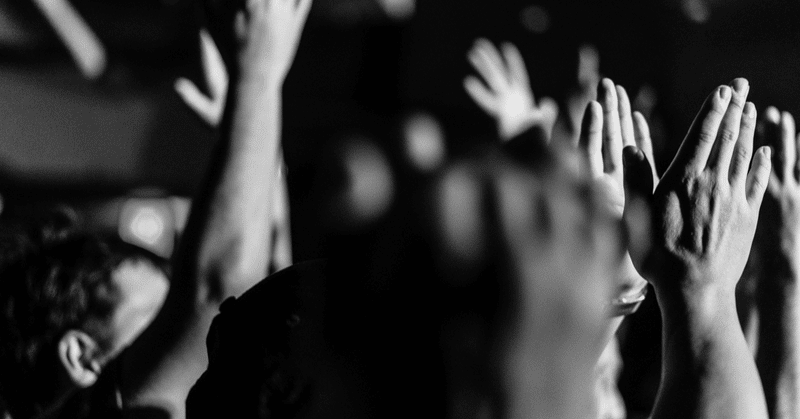
「受け手」が、「贈り手」を育てる
まだ世の評価の定まらない仕事であったとしても、それを受け止め、価値を見出してくれる「受け手」のあることが「贈り手」の背中を押す。仕事の主の勇気になる。受け取ってくれる人の笑顔が、「贈る」ことのよろこびを教えてくれる。
想像してみてほしい。
こういう「受ける」ことが上手な人で満たされたまちがあったとしたら?
何か発信があったり、新しい挑戦を始めたりする人に対し、厳しくも温かいリアクションの返ってくるまちがあったとしたら?
「他にはまだ誰もそれを『いい』と言ってくれる人はいないけれど、自分はそれ、いいと思う」と言ってくれる人が辻々にいるまちがあったとしたら?
きっとそこには、たくさんの「贈り手」をも生み出しているはずだ。
「ゆっくり、いそげ カフェからはじめる人を手段化しない経済(著・影山知明さん)」の第4章 「交換の原則」を変える からです。
「受け手」が、「贈り手」を育てる
これが正しいかどうか、それは僕も正直分かりません。でも、正しいんじゃないか、そう感じています。だから、実現してみたい。そう思いました。
スパークス・アセット・マネジメントさんが運営されている、アクティブファンドの5年前に発信された月次レポート。
現在発信されている、他のほとんどのアクティブファンドと比べても、内容は具体的であると感じます。
このレポートが5年経ってどうなっているかというと、以下の通りです。
さらに進歩、進化していると感じます。この進歩、進化の過程で「受け手」が増えたことがどの程度影響しているのか、分かりません。しかし、「受け手」を増やすこと、また、「受け手」がレスポンスを発信する機会が増えることでさらなる進歩、進化が起きるのではないか、と考えています。
今朝出会ったツイートです。
急にジャムおじさんみたいな話になるけど、長期投資を行う時には、その企業が提供するものに魂が込められているかという点が大事だと思うようになった。
— res (@rescale) September 4, 2021
アクティブファンドにも当てはまることだと思います。ファンドマネジャーの皆さんにとって、その一瞬、一瞬のポートフォリオは受益者(投資家)、社会に提供するもの。それをどんな想いでつくったか、を説明、報告する情報発信、月次レポートもその一部だと思います。そこに魂が込められているか、それによって「受け手」の心を動かせるか。
抽象的な内容で、毎月ほぼテンプレートのようにコピペしているんじゃない?と感じさせる、また、先月のレポートと並べて読ませない(過去の月次レポートのリンクなし)、そんな姿勢のアクティブファンドに「魂」を感じることは無理でしょうし、結果、「受け手」がレスポンスする材料が、フィーの多寡だったり、基準価額の値動き(都合よく切り取ったりされたり)だったりになってしまいます。
月次レポートもアクティブファンドの一部、
商品を構成する非常に重要な一部です。
とすると、そこに「魂」が感じられなければ、当然、ファンド全体からも「魂」が感じられないのは当然ではないでしょうか。
つまるところ、日本における極端なインデックス投資吹聴者の発生は、長年の金融業界の身内の論理が根本的な原因だと思うので、身から出た錆びですね。錆びは蔓延ります。 https://t.co/dCkDgSxD2G
— K.の株式投資録 (@K92557576) September 3, 2021
多くのアクティブファンドの月次レポートやその開示姿勢を見ていると、ものすごく酷い「錆び」を感じます。蔓延っている、と僕も思います。「錆び」を落とさなきゃ、と本気で考える人たちが増えるには、『いい』と発信してくれる「受け手」の存在が必要だと思います。
そんな「受け手」の”輪”を広げる。
アクティブファンドは月次レポートで選ぶ。
これが月次レポート研究所の目指す到達点になるだろう、と考えています。
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5
