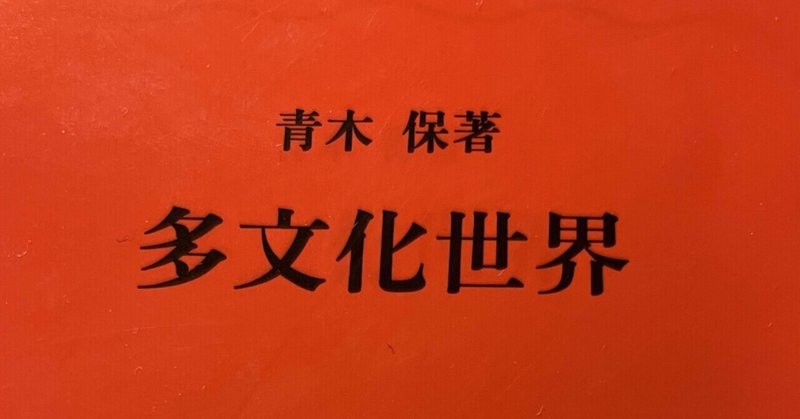
青木保氏の『多文化世界』3
さて、1.2を通して得られた結論として、「国際社会化」という表現と考えの脆弱さ、それに変わるものとして多文化共生を取り上げた訳ですが、これについても問題点が見られました。次の段階として、では結局多文化共生をどう実現するのかについて考えます。※メモをそのままコピーしてますので状態文です。
次に具体的に多文化共生社会を実現するために何が必要なのか考える。筆者は人間を「人」と捉えるか「族」すなわち集団として捉えるかが最も重要だと考える。
かつて国家の形態として「帝国」が存在した。当時帝国は異民族を支配し、領土を広げることが目的だった。したがって帝国は自ずと多民族国家をとった。なので「族」と認められればそれなりの扱いを受けられた。逆に個人はそれが望めなかった。つまりはある程度の「自由さ」が「帝国」の文化であったとも言える。
対して、近代の国民国家では、人間は個人として捉えられ、国籍さえ有していれば法の下の平等が受けられる。しかし、これは建前であることが多いと筆者は考える。多数民の場合は国民や市民と一致する可能性があるが、少数民の場合はそれが難しいという場合がそうだ。当然、少数民は不満を感じるだろう。異民族の存在は認めないと言っておきながら、多数民は認めるくせに少数民はなぜ認めないのだと。そこで、少数民は多数民のようにまとまって「族」を形成しようとする訳だが、そうすると今度は多数民との社会的対立の原因になる。かといって個人として生きれば、十分な権利や法の保護を受けられない。こうして、不平等感や差別感が強くなってしまうという。
そこで私は考える。こうなってしまうのは、「国民国家」が、異民族集団の存在を認めないと言いつつも、多数民に関しては国家の一員としまっているという曖昧さである。多数民であれ少数民であれ、認めないなら認めないと貫かないから、こういった対立が起こってしまう。でも、そう出来ないのには理由がある。多数民の影響力は凄まじく、人数が多いということはすなわち、それだけ国民や市民の中に彼らに賛同する者が出やすいということだ。今さら異民族禁止と言っても、多数民が既に国民と融合して、文化・慣習として成立してしまっており、異民族集団を認めたくなくてもどうしようもないという場合である。少数民はこれを受け入れなければならないのかもしれない。
「帝国」では「民族集団なら認め、個人は認めない」とされていたのが、「国民国家」では「個人は認めるが、民族集団は認めない」と真逆のことが起こっている。もしかしたら、世界は未だ「帝国」時代の面影が残っており、完全に「国民国家」へとシフトしきれていないから、こういった混乱が起こるのではないか。早い話、個人としても集団としても認められることがベストだと思うし、筆者もそう考える。しかし、社会の中に異文化・異民族の独立した存在が認められない以上難しい。かといってそれを認めてしまえば国家の同一性は揺らぐ。筆者が考える方法としては、根本から「国民国家」というシステムそのものを一から見直すということだ。それは「グローバル社会」を実現しようとする前提で、国家と社会を再構築する必要があるということを意味する。
そもそも単一民族社会と謳う日本でさえ、実は多民族社会である。文字通り単一民族社会の国はとても珍しい。「国民国家」は頻繁に、自分達は単一民族国家だと主張する傾向にあるが、それはそういうシステムを取ってからであり、大元を辿れば自分達も多民族国家なんだという意識を持たなければならない。(本当に単一民族社会なら必要ないが) そういう意識を持てば、今度こそ本当に多民族国家の実現、多文化共生の兆しが見えるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
