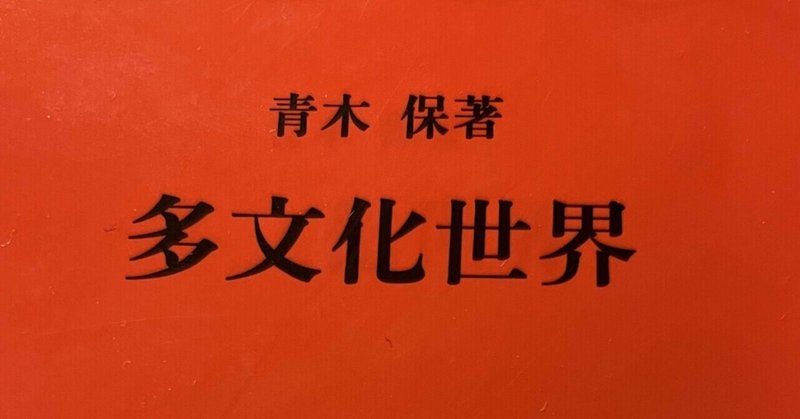
青木保氏の『多文化世界』2
今回は続きです。こちらもメモをそのままコピーしてますので常態文になっています。ぜひ1の方もよろしくお願いします。
1で私は、世界が一様にして国際社会化することは決して良いこととは限らないと気づいた。そこで、1の最後に「多文化共生」を目指すと書いたが、今度は「多文化共生」の問題点はないか考えてみた。
日本を含めた近代の国民国家とは、国内に自立した民族共同体の存在を認めない、つまり、方の下の平等で個人が国民として国家に所属することが前提としている。多民族・多文化社会のための「国家」を、現代の「国民国家」に当てはめるのには限界があるらしい。多文化(共生)社会には世知辛いなあと私は思った。そこで、ではなぜ「国民国家」でないといけないのか。その必要性を探った。
確かに、国内の異民族集団を認めることで「方の下の平等」がまっとうされず、多数民と少数民の間で差別が出てきてしまうことが現実問題としてある。北アイルランド、カシミール、スリランカ、チェチェンなどにおける問題が代表例である。これらは国家内に信仰する宗派が異なる、異民族集団を国民として認めてしまった結果、対立や紛争が起きてしまったのだ。
このように異民族集団の存在を認めてしまうことで、実際、「国民」を構成する少数民・多数民の存在が、対立という形で浮上し、「国民国家」の枠内ではうまく処理できないという問題が数多く出てきている。なぜ世界の多くが「国民国家」というシステムを取り入れるのかは理解できた。「国民国家」に、さらに多文化社会としての「国家」を付け加えることは難しい。両方持たせることはできないのだろうか。
異民族集団の存在を認めないという「国民国家」というシステムは、多文化社会実現には世知辛いかもしれない。しかし確かにそういった対立が生まれないようにするために必要な仕組みとも言えるだろう。異民族集団との共生が仮にも不可能だとしても、多文化共生が絶たれた訳ではない。しかし、ある意味では手っ取り早く実現できたであろう方法としては絶たれたかもしれない。1では世界が一様にして国際社会化することは決して良いことであるとは限らないと考えたが、この章では多文化共生も簡単に実現できることではないと痛感した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
