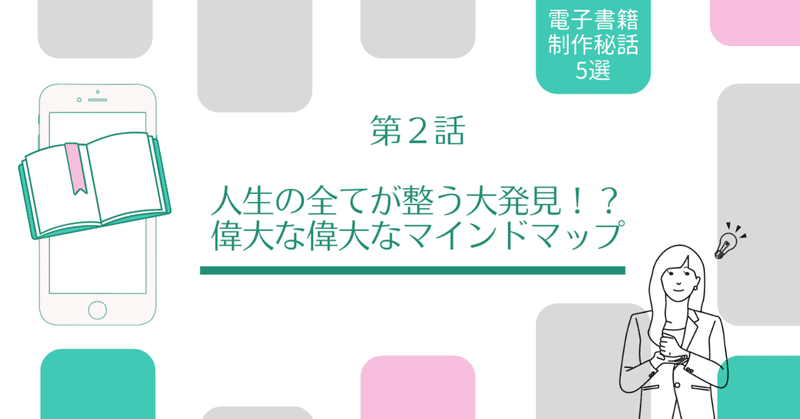
人生の全てが整う大発見!?偉大な偉大なマインドマップ
本を書くときだけでなく、すべての思考の整理に使える神ツール、それがマインドマップです。
世界中で何億人もの人が愛用している究極の思考ツールで、いまさらわたしが取り上げるまでもないのですが、これなしでは書籍をつくりあげられなかったと思うので紹介します。
電子書籍のテーマを決めた後、どんなことをどんな順番で書いていくのか、すべてマインドマップで整理していきました。
電子書籍のテーマ決めについては、昨日の記事を読んでくださいね。
本日は、このマインドマップの偉大さについて語っていきます。
マインドマップの3つのすごい特徴を知ったら、きっと使わずにはいられなくなるはず!
いまあなたが取り組んでいることの全貌がピシッと整理されて、ぐんっと加速すること間違いなしです。
マインドマップとの出会い
わたしがマインドマップに出会ったのは、「ライカレ」と呼ばれるライティングスクールです。私はこのスクールで電子書籍のいろはを学びながら、今回の出版にこぎつけました。
ライカレについては、このnoteがわかりやすいので興味ある人は見てみて!
ここで講師のまよ先生に「ライター必須のツール」と教えてもらったのが、マインドマップでした。
まよ先生もおっしゃっていましたが、何かを書くときだけじゃなく、ありとあらゆる場面で使えます。
今までこれを知らずによくブログを書いてこられたなぁと思うくらい、今ではわたしの相棒のような存在です。
マインドマップのここがすごいよ、3選
それではマインドマップの何がすごいのか、その特徴を3つお伝えしましょう。
1.全体像が見渡せる
まずは、マインドマップそのものを見ていただきましょう。

これは、今回の記事に書くことを整理したときのマインドマップです。
何をどんな順番で書くのかといった記事の構成を作りました。記事全体の構造をひとめで見渡すことができます。
こうやって記事の構成を作っておけば、あとは文章をその通りに書いていくだけ。「次に何を書こう」と悩むことも、話がいったりきたりすることもありません。
長い文章になればなるほど、この記事の構成をしっかり作っておくことが必須になります。
パソコンの画面を2分割してマインドマップを常に横に置きながら執筆すると、とてもはかどりますよ!
(この技は最近覚えました。Windowsを使っている方は、Windowsキーを押しながら矢印キーの左右どちらかを押すと画面を分割できます)

2.もれなく、ダブりなく
自分の書きたい内容がもれなく伝えられているかをチェックするののにも、マインドマップが威力を発揮します。
さらに、ダブりがあった場合も見つけやすいです。
「もれなく、ダブりなく」はMECE(ミーシーと読む。Mutually Exclusive, Collectively Exhaustiveの略)と言って、ロジカルシンキングにおいてとても大事な概念。
論理的に考えをまとめるのが苦手な私のような人こそ、マインドマップを使ってきちっと構成を作っていくのが大事なんだと実感しています。
どこの階層にどの内容を組み込むのがわかりやすいか、パズルのように組み替えながら文章の構成を作っています。
3.何にでも使える
電子書籍の内容を整理するツールとして知ったマインドマップでしたが、今では公私ともに大活用しています。
・記事や書籍の構成を作る
・セミナーや講座の構成を作る
・ブログのサイトマップを作る
など、なにかを作り上げていくときの思考や行動の整理にもってこい。
他にも、
・夢を叶えるためのやることリスト
・引っ越しの準備でやるべきこと
・家づくりのアイデア整理
など、私生活でやりたいことを洗い出していくのにも役立ちます。
頭のなかにある考えを見やすく整理するツール、それがマインドマップです。
マインドマップを使おう
わたしは、mindmeister(マインドマイスター)のマインドマップを使っています。
無料版だと、マインドマップを3つまで作成可能。使うたびにマップを消していくのが苦じゃなければ、無料版でも十分使えます。
他にもマインドマップ作成ツールはいくつかあるので、自分に合うものを探してみてください。
マインドマップについてさらに知識を深めたいときは、マインドマップの発明者が書いた『ザ・マインドマップ』をおすすめします。
書き方から活用法まで1冊で網羅されていて、読むと人生がより充実したものになるでしょう。
さて、今回は電子書籍の構成を作っていくのに必須なツール「マインドマップ」のすごさについてお伝えしました。
構成ができればあとはそれに沿って書くだけ...なのですが、今回の書籍ではより内容を充実させたくて取材を行いました。
人に話を聞く取材は、実は今回がはじめて。ここでも多くの学びがありました。
明日は、取材のコツについてお話しします。
それでは、また明日!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全5回にわたって、電子書籍出版の制作秘話をお届けします。
次のお話も読みたいと思ってくださったら、ぜひフォローをしてください!
いいねも押してくださると、とても励みになります^^
記事を読んでくださってありがとうございます。いただいたサポートは、書籍購入費用に充てます!良い読書は良い文章を創る。記事を書いて還元いたします。
