
声出し応援再開の機運について感じた事
2022.5.25、DDTプロレスリングより、とあるリリースがなされた。
✨特報✨
— DDT ProWrestling (@ddtpro) May 25, 2022
/
📢7月7日の無料大会は”声援可能”!!
\
座席間隔を十分に取り、安心して楽しめる環境を提供いたします👍
大会名も以下に変更!
『DDT FREE ~みんなで声出そう!~』
心置きなく声を出して選手を応援しよう🔥
■詳しくはコチラ👇https://t.co/YYzZRcazwB#ddtpro pic.twitter.com/8BEhkCsmwm
2022年に入り、毎月行われているDDTの無料興行において、久方ぶりに声出し解禁を打ち出した興行の発表…。
新型コロナウイルスが蔓延し始めた2020年春以降、多くのイベント・エンターテインメントで禁止されたのが"声援"である。
コロナ禍に突入した2020年春以降、規模が大きくない団体によっては声援が許可されるケースはあったものの、【マスクを鼻まで覆う】、【大声での声援はNG】という条件付きでの実施だった。
(※思わず漏れてしまった、どよめきや笑い声に関しては、その限りではない)
今回発表されたDDTの興行についても、新宿FACEの会場収容可能人数450名に対し150名限定と、ソーシャルディスタンスを確保した上、不織布マスクの完全着用(鼻から顎まで)が必須。
とはいえ、サイバーエージェントのような大資本傘下の国内団体で、"声援"が許可される興行は、恐らくコロナ禍以降初と思われる。
そんな今回の発表は、国内プロレス業界において一歩前進させる期待感を抱いた一方、私としては若干の不安も感じていたり…。
以下は、個人的偏見と体感からの私見になります…。
「DDTなら成功するだろう」という信頼感
今回DDTが発表した興行に対して感じたのは、「DDTなら、今回のチャレンジを成功させるだろう」という絶対的信頼感だった。
DDTという団体は不思議なもので、コロナ禍以前から、所謂【汚い野次】を聞くことが皆無に近いくらい、傍から見てもファンの雰囲気が良好な印象を受ける。

メイン後にユニットや団体を越えてリング上に集う光景は、DDTの持つ特色ならではと言える。
故に、プロレスにおけるヒールユニット的存在は育ちにくいきらいはあるものの、そうした土壌が独自の温かな雰囲気を生み出している。

反則介入も行うが、個人的にはヒールというよりアンチヒーロー的な人気も感じさせる存在だ。
今回のようなチャレンジが出来るのも、DDTグループ(DDT、ガンバレ☆プロレス、東京女子プロレス)の強みではないかと私は思う。
これが他所の団体とかだと、中々試験導入も難しかった気がする。
上述したようなDDTの持つカラーリングが、観客が自分に酔って茶々を入れて、場をコントロールする行為自体を野暮に感じさせたり、陳腐化させたりしているのもデカいかもしれませんが(よせ)。
声が出せるといっても〜コロナが終わったわけではない〜
声出し応援解禁の流れを語る上で、私自身、前提としておきたいものがある。
それは、今回の解禁案が出た今現在も「新型コロナウイルスが消滅した訳ではない」ということ。
(当たり前かも知れないですが…)
声が出せると言っても、不織布マスクの完全着用は必須。
今回のDDTにしても、6月に予定されているJリーグの段階的導入にしても、声出しエリアはソーシャルディスタンスが確保された上で行われる。
手洗い・うがいの励行によりインフルエンザの感染者数は減った一方、新型コロナウイルスの感染者数が同じように推移しない現状を鑑みても、コロナは"ただの風邪"では決して無い。
依然として、そうした感染対策は不可欠であり、そうした中で興行が行われる事は忘れないでおきたい。
その点で考えてしまうと、コロナ禍以降、会場の密を避けるべく実施されている【規制退場】に関して、再三のアナウンスにもかかわらず、待たずに無視して退場する人が増えている実感がある。
(どの界隈にも、それは見受けられる印象)
そうしたルールさえも守れなければ、会場で好きなものが見れなくなってしまう恐れもある。
私としては、2020年3月頃〜6月頃や、2021年のゴールデンウィークなど、緊急事態宣言でエンターテインメントが軒並生で見られなくなってしまったキツい時期は、もう体感したくないところ。
今一度、そうしたルールを遵守して楽しむという点は重要なのではないだろうか?
汚い野次を聞く可能性が減った、コロナ禍の会場
2020年春以降、約3ヶ月前後に及ぶ無観客試合期間を経て、プロレスは再び有観客の場に帰ってきた。
一方、その期間でプロレスから離れた方も少なくない、という体感が私にはある。
声援が禁じられた事により、選手の名前を叫べなかったり、エルボーなどの打撃技に合いの手が被せられるようになったり、個人的に弊害も感じる訳ですが、何も悪いことばかりではなかった。
誤解を恐れず言うと、声援禁止によって「客が野次で試合を壊す」懸念が払拭されたからだ。
声援と言っても内容は様々で、選手の名前を叫んだり、純粋な応援の気持ちから発せられるものもあれば、極端な話、ウケ狙いや【自分が会場を支配したい】欲だけが伝わってくる野次もある。
野次の内容自体は人それぞれ基準がある故に、ジャッジが曖昧模糊としていたけれど、コロナ禍で声援禁止になった事により、"声を出す行為"そのものが纏めてNGになった。
このフィルターが機能している事で、野次により興行や試合が壊される心配は無くなったとも言える。
2年ちょっとの期間でそれに慣れてしまうと、良くも悪くもそれが居心地良い。
私自身、忘れられない出来事がある。
2022.4.29、両国国技館でプロレスリング・ノアを観戦した時の事だ。
中盤戦で組まれた『覇王vs仁王』は、【敗者リングネーム剥奪&髪切りマッチ】という、己のプライドをかけた一戦となった。
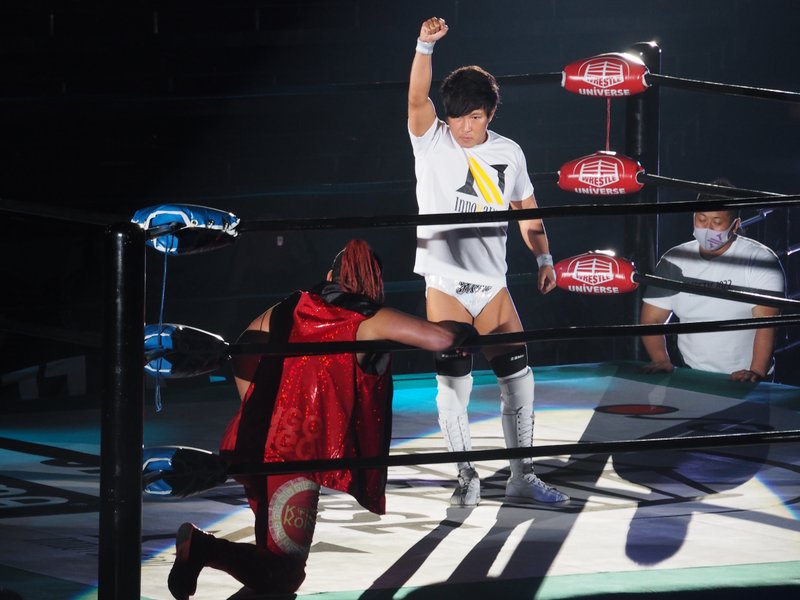
試合が始まって間もなく、会場内の升席に入ってきた男性が大声を発した。
「ヒロキー!!!」
(※仁王の元リングネーム・Hi69)
その後も、リング上の攻防で声を発する男性。

ここで男性が「落とせ」コールを叫び続ける悲劇…
場内のスタッフが駆け寄るも、スタッフの説得にも真面目に応じなかった彼は、結果として強制退場と相成った。
仁王が髪を切られているのと同じタイミングで、大声出して仁王を応援していた人が大勢のスタッフに連れられて強制退場させられるという、凄い光景を見ております(白目)
— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 29, 2022
大声出してる観客を強制退場させたNOAHスタッフの皆様、ホンマ最高!!!
— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 29, 2022
ありがとうございます!ありがとうございます!!!!!
感謝!!!!!
そんな雰囲気故、事前に高まっていた試合の因縁も何もかも、一観客によってぶち壊されたのである。

今日の『覇王vs仁王』でつくづく感じたけれど、声援禁止のルールを守れない人が選手の名前を叫んじゃうと、真っ先に下がるのはその選手の印象だよなあ、と
— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 29, 2022
(何もしてないのにね😢)
正直なところ、私のマインドも「ふたりとも負けてほしくない」から「覇王勝て!」に変わっちゃったのよね…(リアル)
この件でツイートした際、「これだからNOAHファンは〜」なんてリプライが何故か私宛に来たのだけれど、これだけは断言していい。
コロナ禍の2020年春以降、私はNOAHの会場で50回近く生観戦しているけれど、そうした客は彼くらいしか見たことがない。
ワイの強制退場ツイートに『ノアは客も最悪だな』とか引用リツイートで吐き捨てる人が現れたのですが、ワイからしたら貴方が最悪です(唾棄)🤦♂️
— レンブラント🍻🤼🎸🍴🍹 (@rembrandt_kbs) April 29, 2022
ただ、これが声出し可能なコロナ禍以前のレギュレーションであれば、不快に思う人は生んでも、退場とまではならなかったような気もしている。
声出し禁止のルールがあったからこそ、無条件で彼を退場に出来たのだと思う。
私自身、熱気が戻る待ち遠しさを感じる一方で、そうした不安を少なからず抱えているのが正直なところだ。
そこは、再開する上で避けては通れぬ部分なのかもしれないけれど…。
まとめ〜コロナ禍で分断された客層と価値観〜
コロナ禍以降、今現在も会場でプロレスを観戦している人達は、基本的に声は出していない。
不織布マスクの完全着用に限り、声援可能な大会にも何度か足を運んだが、観客もまだまだ様子を窺っている事が肌感覚で伝わる。
他の格闘技やサッカーなどに比べても、声を出さない傾向は顕著だし、実際記事にもなるくらいだ。
そして、数少ない【ルールを無視して声を出している団体・興行】は、客層や運営の杜撰さがハッキリしてくる実感…。
偏見込みで言うなら、コロナ禍以降の観戦ルールに慣れていない(或いは知っていてもガン無視している)人ほどやらかしてる印象が強い。
ストロング○タイルプロレス(リアルジャ○ンプロレス)とか。
そうしたルールを守らない人が出ると、批判されるのは、ルールを順守している大多数のファンだ。
【普段団体を見ない人がガンガン声を出していて、当事者は総合格闘技系の関係者でした】なんて嘘みたいな本当の出来事も、最近某会場で目の当たりにしたので、余計にそう思う。
野々村 芳和「日本だからですよね。日本のコロナの政策がまずあって、その中でも、僕らの実現したいサッカーという作品を本来の形に戻すためには、まだまだ納得してもらう人たちに納得してもらわないとダメだっていう風に言われてしまう。なので、少しずつ、最初の2試合(※筆者注:6月の声出し応援対象試合)でどんな結果が出て、『これなら安心できるよね』というエビデンスをそこでもしっかり溜めて、次のステップに行く。」
現Jリーグチェアマンの野々村芳和氏による発言である。
コロナ禍から2年以上経ち、声出し応援の再開に向けた機運が高まってきたが、前述したように、ルールをしっかり守っていく事が肝要だと思われる。
一気に状況が良くなるミラクルも、期待しづらいだろうから…。
最終的には各自治体の判断というよりは、各会場の判断という事になるんだと思います。
— 松井幸則 (@matsui1_2_3) May 25, 2022
中には難しい会場もあるんだとは思いますが…。
この新宿FACE大会をきっかけに、少しずつあの頃の会場の雰囲気に戻って行けたらいいと思います。
まずは七夕のこの大会から! https://t.co/f8Gp0pVzZD
声出し応援に関して不安を感じる書き方になってしまったが、私自身、声を出す事は好きだ。
2019.8.24に行われた『関本大介vsマイケル・エルガン』(大日本プロレス・後楽園ホール大会)では、声も含めた会場中の熱気が、今でも忘れられない思い出を私の中に刻んだ。

2019.12.28のDDTプロレスリング後楽園ホール大会では、メインで遠藤哲哉と田中将斗の名前を叫ぶファンの熱がぶつかり合って、圧巻の光景を創り出した。

私自身、会場で選手に声援を送れないもどかしさは、今でも感じることがある。
その一方、会場での声援無し観戦をスタンダードにしたコロナ禍は、人の価値観や思考も変容させてしまった。
その出来事の大きさと重さを、今回の声出し応援解禁の動きを見ていて、改めて感じたのでした…。
※関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
