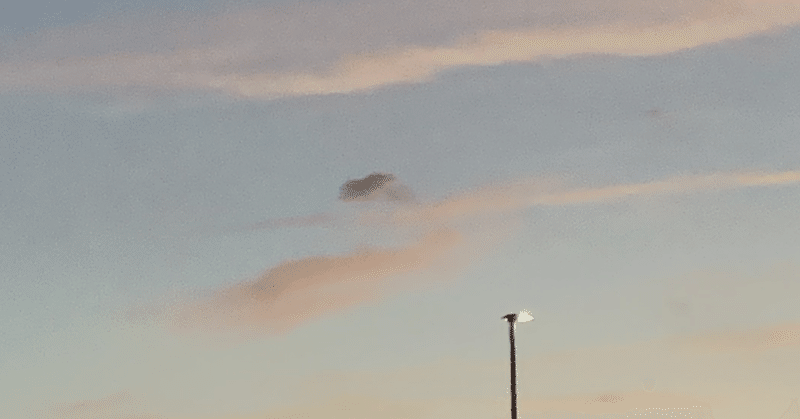
学校の課題したくなさすぎて存在意義について考えた
私は、学校の先生が苦手だし、その苦手な先生が出す課題って事実も苦手だし、課題に取り組むのも苦手だし、締切があるのもちょっと苦手。
(学校の先生が苦手な理由はややはっきりしているが、その理由は機会があれば書くとして、今回は課題に焦点を当てようと思う。)
私にとって課題は“めんどくさい”。
やりたくないけど、やらなくちゃいけない。
けどやりたくない、けど、、ってループで夜の23時過ぎにやらなくちゃ!って始めてあまり考えずにすぐ終わることを優先してチャチャッと30分〜1時間程度で終わらせる。書くことは質より量。あまり中身がないのはわかっているが、めんどくさいながらの行動だから、そうなってしまう。
そこで私は、課題の締切が迫ってる最中、課題の存在意義について考えた。
私の現在の課題は、先生によってジャンルがバラバラである。1.2年前の課題は、だいたい覚えているものから忘れているもの、こういう事を書いたなってものをやんわり覚えている。
このように課題について思い出した時に、学校の課題は、その事について考える機会をくれているのかなと思った。学校なしの生活を考えたら、その生活の中で自ら課題のテーマとなるようなことを考え、文章にすることは滅多に無いと思う。課題を提示してもらった時、その課題をある程度理解できて構成が作れた時、知識を練ることができた時、私たちはその課題についてあたかも提示前から考えていたかの気になるが、知識の1部としてあっただけで、考えてはいなかったと思う。課題を提示してもらったからこそそのテーマについて考えるようになった。
同じ課題など幾度となく、その事について考えることができるのは意外と希少であり、人生全般で見たらほんの一瞬にも満たない経験である。そして、時が経てば忘れて考えることもなくなる。だからこそ、考えるチャンスも挑めるチャンスも、その課題に取り組めている時だけであり、幾度とないチャンスを活用するべきだと思う。
そして。やりたいことじゃないことでも頑張ってみることで、頑張ることができる範囲が広がる気がした。頑張ることができる範囲は、広ければ広いほど成長への結果につながると思う。この分野成長したい!と思っても、忍耐力がなければつらいところである。自分にとって絶対に手に入れたい高いものがいきなり現れた時にすぐさま挑戦できるための、頑張ることができる範囲の強化、拡大は長年によって培われるものである。だからこそ、やるべきことがたとえやりたいことじゃないことだとしても、やるべきならやるべきだと思う。
まとめると、私が考える課題の存在意義は、その事について考える機会を作るため、やりたいことじゃないことをあえてすることで頑張ることができる範囲を広げるためである。知識と忍耐力という将来への投資である。
だから、課題がめんどくさいってこれからも思うだろうけど、思ったら私なりに考えた課題の存在意義と頑張ることができる範囲論を思い出そうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
