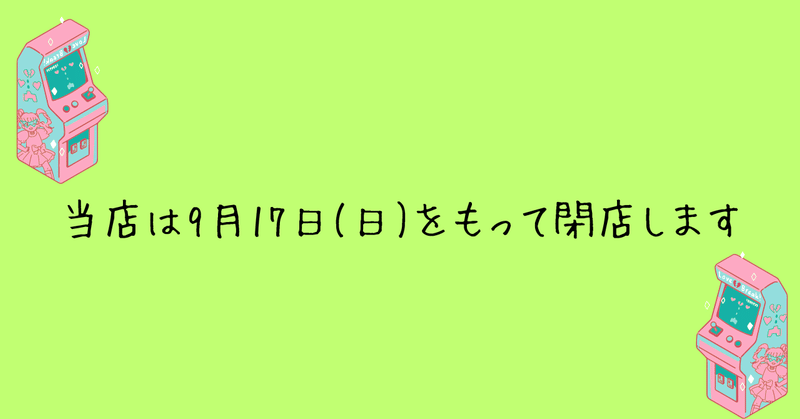
小説:当店は9月17日(日)をもって閉店します 2
2 大池康生
「ごめん、田原さん。実はこの店、九月十七日で閉店することが決まったんだ」
八月から契約社員として勤務する予定だったパートスタッフの田原さんにそう告げるのは、他のどのスタッフに閉店を告げるより心苦しかった。
彼女の手に握られた、「契約社員になるにはこの書類が必要だから集めて持ってきてね」と自分で言った諸書類が、所在なげにしなっていたのをありありと覚えている。
「どういうことですか?」
責めるような彼女の口調にたじろぎながら、事情を説明したのが昨日のことのようだ。
本部から閉店を知らされたのは、彼女が書類を持ってくる一時間前のこと。事務所で、事務仕事をこなしていたら一本の電話がかかってきて、「大池くん、すまない。アミューズパークなんだけど、施設側との契約交渉が上手くいかなくて閉店することになった」とエリアマネージャーから告げられた。
当然ながら俺だって「どういうことですか?」とエリアマネージャーの豊永さんに言ったけれど「決定事項だから」と「お客様とスタッフへはまだ告知をしないように」以外の言葉を発してはくれない。言いたいことだけ言うと、豊永さんは電話を切ってしまう始末で、俺は事務所で一人、頭を抱える羽目になった。
自分の気持ちも整理出来ないまま、田原さんがやって来て、九月で閉店することが決まっていながら契約社員にするというのもおかしな話なので、誰よりも早く彼女に閉店を告げなければならない状況が生まれたのだ。
結局翌週までスタッフへの閉店告知の許可が下りず、彼女には一週間近く知らない振りをして貰うことになって、重ね重ね申し訳ないことをしたなと思う。
田原さんは三年前からアミューズパークで働いてくれているパートスタッフで、去年、主力スタッフだった大上くんが社員に上がってからは、大上くんのかわりとなってメダルコーナーとメンテナンスで活躍している主婦スタッフさんだ。
今は朝番の主力スタッフの一人と言っても過言ではなく、真面目な仕事ぶりに信頼を置いている。彼女が契約社員となって働いてくれたら、きっともっと良い店になっていただろう。
けれどそんな日は来ない。せっかくやる気を出して、契約社員になると手をあげてくれたし、俺も期待をしていたのに。
でも今最大の問題はお客様への告知だ。本部は頑なに、お客様への閉店告知をさせてくれない。一番近い系列店舗が隣県になってしまうアミューズパークでは、お客様がメダルキーパーに預けている貸し出しメダルを他店に移すことが出来ず、閉店日をもって消滅することとなる。
お客様のことを考えると売り上げが下がっても、これから閉店をするこの店舗でのメダル貸し出しは勧めたくない。黙って今まで通り運営することは簡単だけれど、とても不誠実だ――そう思った。
とはいえ、俺だって言うなればただの会社員。本部の言うことにそう簡単に逆らうことはしたくない。したとしてもバレたくないと思うのは自然な流れだ。
下手に本部に逆らって、降格でもしたら目も当てられない。俺には、本部の気まぐれな転勤に付き合ってくれる大切な家族だって居るんだ。
妻の遥は二つ年下の四十歳。二人の息子は、小学六年生の太一と小学三年生の輝。遥には閉店することを伝えたが、息子には口が滑って閉店情報を話されたら困るのでまだ伝えていない。
「閉店ってことは、転勤があるってことよね?」
そう訊ねる遥の声は、言外に「太一は今年小学校卒業なのに」と言っていた。
閉店と転校を告げたら太一はなんと言うだろう。絶対に嫌がるだろうな。青葉市に来てからの友だちと、ものすごく楽しそうにしているし。
スタッフたちにはまだ話していないが、次に入るテナントはもう決まっている。業界大手のゲームセンターがアミューズパーク跡地に入る予定で、下見の対応などもしなければならない。それもスタッフに、次に入るテナントを気取られないようにしながら。
面倒だな。ぼんやりと思った後、そんなことは仕事を失う人だって居るのだから思ったらいけないと自戒した。
八月に入ったが、本部からはお客様への閉店告知のゴーサインが出ない。もうこれ以上本部からの指示に従っていたら、お客様の被る損が大きくなりすぎる。
もう我慢ならんと思った俺は、事務所のパソコンに向かって文書作成ソフトで簡単にお知らせを作る。出来上がったお知らせは田原さんに渡して、メダルコーナーにのみ掲出してもらうことにした。
当店は九月十七日(日)をもって閉店します。長らくのご愛顧ありがとうございました。そう大きく書かれた文字の後に、小さな文字で閉店に伴いまして、メダルキーパーの預けメダルは九月十七日(日)までで消滅します。他店舗への移動は出来ませんので予めご了承くださいませ。と続けて書く。
お知らせの紙を田原さんに渡しとき、彼女から「お客様から、絶対文句出ますよね」と言われて返す言葉もない。俺だって分かってる。そりゃ、文句出るよ。ため息を吐きながら事務所を後にする田原さんの背中に、心の中で「ごめんね」と言う。
メダルコーナーで、お客様の矢面に立って対応をするのは彼女だ。俺じゃない。うんざりする気持ちも痛いほど分かる。それでも彼女はお客様に対して真摯で居てくれるし、お客様からの信頼も厚い。だから彼女に任せるのが一番正しいのだと自分に言い聞かせる。そうでもしないと、罪悪感で何も出来なくなる。
当然のようにその日の朝は、常連のお客様から「告知が遅すぎる」とのお叱りの言葉をたくさんいただいたと、田原さんが休憩に入るため事務所へ戻ってきたついでに教えてくれた。彼女の顔はいつも以上に疲れており、申し訳なさが募る。
「でも、二割くらいのお客様はただ寂しいっておっしゃっていて。ここは遊びに来る場所だけど、お客様の居場所でもあったんだな、って思いました。じゃあ休憩いただきます」
田原さんがぽつりと言って、事務所を出て行く。二階にある従業員休憩室にでも行くのだろう。彼女は大体、事務所ではなく二階の休憩室へ行って休憩をとることが多いから、いつものルーティンだ。
田原さんが休憩で抜けたメダル側に俺が入ると、やはりお客様から厳しいお言葉をいただくことが多い。入れ替わり立ち替わりきつい言葉を言ってくるお客様の対応は、店長になったって堪える。これを、ただの報告程度で済ませてくれるのだから、田原さんには感謝しなければならないだろう。
十九時半に家へ帰ると、家族はもう夕飯を食べ始めていた。「ただいま」と言う俺の声に、三つの声が重なって「お帰りー」と返ってくる。
お客様への告知が終わった今、残るは子どもたちへの閉店と転校のお知らせである。
手を洗い、リビングへ行くと遥がもう俺の食事の準備を始めていて、すぐに温かい生姜焼きと味噌汁、白ご飯が出てきた。
自分の定位置に座り、まずはコップに麦茶を注いで一口飲む。それから意を決して、俺は話しを始める。
「太一と輝に話がある。実は、アミューズパークが九月十七日で閉店することになった。お父さんは、他の店舗へ異動する。青葉市には他に系列店舗がないから、転校は確実にしないといけない」
そこまで言うと太一が箸を置いて、俺のほうをじっと見ている。
「俺、転校したくない。今の学校で卒業したい」
予想通り、太一が転校したくないと言う。そりゃそうだよな。分かる。今の学校の友だちとお前、かなり仲いいもんな。
「すまない。転校は確実だ。卒業までお父さんが単身赴任みたいな感じにすることも考えたけど、二拠点生活はかなり厳しい」
親の都合で引っ越しばかりの生活を強いているのが、申し訳ないと思う。大人はまだいい。でも子どもに引っ越しの度、コミュニティを一から構築しろと簡単に言ってしまうのは暴力的だ。そんなことは分かっているけれど、今の仕事を手放すことも出来ない。
話を始めるまではいつも通りの楽しい食事風景だったはずなのに、今は太一の目にはみるみるうちに涙が溜まっていって、幼い身体が怒りに震えている。楽しさなんてどこかへ消し飛んでしまった。
「俺、転校しない。絶対、青葉に残る。お父さん一人で行ってよ。六年生の九月の途中なんて、次の学校へ行っても今くらい仲いい友だちなんて出来ないじゃん。俺、そんなの嫌だ」
そう言うと太一は残っていた夕飯をかき込み、食器をキッチンへ下げて子ども部屋へ行ってしまった。兄の怒りに圧されて、輝は困った顔をしている。
太一が去った食卓では、もう誰も口を開かなかった。ただ黙々と、それぞれが自分の目の前にある夕飯を口に運ぶ動作を繰り返す。閉店が無かったら、こんなことにはならなかったのに。
お客様へ閉店のお知らせをしてから一週間。本部からは、まだ正式な閉店告知の許可はおりていない。いくらなんでも遅すぎるだろうと本部をせっついてはみたが、いい返事はもらえずにいる。
今朝は次に入るテナントが下見に来る予定だ。次に入るテナントがどこかというのはまだ伏せておかなければならないのだが、次が決まっているということ自体はもうスタッフにも話している。
朝「次のテナントさんが下見にいらっしゃいます。自由に見てまわられるので、みなさんはいつも通り開店準備をしてくださいね」と伝えてミーティングを終えて事務所へこもる。
朝番のメンバーは和気藹々としていて、開店準備中もインカムでの会話が盛んだ。今日の朝番は桃田さん、田原さん、富永さんと女性三人だ。
店舗最年長の桃田さんと二十代後半の富永さんは、年齢こそ離れているが入社時期ではほぼ同期で親しく話している姿をよく見るし、田原さんもそれに馴染んでいる。
富永さんはプライズ担当としては優秀だけれど少しクセのある人なので、富永さんに対して苦手意識を持っているスタッフは少なくない。
その点、桃田さんと田原さんは富永さんとも上手くやってくれるので、富永さんをシフトに入れるときはつい二人をセットにしてシフトを組んでしまう。
「あの、次のテナント、何が入るか分かっちゃいました」
そうインカムを飛ばしたのは田原さんだ。
「次入るのプラットみたいです。さっき、下見にいらしてる方の、資料見えちゃいました」
嘘だろ? なんでスタッフに資料見えるような持ち方してんだよ。そう思いながら、俺はインカムに反応せず聞き流す。
富永さんと桃田さんは、もちろん反応していて、「プラットってガイアに入ってるのにアオモにも出店するの?」と富永さんがとても驚いた様子で言っている。
ガイアというのは青葉市最大のショッピングモールで、土日ともなると車が止められないほどの人気がある施設だ。
プラットはガイアが青葉市に出店してからずっとテナントとして入っているらしく、アミューズパークより長く青葉市で営業している。
大手アミューズメント施設運営会社が運営するプラットは、業界最大手のゲームセンターで全国いたるところに店舗があり、アミューズパークの運営会社ではその運営力には敵わない。
今回、契約更新の交渉が上手く進まなかったところにプラットが出店したいと手をあげ、施設へのプレゼンで闘ったところ、アミューズパークがプレゼンで負けたというのが今回の閉店に至る背景だ。
施設側の要求に応えられなかったのだから、今回の閉店は仕方が無い。そんな風に割り切れたらどんなに楽だろう。
アミューズパークの店長として青葉市へやって来て四年目。どちらにせよ、そろそろ転勤の辞令がいつきてもおかしくない頃合いだった。それでも子どもたち、特に太一のことを思うと、今年度いっぱいは青葉市で過ごしたかったというのが本音ではある。
もしもプラットが出店に手をあげなければ、施設側はテナント料のために営業を続けさせてくれたかもしれない。なんて甘いことを考えているから、俺はいつまで経ってもエリアマネージャーになれず、店長職なんだろうな。
そんなことを考えながら、かしましいインカムを延々と聞き流し続ける。閉店が決まったって、まだしばらくは新しい景品が入ってくる。店舗の運営は最後の日まで続くのだ。気持ちを切り替えなければならない。
プラットから「現在アミューズパークさんで働かれているスタッフさんで、希望される方は優先的に新店で採用をしようと思っているので、希望者を募ってもらえますか?」と連絡が来たのは、下見から二日後のことだった。
最初に面接をするのは契約社員を希望する人から、という先方からの要望もあり、現在契約社員として働いている桃田さんと富永さんの二人に加えて、八月から契約社員となる予定だった田原さんの三人へ電話をもらってすぐ声をかける。
全員が即決で「面接を受けたいです」と言い、その旨を先方へ伝えると彼女たちの面接予定がすぐに組まれた。来週、三人同時に先方の話を聞き、そのまま面接という形になるらしい。
大学生のアルバイトスタッフたちにも、同じことを伝えていく。スタッフたちは当たり前だが一様にほっとしたような顔をする。そりゃそうだよな。俺は社員だから転勤をするだけだけど、スタッフのみんなは閉店=仕事を失うってことだから。
閉店を伝えてから、多少の動揺はあってもみんな割と淡々と通常業務をこなしてくれていたから、そういうことすら気にかけられてなかった自分が恥ずかしい。
それぞれがきっと不安だったはずなのに、一切それを俺に見せないうちのスタッフは優秀だなと思う。
メダル側では田原さんが、「閉店までに大型メダル機全部メンテします」と宣言して、出勤日に時間を見つけてはお客様対応と並行してメンテナンスを行っている。
桃田さんと富永さんはお客様対応をこなしながら、プライズ担当としての仕事を変わらず淡々とこなしていて、閉店なんて嘘みたいだと思ってしまう。
遅番の大学生たちだって、相変わらず仲よさげに仕事をしていると副店長の友田くんは言っていたし、それまで当然にあった日常が続いているのに、この日常は九月十七日までの期限付きなんだなと思うとひどく寂しい。
てきぱきと働くスタッフたちを、事務所のカメラで時々見ながら、俺に出来ることってなんなんだろうなと考える。閉店する店舗の店長なんて、スタッフたちに返せるものなんて何もない気がして、心が重くなった。
「お父さん、俺、友だちと文通する約束した」
家に帰り、食卓につくと太一が開口一番そう言う。
「文通? 今どき珍しいな」
そう言うと、太一はむっとした顔をして言葉を返す。
「なら、スマホ買ってよ。スマホが無いから文通になったんだから」
やぶ蛇だった。ちょっと考えれば分かるのに、つい口をついて出てしまった言葉は取り消せない。
「いや、文通いいと思うぞ。スマホのメッセージとかより、時間がかかる分楽しみもあるしな」
大袈裟にそう言って見せるが、太一の目は厳しい。
「お父さんの仕事は転勤があるの当たり前って、ちゃんと俺分かってるから。聞いたばっかりのときは嫌だって思ってたけど、新しい場所でも友だちはきっと出来るし、今の友だちとも文通とか電話でやり取り出来る。友だちなのは変わんないから、それでいいと思って」
太一はきちんと前を向いている。小学六年生、しっかり成長している我が子が誇らしい。俺も、前を向いて閉店と向き合わねば。
家族と夕飯を摂りながら決意を固める。明日からは、寂しいなんて思っていないで残りの日々を楽しみながら過ごそう。
せっかく良いスタッフに恵まれたんだ。最後までみんなが輝ける店舗作りをしてやろう。売り上げ上位店舗にまでなれたのはみんなのおかげなんだから。
お盆の繁忙期を前にして、本部からやっと閉店告知をお客様へ行っても良いと許可が出た。とはいえ、もう独断で告知はしているのだが、本部から送られてきた閉店を告知するお知らせ文を印刷して、現在掲出している俺が簡単に作成したものと入れ替えなければならない。
本部からは印刷用のデータと、店頭掲出用の閉店を知らせるポスターが送りつけられてきた。ポスターに手書きで九月十七日と書き入れてから、大学生のアルバイトスタッフ荻野くんへ渡す。
「なんか、こういうの見ると、本当に閉店するんだなって感じですね」
荻野くんは大学一年生の頃からアミューズパークでアルバイトを続けていて、この店舗での勤務歴は俺より長い。留年を何度かしていて、なかなか卒業出来ずにいるのがほとんど持ちネタとなっているが、スタッフとしては優秀だ。
「確かにねー。俺もさすがに、閉店するんだなーって実感した」
そう返すと、「店長はもっと早くに実感してくださいよ」と彼は笑う。
「そういや荻野くんはプラットさんの面接受けるの?」
軽い気持ちで訊ねる。
荻野くんは少し間を開けてから「まだちょっと考えてます。でも、バイトはしなきゃなんでたぶん受けると思います」と答えた。
彼は彼なりに何か考えているのだろう。次をどうするかは、みんなにとっては大きな問題だ。優先的に採用されるのが助かるという人はもちろん多いと思うが、これを機に環境を変えようという人ももちろん居ると思う。
俺が出来ることは、ただ、それぞれが一番いい選択をすることが出来れば良いと願うことくらいしかない。
つづく
第3話 坪田智美
よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは小説を書く際の資料などに使わせていただきます。

