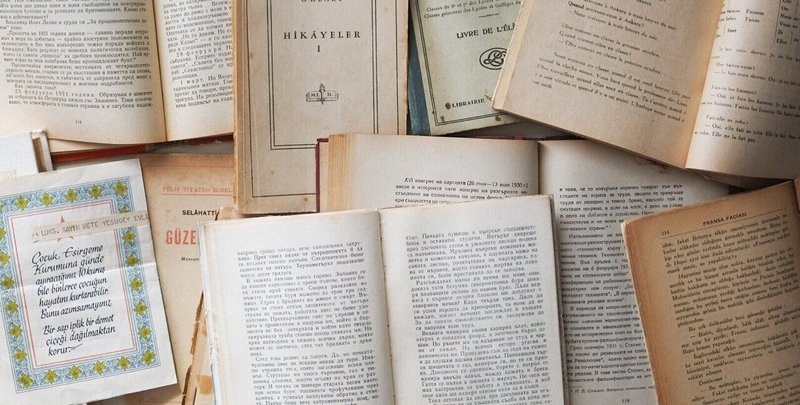
ゲッターに関する俗説や通説の検証~ゲッター線は緑ではなかったとか
ちょっと自分でも検証し直した結果がショックだったからメモ。
漫画版ゲッターはアッパー系ヒャッハー作品では無いし、グルグル目や石川笑いは倫理観とかすっ飛んだ狂気の表現でも無いし、竜馬や隼人は理性やモラルに欠けてるなんてこともないだろうというのは以前書いたのでそれ以外。
(余談だけどいくら資料読んでも狂気なんて言葉が出てくるのは編集やOVAやアニアクスタッフであって、原典に深く関わった人物や石川先生御本人から漫画版についてそんな言葉は出てこない……)
【ゲッター線の色について】
結論から言うと、十中八九、漫画版ではゲッター線は緑色では無い。
おそらくは白、であり基本的には色は無かったのかもしれない。
カラーイラストを見る限りエネルギー波やゲッター線らしきものを緑で彩色しているものはほぼ見つからない。後年の真やアークでも。(全ての資料に目を通せた訳では無いため言い切ることは出来ないが/2022.5.31現在資料としているのは大全の「カラー原画大全」、ゲッターロボジェネレーション、復刊画集)
漫画版真の序盤、敵の襲来に真ゲッターが反応しているかのようにゲッターエネルギーを増加させるシーンがある。実はこのシーン、石川先生自身が着色されたページが図録に収録されており、そこでは緑ではなく白で彩色されている╱2022.8.18追記
背景などに緑が多いのはゲッター1が赤なので反対色である緑を使用することが多かったためと見られる。この傾向は機体が青かった號では背景に赤や白系統の色が多いことからも含めた推測。(石川先生は主題を目立たせるために背景には対比が強くなる色を置く傾向は無いか)
緑は漫画版で最初にその色を持たされたのは一文字號である(髪の色に基本緑が入る)が、同時にアークでのカムイの肌色でもある。ゲッター線を緑色と考えていたらそうしてるだろうか?
東映版ではゲッター線自体への色の言及は無く、ゲッタービームは赤っぽい色をしており、ゲッターエネルギーを最大で使用するシャインスパークではその名の通り白というか光り輝くエネルギーをぶつける。
おそらくこのイメージが漫画版にもあったから色が着いてないのではなかろうか。
(漫画版は案外東映版との関係が深く、関係者インタビュー等読んでも石川先生は初期設定を大事にしてくれていたのではないかという話がちょいちょい出てくる/40周年記念原画図録とか)
漫画版の中で取り込まれかけた時に「白い闇」という言葉が出てきてたが、それも元々石川先生がイメージしていたゲッター線は白い/色の無い光だったならすんなりと納得できる言葉。
まあ根本的に言うと地表に降り注いでる設定であるからには透明だし、可視光線であるかどうかすらわからないんだけど。
で、あるからには
・緑という色から付加されるイメージは本来無い(毒っぽいとか再生とか)
・竜馬のパイロットスーツなどの色とも一切関係は無い
後者に関しては、漫画版での彩色の基本となっているだろう東映版での彩色設定において三人のパイロットスーツや機体は「性格を表した」事をロマンアルバムでスタッフが話しているし、そもそも彼らのパーソナルカラーは何色だったかと言うと機体色の方が強かった形跡もある。挿入歌のひとつには彼らの内面は機体の色と歌っている。
https://animesongz.com/lyric/741/4158
ゲーム大決戦のムービーとかで竜馬の瞳の色が緑がかっていたりもするが、色が着いてる場合、東映劇場版一作目にわかりやすいが明確に青い。(東映版竜馬の茶髪青眼はガッチャマンなどのタツノコヒーローからの影響ではないかとのご意見も伺った。緑目は脇役だったそうな)
流竜馬とゲッター線を結び付ける要素は実は全然無かった、という事でもある。
(頑張って東映版ゲッタービームの色が赤い事を結び付けるので精々であろう。しかしそれだと同時にシャインスパークの色に対応する人物も挙げなければならない。白と考えるならジャガー号が白かった隼人、光=黄の要素なら武蔵か、橙のベンケイとなり竜馬には結び付かない)
じゃあゲッター線は緑って何から来てるのか、というとおそらくはOVAから根付いた話であると思われる。
OVAチェンゲとネオゲの時期は漫画版は真ゲッターとアークの連載時期に被る(OVA新ゲッターは連載終了後なので除外)ので、影響があってその辺からだが、最初に述べたようにアークですらゲッター線は緑では無かった。
石川先生は終始ゲッター線は緑だとは考えておらず、OVA以降のこの20年間に映像化作品を元にファンの間でも共有された通説、というのが正しいところではないだろうか。
(なお、チェンゲも今川監督が製作していたであろう4話くらいまではゲッター線というか機体周り関連は緑ではなかったりする。ということは……。余談だが私はゲッターの映像化作品で石川笑いの解釈が一致してるのは今川監督だったろうチェンゲ3話の真ゲッター発進~ミサイル阻止の場面でのそれのみであったし、今川監督は漫画版を理解した上でクラッシュしようとしていたのではないかと思えてならない)
(2022.2.18追記 東映版G終盤を見ていたところ度々ゲッター線関係無く爆発に緑色が使用されていた。
99年のゲーム、ゲッターロボ大決戦では六話で大量のゲッター線の奔流という描写があるが緑色では無く、その他見ていてもOPでブラゲのアクション線に使用されていたなどはあるが緑での描写は少ない。明確に緑色のビーム自体は存在し、百鬼メカが使用した)
【チェンゲ隼人はイレギュラーという説】
「チェンゲ隼人だけは置いていかれなかった」などと小耳に挟んだが、東映版とネオゲが忘れ去られていないだろうか。
一応以下に原典+OVAの隼人の結末について一覧。
東映版→ゲッター線の設定がああなる前なので無い
漫画版→隼人置いて永劫の戦いに出たかもしれないけど號で明言されてたのは種子を残すためであり未確定
チェンゲ→三人で戦い続けるエンド
ネオゲ→誰も行ってない
新ゲ→竜馬だけ戦い続ける
アニアク→隼人はゲッターに同化してないらしい事だけ確定
隼人が置いていかれたと明言できるのは漫画版と新ゲのみ。アニアクが解釈次第。
(アニアクでは隼人との会話で「新しい旅立ち」とかなんとか竜馬は言ってたし、ラストのゲッター天のカットでは意味深に二号機の顔がそこにある事を見せていてもいたはずで、スタッフコメントが出る前から同化せず個を保ったままそこにあるという解釈を私はしていた。確定した事実としては同化していない事のみとなる)
唯一三人で戦い続けるのがチェンゲ。
東映版とネオゲは置いていかれたもなにもそもそも行ってない。
以上から、「チェンゲの隼人だけは置いていかれなかった」というのは特に根拠の無い話となる。漫画版號のラストで託され残された印象が強すぎて勝手に着いたイメージが先行したのかな。せめてネオゲ忘れないで……。
「チェンゲ隼人は唯一三人で永劫の戦いに赴いたイレギュラーである」というなら幾分合致はするが、そもそも規定チーム三人揃って永劫の戦いに赴いたと確定できるタイトルがチェンゲのみであって隼人がどうこうの話でも無い気がする。
イレギュラーというなら、ものすごーく根本的な話をすると、神隼人という人物自体がゲッターロボという作品の原典二作品において妙な存在感放ちまくり、石川作品括りで見てもあの顔面でありながら敵でも無く死にもしなかったある種のイレギュラー存在ではあるとは思う。なんなんだお前は。
〖余談:スーパーロボット乗りの主人公は単細胞な熱血漢か?〗
スーパーロボットの主人公、といえばあまり頭が良くない単純思考の熱血漢的、ガキ大将的なイメージが現在では先行すると思われる。少なくとも私はなんとなくそんなイメージを持っていた。
が、今回ゲッターからスーパーロボットの始祖たるダイナミック系ロボット物を調べてみたが、そんなことは無かった。
確かに敵に対して怒りを燃やす熱血漢が多いのはそうではあるが(大体のヒーロー物はそうでもなきゃ話にならんというのは置いといて)
グレートの主人公剣鉄也は戦うための教育を施された冷静で大人びた人物が基本筋であるようだし、グレンダイザーのデュークは亡国というか滅ぼされた星の王子であり一話はスカしたイケメンといった雰囲気だったし、ゲッターの竜馬は昭和硬派系優等生だし、一番近いのはマジンガーの兜甲児と思いきや彼は科学者一族の家系で特に頭がよくグレンダイザーで出てきた際にはすでに研究者となっているし、ガキ大将はむしろボス。
総じて頭が良く優秀な人物で、思い込みとっぱらって考えれば人智を超えた力を持って人類を守ろうとする人物は頼りになる方がそりゃ良かろう。彼らはロボットの製作者に選ばれて託されているとか元々王族であって、兜甲児にしろ流竜馬にしろ出自こそ一般学生だが能力は高い。
ダイナミック系ロボット物、というよりヒーロー物といえるかもしれないが、主人公達は何かしらの孤独や寂しさを抱えて、友人関係の描写は少ないようでもある。(甲児くんにはボスが、竜馬にはハヤトとムサシがいるが、取り巻きがいて慕われていた描写が明確にあるのはボスとムサシ/これはあとで気付いたのだが「親分子分」とは「上下」の関係性であるために支配構造と直結する。他者を思う理性を所持する主人公たちに、あくまでも「対等な関係性」を重要視している子達であるとするために「子分」を持たせなかったのではないだろうか?)
調べながら果たして自分が持っていたイメージは何から来ていたのか、と真剣に悩んだ程度には違っていた。本当になんでそんなイメージ持ってたんだろう?
スーパーロボットは荒唐無稽(=根拠が無く出鱈目で現実味が無い。もっぱら悪い意味で使われる)な話筋をしていると言い切れる訳でもないようだ。
全話視聴したのはゲッターだけだが、就学児童を基本ターゲットとしていた事もあろうが、一話完結する単純明快な話が多い傾向はある。しかしその中でもリアリティは追求しようとしていたと散見されるし、話の整合性も基本取れていた。
Gのラストでハヤトが生きてる事が唐突すぎて爆笑した程度には超展開っぽい物もない。ご都合主義的な部分はあるが結構容赦なく敵も一般市民も死ぬ。ゲッターはムサシすら死んだからそりゃそうだろうが。
マジンガーも漫画版読んだ限りでは似たような感じであったし……。
ダイナミック系ヒーロー物は派手に敵を倒すのが特徴だったが同時に「敵が人間だと派手に倒すのは倫理観的に問題があろう」という事で敵は人間では無いとしていたらしい事も大全などのインタビューから読み取れた。
当時情勢なども含めて就学児童向けに大人が真剣に取り組んだ結果という感触があった。(70年代初頭はまだアニメは大人が見るものでは無いという感じだったらしいし)
……じゃあなんで今みたいなイメージになってるんだろう? と今現在も割と首を傾げている。
もしかして、70年代末にガンダムが放映され、より現実的に人間同士の戦争と兵器としてのロボットを描いた事でリアルロボットという区分が生まれてからの話だろうか。
未知の超合金やエネルギーに根拠が無く非現実的というならリアル系ロボットの殆どもそうで、結局程度の差でしか無いのもあり、比較の際に単純なイメージとして戯画された物とか。スパロボの影響もあったりする??
私はその辺の流れを知らない(その時代、私の両親すら結婚してないだろう)ので、気になるところではある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
