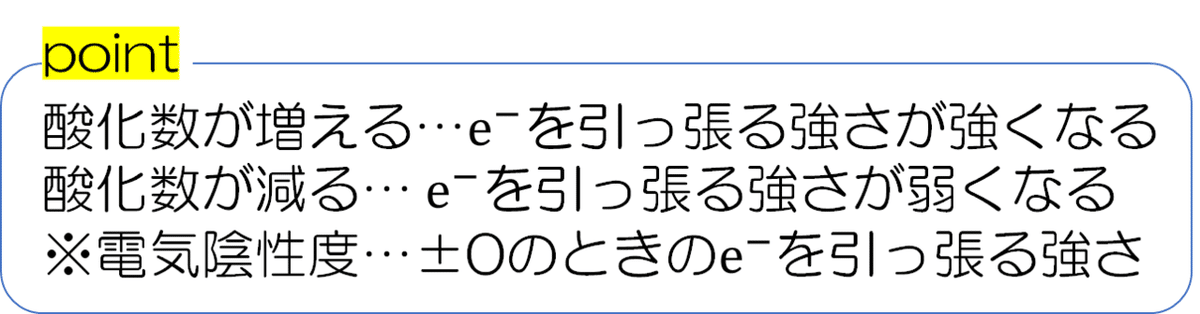高校無機化学#8(17族)~ハロゲンオキソ酸~
今回は、17族の最後にハロゲンオキソ酸を勉強する。
まず、オキソ酸の定義から.。
例として、最もよく出題されるClのオキソ酸で考える。Clのオキソ酸には、次亜塩素酸HClO, 亜塩素酸HClO2, 塩素酸HClO3, 過塩素酸HClO4がある。このように、ハロゲン元素は原子価が4であるため、形成できるオキソ酸の種類が4つであり、種類が最も多い。
ここで、電子を引っ張る強さについて1つ確認、
ある元素について、酸化数が増える、つまり、正に帯電すればするほど電子を引っ張る強さは強くなる。逆も、同様。
以上のことを確認したうえで下の図を見てほしい。
①Clのオキソ酸の酸としての強さ
まず、酸の強さについて。中心元素のClの酸化数が増えれば増えるほど、電気陰性度がO > Clにもかかわらず、Clがより強く電子を引っ張り、Oが電子を奪われるようになる。その結果、OはClに電子を奪われている分、Hから電子をより強く引っ張ろうとするので、OーH結合の極性が大きくなり、H+が電離しやすくなる。したがって、ハロゲンオキソ酸は酸化数が大きいほうが酸として強いこととなる。
②Clのオキソ酸の安定性
結論から言うと、安定性はHClO4> HClO3 >HClO2 >HClO となり、酸化数が大きいほうが安定となる。この理由は高校の化学の範囲ではないので理解していなくてよい。(共鳴構造が多いほど共鳴エネルギーが放出されて安定になることが理由のようだ。)
まとめ
以上、①、②はハロゲン以外のオキソ酸でも成り立つ。
知識
身の回りの、ハロゲンオキソ酸(の誘導体)について。
①NaClO
#1の混ぜるな危険反応で見た物質である、次亜塩素酸ナトリウムNaClOは不安定で、かつ、もともと電気陰性度の大きいClが正に帯電しているため、酸化力(電子を奪う力)が強いので、塩素系漂白剤として広く用いられている。また、次亜塩素酸ナトリウムの水溶液は加水分解により、塩基性を示す。
②KClO3
次に、過塩素酸カリウムKClO3について。16族でも登場することとなる物質であるが、私たちがよく目にするものに使われている物質でもある。
マッチの頭薬である。マッチの横薬が赤リンであることもあわせて覚えておきたい。
以上。17族完結です。
次回からは、16族。酸素Oや硫黄Sについて考えていこう。バイバイ。