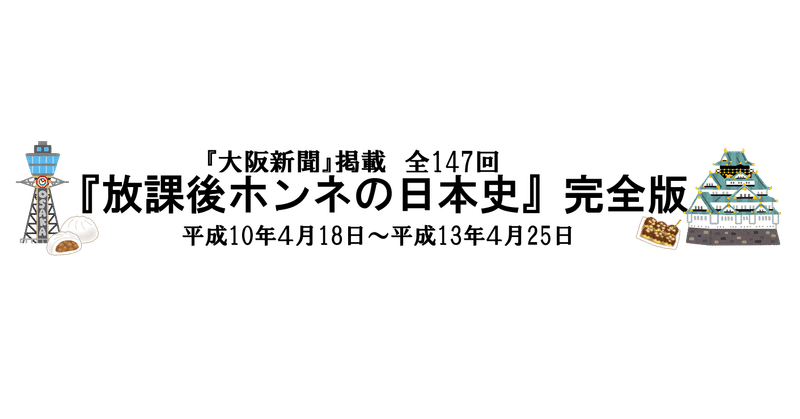
教科書が教えない軍人伝① 山県有朋(1838~1922年)
日本陸軍のドン・山県有朋は、天保9(1838)年、長州藩の足軽の家に生まれました。20 歳の頃、久坂玄瑞の紹介で吉田松陰の松下村塾に学び、文久 3 (1863)年には高杉晋作の組織した奇兵隊に参加しています。その翌年発生した四国連合艦隊による下関砲撃事件に従軍した山県は、軍備の近代化の必要を痛感して、攘夷論を放棄したと言います。
戊辰戦争では官軍の一員として活躍しました。明治2(1869)年にはヨーロッパへ軍隊制度を調査に行き、帰国後は、兵部省の要職につきました。そして明治6年に初代陸軍卿(長官)に就任して徴兵制を実施するなど、我が国の軍隊制度確立に大きく貢献しました。
明治11年に山県は陸軍参謀本部を設置して軍政と軍令を分離し、統帥権の独立を確保しました。明治7年の台湾出兵の際、陸軍の最高責任者であった山県の反対にもかかわらず、大久保利通によって出兵が行われたことが、統帥権独立を強く願うようになったきっかけだといわれています。
山県が我が子のように陸軍を愛したわけは、もちろん草創期から自分がその組織をひとつひとつ作ってきたからなのですが、その裏には、「陛下の軍隊」として、非の打ち所のないものにしたいという、彼一流の尊皇精神が底流としてあったのです。明治15 年に「軍人勅諭」を作ったのも、統帥権を独立させて、天皇が直接指揮を執るというカタチを重視したのもそのためでした。
一方山県は、明治18年に成立した第1次伊藤博文内閣で内務大臣に就任しています。次の黒田清隆内閣にも留任して手腕をふるうと同時に、自分の息がかかった内務官僚を育て上げてゆき、陸軍における長州閥と共に、内務省における「山県閥」が、その後大正期まで国家の中枢を握ることになります。
大日本帝国憲法が発布された明治22年の12 月には第1次内閣を組織して位人臣を極めます。この時に第1議会が招集されました。施政方針演説の中で山県は、「主権線と利益線」の確保の為の軍備増強を主張します。主権線(国土)を守るためにはその外側にあって敵国との中間にある利益線を防衛する必要があるというものです。地政学上、我が国にとっての利益線は言うまでもなく朝鮮です。しかし、これは後に行われる日韓併合を暗示しているものではありません。利益線を領土とすれば、新たな利益線が必要になり、それは無限に拡大してしまうからです。ところが、山県の息子である昭和の陸軍は、中国大陸でその愚を行ってしまったわけです。
元老となった山県が一目置きながらも、首相の座につけるのを渋っていた原敬が大正7(1918)年に首相になると、大衆化、民主化の進展と共に、山県の影響力は急激に衰えました。
政党嫌いで軍拡主義者。今日では評判が悪い山県ですが、外交的な意見は決して過激なものではなく、慎重で、他の国々への配慮を忘れないという一面もありました。
良くも悪くも、山県は、明治大正期の日本の政治を形成した典型的な軍人政治家だったのです。
連載第63 回/平成11年7月7日掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
