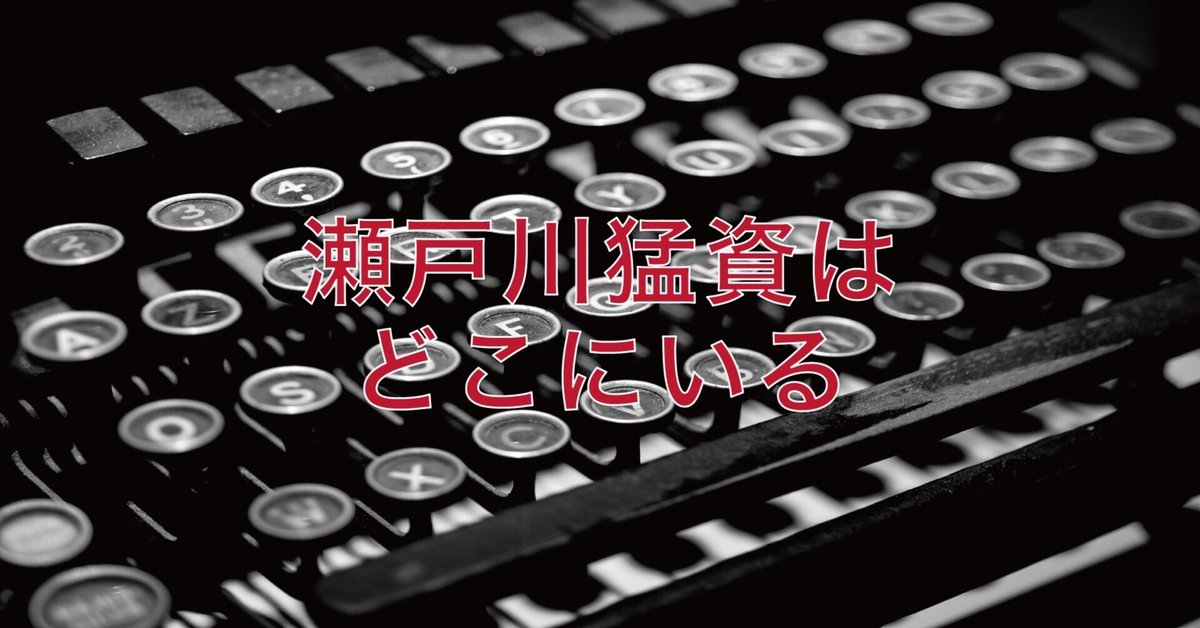
第12回「ブックマン瀬戸川猛資⑥」
今回から、瀬戸川猛資の新聞での書評活動についてご紹介していく。
新聞書評は、当然ながら雑誌よりもさらに広い層をターゲットとする(殊に瀬戸川が新聞に書評を書いていた90年代は新聞の発行部数が現代よりも遥かに多く、またインターネットの書評などもなかったため、その影響力は現代の比ではなかったと推測できる)。その広さというのは、年齢にしても読者の興味関心にしても同様であり、そこで広く一流と認められるのは生半に簡単なことではないのだ。
〈毎日新聞〉の読書欄「今週の本棚」にて瀬戸川は長らく書評委員を務めたが、丸谷才一のエッセイ「三ページの書評欄の二十年」によれば、この「今週の本棚」は他の新聞・雑誌の書評欄を圧して影響力を及ぼしていた、こともあったらしい。その中でも瀬戸川猛資の書評は、向井敏のものと並んで、とりわけ編集者たちの間で高評価であったそうだ(『愉快な本と立派な本 毎日新聞「今週の本棚」20年名作選(1992~1997)』巻頭に収録)。
瀬戸川はこの欄に、1992年から1998年まで7年間に渡って100本以上の書評を寄稿したが、そのことを今覚えている人はほとんどいないだろう。これは実に残念なことだ。というのは、往時の反響ぶりからすると嘘みたいに忘れられている彼の新聞書評を今読み返してみると、そのクオリティの高さに驚かされるからだ。忘れられてはいるものの、これこそ彼のキャリアハイなのである。取り扱う分野も実に広い。ジャンル小説を扱うこともあるが、教養新書や人文書、普通小説まで「瀬戸川猛資の好きなもの」という大きなカテゴリーを外さない範囲で様々な内容の本が取り上げられている。彼が80年代に〈BOOKMAN〉他の媒体で鍛えた「対応力」が如何なく発揮されていることが分かる。
個別の論に入る前に、まず瀬戸川猛資の新聞各社への寄稿について、以下のようにまとめてみた。
①〈産経新聞(夕刊)〉「読書欄」:1988/6/29~1991/10/11(全7回)
②〈毎日新聞(朝刊)〉「リレー書評」:1988/7/10~1991/10/11(全39回)
③〈読売新聞(朝刊)〉「昭和30年代翻訳ミステリ雑誌の疾走」:1989/9/4~1989/9/25(全4回)
④〈信濃毎日新聞(夕刊)〉「水曜ライブラリー・推理の世界海外編」:1992/2/19~1993/3/3(全11回)
⑤〈毎日新聞(朝刊)〉「今週の本棚」:1992/4/20~1998/10/4(全79回)
このうち、長期連載となった②⑤については次回に回して、先に①③④について見ていく。
瀬戸川が80年代に〈週刊サンケイ〉(「現代ミステリー事情」「ミステリー」)、〈正論〉(「ミステリー昨今」)といったサンケイ系列の雑誌で長期の連載を持っていたことは既にご紹介した通りである。おそらくはその流れで、〈産経新聞〉「読書欄」への寄稿を依頼されたものと推測できる。ちなみに〈産経新聞〉の「読書欄」は、1988年6月1日に紙名を〈サンケイ〉から〈産経新聞〉に改めた際に、これまでは週1回だったものが大幅に刷新され、毎日掲載となった(夕刊がない日曜日を除く)。曜日ごとに「科学」「文芸」「エンターテインメント」「文庫」「社会」「児童書」とおおまかなテーマが決まっていて、瀬戸川は「文庫」「エンターテインメント」の欄に顔を見せている。
既存のミステリ時評連載の流れで引き受けたためか、書評のテーマは海外ミステリ方面に限られていて、以下の作品を取り上げている。
・パスカル・レネ『三回殺して、さようなら』(1988/6/29)
・H・F・セイント『透明人間の告白』(1988/7/7)
・パトリシア・ハイスミス『殺意の迷宮』(1988/7/27)
・ピーター・ラヴゼイ『殿下と騎手』(1989/2/1)
・ネヴィル・スティード『ブリキの自動車』(1989/4/12)
・ピーター・ラヴゼイ『煙草屋の密室』(1990/3/7)
・ジェイムズ&クリッチリー『ラトクリフ街道の殺人』(1991/10/11)
1988年~1989年は頻繁に寄稿しているが、〈正論〉における「ミステリー昨今」の連載が終了した(1989/5)ためだろうか、その後は寄稿頻度が極端に下がっている。そして1992年9月に再度の「読書欄」の改組があり、枠が減ったため、フェイドアウトした。本欄についてはいい意味でも悪い意味でも、「ミステリー昨今」の外付け的な扱いとみるのがよいようだ。
個人的な話であるが、この〈産経新聞〉「読書欄」の確認は瀬戸川の資料のチェックのなかでもとりわけ苦労させられた。例えば〈毎日新聞〉や〈読売新聞〉は、バックナンバーがすべてデータベース化されていて、国会図書館(あるいは市区町村の図書館のうち、契約があるところ)の端末から、記事の掲載情報やその記事の内容にアクセスすることができる。しかし〈産経新聞〉は、上で述べた改組後の「1992年9月以降」の分しかデータベース化されていない。まさに「見たいところだけがピンポイントで見られない」状態なのだ。仕方がないので、1988年6月から1992年9月の期間のマイクロフィルムを、国会図書館の新聞資料室で数日に分けてすべて閲覧して先ほどの7本の原稿を掬い上げた次第である。「日付」や「朝刊・夕刊」のような切れ目で頭出しすることもできず、貴重な休日にハムスターのようにひたすら回し車を回し続ける、あるいは川土をひっくり返して砂金を掘るような生活は大変心にクるものがあった。もちろん、「日付は不明ながらいくつかはある」ことが分かっていたからこそ続けられた作業であって、まったくの無根拠であればとてもできなかっただろう。本職の書誌研究家の方々の忍耐強さ、そこから新資料を発掘する実績には、ただただ敬服するばかりである。
続いて「昭和30年代翻訳ミステリ雑誌の疾走」について。これは月単位で寄稿される全四回構成の連続コラムである。なぜ読売新聞か、なぜミステリ雑誌をテーマにしたのかといったディテールはさっぱり分からないが、まあそういう記事であったとご理解いただきたい。
第一回は〈日本版EQMM〉、第二回は〈マンハント〉、第三回は〈ヒッチコック・マガジン〉と紹介し、最終回ではそれらをまとめている。ただお話の中心となるのは雑誌の内容ではなく、主に各雑誌の編集者たち、翻訳者たち、そして評論家たちの系譜である。田中潤二に代わって〈日本版EQMM〉の編集を取り仕切らなければならなくなった都筑道夫、〈マンハント〉に寄稿した小鷹信光や田中小実昌、植草甚一といった綺羅星の如き人々、そして〈ヒッチコック・マガジン〉を自分なりのものとして完成させてしまった中原弓彦(小林信彦)。瀬戸川は語る。彼らの仕事は太平洋の向こうからミステリ雑誌を輸入し、それを横から縦に移すことではなかったと。彼らがアメリカから持ち込み、独自のものに作り替えて発信したのは〈カルチャー〉であったと。各回1200文字ほど、一般向けも意識したためか、内容的には深掘りされておらず散漫なものになってしまったのが残念だが、テーマとしては面白い。なお、後に鏡明が『ずっとこの雑誌のことを書こうと思っていた』(フリースタイル)で雑誌〈マンハント〉とアメリカの〈カルチャー〉を受容することについて大いに深掘りしているので、まだ読んでいない人にはこちらもおすすめ。個人的な体験から敷衍して、当時の関係者に寄り添う姿勢は、瀬戸川のこの連載とも共通している。
最後に〈信濃毎日新聞〉「水曜ライブラリー」について。副題に「推理の世界海外編」とあることでも分かる通り翻訳ミステリーに特化したコーナーで、新しい要素はあまりない。時期的には〈毎日新聞〉の「今週の本棚」初期と重複しているが傾向は異なり、先に触れた〈産経新聞〉「読書欄」への寄稿にむしろ近い。取り上げた作品をまとめると、以下の通り。
・ジョン・ディクスン・カー『エドマンド・ゴドフリー卿殺害事件』(1992/2/19)
・パトリック・マグラア『グロテスク』(1992/3/18)
・アーロン・エルキンズ『断崖の骨』(1992/4/15)
・トニー・ヒラーマン『話す神』(1992/5/20)
・ニコラス・コンデ『殺人愛好症の男』(1992/7/1)
・マイクル・クライトン『ライジング・サン』(1992/8/5)
・パトリシア・ハイスミス『イーディスの日記』(1992/9/9)
・レン・デイトン『マミスタ』(1992/10/28)
・ジョン・D・マクドナルド『シンデレラの銃弾』(1992/12/2)
・コリン・デクスター『消えた装身具』(1993/1/27)
・ディック・クラスター『差出人戻し』(1993/3/3)
この中でも特に注目されるのが、マイクル・クライトン『ライジング・サン』だ。「日本式ビジネスの暗部」「日本とアメリカの文化・考え方の違い」を、いかにもクライトンらしくディテールを詰めながら執拗に描きこんだサスペンス小説で、映画化を見据えて日本でも素早く翻訳刊行された(ハヤカワ文庫NV)。瀬戸川は〈ミステリマガジン〉での特集にも寄稿しているし、〈This Is 読売〉といった雑誌でも本作について記事を書いているが、他の評者がしばしば本作を「アメリカ人による日本バッシングの書」であるとしているのとは対照的に、一貫して「サスペンス小説としてどう見るか」という視点から評価を提示している。この辺りに、瀬戸川の評者としての誠実さを見て取れるように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
