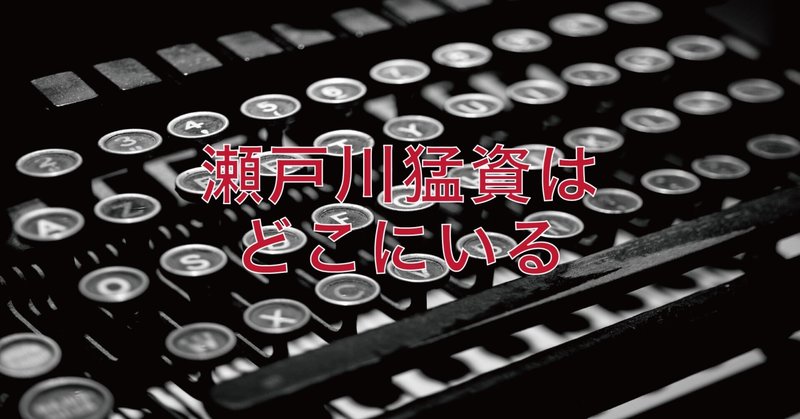
第10回「ブックマン瀬戸川猛資④」
前回ご紹介した〈バラエティ〉に続いて瀬戸川猛資が寄稿を始めたのが光文社の雑誌〈週刊宝石〉の書評コーナー「本のレストラン」である。〈週刊宝石〉は1981年10月創刊(創刊号は10月17日刊)、〈バラエティ〉と比べてグッと砕けた「サラリーマン御用達」の週刊誌である。過激なルポやグラビアが多いのも特徴で、国会図書館の端末で「本のレストラン」のページを探している時にうっかりセミヌードグラビアのページを開いてしまい、慌てて閉じたこともあった。
「本のレストラン」は創刊と同時に始まった書評コーナーで、内容は同時期の週刊誌の読書欄と比べ、図抜けて充実している。全4ページの構成は、1ページ目「前菜」は、高千穂遙や内藤陳、井崎脩五郎他の計五名による新刊三冊のクロス短評(内藤が〈プレイボーイ〉で「面白本紹介」を開始したのは1978年7月号からだが、その連載が人気を集め「日本冒険小説協会」の設立にまで至るのは1981年中頃のこと。このコーナーに招聘したのはタイミングがよかった?)、2ページ目・3ページ目「メイン・ディッシュ」は、見開きに約2,000文字の長文記名書評+無記名の短評数本、4ページ目「凝ったデザート」は、約1,000文字の本格的コミック評となっている。
「メイン・ディッシュ」や「凝ったデザート」には、瀬戸川猛資を始め、吾妻ひでお、新井素子、いしかわじゅん、鏡明、柿沼瑛子、呉智英、黒丸尚(LEO名義)、斯波司、関三喜夫、関川夏央、中島梓、橋本治、福本直美、藤田尚、藤原龍一郎、宮脇孝雄、宮本和男(北村薫)……(以上五十音順、敬称略)と、当時30代、あるいは20代の気鋭の書き手たちがこぞって寄稿している。パッと見、ワセダミステリクラブの関係者が多いこと、また他の寄稿者のメンツからも分かる通り、この書評コーナーもまた編集者秋山協一郎の尽力により作られたものである(そしてこのメンバーのうちかなりの部分が、〈BOOKMAN〉寄稿者でもある)。
この中で瀬戸川は、宅和宏名義の4回を含めて20回書評を寄稿した(「メイン・ディッシュ」に17回、「凝ったデザート」に3回)。ルース・レンデル『わが目の悪魔』やサイモン・ブレット『スターは罠にご用心』、コリン・デクスター『謎まで3マイル』といった翻訳ミステリを扱った回もあるが、他の媒体であまり見られないような本を扱った回の方がむしろ面白い。
例えば、瀬戸川が「本のレストラン」に初めて登場した1981年10月31日号の「メイン・ディッシュ」では「本が読みたくてたまらなくなる“読書論”」と題して、新刊一冊、既刊二冊を取り上げている。その新刊こそ開高健・谷沢永一・向井敏『書斎のポ・ト・フ』(潮出版社)である(現在はちくま文庫)。本書は、昭和20年代に同人「えんぴつ」に集い、爾来三十年近くの付き合いを持つ三人の読書論客が、捕物帳、ピカレスク・ロマン、政治小説、児童文学など八つのお題に沿って「面白い本」の話を喧々諤々ぶつけ合うその軌跡をまとめたもの。読むと「そんな面白そうな本があるのか」とうっかり説得されてしまい、古本屋を探しまくる羽目に陥ること必至である。
閑話休題。こういった「優れた本を紹介した優れた本」を前にして書評家にできることはあまりない。何しろ面白いことを書こうとすると、何を書いても孫引きにしかならないのだから。そこで瀬戸川はこの三人の「論客」の個性を際立たせ、それをもって本書の紹介に替えることとしたようだ。「〈この人、こんなに本を読んでいて、いつ小説を書いているのだろう?〉といいたくなるほど博学多識の作家開高健」、「強烈な毒舌を随所にちらつかせつつ、〈何を聞いても答えてくれる〉博覧強記の国文学者谷沢永一」、「二人の間に割って入って、話が脱線しそうになるのを食い止め、巧妙に整理してまとめあげる、練達の読書人向井敏」、この最強の三人組が絶妙なパワーバランスの上で、すさまじい饒舌を疾風怒濤の勢いで展開する読書鼎談、と書かれては気になってしょうがない。本を食わずに生きていけない類の人間で、これを無視できる者などいない。ミステリだからとか歴史小説だからとか、そういうカテゴライズを全部ぶっ飛ばし、「面白い本」を読むための必須読本であろう。実際、私も瀬戸川に背中を押されるまま『ポ・ト・フ』を読み、その結果、ダフ『タレイラン評伝』であるとか、クライトン『大列車強盗』であるとか、色々買い込んでしまった。
このような具合に見開き2ページでバンバン押しまくられてはそりゃ説得力もあろうというものだ。雑誌〈週刊宝石〉の中心的な読者層(セミヌードグラビアやスキャンダラスなルポルタージュを読みたい中年サラリーマン)が、瀬戸川の口車に載せられてうかうか『ポ・ト・フ』を買ってしまうという面白い図が当時見られたのではないかと想像すると笑ってしまう。
コミック評にも出色のものがある。1985年9月27日号に掲載された『アドルフに告ぐ』評(宅和宏名義)がそれだ。何しろ書き出しが「昔からそうなのだが、なぜか手塚治虫の長編マンガを雑誌連載中に読む気がしない。」だからふるっている。床屋か喫茶店で〈ビッグコミック〉を手に取る機会があると、ちばてつやから始まってなめるように読んでいくのに手塚作品だけは読まない。単行本になるのを待っているというわけでもなく、ただ何となく読まない。単行本になったら半ば義務的に購入するがそれでも何となく読まない。それがある日、何となく読み始めるともう止まらない。一気に読み終えると「すごい」「もう文学も顔負けだあ」と周囲にふれてまわることになる……「俺は俺の読みたいときに読む」の極致。なんてワガママな奴だ。
瀬戸川は手塚の「構成力とプロット」・「オリジナリティ」を絶賛、「時間的空間的に雄大なスケールをとり、たくさんの登場人物を有機的に動かして面白さを盛り上げてゆく手腕はあきれるばかりで、“物語”“ロマン”そのものとしかいいようがない」と手塚作品の特徴を上げながら、それが『アドルフに告ぐ』でいかんなく、いや最大級に発揮されていると指摘。とはいえ結論は「しかし、あいにくと現在はまだこの3巻までしか出ていないから、あとはなんともいいがたい。先にも述べたごとく、筆者は「週刊文春」の連載をまるで読んでおらず、結末も知らないのだ。」となるのだが……「週刊文春」で連載を持っているんだから、素直に読んでおきなさい!(笑) 瀬戸川猛資の不思議な頑なさが垣間見える一幕である。
瀬戸川はそんなに熱心な手塚ファンだったっけと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれないが、それがあまり知られていないのは、彼にコミック評を書く機会が少なかったためだろう。数少ない事例であるが、例えば先に紹介した〈スターログ〉では、「鉄腕アトムとライバルたち」(1979年4月号)と題してキャラクター紹介や図説の原稿を寄稿している。また同誌1979年11月号では「フランケンシュタイン博士の末裔たち」というロボットマンガについての原稿(当然『鉄腕アトム』が中心)を書いている。評者たちが日頃あまり書く機会のないジャンルの評論を読むことができるのは、この「本のレストラン」の大きなポイントであろう。
そのほか、瀬戸川は年始の号に掲載される「新春特別企画――総括座談会」に、鏡明とともに毎回のように登場している。その年に「本のレストラン」で取り上げられた100冊ほどの文芸書・エッセイ、ノンフィクション・エンタメ・コミックの中から登壇者好みの本を選りだしていくという内容。匿名の質問者はおそらく秋山協一郎だろうから。もうほとんどワセミスOB座談会のノリなわけです。この剛腕二人に巻き込まれ、話を聞かされているうちに自分も色々語らされてしまう三人目の登壇者(毎年変わる)が面白い。似たような企画をやる雑誌も当時から決して少なくはなかっただろうけど、このワチャワチャした内輪の感じは独特の魅力といっていい。〈BOOKMAN〉第17号に秋山が寄稿したエッセイによれば、「本のレストラン」というコーナーを斬新だと褒める人もいれば軽薄で軟派な内容に苦言を呈する人もいたようだけれど。
最後に、『本とつきあう本』についても触れておこう。この本は、1986年に光文社文庫から刊行された「読書論」の本で、執筆者には「本のレストラン」常連寄稿者がずらっと揃っている。K社のA(これはもちろん「綺譚社の秋山」のこと)という編集者から原稿の取り立てを食らっている中島梓が、「「趣味は読書」なんてちゃんちゃらおかしいや」といきなりぶちまける辺りからも本書のパンキッシュな内容が計り知れるのではないだろうか(本を読むのなんて当たり前すぎて、「本を読みます」は「朝はパンとコーヒーです」というのと同じである。なお最近の私の趣味は音楽……という趣旨)。ちなみに瀬戸川は、最近新潮文庫の森鴎外『阿部一族・舞姫』にアニメイラストの表紙のものが出て……という話をしています。
ということで、ここまで、四回に渡って〈バラエティ〉=〈週刊宝石〉=〈BOOKMAN〉における書評の流れについて概観してきた。当時から現在まで、非ジャンル系の月刊誌・週刊誌の書評コーナーはほとんど読み捨て・一過性のもので、後に顧みられることが少ないのが当たり前になっている。内藤陳のようによほどキャラクターが立っていればまとめられて単行本として出版されることもあるかもしれないが、瀬戸川に限らずほとんどの書評家・評論家の文章は散逸してきた。しかし、それらを改めてまとめ直そうという試みが近年現れつつある(まだ情報が公になっていないものも含めて)。その過程で、瀬戸川や秋山のような編集者の立場にあった者たちが執筆者やその原稿とどのように向き合っていたか明らかにするような聞き取りが行われることを切に希望する。八〇年代ももはや四十年前。辛辣な言い方をすれば、もう十年十五年もすれば(いや現時点でも既に)、当時の若き書き手・編集者たちにお話を伺うことなどできなくなってしまうかもしれないのだから。
・Twitterで当時の書き手の人たちとやり取りする中で気になった近刊書。多分買って読むと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
