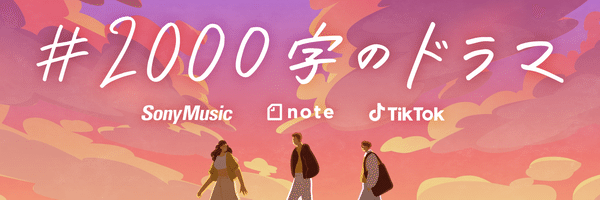時よ止まれ、お前は美しい【#2000字ドラマ】
ツキがない時……なぜか色んな“ついてない”は、だるま落としみたいに重なる。体育でボールが顔面に当たった。自販機で好きな飲み物が品切れだった。お気に入りのキーホルダーが壊れた。
そして今、学校の帰り道。ダイヤが乱れて駅は激混みで、人混みに押されながら電車に乗り込み、吊革にしがみついた。そして右の隣の隣に苦手なクラスメイトの男子、加藤(かとう)の姿を発見した。いつも無表情で、あまり人とつるまずに、一人で音楽を聴いてる加藤。今まで話したことはない。
加藤は私に気づいたようだけど、表情を変えずに窓に顔を向けた。どうせあっちも私と同じような事を考えてるんだろうな。私の名前も知らないかもしれない。我ながら目立つ特技は何も無い、モブキャラ女子だし。
「ふえ、あぁ」
突然の声に私は右隣を見る。加藤と私の間で吊革に捕まる若い女の人の、抱っこ紐の中の赤ちゃんの声だ。女の人は右手で吊革に捕まり、左手で畳んだベビーカーを持ち、大きくて重そうなバッグを肩に担いでいる。細い肩は今にも折れそうだ。赤ちゃんは顔を歪めて泣き始め、女の人は赤ちゃんを小声であやしながら、自分も泣きそうな顔になっている。
車内の空気は固く張り詰める。近くの客は彼女から目を逸らし、遠くの客はチラチラこちらを伺う。前の座席に座っているおじさんは寝たふりをし、私はどうすればいいか分からず、早く駅に着く事を念じた。
駅に滑り込んだ電車が停車する直前、大きく揺れて、女の人がよろけた。加藤が支えて「大丈夫ですか」と声をかける。「すみませ……」女の人が言い終わらないうちに、また揺れが来て、彼女の左手がベビーカーから離れ、今度は私がそれを掴んだ。私と女の人と加藤、三人が眼を見交わした瞬間、電車の扉が開いた。
「ここで降ります?」
加藤に問われて、女の人は頷いた。
「すいませえん降ります」
加藤は声をあげて、女の人と泣いている赤ちゃんをエスコートするようにドアに向かうと私を見た。私は思わず「これ持っていく」と頷いて、ベビーカーを持ち上げた。その重さに一瞬、怯む。腕に力を込めてベビーカーを抱え、二人と一緒に電車を降りた。
ドアの向こうは、降りる客と乗ろうとする客で混雑していて、その人ごみをかき分け私達三人はゆっくりとホームの登り階段の下まで移動する。駅の出口はひとつしかなく、当然、階段も人でいっぱいだ。
「依田(よだ)、それ持つから貸して」
加藤は私からベビーカーを受け取ると、軽々と抱えて階段を登り始める。
「あのっ、すみません」
女の人は慌てて加藤に声をかける。けど加藤はそれに答えず、私の顔を見て「荷物」と言った。私はまた頷いて
「荷物持ちますよ。改札まで行きます。大丈夫です」
と声をかけた。女の人は泣き笑いのような顔をして
「ありがとうございます」と言った。
改札の横で、女の人はベビーカーをぱぱっと車の形に戻して、赤ちゃんを寝かせた。ぐずっていた赤ちゃんはぴたっと泣き止み、私と加藤は思わずホッと息をつく。赤ちゃんは、大きくて濡れた瞳で私をじっと見つめる。
「可愛い……」
私は思わず呟いた。女の人は微笑んだ。
「本当に、ホントに助かりました。ありがとう嬉しかった。これ良かったら。ごめんなさいこんなものしか無いけど」
女の人は荷物から小袋入りのグミキャンディを取り出すと、私と加藤に渡して、何度もお辞儀をしながら改札を抜けていった。
私達は手元のグミを見つめた。加藤のはぶどう味、私のはりんご味。加藤はグミを私に差し出した。
「交換しよ」
「りんご好きなの?」
「お前がぶどう好きなんじゃん」
「えっ、何で」
「今日、ぶどうジュース買えなかったって騒いでたし」
私は驚いて彼の顔を見た。加藤はぶどう味のグミを私に押し付けて、りんごの方をひったくった。私達は階段を再び登って、ホームに戻った。
人が行き交うホームで、私と加藤は何となく並んで、開封したグミを頬張りながら電車を待った。加藤はひと粒、りんごグミを取り出すと、こちらに差し出した。
「一個、交換して」
私は加藤の指からグミをつまみ取り口に入れ、ぶどう味を袋から出した所でギョッとした。加藤はアーンと口を開けて待っていた。こんな事は何でもない、というフリをしながら、彼の口にグミを放り込む。
「うん。ぶどうだ」
加藤は口の中でグミを転がして笑った。目が合った途端、私の胸がずっきゅん、と鳴った。
———-うわ何これ、心臓ヤバイ。
私は口内のりんごグミを舌でそっと押す。柔らかい感触。味が全然分からない。
「お前の声さぁ」
加藤の声に、彼の顔を見る。彼は向こうのホームに顔を向けたまま声を張り上げる。
「お前の声だけはさ、なんかスゲー聞こえんだよね。俺さぁ……」
その時、電車が滑り込んで来て、私達の髪と服をはためかせる。彼が何かを言っているけど、動悸の音がやたら大きく耳元で響いて、聞こえない。
このまま時が止まればいいのに、と強く思った。
(完)
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?