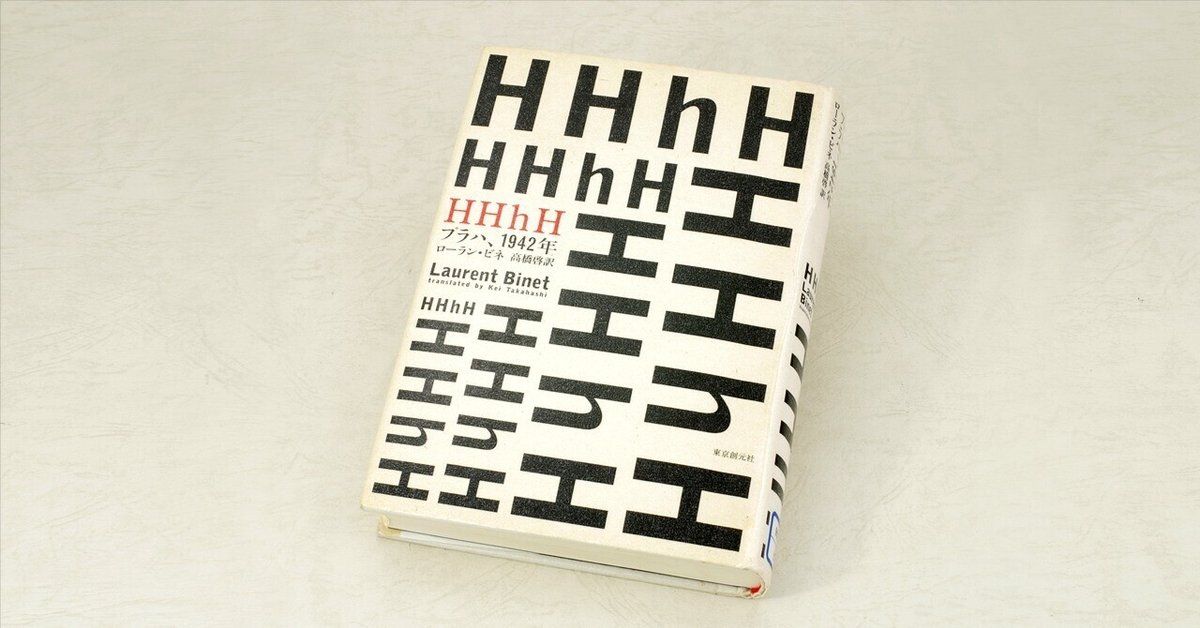
「HHhH (プラハ、1942年)」
ローラン・ビネ著 高橋啓訳 東京創元社 2013年6月
本屋大賞2014年翻訳小説部門第1位。
ハイドリヒ暗殺を扱った4本目の映画「ナチス第三の男」の原作にあたる小説。
映画の方は2017年製作で日本公開は2019年、ただし、評判はどうも芳しくないようです。
私は以下に掲げる理由により未見。
小説の方は2010年に発表されたもので、HHhHとは“Himmlers Hirn heißt Heydrich”「ヒムラーの頭脳はハイドリヒと呼ばれる」の略号だとのこと。
こちらは著者の母国フランスで2つの受賞歴があるほか、アマゾンのレビューでもなかなかの高評価の由。
内容は大きく二つに分かれ、前半はハイドリヒが如何にしてナチズムに傾倒し、ヒムラーに次ぐ地位まで上り詰めたかを描き、後半がチェコでの暗殺計画について実行者のガブチークとクビシュについて語られていきます。
この本が普通のノンフィクションノベルと大きく違うところは、著者が過去の描写について本来は不可避的に創作が挟まることを潔しとせず、逡巡する心情をところどころで述べていることで、出だしの20ページほどは小説の著述に関してのあれやこれや、ようやく物語を書き始めた後も、著者の見解というより想いや心情の吐露が頻出するところにあります。
途中まで数ページに亘って記述した内容を後から書き直したり、新たに入手した資料についての感想などを書き連ねたりしています。
人によっては物語に集中できず、作者が小説内に頻繁に顔を出す描写に自己陶酔の極みなどと非難したくなる可能性はあると思います。
とはいえ、ハイドリヒ暗殺という幾度となく映画や書籍に登場するネタで新たに物語を紡ぐとなると、こうした切り口が必要との判断もあったであろうし、なにより作者がこのネタについて自身の想いを語るにはこの方法をとるよりほかなかった、ということではないかと思います。
物語の内容はだんだん具体的になり、作者の登場頻度はある程度抑制的になってはいきますが、後半になるに従って、感情の表出の度合いが大きくなり、特にガブチークとクビシュが主役となってからはそれを押し留めることができなくなっていく様子にただならぬ気配が帯びていきます。
物語全般に亘ってそうなのですが、ハイドリヒ本人とその暗殺について必要な記述を満遍なく述べるというわけではなく、作者にとって重要と思われる事項を抜き出して書いている、という印象が非常に強く表れています。なので、本書でハイドリヒその人と暗殺計画の顛末を詳しく知りたい、という人には本書だけでは空白となる部分が相当出てきます。
読み進めていくうちに、本書が単なるノンフィクションノベルというより、ハイドリヒとその暗殺計画についての作者の個人的想いを語るための私小説である、ということに気が付くことになるのです。
小説の前半ではハイドリヒその人についての著述以外にもホロコーストの「意図主義」と「機能主義」についての論考や、ユダヤ人問題へのナチズムの対応の変化、ヒムラーやアイヒマン、シュペーアやヒトラーといった人物論、チェコのおかれた状況の英仏とドイツの関わりといった広範な話題についての指摘、後半はガブチークとクビシュがチェコからロンドンの亡命政府への脱出と暗殺作戦への参加、そのヒロイズムと犠牲になったチェコ市民への深い共感と哀悼という、大変振れ幅の大きな内容となっています。
一口に「ハイドリヒ暗殺についての小説」といった範疇に収まりきらない、なるほど斬新な小説ということができるでしょう。
事の顛末や歴史的事実の羅列よりも、作者の関心事に興味を覚える人にとっては大変刺激的読書体験となるのではないかと思います。
そういう意味では大変読み応えのある小説でしたが、さて、これの映画化となると、果たしてどうなるのか?
本書の最大の売りは前述のように描かれている内容よりは、作者の心情の吐露にあるので、それを映像化しないことには単に歪なハイドリヒの半生と暗殺の顛末を羅列しただけの物語になりかねない、という危惧があります。
芳しくない評判の多くはやはりそこにあるようです。
作者の顔が見えない描かれ方をしているようであれば、映画はスルーでもいいのかな、という気がしたのでした。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
