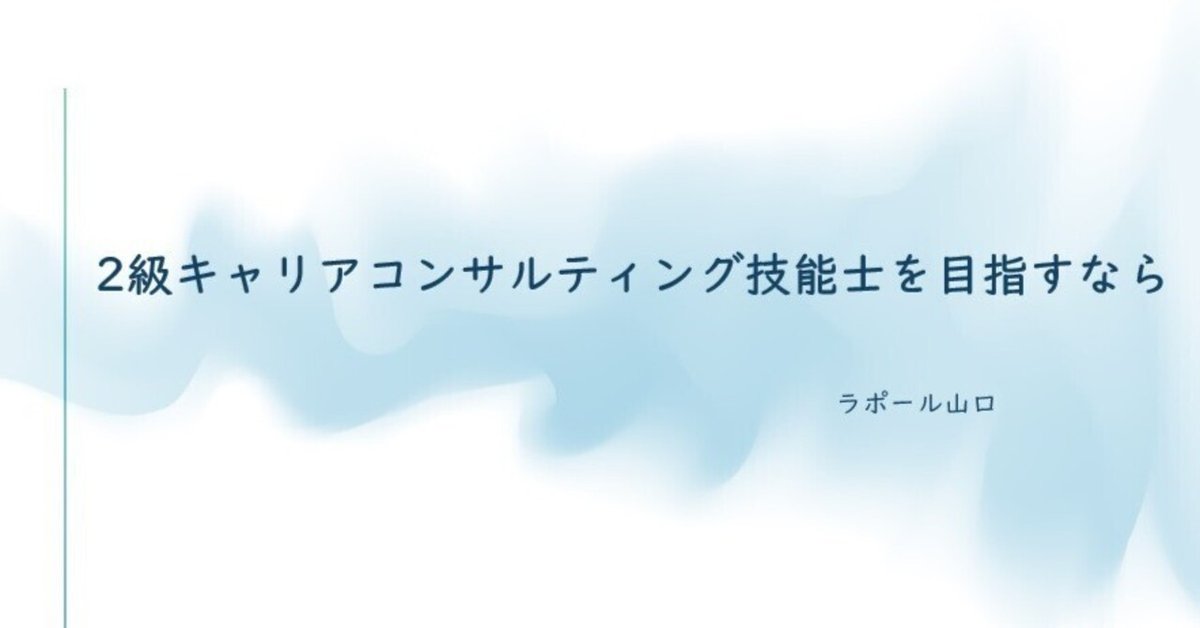
2級キャリアコンサルティング技能検定実技(面接)試験で「具体的展開力」の壁を超えるには
キャリアコンサルティング技能検定の受験申請期間(2023年9月19日~10月3日)ですね。みなさん申請されましたでしょうか?
今回は2級キャリアコンサルティング技能士の「具体的展開力」の壁を超えるにはです。
私自身、3回不合格だったのですが、いずれも具体的展開力が所点未(不足)で、壁にぶち当たって苦労しました。
・聴くことはできたがその後どうすれば良いか迷って何もできなかった…
・もう少し早く進めて提案できたらよかったのか…
・提案はしたものの相談者が固まってしまって違ったのか…
・提案してCLの合意をもらわないと合格しないのでは…
等々、迷いを抱えていたわけですが、壁を越えられた時に自分の意識を変えたポイントは以下の2つで、この意識が実務でも大変強みになっていると実感しています。勇気は要りますが迷っている人は是非以下の2つを試してください。
① 選択する支援をしない(=悩みや迷いと向き合う支援をする)
ポイントは来談第一声の選択肢を選択するための支援をするのではなく、選択できない相談者が自身の悩みや迷いなど内面と向き合う支援をすることです。問題把握力を本質まで高めることにも繋がります。
例えば「出来れば今の仕事を続けたいが、転職も含めて迷っている」という設定があると「どちらがいいのか選択を支援しよう」ということにキャリアコンサルタントとして意識が向きがちになりますが、その結果何が起こるかというと、内省の支援が疎かになり、相談者の状況や希望を聞いてどっちがいいのかキャリアコンサルタント自身が考え始めて、条件を並べて選択を迫ってしまいます。
もしくは相談者の内省が深まっていても、要約で来談第一声に戻り「・・で、今の仕事を続けるか転職を考えるかどちらがいいのかということですね」になってしまい折角内省して展開しているのに元に戻ります。もったいない。要約するなら「〇〇したいけど、◇◇の思いがあって、だから悩んでいるんですね」と問題を概念化(構造化)した要約を入れられるよう、練習して試してください。選択出来ない、前を向けない相談者の内省を支援して相談者の自己概念の成長や自己理解の深まりがあって、それを相互に共有できるのが具体的展開の第一歩です。そうすることで相談者は自ら方向性や、選択するために必要なことに気付きます。
2級の試験では「ありたい」や「ねばならない」の他にも防衛や抵抗、障害があることが多いです。そこに向き合えるように支援できでるのが熟練レベルですね。
② 提案しない(=相談者に考えてもらい言葉にしてもらう)
2級の勉強を始めた当初は「こうしてみてはどうですか」と提案できるのが合格ラインだと勘違いしていました。でも目標を決めるのは相談者ですから、まずは相談者自身が目標を立てられる支援しましょう。
これをやるには問いかける力や問いかけの引き出しが要りますね、私の場合「今考えていることを言葉にできますか?」「何か行動出来ることはありますか?」など問いかけに徹しました。また踏み込まないといけない場面や違和感を感じた事は「私は〇〇を感じたのですが、いかがですか?」とアイメッセージを添えた問いかけにしました。(これは1級の試験も同じです)
問いかけを繰り返すことで相談者自身が気づき、自分自身で目標を考え始めます。そして仮に相談者の立てた目標に不足があれば「足す」ことが出来れば尚良いです。
試験対策として20分の面接試験で焦って提案して方策を進めることはありません。「気づき」があればそれを目標として方策以降は口頭試問で挽回できます。(もちろんここは鍛える必要はありますよ)
以上は私の経験ですが、3回の不合格の後 ①②の意識を変えたことで、それまで50点や55点だった具体的展開力は70点で合格しました。合格点に達しないと上手くいった/いかなかったは気になりますが、キャリアコンサルタントとして自分の意識や態度そして関わり方を見直して高めてみることが成長にもなりますし、実はそれが熟練レベルと名乗るには必要なことだと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
