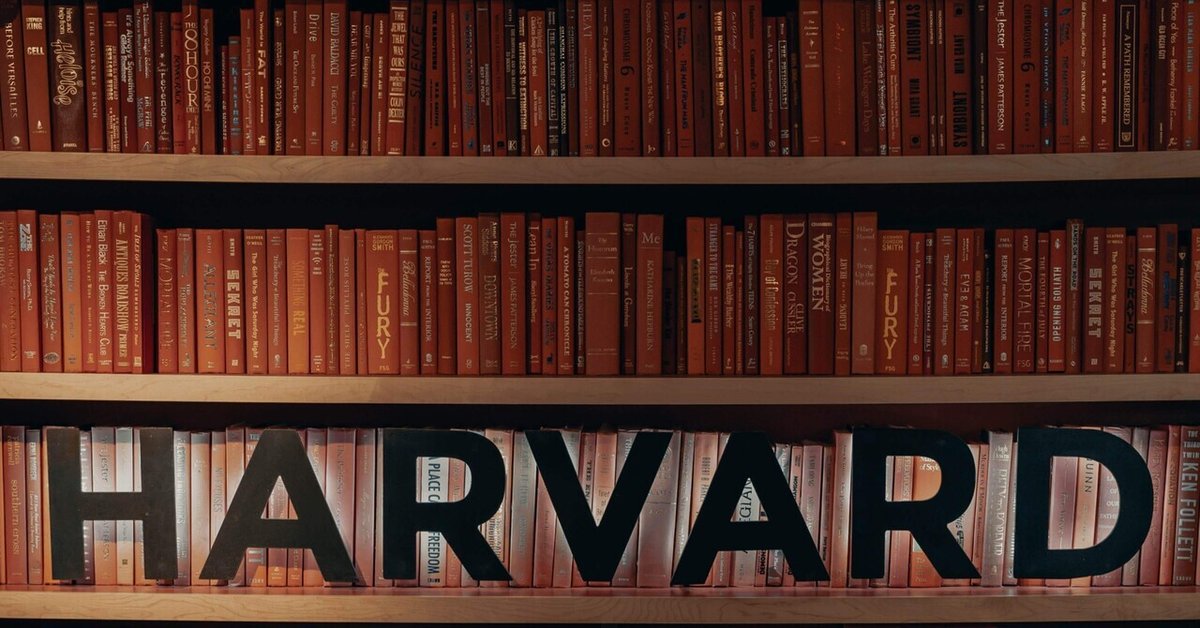
サンデル先生、「実力も運のうち」ってどういうことですか?
社会的・経済的に成功している人について、多くの人びとは次のように考えることだろう。
彼/彼女らが成功することができたのは、それ相応の努力を重ねた結果なのだ、と。
実際に、トマス・J・スタンリー著『1億円貯める方法をお金持ち1371人に聞きました』では、次のようなアンケート結果が紹介されている。
経済的に成功できた理由として、幸運であることを〈非常に重要〉な要素と感じている金持ち医師はわずか4%だけで、対照的に73%が精神的鍛錬を〈非常に重要〉と答えている。彼らのほとんどは、高校入学前から医者になろうと考え、その目標を掲げて以来ずっと努力を続けてきた人たちなのである。
このように成功者の多くは、運よりも実力で成功したと考えており、成功するためには、精神的な鍛錬といった努力が必要になると考えているのだ。
それでも成功者たちは、運も経済的成功の一つの要因であると信じている。
億万長者にとっての「運」とは、天候や競争相手の出現、金融政策、個人所得の変動、景気後退といった、自分一人では制御不能な要素を左右するものなのである。
そして、言う。「仕事に打ち込めば打ち込むほど、運もよくなる」、と。
運も実力のうちというわけだ。
ところが、その逆で「実力も運のうち」と主張する人物がいる。
アメリカの政治哲学者でハーバード大学教授のマイケル・J・サンデルだ。日本では『これからの「正義」の話をしよう-いまを生き延びるための哲学』で注目を集めたことが有名だ。
サンデルは過去の著書で議論を展開しているように、民主的なコミュニティを通じた「共通善」を追求している。そのなかで、功利主義や市場主義に基づく思想を批判するという立ち位置をとっている。
サンデル先生との対話(フィクション)
最近、新刊『実力も運のうち 能力主義は正義か?』を上梓したサンデル先生のもとをある青年が訪ねた。
青年は能力主義社会について考えてみたいと、サンデル先生の研究室を訪れたのだ。
サンデル先生は、コーヒー☕️とともに温かく迎え入れてくれた。
裏口入学はどうしてなくならないのか?
青年:
サンデル先生、本日はよろしくお願いいたします。ぼくはある有名大学を卒業し、そこそこ有名な企業に勤めています。社会人になって感じるのは、有名大学を出ていてよかったということもありますが、昔ほど有名大学出身ということにみんなこだわりがなくなって、実力重視になっているということです。にもかかわらず、名門大学への裏口入学がなくならないのはどうしてなのでしょうか?
サンデル:
現代は格差の広がった不平等な社会です。この不平等な社会で頂点に立つ人びとは、自分の成功は道徳的に正当なものだと思い込みたがります。能力主義の社会において、これは次のことを意味します。つまり、勝者は自らの才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じなければならないということです。
青年:
えっと、それが裏口入学とどう関係するのでしょうか?
サンデル:
焦らないで聞いてください。逆説的ですが、自分の才能と努力で成功を収めたという考え方こそ、不正に手を染める親が子どもに与えたかった贈り物なのです。親御さんの本当の気がかりが、子どもを裕福に暮らせるようにしてやることに尽きるとすれば、子どもに信託ファンドを与えておけばよかったはずですよね?ですが、彼らはほかの何かを望んでいた。それこそが、名門大学への入学が与えてくれる能力主義の威信でなのです。
青年:
能力主義社会を自分の才能と努力で勝ち抜いた結果として名門大学卒というステータスがあるのではなく、名門大学出身というステータスが能力主義社会を自分の才能と努力で勝ち抜いたという自信を与えるということですね。
サンデル:
その通りです。裏口入学というのは、親から子どもにとっては名門大学出身というステータスのプレゼントになり、子ども本人にとっては自分はこの社会で成功者になるにふさわしい人間だという自信を与えてくれるのです。
能力主義者のおごり
青年:
でも、それってその子の本当の実力じゃないですよね?なんだかその子どもも犠牲者って感じがしますね。
サンデル:
そうした見方もできるかもしれません。しかしその一方で、どういった手段であれ社会的なステータスを手に入れ、自分の才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じる成功者の中には、能力主義的なおごりを覚える人がいるのも事実です。
青年:
自分は頑張ったんだという自信がおごりに変わるということでしょうか。自信になるならいいでしょうが、おごりに変わると周囲に迷惑をかけそうですね。
サンデル:
例えば、成功を収めた人びとは自分が「神の仕事をしている」と信じるようになる一方、ハリケーン、津波、健康被害といった災難の犠牲者を、彼らの陥った状況について非があるとして見下すようになるということがあるでしょう。
青年:
震災や豪雨災害が起こったときに、天罰発言をする人が出てきて、それに一定の共感が寄せられるということは確かにありますね。東日本大震災の時にも耳にしました。
そもそもの条件が違うという問題
青年:
でも、能力主義社会への移行は、出自という自分ではどうしようもない要因により社会的な立ち居振る舞いが決定される貴族制社会に止まるよりは、随分マシなことなのではないでしょうか?日本でも明治維新以降、「立身出世」の掛け声の下、士農工商の身分社会を解体し、能力主義的な社会に少しずつ移行するなかで、ぼくたちは多くの自由を手にしてきているのではないでしょうか?日本の有名な政治思想家である丸山眞男風に言えば、「○○である」ことよりも「●●をする」ことへの移行というのは歓迎されるべきことではなないのでしょうか?同じように成功できる条件があるとすれば、能力主義に批判される理由はないのではないでしょうか?矢継ぎ早にすみません。
サンデル:
一呼吸おきましょうか。まあコーヒーでもお飲みください。あなたの疑問は多くの人が抱えている疑問かもしれませんね。問題は、あなたの最後の疑問です。あなたは「同じように成功できる条件があるとすれば」と言いましたね。さて、わたしたちには、本当に「同じように成功できる条件」が与えられているのでしょうか?
青年:
そうなんじゃないんですか?少なくともぼくは、親や周囲の大人からそのように言われて育ちましたよ。父親なんかはよく自分の子どもの頃は今よりも貧乏で、なんとか苦労して高校までは出してもらって、会社に入って一生懸命働いて出世したんだ。お前には同じ苦労はさせたくないから、大学まで出て、大企業に務めるか、公務員になることをアドバイスするよ。なんて言われて育ってきたんですよ。
サンデル:
確かにそういう育てられ方・育ち方をしている人もいるでしょう。しかし、「出世のレトリック」はいまや虚しく響いています。現代の経済において、社会的に上昇するのは容易ではありません。貧しい親のもとに生まれたアメリカ人は、大人になっても貧しいままであることが多いのが事実です。所得規模で下位5分の1に生まれた人びとのうち、上位5分の1に達するのは、だいたい20人に1人にすぎません。ほとんどの人は中流階級に上昇することさえないのです。
青年:
社会的な流動性が低いと考えるのであれば、それを高める政策を実施すればよいのではないですか?日本で言えば、年功序列の賃金制度や終身雇用の廃止、退職金の廃止または一本化、転職支援の強化などを実施すれば、社会的な流動性は高まり、結果として格差は是正されるのではないでしょうか?
サンデル:
現在あなたのような議論は盛んに行われていますね。しかし結論を言えば、社会的流動性によって不平等を埋め合わせることはもはや不可能なのです。貧富の差に真剣に対処しようとすれば、権力と富の不平等に直に取り組む必要があります。人びとが苦労してはしごを上る手助けをするプロジェクトで満足してはなりません。はしごの一段一段の間隔はますます広がっているのが実態なのですから。
贈り物としての才能
青年:
サンデル先生はどうしろと?
サンデル:
税負担を労働から消費と投機へ移すことが必要でしょう。進め方としては急進的または穏健的な進め方がありますが、給与にかかる税金を引き下げるか撤廃し、同時にその分の税収補填として、消費と資産と金融取引に課税するということです。そうすることで、社会的な再分配が機能することになります。
青年:
おっしゃっていることは理解できます。しかし問題は、多く課税されることになる人びとが、つまり成功者や富裕層と呼ばれる人びとが理解してくれるかということじゃないでしょうか?
サンデル:
成功者や富裕層は、「自らの才能を見出し、それを活かした努力をしてきたからこその成功であり、資産を築くことができたのだ」、と当然主張するでしょうね。ですが、自分の才能が、遺伝的な運あるいは神によって授けられた贈り物だとすれば、われわれは自分の才能がもたらす恩恵に値するという想定は誤りであり、うぬぼれであるとわたしは考えます。
共通善から成功を考える
青年:
確かにそういう側面はあるでしょう。でも、努力という点ではどうでしょうか?社会的な成功者や富裕層は、社会に対して有益な貢献をしているからこそ、その対価として莫大な資産を築くことができているのではないでしょうか?
サンデル:
市場の需要に応えることは、何であれ、人びとがたまたま持っている欲求や願望を満たすという問題に過ぎません。
青年:
それはそうですが、他人の欲求を満たせるということに資本主義社会における労働の交換価値はあるのではないですか?
サンデル:
ここでは倫理的観点から考えてみましょう。人びとの欲求を満たすことの倫理的意義というのは、その欲求の道徳的価値に左右されます。例えば、目的地に1分1秒でも早く行けるようになりたいという欲求があるとします。そのために時速300キロで走ることができる自動車を開発することができれば、他人の欲求を満たすことができます。しかし、時速300キロで走れる車を作ることは倫理的に見て、どう考えたらいいでしょうか?
青年:
ピンと来ません。話を進めてください。
サンデル:
わかりました。欲求の価値の評価には、論争を呼ぶことが明らかな道徳的判断が含まれますが、こうした道徳的判断を経済分析によって下すことはできません。時速300キロの車が公道を走れるようになれば、交通安全や環境保全といった観点から欲求を満たすことの正当性が議論されることになるでしょう。その正当性は、経済的な判断のみによって保障することはできないですよね?少数の人びとの欲求を満たすために多数の人びとの欲求が犠牲になるということは起こりうるのです。
青年:
それはそうですね。
サンデル:
であるからして、才能の問題を脇に置いたとしても、人びとが消費者の好みに応えることで稼ぐお金は、功績や道徳的な手柄を反映しているという想定は誤りなのです。これは私が研究していることで言えば、市場でやりとりされる金銭的多寡は、「共通善への価値ある貢献」を表現してはいないということです。
青年:
なるほど、そういう考え方はありますね。でも、それに富裕層は同意しますかね?
サンデル:
富裕層が同意するかどうかは問題ではありません。わたしたち一人ひとりが同意し、社会的判断を形成する必要があるという問題なのです。ここで課税の話に戻しましょう。課税は、たんに歳入を増やす方法というだけではありません。それは、共通善への価値ある貢献として何を重んじるかという社会の判断を表現する方法でもある。これこそがわたしたちにとって重要な考え方なのです。
実力も運のうち?
青年:
サンデル先生の考え方はわかりました。社会的・経済的成功を能力主義的には考えるのは間違っているということですね。しかし、いま多くの人はそのように考えてはいません。どこに分岐点があるのでしょうか?
サンデル:
「運も実力のうち」ではなく、「実力も運のうち」と考えるといいでしょう。そして、それをシステムに組み入れるようにすることです。例えば、社会的ステータスの第一歩となる大学入試については、選別事業を止めることを提案します。
青年:
しかしどうやって、大学の入学者を決めるというのですか?まさか生まれた場所で決まるとおっしゃるつもりですか?
サンデル:
生まれた場所で決まるとは言いませんが、運の要素は取り入れます。わたしの提案はこうです。まず出願者のうち、その大学では伸びない生徒、勉強についていく資格がなく、仲間の学生の教育に貢献できない生徒を除外する。そうすると適格な受験者が絞られることになります。そのうち誰が抜きん出て優秀かを予測するという極度に困難かつ不確実な課題に取り組むのはやめて、入学者をくじ引きで決めるのです。
青年:
何ですと?!くじ引きで決めるだと!そんなの誰が納得するんですか!?
サンデル:
わたしの提案は、能力をまったく無視するわけではありません。適格者だけが合格するのです。しかし、能力を資格の基準の一つとして扱うだけで、最大化すべき理想とはしません。どれほど目の肥えた入試担当者であろうと、どの子が将来、ある分野で真に傑出した業績を挙げるかを正確に評価するのは不可能です。
青年:
しかし・・・
サンデル:
メジャーリーグ史上最も優れた投手の一人であるノーラン・ライアンは、通算最多奪三振記録を持ち、野球殿堂入りを果たしています。しかし彼は18歳のとき、ドラフト12巡目でようやく指名されて入団しています。もしかしたらドラフトからわずか1枠の差でこぼれ落ちた人の中から、さらに優秀な選手が誕生した可能性は否定できません。頂点に立つ者は自力で登り詰めたのではなく、家庭環境や生来の素質などに恵まれたおかげであり、それは道徳的に見れば、くじ運がよかったに等しいというのが普遍的真実だとわたしは考えます。
何を「善」と考えるか
青年:
しかし、それでは社会人としての責任感は育つのでしょうか?わたしたちは、自ら選択しているという自覚があるからこそ、その結果に伴う責任を負えるのではないでしょうか?「くじ運」による運命、人生ということになれば、それはあらゆる言い訳の拠り所となってしまうのではないでしょうか?自分がいま成功していないのは、くじ運が悪く有名大学に入れなかったからだというように。
サンデル:
あなたがいう責任というのもまた、能力主義に囚われたものになっていないでしょうか?つまり、あなたの意見を言い換えると、自分がいま成功しているのは自分の才能と実力によるものであると言い換えることができるのです。能力主義的なコンテクストにおける責任とは、「自分自身の面倒を見る責任、そしてそれに失敗すれば、結果は自分で引き受ける責任」の意味で使われます。そしてそれを利用する形で、社会保障制度は「責任緩衝」機能を弱め、「責任追及」機能を強めています。その結果、能力主義に対するポピュリスト的な反発を誘引しているのが実態ではないでしょうか?
青年:
確かにこの間、社会保障制度は抑制され、リスクは政府や企業から個人へ移そうという試みが繰り返しなされています。さらに、それで困る人がなぜか自分たちを苦しめることになる政策を実行する政治家を選んでしまうという理解しがたい状況もあるように思います。
サンデル:
われわれは自分の運命に責任があり、自分が手にするものに値するという考え方にとって最強のライバルとなるのは、運命は支配できるものではなく、われわれの成功も苦労も、神の恩寵、運命のいたずら、あるいはくじ運のおかげだという考え方なのです。結局のところ、何を「善」と考え、どのような社会をつくっていくのか?それが、わたしたちの課題なのです。
青年:
何を「善」と考えるべきなのか?すぐには答えは出せそうにありません。これからの人生の中で考えていきたいと思います。サンデル先生、ありがとうございました。
青年は、カップに残った冷めたコーヒーを一気に飲み干すと、一礼してサンデル先生の研究室を後にした。
帰路についた青年の目の端には、公園で開催されている炊き出しに行列をつくるホームレスの姿が映り込んできた。
青年はサンデル先生の言葉を反芻しながら考えていた。
いまの自分の社会的地位が多くの幸運によって成立していること、を。
そして同時に、すぐにはその地位を降りられそうにないということも感じていた。
しかし、そこにあるのは諦めではない。
それは、新学期、一つ学年が上がったときに、少しレベルが上がった宿題を課せられたときの、あのワクワクに似ていると思った。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
