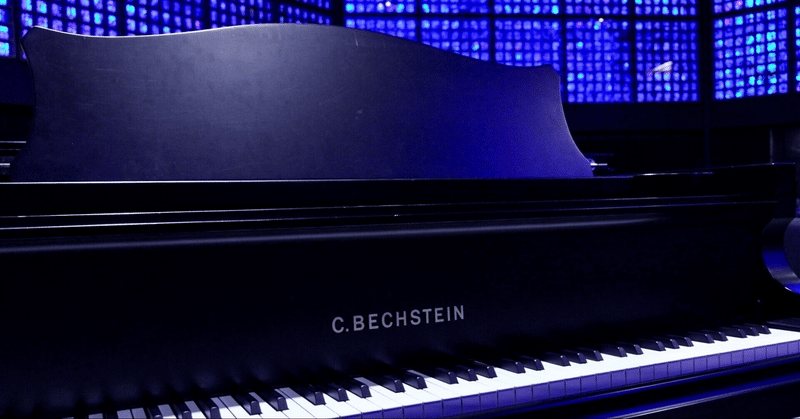
村上春樹とシューベルトのピアノ・ソナタ17番
村上春樹が『海辺のカフカ』などで、シューベルトのピアノ・ソナタの17番を退屈だけど重要な作品、と言及していることは広く知られています。音楽エッセイでは、ロマン派をめぐる解釈も書きつけられ、村上文学のある秘密に触れる告白にも思えます(それ自体が文学的韜晦の可能性もありますが、とりあえず正面から受けて止めておきます)。
シューベルトのピアノ・ソナタ全曲盤のある演奏を聞いていて、誰の演奏が念頭にあったのだろうと思いました。クラシック音楽にはさまざまな解釈がほどこされますが、シューベルトのピアノ・ソナタはかなり振り幅が大きいようにも思います。興味を持って聞いたなかで、違いが大きいことに驚いたので、その備忘録としてメモしました。
これはちょっとないんじゃないか、と思ったのがリヒテルの演奏でした。リヒテルは何度か録音しているのですが、リズムの取り方が機械的で、問題となる第4楽章もパッセージを速く弾きすぎて、「彼方」がよく見えてきません。向こうに何かがある感じが、村上春樹を惹きつけたはずですから、この演奏ではない気はします。
同じロシア系でもギレリスはさすがにもう少しわかっているようで、第4楽章を丁寧に演奏しています。けれども速いパッセージの処理が性急に思えます。爽快感が前に出てしまうと、この楽章はやはり台無しになる気がします。
ロシア系に対して、さすがにシュナーベルは異なり、右手の響かせ方も好ましいものです。途中まではかなり良いのですが、速いパッセージになると、どうしても指遣いのほうに関心が向いてしまうようです。もう少し音楽全体を大きく捉えてもいいのではないかと思いました。シュナーベルがシューベルト再評価の口火を切った功労者だったとしても、彼のベートーヴェン解釈にかなり近い気がします。
それに対して、レオンスカヤの演奏はかなりふさわしいものでしょう。第4楽章の向こうにあるものを捉えていて、平明に見える音符の奥に何かがあるように聞こえます。
そして、一つの理想と言えるのが、やはり、ウィーン三羽烏のひとりバドゥラ=スコダの演奏でしょうか。このあたりのシューベルト演奏が村上春樹が夢見たシューベルトだったのではないか、と勝手に推測します。もちろん正解かどうかはわかりませんが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
