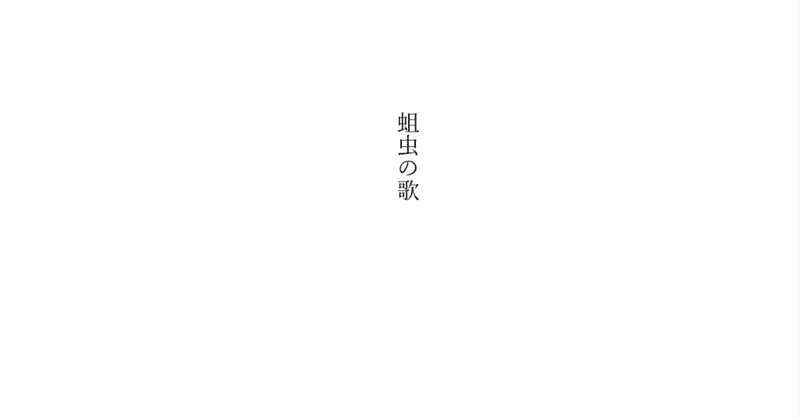
蛆虫の歌 12(終)
12
僕も愛理もお互い孤独であったからこそ孤独から抜け出すことが出来た。そんな矢先僕の元に一本の連絡が入った。
「もしもし、大野雪成さんのケータイでお間違えないでしょうか?」
「はい。どちら様でしょうか?」
「私、新田康太郎の父親の康次(やすつぐ)と申します。」
全く予想していなかった相手からの連絡であった。
「あ、普段お世話になっております。」
何故全く関わりのない康太郎の父親から連絡が来たのだろうかと、疑問に思いながら社交辞令を返す。すると、浮かんだ疑問はすぐに答えが出ることとなった。
「こちらこそ大変お世話になっています。今回何故僕の方から連絡させて頂いたかと言いますのも、誠に申し上げにくいのですが、急性心不全のため康太郎が三月三十一日に永眠致しました。」
僕は言葉が出なかった。というよりかは電話の相手が何を言っているのか理解が出来なかった。康太郎が死んだ?
僕は呆気に取られて三十秒ほど何も喋ることが出来なくなった。しかし、何故か恐ろしいほどに冷静でいられたのだ。決して思考を放棄したというわけでもなく、逆に言葉にならないほどの激情に駆られ取り乱したわけでもない。自らが目にしたもの以外真実であるとは思えなかった。そんな大ごとを電話で話されたところで受け入れられるわけもなかったのだ。そんな僕のことを察したのか、康太郎の父親が言葉を続けた。
「心中お察しいたします。中々受け入れがたい話ではあると思います。突然こんな連絡をしてしまって申し訳ございません。生前康太郎は雪成くんと佑介くんが一番の親友だと言っておりました。そこで本当に直前のご連絡となってしまって申し訳ないのですが、明日葬儀を執り行う予定なのですが、ご都合よろしければお越し頂けないでしょうか?家族葬ではあるのですが、私たちとしても親友である雪成くんと佑介くんには生前の面影がある状態でお別れして頂きたいのです。」
僕は勿論行くことに決めた。その後斎場や時間などを教えてもらい、バイト先にも急遽休むことを連絡した。
時刻は午後四時を回った。自分の部屋の押し入れから喪服を取り出し、明日の準備を整え窓を開けてタバコを吸った。空を眺めていると大量の涙が頬を伝った。僕は真実を受け入れることを恐れたのだ。未だに康太郎が死んでしまったということを信じ切れずにいたが、夕焼けの朱色の染まった空が僕を圧し潰すように降ってきた。まるで、僕があの時感じていた鬱と同じだ。僕の部屋を支配していた孤独が部屋どころか世界を飲み込んだのだろう。
もう本当に康太郎はこの世にいないのだろうか。それも明日になれば分かることだが、僕の中でまだ真実を受け入れる覚悟は出来ていなかった。そのことばかりが僕の脳内を支配してその日僕を寝かしつけなかった。
一睡もすることが出来ぬまま翌日を迎え、時刻は午前八時を回った。康太郎の父親からは十時にK斎場にと伝えられていた。どれだけ天井を見続けても、どれだけ空を眺めても、どれだけタバコを吸っても康太郎が死んでしまったという事実を信じることは出来なかった。
葬儀に呼ばれている佑介とも連絡を取り、九時五十分に斎場の前で待ち合わせをすることにした。朝の九時五十分は僕らが学生時代に二限に向かう際よく待ち合わせにしていた時間であったことを思い出して、懐かしさと共に虚しさが押し寄せてきた。
一睡もしていなかったため途轍もなく身体が怠かった。シャワーを浴びて目を覚まし、喪服に着替えたが、未だに康太郎は死んでいないように思えて喪服に着替えるのもどこか違和感を覚える。
準備を終えて家を出る時刻までに三十分ほど時間があった。葬儀の時刻が着々と近づくにつれて真実を目の当たりにする恐怖も増してくるのを感じる。何とか落ち着こうとタバコを吸ったが、二口吸っては消しまた二口吸っては消しのチェーンスモークを繰り返した。
全く落ち着くことが出来なかったため、出発の目安としていたよりも二十分ほど早く家を出た。こんな日であっても快晴の空模様であることがとても憎い。こんな天気がいい日に親友が空へ旅立とうなんて信じられるわけがあるものか。
落ち着かずに飛び出すようにして家を出てしまったが、斎場へ行くには早すぎる時間であった。僕はいつしか康太郎と二人でマリファナを吸って喋っていた公園に向かった。たった二、三ヶ月前のことであるのにどこか懐かしさを感じる。公園には心地よい風が流れていて、その匂いを辿ればあの時話していたことや感じていたことも鮮明に思い出せる気がする。そう考えると尚更、これからも康太郎と下らない話で盛り上がれる気がしてならなかった。
二人で散歩していた道を辿りながら遠回りをして最寄り駅へと向かった。ここまで少し歩いてはみたものの、二年前に死んでしまった祖母の葬式以来の喪服はまだまだ身体に馴染まない。スーツと疎遠の生活をしていれば尚更のことではあるが、今日という日に限っては永遠にこの喪服が僕に馴染むことは無いのだろう。
時刻は九時十分、最寄り駅はまだ通勤するサラリーマンの支配下にあった。無限にも思える人混みをかき分けて電車に乗り込んだ。スーツ姿のサラリーマンに紛れて出勤する時間帯の電車に乗り込んで社会人体験を味わったが、社会人というのは毎日こんなにも味気ないものなのだろうか。
車内でイヤホンをしてオアシスを聴いた。今にも泣き崩れそうになるのを何とか堪えながら電車に揺られていると、斎場の最寄り駅に到着した。時刻は九時三十分を迎えようとしていたが、経路確認をすると最寄り駅から斎場までは約十分程で到着するらしい。僕はコンビニでメビウスのスーパーライトとハイライトメンソールを一箱ずつ買った。康太郎が人生で初めて吸ったタバコと、僕が初めてタバコを口にしたときに康太郎がくれたタバコを手向けにしようと買って斎場へと向かった。
斎場に向かっている際に佑介から電話がかかってきた。
「もしもし、今どこにいる?」
「俺はさっき斎場の最寄り着いて、もう向かってるよ。あと三分くらいで着くかな。」
「なんか棺桶に入れるもの持ってきた?」
「俺は家からなんか持ってこようかと思ったけど、どれもあんまり燃えるものではなかったから、タバコ買ったわ。」
「なるほど、とりあえず俺もそっち向かうわ。入口のところで待ってて。」
僕が「はいよ」と返して電話を切った。
思い出を掘り起こす時間と、手向けのものを選ぶ時間、そして佑介との会話を経て段々と今日が葬式であるという実感が自分の中で湧いてくるのを感じる。
上り坂を上っていると苦しさを感じるのは、押し寄せてくる空のせいであろうか。気づけば空にはおぼろ雲がかかっていて、次第に太陽を隠していくのが見える。晴れているのに、何故だか不気味な雰囲気が空気中を漂っている。
こうして斎場に辿り着いた。佑介と待ち合わせた時間より十分ほど早く着いてしまったが、辺りには時間を潰せるような場所は見当たらなかった。仕方なく音楽でも聴いて待って医療と思っていた矢先、坂を上ってくる佑介の姿が見えた。
「あれ、意外と早かったな。」
「一応、こういう時は早めに行ったほうがいいのかなって思ってさ。とりあえず喫煙所探して一服して行こうぜ。」
僕も彼が到着したら一服しようと言おうと思っていた。斎場の見取り図を眺めると、喫煙所は外にあるらしい。僕らは如何にも落ち着かない様子で、早足で喫煙所へと向かった。
喫煙所には誰もいなかったが、タバコを吸っている時に僕ら二人は一言も会話を交わさなかった。僕らはお互いに不用意に口を開くべきではないと察していたのだ。きっと、何か康太郎のことに関する話題を出そうものなら、抱えた感情の全てが吹き出してしまうことくらい分かっていたからであろう。
僕は久しぶりにタバコを一本吸い切った。「落ち着いて」というわけにはいかなかったが、一人でいるときよりも佑介が隣にいてくれた方が、心なしか安心して一服することが出来たのは間違いのない事実であった。
僕ら二人は斎場の中へと足を踏み入れた。僕らは二人とも康太郎の家族とは面識が無かったため、控えていた康太郎の父親に連絡をして、どこにいるのか確認を取った。どうやら吹き抜けになっているロビーで座って待っている様で、僕らもそこへ向かうと少し康太郎の面影がある康太郎の母親であろう人物の顔が見えた。本当に康太郎の家族であろうかと佑介と何度も顔を合わせて確認し、恐る恐る会釈をして挨拶をした。
「康太郎のご家族様でいらっしゃいますでしょうか…?」
「はいそうです。今日はお忙しい中お越し頂き本当にありがとうございます。私が康太郎の父親の康次でこちらが私の妻で康太郎の母親の…。」
「希美(のぞみ)と申します。私からも御礼申し上げます。本日はありがとうございます。」
僕と佑介もそれぞれ挨拶をした。全員の顔を見ると余すことなく全員瞼が腫れていた。きっとここにいる全員、流した涙は同じであった
挨拶を全員に済ませたタイミングを見計らっていたのか、丁度よく葬儀の担当の人が表れた。
「それでは皆様お揃いでしょうか。これより新田康太郎様と最後のお別れをして頂くこととなります。準備が宜しいようでしたらご案内いたします。」
エスカレーターを上がり二階へと向かう。心臓の拍動が早まるのを感じる。もうあと少しで僕は真実を目の当たりにするのだ。
きっと佑介も似たような感情を持っているに違い無かった。僕ら二人は涙は流さずただ重苦しい沈黙を保ったままでいるのが何よりの証拠であろう。きっと、心のどこかでもう康太郎がこの世にいないことなど分かっているのだ。しかし、心のどこかでそのことを認めたくないのだ。そのことを認めてしまうのは、僕らが康太郎を見放してしまうことと同義であるのだ。
我々一向は火葬場の前に辿り着いた。焼却炉の前に棺が置かれているのが見える。我々は棺の足元の部分を囲むようにして立った。
「それではこれから故人、新田康太郎様との最後の対面となります。お別れの挨拶等、ここが最後となりますので心残りのございません様、お願い申し上げます。」
葬儀の担当者がそう言って、棺の顔の部分の扉を開いた。康太郎の親族を先頭に、その顔を確認する。
康太郎の母親は泣き崩れ、父親は気丈に振る舞おうとしているものの、目からは大量の涙が溢れていた。
僕は子を失ってしまった人間の崩れる様を見るのが本当に心苦しかった。康太郎の親族もきっと愛理と同じ様にこれから失意の海の中を歩かねばならないのだ。そんな愛理を間近で見ていたからこそ僕は残された遺族に心の底からの同情を送ろうと心に誓った。
いよいよ、僕と佑介に順番が回ってきた。棺の中を覗くと魂が抜け、入れ物だけとなった康太郎の寝顔がそこにはあった。一瞬何かの悪い悪戯のようにも思えて、康太郎を精巧に模した人形のようにも見えたが、数秒見つめると目の前にある遺体は間違いなく本物の康太郎であることが分かった。僕はこの瞬間「康太郎がもうこの世にいない」という真実を目の当たりにした。僕は康太郎の顔に触れた。熱くなった僕の体温と死んで動かない康太郎の冷たい体温が僕らの生と死を分けている。もう視界が涙でぼやけてしまって全く前が見えない。僕はこの日親友を失った。
僕と佑介は遺体となった康太郎に一つも言葉をかけることが出来なかった。僕は手向けの花とタバコを棺の中にしまった。佑介は何やら手紙を用意していたらしく、それを花と共に棺の中に残した。僕は佑介にどんな内容を書いたのか聞いてみたくなったが、それを聞くことほど無粋なことも無いかと感じて聞くのを辞めた。
残された遺族も思い思いの品を棺に入れ手向けた。こうして最後の別れの挨拶が終わり、遺族と一緒に棺に蓋をした。葬儀の担当の人とも最後の確認を済ませ、康太郎は焼却炉へと入れられることとなった。僕も佑介もとっくに涙が涸れ果てていた。
康太郎の遺体を燃やすまでに一時間ほど斎場で待つこととなったが、遺族も含め全員が康太郎が死んでしまった現実を受け入れられずにいた。思い耽っていたからなのか、感情を失ってしまったからなのかは分からないが、その一時間の間に誰一人としてまともに口を開くことは無かった。
「火葬の方が終了致しましたので、もう一度先程の焼却炉の方へご移動願えますでしょうか。」
時刻は午前十一時半を回った。僕はとても切なく不思議な感覚に陥った。どれだけ懸命に生きたとしても、人があの世へ旅立つ瞬間というのはあまりに刹那的であまりに儚い。
我々は再び焼却炉の前に立たされた。骨になって出てきた康太郎からはもう面影さえも感じとる事が出来なくなっていた。葬儀の担当の人がどれがどこの骨かという説明をしてくれているが、遺族も佑介も含め全員心ここにあらずといった様子で目から光が失われていた。
こうして骨となった康太郎を骨壺の中に納め、康太郎の葬儀は終了した。遺族とも挨拶をし、また法要について何かあれば連絡をすると康太郎の父親は僕ら二人に話して解散となった。佑介とも斎場で解散した。ご飯でも食べに行こうかと考えはしたものの、何も喉を通りそうになかった。僕はこうして再び孤独と戦うこととなった。
康太郎の葬儀からどれほど経ったであろうか。しばらくカレンダーも時計もケータイも確認していなかったが、どうやらもう一週間ほど経過した様であった。しばらく愛理にも連絡を返せていなかったが、元気にしているだろうか。佑介からも何も連絡が無い。きっと彼も僕と同じ様にしていることだろう。
しかし、いい加減何かしなくてはいけないのも事実であった。この一週間バイトも全てサボってしまった。きっともう店長には愛想をつかされていることであろう。
この一週間、佑介が康太郎に向けて書いた手紙のことが頭から離れずにいた。どんなことを書いたのであろうか。思い悩んでも仕方が無いことだが、そればかりが脳内でちらついて気になって仕方が無かったのだ。
何かしなければならないなら、彼に向けて歌詞でも書こうか。手紙の代わりではないが、それが僕に出来る康太郎に対しての最後の手向けであるようにも思えた。
ペンと白紙を手に取り机に向かった。皮肉なことに、親友を失って初めて歌詞を書いた時の初期衝動を思い出すことが出来た。ペンを走らせる度に涙が溢れて止まなかった。それでも白紙の隙間が無くなるまで、書き続けることを辞めなかった。
「どこを探しても
どれだけ声をかけても
君はどこにもいないんだ
寂しくなるよ
もうこれから会えなくなるんだね
触れて分かる体温の差は
触れ合うことの出来ない生と死の壁だ
冷たく横たわって何も答えない君
目の前にいるのにどこにもいないみたいだ
君の死は僕の心に冷たく突き刺さったんだ
そして生きている僕の血の温かさが僕の胸を締め付けたんだ
君の行きついた先に体温があったらいいな
皮膚と皮膚が触れ合うように
心と心が触れ合うように
またいつも見たく笑い合おうじゃないか」
僕は書いた歌詞をいつしか康太郎に届けようと心に誓った。
なんだかこれまで流していた涙よりも暖かく感じられる。僕はこの先生きていくために再び命の炎を燃やすのだ。
気分転換に普段つけないテレビをつけてみた。チャンネルをガチャガチャと変えずに僕は現在やっているニュース番組を見続けた。普段ネットニュースで事足りていたが、ここ一週間程外界を全く接触しない生活をしていたため、生活習慣を取り戻すのにもいい機会だと思ってしばらくニュース番組を眺めた。
政治や金融、時事問題のニュースが流れていたがどれも僕の興味をそそらないものばかりであった。何か大きな時事問題が取り上げられる度に専門家やコメンテーターが番組内で意見を交わし合うが、何故解決する気もないことについてこの人たちは議論をしているのだろうと疑問に思う。それだけの熱量があるなら今すぐに僕を人生の底から引きずり上げてくれないだろうか、なあお偉いさん方。
そんなニュース番組を蔑みながら眺めていると、事故や事件のコーナーに移ったようだ。テロップには速報と流れている。どうやら普段この番組ではこの時間、別のコーナーをやっているらしく、アナウンサーも「番組内容を一部変更してお伝えします。」と伝えている。
「先程午後九時半、神奈川県横浜市内の…」
なるほど、確かにそれは速報だ。時刻はこれから午後十時を迎えようというところであった。僕は何故だか少し気になってその速報を見続けた。
「…神奈川県横浜市内の路上で歩行者一名と車二台が絡む交通事故が発生しました。警察は現在事故に絡んだ人々の安否確認と身元の確認を急いでいるとのことです。」
映像を見てみると、車は一台が大部分が損傷しており、もう一台はフロント部分が大きくへこんでいた。この事故に歩行者が巻き込まれたともなれば無事では済まないだろう。
少しして、番組も軌道修正をした。どうやら次は国際問題の様だ。この問題にも専門家やコメンテーターが首を突っ込んでは議論をしている。もういい加減飽きたと思い、窓を開けてテレビから目を離してタバコを吸った。
タバコを吸っていると先程の速報の続報が飛び込んできた。
「先程午後九時半、神奈川県横浜市内の路上で発生した交通事故についての続報が入ってまいりましたのでお伝えします。被害に遭われた歩行者の身元が判明しました。「坂本佑介」さん二十三歳男性がこの事故で亡くなったとのことです。」
僕は呆気にとられた。何かの聞き間違いだとも思ったが映像を再度見てみると、事故の現場は佑介の現在住んでいるアパートから歩いてすぐのコンビニの近くであった。
僕は急いでケータイを開き、佑介に電話を掛けたが一向に出る気配が無い。凄まじい悪寒が僕を襲った。ただ、事故に遭った人物が僕の良く知る佑介だと確認する術は現状無かった。
あまりに信じがたいニュースを目の当たりにしたせいか、激しい頭痛が僕を襲った。僕はそのまま意識を失った。
目が覚めると雨天の朝を迎えていた。どうやら中学時代に悩まされていた偏頭痛が今になって再び目を覚ましたようだ。
僕は昨日気を失ってしまう前に見ていたニュースを再びネットで調べ上げた。しかし、どこを探しても、被害者の男性「坂本佑介」=僕の良く知る佑介の数式が完成するような情報はどこにも載っていなかった。
時刻は午前九時半、再び佑介に電話をかけたもののやはり彼が電話に出る様子は無い。
僕はもう何もかもが分かってしまったような気がした。きっとこれから佑介の親族が僕に連絡をしてくるはずだ。それが答えだ。
僕の頬をまた冷たい涙が伝う。ねえ、神様。僕の親友が一体何をしたって言うんですか。
僕はこの時、康太郎が昔言っていたことを思い出した。
「この世を操作する神がいるかは見たことが無いから分からないけどね、例えばこの世の理不尽で死んでしまう人間が沢山いるけど、彼らは神に選ばれなかったんじゃなくて、きっと死神に選ばれたんだろうね。神が悪人を裁くために人を殺すなら、死神は気まぐれで人を殺しているんだ。神の寵愛とやらを受けている人間が心底羨ましいよ。けど、それと同時に死神の気まぐれで死んでしまうのも時々羨ましいとも思うんだ。ねえ、雪成。俺らはどっちかに選ばれる時が来ると思う?それともどちらにも見放されたまま人生を終えると思う?」
佑介も康太郎も、そして愛理の息子の夢人も。きっと彼らは死神に選ばれてしまったのかもしれない。あまりに残酷なことに感じるが、そう解釈した方が理不尽なことや辛いことにも盲目でいられるような気がした。
それならば僕は神にも死神にも選ばれなかったのだろうか。寧ろ僕は神にも死神にも見えていない透明の存在なのだろうか。
僕はギターのシールドを二本取り出し、わっかを作って天井に括り付けた。僕は神にも死神にも選ばれなかったらしい。ならば僕は僕自身を殺そう。
僕は首を吊って自らの手で命を閉ざした。薄れゆく意識の中、ケータイが鳴っているのが見えた。だが、僕にはもう関係のないことだ。僕は再び青い光を見た。どうやらこの先に佑介と康太郎と夢人はいるらしい。
ごめんね愛理。夢人とこっちで仲良くやってみるよ。
僕の部屋にはもう孤独すら存在しない。孤独は僕がいてこそ存在しうるものだったのだ。孤独だけはいつまでも僕を苦しめながらも常に僕に寄り添った理解者であった。僕は人生最後の日に最大の敵に心からの感謝を送った。
「僕が生きることが出来たのも、死ぬことが出来たのも君のお陰だったんだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
