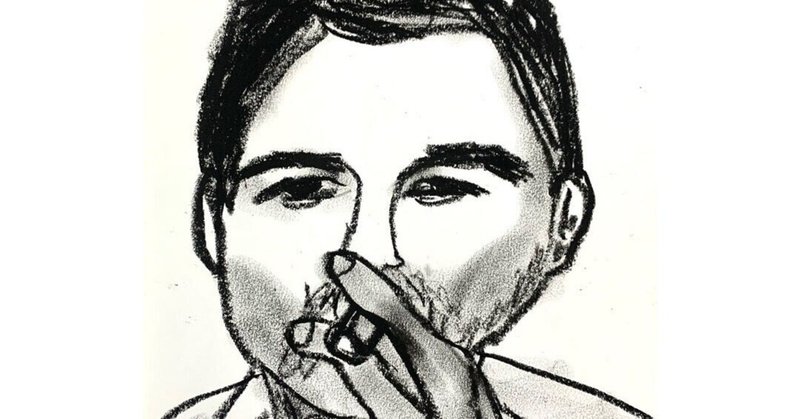
ジョイントを巻く女
窓から外を眺めていると、道を歩く人たちが足早になるのに気がついた。鞄から折りたたみ傘を出して、忙しなく広げている人もいる。
「降ってきたみたいだな」
俺は視線を戻して正面に座っているタツヤに言った。タツヤはストローで、ほとんど残っていないオレンジジュースをすすりながら窓の外を見た。それから「ああ……」と気のない相槌を俺によこした。
そうしている間にも雨はどんどんと勢いを増し、やがてスコールのような激しいものとなった。俺たちがいまいるファミレスに、ずぶ濡れになった人々が次々と入ってきた。
「これじゃあ帰れねえな」
俺の横に座っているハルが呟いた。俺とタツヤはそれにはなにも返さず、煙草を咥え、火を点けた。俺たちがふう、と煙を吐き出すと、ハルも煙草を咥えた。灰皿はすでにいっぱいになっていたが、店員はなかなか取り替えてくれなかった。
タツヤがグラスを持って立ち上がった。俺は自分のグラスをタツヤに渡した。それを見てハルもそうした。タツヤは苦笑いを浮かべ「なにがいい?」と言った。「お前のセンスに任せる」と俺とハルは答えた。
ハルは黙ったまま煙草を吸っていた。俺もなにも喋らなかった。周りの人の話す声が、空中でよどみ、ざわめきとなって俺たちを包んでいた。耳に入ってくる内容は、そのどれもが取り留めもなく、そして他愛のないものだった。
「いま何時?」
ハルがそう訊ねてきたので、俺は腕時計を見た。「五時半」と俺が言うと、ハルはふうんと言ったきりまた黙って煙草を吸い始めた。
タツヤが戻ってきた。俺にはアイスティーを、ハルにはコーラをそれぞれ入ったグラスを渡すと、自分はカルピスを飲み始めた。
「明日の対バン、インディーズでやってるところも出るみたいだな」タツヤが言った。
「それに、大阪から来るってバンドもいるらしいよ」ハルは煙草をもみ消しながら言った。
「すげえな、わざわざ東京にまで? なにで来るんだろうな。やっぱハイエースで来るのかな」
「ずいぶんステレオタイプのツアーだなァ」ハルが言った。
「じゃああれか、フォルクスワーゲンか?」
「車種の問題じゃねえよ」俺はタツヤに言った。タツヤは少し笑ってから続けた。
「俺たちもツアーやろうぜ。やっぱ遠くへ行かなきゃダメな気がするんだよ。いろんなところでやりてえよ。『フォーエヴァー・マン』として、バンドで有名になりてえよ。狭いところでやんややっててもしょうがねえと思うんだよな」
「ツアーねえ」ハルはまた煙草を咥えていた。
「やるにしてもカネがなあ」俺は言った。実際、バイトの給料だけではなかなか踏ん切りがつかない。
「でもよ、バンドやりたいからって俺たちはいまの生活を選んだわけだろ? それなのにそのバンドすらできてねえってのはかなりマズくないか?」
「そうはいうけどよ、タツヤ」ハルが言おうとするのをタツヤは手で制して言った。
「もう俺たちは安全なカードを全部切っちまったんだよ。あるいは捨てちまったんだよ。いまのままノホホンとやってるだけなら、どっかに勤めながらでもできるはずなんだ。それをしないってなら、腹ァくくらなきゃダメだろう?」
俺とハルは黙ってしまった。タツヤも喋らない。スタジオでの練習を終えてファミレスでくつろいでいるだけのはずが、なぜこんな深刻な話になってしまったのだろうと、俺はいままでの会話の流れを追っていた。タツヤはどうだか知らないが、ハルもきっと俺と同じ心境だろう。苦笑いをしてじっと灰皿を見つめている、その表情を見ればわかる。
「まあ、とりあえず、あれだ」ハルが口を開いた。「雨もあがったし、出ようぜ」
会計を済ませて外へ出た。さっきよりいくぶんは日差しが弱くなった気がするが、雨が降ったせいで快適とはほど遠い気候だった。じっとりと重い空気が、シャツと一緒に肌にへばりつくようだった。心なしか背負っているギターがいつもより重い気がする。
「じゃあ、また明日な」
駅でハルとタツヤの二人と別れた。俺は二人を見送ると、駅前にあるレンタルビデオショップに入った。
俺は明日のライブのSEを任されていた。SEとはバンドがステージに上がるときの入場曲のようなもので、メンバーの士気を高め、かつ、お客さんの興味を引くようなものがいいのだが、なかなかそれを探すのは難しい。
棚をあちこち見て回ると、とにかく様々な音楽がひとつの空間にひしめいているのがわかる。節操というものがまるでない。とは思ったものの、誰もこの店に音楽に対するポリシーなどといったものは求めていない。必要なのは利便性だ。それに尽きる。
俺はアルバムを五枚借りることにした。その中にはビートルズとセックス・ピストルズが含まれている。どちらも俺にとってはとても大切なバンドだ。
店を出ると、外はさっきまで雨が降っていたとは思えないほど晴れていた。空には雲がどこかへ消えていた。駅の改札に向かって歩いていると、正面のキヨスクの入り口に、ゴスロリとでもいうのだろうか、黒のメイド服のような、全体的にひらひらした服を着た、華奢な女の子が俺のほうをじっと見つめ、立っていた。
なんなのだろうと思いつつも、あまりそちらを見ないようにして足早に通り過ぎようとした。と、その女の子が俺の行く手を阻んだ。両手を広げ、真剣な目つきで俺を止めた。見ると彼女は耳と口と鼻にいくつものピアスを開けていて、目はアイラインやマスカラでかなり大きく見せようとしていた。六十八点だな、と思った。それから、面倒臭そうな女だな、とも。俺たちは見つめあったまま動かなかった。
「あんた、バンドやってるの?」
心の中で二十八まで数えたところで彼女はそう言った。
「かもね」
案の定、面倒臭くなりそうだった。俺は適当にあしらおうと、そう答えた。
「かもね、って、ギター背負ってるじゃない」
「なんにせよ、あんたとは関係のないことだと思うけど」
俺は早く帰って明日に臨みたかった。こんなところで油を売っていたくなかった。自分がだんだんと焦れて、イライラしてきていることに気づいた。そして、それを隠す気にはなれなかった。
「手」
「え?」
「なにを持ってるの?」
「それを知ってどうするの?」
「質問を質問で返さないで」
「……答える義務も義理もないね」
「嫌な奴」
俺は大きくため息をついた。
「そろそろどいてくれないかな」
「まだなにも解決してないわ」
「俺にはハナからあんたと解決するべき問題はない」
俺はそれだけ言うと彼女の横を通り過ぎようとした。
「あ、ちょっと待ってよ!」
彼女は俺が背負っているギターケースを掴んで、思い切り引っ張った。思わず後ろに倒れそうになる。
「危なねえな! いい加減にしねえとぶっ飛ばすぞ!」
「そのギターで? あたしをぶっていいのはベンジーだけよ」
「ふざけてんのか?」
「ちょっとしたシャレじゃない」
俺はまた大きくため息をついた。それから心の中で数を数えて、気持ちを落ち着かせようとした。
「あんた、バンドやってるの?」
四まで数えたところで彼女が訊ねた。俺は舌打ちをしてから「やってる」と吐き捨てるように言った。
「ふうん」彼女は俺の中のなにかを見破ったかのような表情をして言った。
「でもあんまりパッとしない?」
「余計なお世話だ」
「まあ、いいわ」と彼女は俺の手首を掴んで改札へと歩き出した。「ちょっと付き合ってよ」
彼女は改札口のカードリーダーにICカードをタッチして中へ入った。俺は財布にカードを入れたままだったので、タッチしそびれ、通り抜けられずに止められてしまった。
「どんくさいわねえ」
「キセルだと思われるだろうが」
俺たちは改めて改札を抜けて、ホームへと歩いた。相変わらず手首は掴まれたままだった。
「どこに行くんだ?」
「いいからついてきて」
黙ったまま三分待つと電車が来た。俺の家とは反対方向の電車だ。座席に座ると、ようやく手首が解放された。
「それ」
「ん?」
「なに借りたの?」
俺は袋からさっき借りたCDを出して、彼女に見せた。彼女はいやに真剣な目つきで、まるでなにかをチェックするかのようにそれらを見ていた。
「ふん」彼女はCDを放り投げるようにして俺に返した。
「なにすんだよ」
「あんた、なんにもわかっちゃいないわね」
「なにが」
「そんなんだからバンドだってパッとしないのよ」
「だからなにが」
「あんたのバンド、聴かないでもだいたい想像つくわ。どうせ『楽しければいい』なんてかこつけて、どっかのミュージシャンのモノマネをするだけのオナニーバンドでしょう? 自己顕示欲をひた隠して『わかる奴にだけわかればいい』なんて思いこんで、そのくせライブが終われば客に『ねえ、今日のライブどうだった?』なんて感想を聞いて回るようなものでしょう?」
「お前にバンドのなにがわかるんだよ!」
「だいたいわかるわよ、少なくともビートルズとピストルズを一緒に聴くような奴よりはね!」
わけがわからなかった。こいつはラリっているのではとさえ思った。それか頭のネジが外れているか。
「はあ?」
はあ、と彼女はため息をついた。どうしようもないバカを相手にして、ほとほと呆れたようなため息だった。それから彼女は黙りこくって一切口を利かなかった。
なんなんだこいつは。男だったら殴っていただろう。俺は苛立ちを必死で抑えていた。
そのまま駅を三つ四つ過ぎ、都心から離れて下町の雑多な風景に変わってきた。俺はスタジオでの練習があるとき以外は滅多に都内には行かないので、一駅一駅、進んでいくごとに「色」が変わるのが新鮮だった。ほんの三分もない移動時間で、がらっと印象が変わっていく。しかし、いまはそんなことはどうでもよかった。
電車が駅に近づき減速を始めると、隣に座っている彼女がまた俺の手首を掴んで、立ち上がった。
「着いたわよ」
電車が止まると、俺は言われるがまま彼女に連れられて電車から降りた。改札を抜けるといくつか出口があったが、彼女は迷いを見せることなくその中の一つに向かって歩いていった。
駅を出ても彼女は信号以外では止まることなく、喋ることもなくひたすらどこかへ向かっていた。
「どこに行くんだよ」
返事はなかった。大通りから路地に入り、いろいろな店がところ狭しと並んでいる、入り組んだ道を通っていく。俺は何度かつんのめってしまうことがあったが、彼女は足をほんの少し止めるだけで意に介すことはなかった。
駅から五分ほど歩くと、ようやく彼女が足を止めた。目の前には小汚い小さなビルがあった。
「ここよ」
「ここって……」
目の前のビルは、明日俺たちのバンドが出演するライブハウスだった。俺はそのことを彼女に言った。
「今日もここでライブがあるのよ」
そんなはずはなかった。今日、ここのライブハウスは休みのはずだった。ブッキングするときに、スケジュールを確認したので間違いはない。
「誰が出るんだ?」俺は訊ねた。
「キッド・スターダストよ」
「バカにしてんのか?」
と俺は思わず怒鳴ってしまった。キッド・スターダストと言えば、バンドブームだったころのバンドで、いまはとっくに解散してしまっている。再結成したのだろうか、と思ったが、そんな話は聞いたことがない。
「あたしね、キッド・スターダストのおっかけをやってたのよ。だから、デビューする前から知ってるわ」
「あんた……いくつなんだ?」
「十七よ」
「ふざけるのも大概にしろ!」
我慢の限界だった。俺は左手で彼女の胸ぐらを掴み、その勢いでブロック塀に彼女の身体を押しつけ、右手で殴ろうとした。拳を振り上げた瞬間、彼女が膝で俺の股間を蹴り上げた。ひとたまりもない。道路に転げ、悶絶した。
「キッド・スターダストはね、このライブハウスから始まったのよ。友達のギグ……あ、いまはギグなんて言わないか。とにかく、そのライブを見に行ったときにたまたま出てね。それからあたしは追っかけるようになったの」
彼女はそう言うと悶える俺のそばにしゃがみ、腰をさすってきた。俺はその手を振り払って、無理無理立ち上がった。
「そこまで年増には見えないけどな」
「だから、あたしは十七歳なんだって」
「計算があわねえぞ」
「計算なんてくそくらえよ。餓死寸前の犬だって食べないわ」
ふん、と鼻を鳴らして、俺は煙草に火を点けた。
「お前は……」
「ノゾミ」
「は?」
「ノゾミって呼んで。あんたは?」
俺は素直に名前を言った。
「で、あんた、なに言おうとしたの?」
「名前で呼べよ。……まあ、いいや。いまは追っかけてないのか?」
「そう、ね。あたしはバンドがデビューするまでを見てるのが楽しいの」
「典型的なミーハーじゃねえか」
「せめてバンギャルって呼んでほしいわね」
「本当に十七なのか?」
ノゾミはクスッと笑った。あどけない笑顔だった。それを見ると十七歳と言われても納得ができる。しかし理屈があわない。思考が錯綜している俺をよそに、ノゾミはくるりと背を向けて、ライブハウスに入っていった。俺もそれに続く。激痛はようやく治まってきた。
ドアに鍵は掛かっておらず、簡単に中へ入ることができた。受け付けにスタッフの姿はなく、電気も点いていない。ノゾミは気にせずに通り過ぎていった。そのまま階段を降りると、少し開けたロビーがあった。ライブがあればここにフライヤーや物販があるはずだが、なにもなかった。薄暗くて、いやにシンとしている。俺は正面の重い防音扉を開け、ノゾミを中に入れてから自分も入った。中は照明が落とされていて、完全な闇だった。なにも見えない。しかし、相当蒸し暑く、前に出ようとするとなにかにぶつかり、結局扉のそばから動けなかった。
「よかった、間に合った」
ノゾミがそう呟くと、俺たちを待っていたかのようにエリック・クラプトンの「フォーエヴァー・マン」が流れ始めた。俺はそれに気がつくと、にわかに興奮した。この曲は俺も大好きな曲で、そのままバンドの名前にしたくらいだ。
照明が点き、舞台袖から三人の男が出てきた。俺と同い年くらいの男だった。その瞬間、いまいる場所の熱気が一気に上がった。周りを見ると、この場所が人でひしめき合っているのがわかった。みんな拳を突き上げ、ジャンプしたりなにかを叫んでいたりしている。ステージを見た瞬間、俺ははっと息を呑んだ。
間違いない、キッド・スターダストだった。しかも「現役」だったころの。いや、それよりは少し若い気がする。ドラムとギターとベースが一斉に鳴ると、会場の熱気はピークに達した。ドラムがカウントを刻み、ギターがイントロを弾き始める。俺も聴いたことのある、テレビでも話題になった有名な曲だ。シンプルなのに胸を打つものがあった。観客が一体となって波を作った。俺は右に左に揺れながら曲に入りこんでいった。
ヴォーカルがギターを掻き鳴らしながら叫びだす。それは俺の知っているキッド・スターダストではなかった。もっと泥臭くて、汗臭くて、なにより熱かった。デビューしてから音楽性が変わった、とか、そういうことではない。やっている音楽は変わってはいない。けれどなにかが決定的に違う。なにが違うのだろうと考えていたが、曲を聴いているうちにそういったことを考えるのが野暮な気がして、すぐに俺もほかの観客と一緒に夢中になっていた。
ふと、ノゾミのことが気になった。それとなく周りを見ると、観客の波の上に乗っかっている少女がいた。うまい具合に前列のほうへ流れていき、しっかりとヴォーカルの目の前にもぐり込んでいた。それがノゾミだった。
曲が進んでも、会場の熱気は衰えることがなかった。むしろさらに上がっていくのが目に見えるようだった。
ヴォーカルが「今日はどうもありがとう、またどこかで会いましょう。最後の曲です」と言って曲が始まった。メジャーデビューしたときのシングル曲だ。イントロが始まった瞬間に、咆哮にも似た歓声がこの小さな会場に轟いた。アップテンポで観客を煽りたてるような、勢いのある曲なのだが、どこか会場の空気は切なげだった。もう二度と会えないとわかっていながら、「じゃあ、また」と友達と別れるかのような、抗うことのできない大きなうねりにゆっくりと飲み込まれていくような、そんな空気だった。
それでも、まるでそれを拭い去ろうとするかのように、観客はさらに激しく彼らに応えていた。ノゾミは最前列で顔を手でおおっていた。波にもまれながらも注意深く彼女を見ていると、どうやら感極まって泣いているようだった。
と、ヴォーカルがマイクから離れ、がむしゃらにアウトロを弾き始めた。もうこのライブも終わる。それからは夢から醒めるように、あるいは悪夢の続きを見るように日常へ戻っていく。会場の全員がお別れの覚悟をきめようとしていると、ヴォーカルが叫び声をあげながら観客の波へ飛び込んだ。アンプからシールドが抜け、バリバリと嫌な音を立てた。観客はみんなでヴォーカルを受け止め、またステージへと帰した。ステージに戻ると「どうもありがとう」と叫び、それで曲が終わった。照明が落とされ、再び静寂と暗闇が世界を支配した。
しばらくそのままじっとしていたが、とくになにが起きるでもなく、時間が止まってしまっているかのようだった。ライブの余韻やついさっきまでの熱気などは、この空間のどこにもなかった。ライブなどというものは最初からやってなかったよ、とでも言うかのように、いやにシンと静まりかえっている。
ひとり興奮冷めやらぬまま、茫漠とした静けさのなか、俺はキッド・スターダストのことを考えていた。俺と同い年くらいのころにはもう、こんなライブをやっていたのか、と。感動するとともに少なからずショックを受けた。俺たちの明日のライブはどうなるのだろうか。明日……そうだ、帰らないと……そういえばノゾミは?
「ノゾミ!」
俺が叫んでも、その声は壁や天井に吸いこまれてしまうだけのように感じた。もう一度叫ぶ。返事はない。さらにもう一度。
「待って! いま行くから!」
ようやく届いた。それからなにも見えないなか待っていると、手首をぎゅっと掴まれた。
「お待たせ、行くわよ」
俺はノゾミに先導されて会場から出た。外はすっかり暗くなり、ぬるい夜風が俺たちの上気した身体をいくらか冷ましてくれた。俺はそばにあった自動販売機でミネラルウォーターを二本買い、一本をノゾミに渡してから一気に半分ほど飲んだ。それから煙草に火を点け、ライブハウスの入り口にしゃがみこんだ。ノゾミは「すごかったでしょ」と言い、俺の隣にしゃがんだ。
「あんなすごいライブやってたんだな」
俺もその場にしゃがみ、ノゾミを見た。「カッコよかったなあ」と、遠い目をして呟く彼女の横顔は、とても十七歳のそれとは思えないほど憂いをおびた、人生の酸いも甘いも知り尽くしたかのような表情だった。
こうしてしゃがんでいると、過ぎていく人たちの忙しなく動いている足がよく見える。みんな俺たちと違って忙しそうだ。いまの時間からして、きっと家に帰るところなのだろう。
「そんなに急いでどこへ行くってのよ」
横でノゾミがぼそりと言った。
「俺も帰るぞ」
「えっ、ちょっと待ってよ」
俺は立ち上がろうとした。と、ノゾミはまた俺のギターケースを引っ張ったので思い切りしりもちをついてしまった。鈍い痛みが尻から全身に響いた。
「痛ってえな、今度はなんなんだよ」
「あたし、帰るところないんだけど」
「知ったことか」
「ずいぶん冷たいじゃない? モテないわよ、そんなんじゃあ」
「別にお前にモテなくても構わない」
「あら、理想がお高いこと。だからモテないのよ」
「てめえっ」
俺が一歩詰めるよりも早く、ノゾミは俺の懐に飛び込んだ。その勢いに乗せて、俺のみぞおちにショートパンチを打ち込んできた。食いしばった歯の間から息が漏れ、その瞬間、呼吸ができなくなった。
「なっさけない……」
かがむようにして腹を押さえている俺を見ながら、ノゾミは腰に手を当てて、あきれたような声で言った。
さっきからやられっぱなしじゃないか? 本当に情けない。なるべく深く呼吸をするようにして、痛みを和らげようとしながら思った。
「……わかったよ、で、どこに行く?」
観念して俺がそう言うとノゾミはぱっと笑顔になり「お腹空いたわね」と言った。行くぞ、と言って俺が駅のほうへ向かって歩き出すと、ノゾミは腕を組んできた。振りほどこうとしてもしっかりと掴まれていてできなかったので、諦めてそのまま歩き出した。
どこにでもあるファミレスに入り、うまくもなければまずくもないメシを食べて、食後に一服していた。店はビルの二階にあり、窓からはいろいろな人が見えた。居酒屋の看板を持ってサンドウィッチマンをやっている人、それに呼び止められて仲間と一緒に店に入っていく人、無視をして去っていく人、顔を赤らめて上機嫌に歩いている人や、疲れきった顔の人、遠目からでもわかるくらいテンションの高い俺と同い年くらいの人。みんなそれぞれ目的を持ってこの街にいるようだった。それは仕事だったり遊びだったり、さまざまだ。
「なにを見てんのよ」ノゾミは微笑んでいた。「そんな寂しそうな目をしてさ」
「なんでもねえよ」俺はアイスコーヒーを一口飲んだ。
「明日、ライブなんでしょう? そんな顔しててどうすんのよ」
「うるせえな……」
俺はノゾミから目をそらして、また窓の外を見た。
「もう俺たちは安全なカードを全部切っちまったんだよ。あるいは捨てちまったんだよ。いまのままノホホンとやってるだけなら、どっかに勤めながらでもできるはずなんだ。それをしないってなら、腹ァくくらなきゃダメだろう?」
ふと、夕方にタツヤが言っていた言葉を思い出した。俺もハルも、あのときは適当に聞き流していたが、本当はタツヤの言うとおりだったと思う。でも、俺たちだって、適当にやっているわけではない。いつだって音楽に対しては真剣に取り組んでいる。たとえばそこの交差点でバカ笑いしている若い奴らとは違う。俺は、俺たちは、「フォーエヴァー・マン」としてプライドを持って生きている。しかし、とまた思考は錯綜する。さっきのキッド・スターダストのライブを見てもまだ、同じことが言えるだろうか。明らかに格が違った。言葉にできない抽象的なこと、ところだが、決定的だった。まるで比べものにならなかった。それでも俺は誇りを持てるのだろうか。
「おーい」
はっと前を向くと、ノゾミが俺の目の前で手を振っていた。
「どうしたの? ぼうっとしちゃって」
「なんでもねえよ」
「……バンドのこと?」
俺は返事をしなかった。
「そんな怖い顔してライブやったって、誰も楽しんでくれないわよ? 自分が楽しまないでどうやって他人を楽しませるのよ」
「お前にバンドのなにがわかるんだよ」
「だから、少なくともあんたよりはわかるわよ。いろんなバンドを見てきたからね。本当にいろいろよ。『ネイキッド・レディ』って知ってる? キッド・スターダストより少し先にデビューしたんだけど、あたし、まだ無名のころ、あのバンドのマネージャーとまではいかないけど、お手伝いをしてたのよ」
「楽屋女か」
「まあ、呼び方はなんでもいいわ。あんたのバンド、そういう女の子、いる?」
俺は黙って首を横に振った。
「なっさけないわねえ、そんなんじゃダメよ。バンドには必要よ、楽屋でジョイントを巻いてくれるような女の子が」
俺はなにも言わなかった。確かにそういう人が必要なのかもしれない。あるいは必要なんてないのかもしれない。どちらにせよ、いまの俺にとってはどうでもよかった。
「余裕ないわねえ」ため息まじりにノゾミが言った。手には伝票を持っている。「ほら、行くわよ」
別会計で支払いを済ませて外に出た。夜も深くなり、人はまばらで店も終わっているところが増えた。それでも蒸し暑く、早く帰ってシャワーを浴びたかった。
「元気がないわねえ」
俺を覗き込むようにして、ノゾミが言った。
「しょうがない、あたしが気合いを入れてあげるわ」
と言うとノゾミはスタスタと歩き出した。俺は言ってもしかたないと思い、おとなしく付いていくことにした。
駅のそばの高架下をくぐり反対口へ出る。路地に入って線路沿いにある、雑居ビルにしてはきらびやかな印象のビルの前でノゾミは立ち止まった。
「まさか、ここに入るのか?」ビルの看板を見て俺は言った。
「ほかに行くとこなんてないでしょう?」
ノゾミは中に入ろうとしたが、二の足を踏んでいる俺に気がつくと立ち止まって、こちらを見た。
「あれ? もしかして、こういうとこ初めて?」
言葉に詰まる俺を見ると、ノゾミはにっこりと笑って俺の手首を掴み、ロビーへ入っていった。
「ねえ、しないの?」
ノゾミの声を背中で聞いたが、俺は返事をしなかった。
「ずいぶんと意気地がないのね」
俺は目を瞑って、眠りが訪れるのを待っていた。
「あら、寝ちゃったのかしら。ちょっと傷つくかも」
疲れているはずなのに、眠れる気がしなかった。
ノゾミに引っ張られるがままに、俺はラブホテルに入った。そこはビジネスホテルに毛が生えた程度のみすぼらしいところだった。よっぽど発情していなければ、こんなところを選ばないだろうといった感じで、よく聞くジャグジーやカラオケ、マッサージチェアといった、気の利いたものは一切なかった。あるのはベッドとティッシュとコンドームくらいだった。
部屋に入ると、俺たちは順番にシャワーを浴び、ペラペラのバスローブに着替えてベッドにもぐった。テレビを見ようとしたが、百円取られるのでやめた。
「なあ」
俺は背を向けて目を瞑ったままノゾミに声をかけた。
「なあに?」
「こんなことしてていいのか?」
「なにが?」
「知りもしない男とホテルに入って」
「でもしないんでしょ?」
「そういうことじゃなくて……なんで俺に声をかけたんだ? バンドやってる奴ならほかにもいただろ。特にこのへんなら」
「なんて言うのかなあ」しばらくノゾミは考えているようだった。「嗅覚ってやつ?」
「はあ?」
「バンギャの嗅覚よ。あんたみたいなバンドマンが好きなのよね」
俺は言葉が出なかった。
「あ、勘違いしないでよ。別に彼女になりたい、とかそういうことじゃなくてね」
「じゃあ、ここにいるのはおかしいだろ」
「ううん、それはちょっと違うかな」
「なにが?」
「そのうちわかるわよ。でね、あんたみたいなバンドマンはね、見ていて面白いのよ。素直で、真っ直ぐで、熱くて。それでいてシャイで、不器用で。斜に構えてクールを気取っているようでも、わかるのよ」
俺は黙って聞いていた。ノゾミはううん、と小さく咳払いをしてから続けた。
「もともとロックって不良の音楽でしょう? というよりは社会に馴染めない人の、っていうか。だからロックをやる人っていうのはそれしか持っていないのよ。勉強も努力もできないし、友達も多くないから、この社会ではちょっと、ね。でも、だからこそ、音楽、ロックに対しては真剣でがむしゃらなのよ」
俺は聞いていて、自分の身体が熱くなるのを感じた。
「最近はまた違ったスタイルのロックができてきたから、一概にそうとは言えないけどね。いまは確かに洗練されてはいるけど、それだけ。面白くない。あたしに言わせればすれてるだけのようにしか見えないわ。でもというか、だからこそ、いまの時代に久しぶりだったのよ、あんたみたいなのが」
「俺みたいなのが?」
「そう。昔のままというか、バカでダサくて……ふふっ」
「なんだよ」
「なんでもないわ。それよりも明日はライブでしょう?」
「うん。だからもう寝るぞ」
「うん。あ、ねえ、あとひとつだけいい?」
「なんだよ」
「あんたのバンド、なんて言うの?」
「『フォーエヴァー・マン』」
「クラプトン?」
「そう」
「いい名前ね」
「寝ろ」
「うん」
昼前にホテルを出て、近くにあったカフェチェーン店に入り、そこのサンドウィッチとコーヒーで遅い朝食を済ませた。店を出ると太陽が容赦なく俺たちを照りつけてきた。空を見ると雲がひとつも見当たらなかった。
「これからどうするの?」ノゾミが訊ねてきた。「リハは午後からでしょう?」
「十一時からスタジオがあるから、それに行くよ」
「ふうん」
「ノゾミはどうすんだ? あ、そうだ、ライブ来るか?」
「ううん。せっかくだけど遠慮しておくわ。見なくてもだいたいわかるし」
「百聞は一見にしかず」
「経験則のほうがあてになるわ」
「でも帰る場所ないんだろ?」
「行く場所ならいくらでもあるわよ」
「まあ、いいや。気が向いたら来てくれよ」
「そう、ね。あんた、がんばりなさいよ。じゃあね」
俺の言葉を待たずに、ノゾミはくるりと背を向けて歩き出した。俺はぼうっとその背中を見つめていた。やがて見えなくなると、俺は反対方向に歩いた。いままでの話をMCでしてみようか、いや、誰も信じてはくれないだろう。それに、口にしたらすべてが溶けて消えてしまいそうな気がした。
そうだ、と俺は思いついた。ノゾミの曲を書こう、と。
スタジオのある駅、ノゾミと出会った場所でもある駅へ向かう電車の中で、俺は頭に浮かぶメロディを必死に記憶していた。曲名は決まっている。
「ジョイントを巻く女」だ。いつかどこかで、ノゾミにもこの曲が届けばいいけど、などと思いつつ構想を練っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
