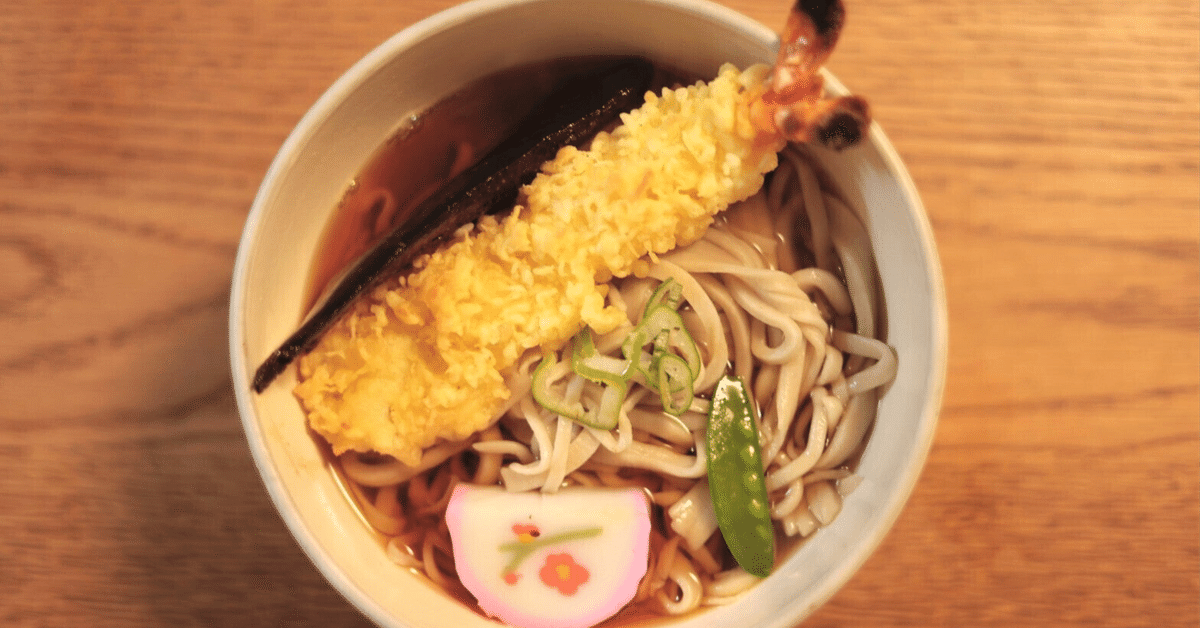
#2022年のわたしと仕事
このテーマについて、2022年1月から12月までのgoogleカレンダーを振り返ってみよう。
・サービス管理責任者基礎研修 ファシリテーター
これはなかなかしんどい研修。講師側にとっても。1日コースでzoomでずっとファシリテートし続けるのはしんどい。
とはいえ、自分の学びにはなるし、就労移行や児童発達のサービス管理責任者になるであろう人材の皆さんへ、就労の視点、発達障害者支援の視点を直接伝えられる場を得られた事は喜びです。
・施設長の他施設見学のアテンド
うちの法人施設の長はなかなか施設見学に行く機会が無く、それをアテンドできたのは良かった。何よりも自分の学びになった。
・東京都のなかぽつ研修に参加
これは貴重な経験。通常は参加できないであろう研修に参加できた。
・就労移行が集まる任意団体の活動
ちょっと盛り下がってきている団体ですが、その中でも意欲のある支援者たちと協働できたのは成果。
就労移行1施設単体ではできない事が、複数の就労移行が集まる事で実現できる事、発信できる事があるって事を再確認した。
思えば、関西の障害者就業・生活支援センターと情報交換をしたり、この任意団体は何者なんだろうか?どこに向かっていくんだろうか?
・就業サポート研究会で大妻の小川浩先生、超短時間雇用実践企業の方との登壇。
これはオープンではない研究会であるけれど、口コミで広がっています。その会で就労支援のプロとしての立場で登壇。実質は小川先生や長短時間雇用実践企業の皆さんに「質問する役」で、役得です。今後の「ジョブコーチが向かう先」を垣間見た会でした。
・埼玉県中小企業家同友会 障害者雇用推進委員会のオブザーバー参加
なかなか発言力が高まりませんが、広い視点で物を言える就労支援の専門家として参加。良い取り組みになっていけばいいなぁ。
・就労移行、自立訓練、B型の見学
今年も色んな施設の見学ができました。様々な施設の良いところ、微妙なところを知れば、自分のいる施設に還元できると信じています。
親切施設などから「ご挨拶を」と連絡をいただくことが結構ありますが、基本的にはお断りしていて、逆に訪問見学をしながらご挨拶をする事を逆提案しています。うちに挨拶に来てもらっても、事務所と片付いていない僕のデスク周りを見てもらうだけですからね。
・テレワークに関するセミナーの参加
新型コロナ以降、テレワークが革命的に進んだと思います。それは障害者の「働く」にも変化を与えています。そして今や「在宅就労を目指す、在宅就労訓練」の本格化がスタートしています。今後の就労移行の利用者確保はここを通らずして進まないと思いますし、障害のある人にとっては訓練と就労の幅が広がり、複雑さも増したかも知れません。
・自立支援協議会 相談支援部会 精神チームと就労チームに参加
ほとんど貢献できてませんが、地域の課題や精神障害者、就労希望者の置かれている状況や課題を知ることができました。知って、考え、行動に移すのは来年でしょうか。
・神奈川県中小企業家同友会 ダイバーシティ委員会例会に参加
超短時間雇用について、東大先端研の近藤先生の活動の進捗を知る。
割と早い段階からこの「長短時間雇用」「20時間未満の働き方」については注目していて、川崎市を訪問視察した年もありました。そしていよいよ法定雇用率に入っていく事となり、この先見の明というかアドバンテージを活かせる埼玉県であって欲しいです。
・埼玉県発達障害者支援地域協議会に委員として参加
県内の発達障害児・者の置かれている現状を知る。就労分野からの意見を述べる。これは素人の立場からの意見や質問をするばかりになりました。とはいえ、就労支援というフィルターを通した「発達障害者支援」についての発信が自分の役割と思って、それを織り込みながらのコメントを心がけました。
自分が自閉症支援・発達障害者支援を20年やれてきた恩返しをできた瞬間のひとつと思っています。
・京都中小企業家同友会ソーシャルインクルージョン委員会の例会に参加
CoCoネットの地域連携の形を知る。なぜかテレビ出演してしまう。
この京都市で展開している取り組みは今後も注目したいです。企業が主体的に動いているという点で新しいと思いますし、障害者雇用が企業の取り組む事であるという現れでもあります。
そして、当日はテレビ取材が入っている事は知っていましたが、まさかの僕の発言シーンが公開されてしまい、嬉しかったです。
・障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修の1コマで講師をする。
これは3年目になりました。今年でお役御免かな?地域連携、ネットワークについて自分の活動している「地域が素晴らしい」って話をしました。
今後、日本の障害者就労支援の中で活躍していく新任の就業支援担当者の皆さんへ、僭越ながら語らせていただき、グループワークの巡回などを務めました。僕よりもむしろ経験豊富な方が新規に着任されるケースも多く、そこから講師が学べてしまう美味しい研修です。ここでの名刺交換が、関西の障害者就業・生活支援センターと関東の就労移行の任意団体の情報交換会開催に繋がるとは・・・。
・グループホーム+B型立ち上げの相談を受ける
なぜか一緒に施設運営、施設経営の姿勢について学ぶ。
地域で就労支援で関わっている法人さんの依頼により。素晴らしい経営をされている理事長に会いに行き、経営のポイントや考え方を語っていただいた場に同席し、僕も学べました。
・厚生労働省の偉い方をお招きしての情報交換の場を作るきっかけになる。
とにかく色んな人と話をして、色んな事を知りたい好奇心が先走り、後先考えずに情報交換会を取り付けてしまう。
後悔先に立たず。言ってみてから事の重大さに気づきますが、後の祭り。それでもこの先走りを止められないのは好奇心と謎の行動力の結果、得るものが大きいからだと思いたい。
・某特例子会社のマネージャーに突撃し、就労移行訪問や特別支援学校分校の見学をアテンドしてしまう。
これは好奇心×好奇心の結果ではなかろうか?マネージャーも個性的な興味深い方だった。
・基幹相談支援センター、就労移行の任意団体、なかぽつ、自立支援協議会相談支援部会の4つの立場が集まる情報交換会を設置
初めは、相談支援専門員さんと話がしたいという動機から始まるが、なぜか話が大きくなって会議体となった。自分の後先考えない行動がみんなの学びに繋がっているのは、結果オーライ。
・県難病相談支援センターとの意見交換
これも好奇心から始まった事ではありますが、相談者さんへの実益もあった良い事例。
難病のある人たちの就労支援分野は可能性の広がりを強く感じています。雇用率に入ってくるかは今後の議論次第、世の中の動向次第ではありますが、現状でもできる支援はまだまだありますから、障害者の就労支援分野で培ったノウハウをどんどん導入していけると良いと思います。
・障害者職業センターとのコラボ研修。
これは地域の支援機関と職業センターのコラボ研修。自分たち主導ではない事の良い面と悪い面を再認識しました。
一番面白かったシーンは、参加者とのグループワーク。即席事例検討や情報共有、他機関(医療)への質問など、それぞれに持ち帰ってもらえたことがあったと確信しています。
・障害者雇用代行ビジネスについての情報収集と検討。
これはこのテーマだけでも複数回の投稿ができる内容。
これまでも県全体の支援機関の会議などでの地域連携の中で関わっている就労支援機関の皆さんの中で「雇用代行ビジネスってどうよ?」というアンケートを実施したところでさらに興味関心が深まりました。
是か否か?善か悪か?感情を交えた議論はある程度されてきたと思っているので、自分は様々な角度から見て、色んな立場の人たちから話を聞きたいと思っています。立場が変われば回答も変わるはず。
国からはある程度の「問題あり」のメッセージが付帯決議を通して出てきた訳ですが、そんなのわかっていた事。この先の近い未来をどのように改善していくかを考える必要があります。まずは知り、そこから考えましょう。
・県の障害者支援関連の課長を施設見学でアテンド
お忙しい課長も地域の支援機関を見て回りたいという発信に、御用聞きセンターとして真っ先に手を挙げました。ここは県内で一番の若輩者が担う役割と自認しています。
とはいえ、これは学びのチャンスでもあります。県の偉い方と同じ物を見て、意見や考えのどこが一致でどこに差異があるのか?を知れる数少ないチャンスです。
・関西の障害者就業・生活支援センター新旧センター長や地域の重鎮との意見交換会開催
先に書いた幕張での研修から関西との情報交換に発展した先にできた会。
雇用代行ビジネスについての東西の違い、支援者の戸惑い、容認できない感情的な面、様々な意見交換ができました。
答えは出ない。地域によって、立場によって、回答は変わる上に正解らしき状態もいくつもあるのかも知れません。
その他、研修参加や情報発信、意見交換会など書ききれない活動をできた1年でした。
今年度はセンター12年目でした。僕がこの地域で連携を広げ始めてから12年が終わります。
来年は13年目に入る年度です。
どんな一年になるのやら?そしてどんな一年にして行こうか。
1年の抱負は1年間覚えていられないので考えませんが、好奇心と思いつきと短絡的な後先考えない行動を心がけて、みなさんと走って行けたらその先に見える景色や絶景になっているでしょう。
僕は元々、考えすぎる傾向を上司から何度となく叱られてきました。考えてから走るんじゃない、考えながら走りなさい、と。
その結果、深く考えずに自分の本能のままに走る、になってしまったのはなぜだろうか。(考えていないわけではなく、考えて一周回って、考えが飛んでいってしまっているようにも思いますが)
つまり、自分ひとりではここまで走って来られなかったという事だけが事実です。これからも色んな立場の皆さんと一緒に走って行けたら嬉しいです。
ということで、僕の2022年の仕事はこれにて終幕です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
