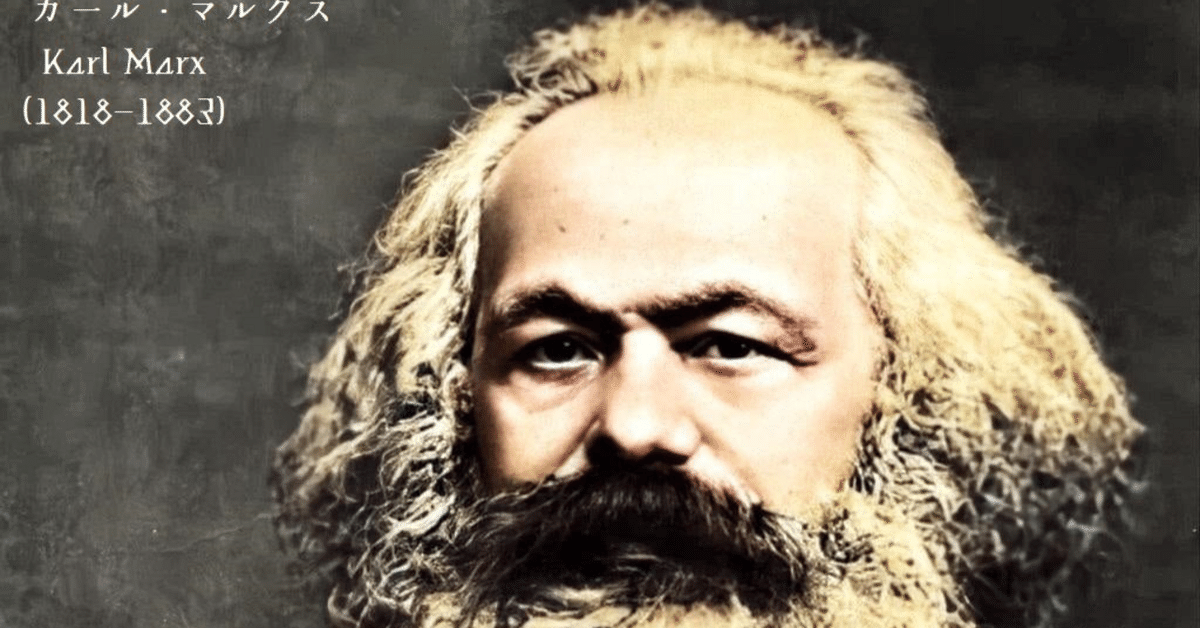
量的な働きあって質的な労働があり得る
「働きと実質の労働の違いと区分」
最初に何があって、何がその実質の労働となるのか、それは気になるところである。
なぜなら、これは、量と質の関係にあり、全体と部分を含む話になるからである。
対になるものを探しあてることができれば、幸である。
「量的である働きが、質的な労働を生みだす」
最初に何があって、それによって、次の労働が決めるような存在を「量的である働き」とここでは呼ぶことになる。
それがあっての「質的な労働」であるような量と質の関係に持ち込もうというわけだ。
次のような例がある。
「量的である働き A群」
ーーーー内的動機/内的報酬ーーーー
⑴無酸素運動
⑵詰将棋
⑶puzzle &クイズ
⑷書くこと
⑸昼食
⑹GTS
⑺立式
⑻音読
⑼思考
これに対応して・・・
「質的な労働 B群」
ーーーー外的動機/外的報酬ーーーー
①有酸素運動
②将棋
③解くこと
④読むこと
⑤夕食
⑥実際のドライブ
⑦解くこと
⑧読むこと/話すこと
⑨プログラミング
「A群の量的な働きあってのB群の質的な労働が可能である理由」
どのような労働にも、それにまつわる働きや環境づくり、イメージングタイムが必ず、必要である。
マラソンランナーが大会本番に出るためには、日々練習に明け暮れるように、量的な働きあっての質的な労働でなければいけない。
まさにここにあげた、1人でできるA群という日々の練習、体力づくりに対して、B群が本番であるような場合がそれである。
これは、B群あってのと、直接的にそれを求める場合、それは、大会本番に何もせず出るようなものである。
ここでは、必ず次のようなものが必要になる。
「A群の主な量的な働きの目的」
a;体力づくり/練習
b;事前の準備/イメージングタイム
c;環境づくり/体調管理
d;全体から部分へと澱みなく流れている
e;全体を視野に入れた部分的な目算/計算/概算
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
