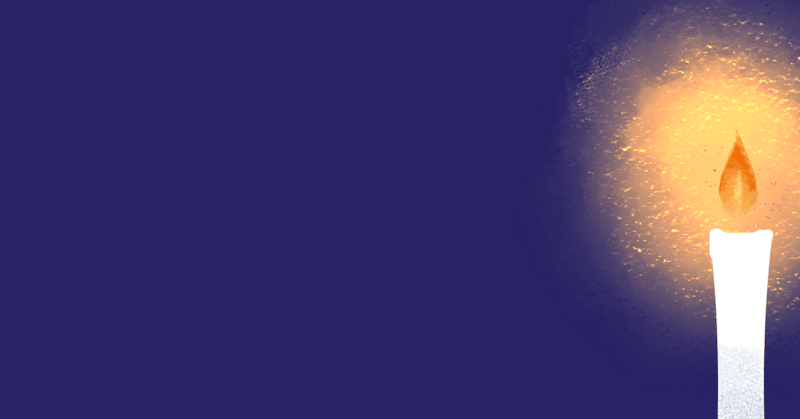
そこまでやる必要はないけれど
お茶の先生は、地域のお茶ネットワークでも一目置かれる、強く、気高く、それでいて情け深い昭和の女。
そんな先生も齢80歳に近づいているけれど、相変わらず、強い。
そんな先生のお宅で夜咄の儀。
半ば強制的に参加させられた、なんて意識の低い姿勢の私。
社会生活ではもはや使うことのないようなくどい挨拶表現に、自分をころして「相手をおもんばかる」を大義名分とした圧力。
お茶会の世界は日本社会の保守的な側面をギュッと詰め込んだような世界のようで、時々とても窮屈に感じることがある。
みんなお酒を飲まないのに、ノンアルの酎ハイで盃を酌み交わす。
「こういう時、なんていうんだっけ」
「もう覚えてないわ〜」
「えっと、『お流れを』じゃない?」
「それそれ!」
先生が懐石料理の準備でいないとき、亭主、客の役割を分担する社中は日常会話の日本語で助け合う。
茶事のマナーを身につけたところで、日常の何に役立つのだろうか。
他にもやるべきことがいっぱいあるんですけど。
嘆いたところできっと、その答えは言語化できるものではない。
身につけた、というより身についた先にいたるのはきっと、幽玄の地、ではないか。
その地はその道を信じて進んだ人だけが悟るような境地で、ただ茶事の表現が使えるようになったり、どんな点前ができるようになることで、もしくはまた、他人から評価されたりすることで到達できるようなものではない。
経験して、感じて、考える。
美しいことばかりではないこの世の中に、美を見出すことができる境地。
ただそれだけだ。
と、日本蝋燭の火の揺れに映える茶花のかげを見て思った。

「今日も絶好調と思ってやるしかないのよ」
茶事の後の椀物のお片付けで、先生からポロリとこぼれたお言葉。
「洗い物の手伝いにきたよ」
22時近く、先生の知人がやってきた。
先生と同年代で、何かと苦労をしていそうな芸術家。先生によくいじられているけれど、結構すごい人。
「あんた、遅い!何してたのよ」
「ごめんごめん、先生だって、なんで電話に出てくれないの」
「私は社中の指導で忙しいのよ!」
私たちの出来が悪く、ごめんなさい。
文句を言っている場合ではない、作家さんをこき使うほどの怖さはさておき、先生の目線まで、お茶の世界でもっと別の世界が見られるようになりたい。
この感覚を、妖艶な蝋燭の光を、釜の中から湧き上がる湯気がもたらす温かみをいつまでも心の中に留めておきたいのだけれど、気づけばまた、煩悩に苛まれる日常に戻ってしまうのだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
