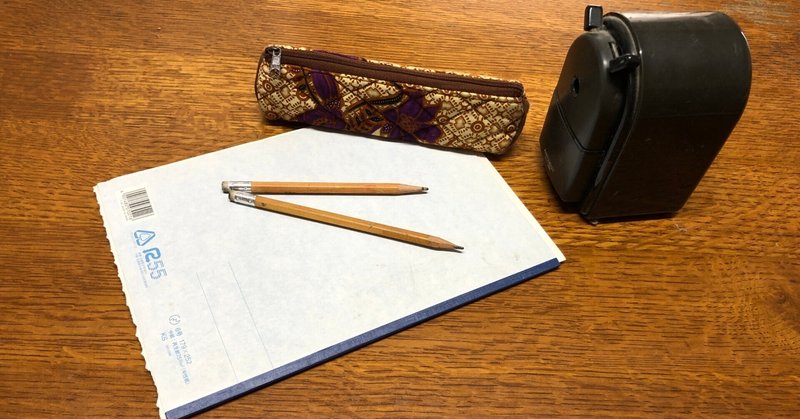
小説の基礎講座を受けた 取材について心に残る話が聞けた
前途多難
先日、ずっと聞いてみたかった人の講演があったので聞いてきた。
小説の基礎講座という題であった。
私も小説をほんのり書く。(ほんのり?)
今は母の戦争体験を書き終えたところだ。
講演で心に残ったことを1点だけ書く。
強く心に残ったので1点だ。
それは取材について。
講師の先生は小説を書く時(小説にもよるだろうが、今回取り上げた小説の時は)、膨大な資料を読んだそうだ。関係者にインタビューもした。
作品の裏にあるその努力は読者には見えない。
たまたまこうして知ることができてよかった。
先生は、必要な事実や事情をよく知らないまま書くのは良くないと言われる。
当たり前のようだが自分の知らない時代を書く場合、往々にしてあやふやなままここに書いてあるからいいやと書いてしまうことがある。
私はそうだったので、本当に大反省である。
また、知らないことを書くときは3冊以上読んで裏付けを取ると言われた。
参考資料が手記やインタビューなどの時だろうが、その人の記憶だけに頼ってはいけないということだろう。
例えば「ぬかるみを歩いた」と手記にあったとする。またはインタビューで答えたのかもしれない。それだけのことでも、その時期その地域に雨が降ったのかできる限り調べるらしい。
それだけの努力を自分はしたことがあっただろうか。
そして1番肝心なことだが、そうして調べた資料を自分の中で再構成してイメージを作り、そのイメージをもとに小説を書く、ということだ。
これが私には難しかった。
自分の小説のことだが、私は戦時中のことが分からない。
資料を調べても調べてもイメージがわかない。それで手記などをつなげて作品を作ってしまった。
あとから読み返して不本意なものになったのは言うまでもない。
しかしどうにもならなかったのだ。
イメージわくくらいまでもっと調べなければいけなかったのか。
調べていけばイメージがわくようになるのだろうか。
難しいなあと思っている。
今、母の小説は1960年の安保闘争のころを迎えている。
相変わらずイメージがわかず、七転八倒している。
もうやめようかなとも思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
