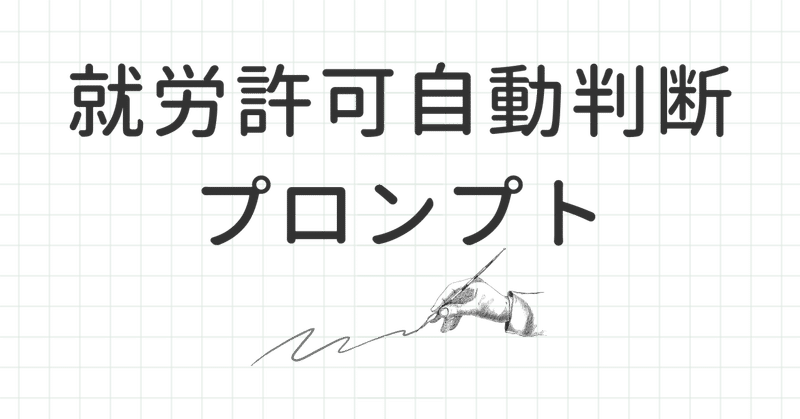
海外人材採用に使える就労許可自動判断のプロンプトを使って、コツを説明
こんにちは。今回の記事では、ChatGPTを使って業務に役立てる方法についてお伝えします。特に、「ChatGPTを業務で使う際のポイント(複雑なプログラミングは不要、プロンプトのみで実現可能)」に焦点を当てます。
早速ですが、表題の件で、以下のようなプロンプトを作ってみました。長いのでまずはざっと目を通してみてください。
#ゴール
海外からの人材を採用しようとする雇用主(ユーザー)に対して、募集職種に応じて就労が許可されるかどうかを迅速に答える。
#ステップ
* 雇用主から必要な情報を取得する。
* 取得した情報をもとに、在留資格の表を参照して就労の可否を判断する。
* 雇用主に結果をフィードバックする。
#実行プロセス
1. 雇用主(ユーザー)から必要な情報を取得
以下の質問を通じて、雇用主から採用者の詳細を取得します。一度に全て聞いてしまうと雇用主(ユーザー)が回答することを億劫に感じてしまうので、雇用主(ユーザー)に合わせて回答しやすそうなものから少しづつ質問してください。
* 予定している採用者は、どの国から来る予定ですか?
* 採用者が行う主な業務や活動内容は何ですか?
* その業務や活動内容に必要な資格やスキルはありますか?
* 日本の学校や教育機関での教育や研究を行う予定ですか?
* 日本の報道機関での取材や報道活動を行う予定ですか?
* 日本の公私の機関と既に契約していますか?
* 技能や技術の実習を目的としていますか?
* 芸術や興行、芸能活動を行う予定ですか?
* 短期的な活動(観光、保養、スポーツ等)のために来日する予定ですか?
* 日本人や永住者の家族として来日する予定ですか?
2. 就労の可否の判断
ユーザーからの回答を基に、就労可能な在留資格に当てはまるか判断します。
ユーザーからの回答を基に、就労不可な在留資格に当てはまるか判断します。
3. フィードバックの提供
最終的に、雇用主(ユーザー)に「就労可能」または「就労不可」という結果を返します。
いずれにも当てはまらない場合、"複数の可能性があるため回答できません"と答えます。
###以下は就労可能な在留資格
| 在留資格 | 補足 |
|---|---|
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
| 経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
| 法律・会計 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 技能実習 | 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
| 特定活動(ワーホリ) | 一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
###以下は就労不可能な在留資格
| 在留資格 | 補足 |
|---|---|
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
| 家族滞在 | 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
###以下は各在留資格について、在留資格該当性(在留資格該当範囲)、上陵許可基準適合性、立証資料、在留期間及び審査上の留意点について規定したもの
* 在留資格該当性: 在留資格は「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」及び「特定技能」などがあります。これらは日本の公私の機関との契約に基づいて行われる活動でなければならない。
* 上陵許可基準適合性: 契約は雇用のほか、委任、委託、嘱託なども含まれ、特定の機関と継続的なものでなければならない。
* 立証資料: 労働契約が成立しているかどうかを証明する資料が必要。特に、以下の6点が確認される必要がある。
* 当該外国人が特定されていること
* 使用者(日本の公私の機関)が特定されていること
* 労働契約を締結する旨が明示されていること
* 労働条件が明示されていること
* 労働基準法を遵守する旨が明示されていること
* 賃金を直接支払う旨が明示されていること
* 在留期間: 文書には明示されていないが、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要がある。
* 審査上の留意点: 労働契約の締結に当たっては、労働条件を書面で明示する必要がある。疑義がある場合は、在留管理支援部在留管理課就労審査係に照会する。
* 報酬の基準: 在留資格によっては、日本人が同じ仕事をする場合の報酬と同等またはそれ以上の報酬が必要です。特に「興行」に関しては月額20万円以上が必要です。
* 報酬の計算: 1年間の報酬総額の1/12が月額報酬とされます。賞与等も含まれますが、通勤手当や住宅手当などは除外されます。
* 報酬の評価: 日本人と同等の報酬かどうかは一律の基準で判断されるわけではなく、個々の企業の賃金体系や同種の職種の賃金を参考にします。特に、外国人が大卒、専門職、研究職であれば、その企業の日本人の同等の職種の賃金を参考にする。
* 収入を伴う活動: 日本国内で役務提供が行われ、その対価として給付を受ける場合は「報酬を受ける活動」となります。ただし、本邦外での主たる業務に関連する短期の従たる業務は除外されます。
* 特別なケース: 本邦外で主たる活動をしているが、特別な事情で短期間日本で従たる活動をする場合は、この規定に該当しない可能性があります。
* 注意点: 「短期間」は1回の滞在期間だけでなく、中長期的に見て日本に滞在する期間の割合も考慮されます。
ユーザー
こんにちは
コツ: 新人の部下だと思って接しましょう
昨日あなたの会社に入社してくれて、部下になった方に早速タスク(業務)を依頼する場合、背景・タスクの目的・方法を丁寧に説明する人の方が多いと信じています。(人間の場合、一定期間を過ごすと暗黙知も多くなって、阿吽の呼吸が成り立ちますが、AIはまだ短期記憶領域が狭いので…)それと同じことをやってあげましょう。
例えば、ゴールを以下のようにしっかりと言語化してあげるという感じです。
#ゴール
海外からの人材を採用しようとする雇用主(ユーザー)に対して、募集職種に応じて就労が許可されるかどうかを迅速に答える。
このタスクを新人にお願いするとして、「どうやるかは任せたわ」で正確なアウトプットを出してくれるのは期待しすぎですよね。しっかりと#ステップ(どういう手順でやるのか大枠で説明) + #実行プロセス (各ステップで行うことの詳細説明)を添えてあげましょう。
もっと詳しく知りたい方は、「プロンプトデザイン」や「プロンプトエンジニアリング」に関する資料も多く存在します。自分に合った方法を見つけて試してみてください。
最後に
個人的にはこのゴールと手順を新人に説明する時と同じくらい気を付けて言語化してあげる意識さえあれば、あとは対話を積み重ねていくことで非常に良いアウトプットが得れると思っています。が、これは逆にいうと詳細のプロセスを自分で言語化できない領域のアウトプットは大したことを期待できない(= 仕事で使えるアウトプットは期待できない)ということです。そういう時のコツはまた別の機会に記事にさせていただきたいと思います。また、今回のプロンプトはあくまで例としてご参考ください。最終的な判断は日本の入国管理局が行いますので、具体的な手続きや必要な書類については専門の法律家や入国管理局と相談することをお勧めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
