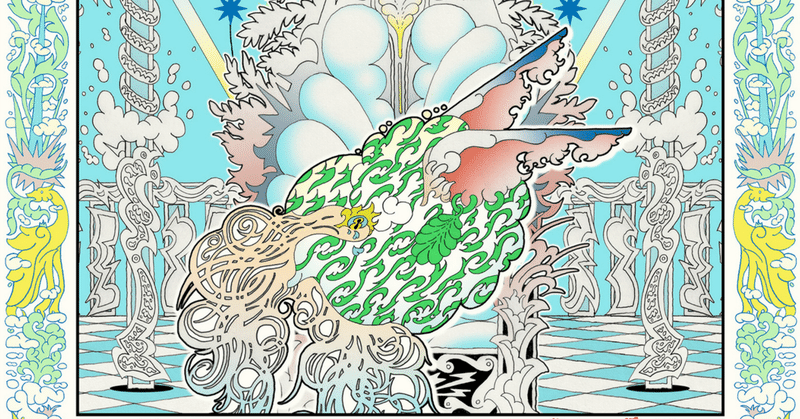
SEKAINOOWARI 「Nautirus」ディスクレビュー
「最も個人的なことが、最もクリエイティブである」とマーティン・スコセッシは残しているが、セカオワとはまさにそんな感じ。「Tree」以降、"音楽的になり過ぎてしまった"と内省する「Eye」「Lip」を通過し、"胃液のような歌"と表現する"Like a scent"が先陣を切る「scent of memory」、そして本作「Nautirus」に至るまでパーソナルな濃度はより濃くなっているように感じる。Fukaseは作りたい曲しか作れなくなった旨の発言をしており、それは当人の体調に起因すると推察できることは酷だが、極く真っ当に誠実な音楽作りとも言える。尤もセカオワはデビュー当時からそういうバンドであると再認識させるアルバムでもあるのだ。
それらが所以か、限り無くベタな曲が多いのも本作の特徴だ(良いかどうかは別として)。「Diary」「最高到達点」「タイムマシン」は正にそう。FukaseにおいてもSaoriにおいても無理やりに歌詞をこねくり回さなくなったというのは非常に興味深い。そしてレコード大賞の受賞はあからさまにタイアップを急増させ、本作を「Tree」以来のベスト盤のようなアルバムとしている(とはいえ彼等がアルバムとしての置き場所にそれほど興味がないということもあるのだが)。それだけではなくオケに対する力の入れ方も間違い無く「Tree」以来だ。総じて一音一音に対してロジカルに丁寧に制作をしているのが伝わってくる。故に想像以上にベタな曲でもテクニカルな部分を感じさせずにスッと馴染む。まさにJ-popアーティストという言葉が似合うバンドになってきている。
ここで曲順にも言及しておこう。5曲目「深海魚」以降、Fukase、Saoriの作詞が交互に続く。本アルバムの精神性を担う「深海魚」「ユートピア」、「Diary」を挟んで、バンドサウンドのみで構成される「ターコイズ」「バタフライエフェクト」、ギターの歪みが印象的な「Eve」「ROBO」、そして「サラバ」と。因みにSaori単独作詞曲でアルバムの最後に来たことは未だかつて無い。Fukaseは三人で作詞作曲に取り組む体制の重要性を口にしている。元来ボーカルだけがフロントマンとして注目を浴びることに懐疑的な考えを持っているが、それだけではなくバンドとして共助の意識への芽生えをここに強く感じさせられる。メンバーの関係性といえば陳腐だが、その体制が多種多様な音楽性に功を奏していることは言うまでもない。
Fukaseは「タイムマシン」「デッドエンド」「ユートピア」で時の不可逆性について言及している。本アルバムで自身の作詞曲の内8分の3。「不死鳥」「Missing」などでも勿論そのような表現はあるが、ここまで連続しているのはきっと偶然ではないだろう。Fukaseは"書きたいときに書きたいものを書く"私小説的な作家で、そういう生き方しかできない人間なのである。
「Terminal」羽田公演を観た身から推察するに、「Nautirus」は絶望の先を見据えたアルバムなのだろう。アルバムの最後を飾る「サラバ」という曲に好きな一節がある。
両手いっぱいの花束みたいに
幸せだって受け取っていいと
恐れることは何もないんだと
ふと思っていた 君の隣で
ふと思っていた、に留まっている点が良い。この表現は「family」という曲にも通ずる。
「ただいま」っていう声が
聴こえたその瞬間に
気が抜けて語尾を伸ばした
「おかえり」って言いたい
当たり前に言いたい
声には出せず、行動に移せなくても孤独な心の中に確かな変化が生じている。それらを不器用でも一つずつ表出していく。そんな作業がセカオワの音楽作りであると改めて明示している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
