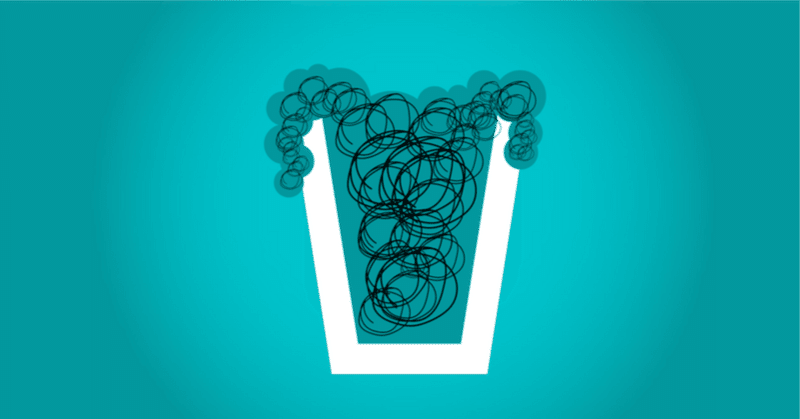
【短編小説】無知なものたち
アイスコーヒーの氷が、ゆっくりと崩れた。
友人は少し大げさにため息をついて、「ほんとAI絵師ってクソだ」と言った。
僕たちはファミレスの隅っこの席で、ドリンクバーを利用して長居していた。僕はこういうのが苦手だ。ドリンクバーだけで五時間も六時間も居座る神経がないからだ。だから僕はポテトやデザートを追加注文していた。こういう点、友人は図太いので何も気にしないでここに居座っている。
僕はアイスティーを飲みながら、友人の言葉をかみしめる。
確かに、最近SNSが騒がしい。
AI技術によるイラスト生成には、新たな技術として様々な期待が寄せられた。事故で腕を失ったイラストレーターが自分の絵をAIに学習させ、創作活動の手助けに活用している事例は多くの人々を感動させた。しかし世間ではそのような使われ方はしていない。「自分の絵が他人の手によってAIの学習元にされ、自分の絵柄をパクられる」事例に多くの絵描きが声を上げた。僕は絵を描かないが、物書きのはしくれとして彼らの不安は分かる。実際、絵描きのフォロワーが「イラスト生成AI ここがよくないよ」とまとめた四枚の画像を投稿しバズっていた。
一方、AI絵師――この呼称についても様々言われているが、現状最も浸透している言葉なので、僕は彼らをAI絵師と呼んでいる――たちも黙っちゃいなかった。
「絵が描けない人たちがAI技術のおかげで希望を持てるようになったんです」
「絵かきだけが絵を独占してずるい」
「法律に触れているわけじゃないのにギャーギャー言われる意味が分からない」
「他人が楽をしている様子を見て嫉妬するくらいなら、絵師様もAI絵始めれば?」
と徹底抗戦。さらに有名なイラストレーターがAI絵師としての活動を始めた事例まで出てきて界隈は阿鼻叫喚。
「絵は元からみんなのためにあるよ。目の前にペンと紙があったら誰だって絵描けるだろ。AI絵師の言う絵が描けないって、もしかして何かイラストを描き始めたら秘密警察が飛んできて拘束してくるとかそういう意味か?」
「神絵師だって底辺絵師だった時代があるんだけどなぁ」
「AI絵師の理屈を要約すると『ぼくはどりょくせずにきれいなえをかけるようになりたいです』ってことだろ」
何か新しいものが出てくるとき、法律はいつだって追いかける側だ。生成AIがもっと遠くに行く前に、何かしらの規制をする必要がある。しかし、それは未だになされていない。
「俺も『AIイラストですか?』って言われることが増えたから、いちいちタイムラプスを記録しないとならなくて。面倒ったらありゃしない」
友人はため息をついた。彼はいわゆる神絵師……というわけではなかったが、SNSに絵を投稿すると結構な反応がやってくるくらいの絵描きだった。大人気イラストレーターというわけでもない(本人がそう言った)自分のところにもAI疑惑がくるなんて思っていなかった。友人はそう言って、入れ忘れていたポーションミルクの封を切った。白い液体がじわじわとアイスコーヒーを侵食していく様に、僕は昨今のイラスト界隈の騒動を見た。
「ただ、AI絵師の連中の言うこともちょっとわかるんだよ。俺もすげー絵を見ると『自分にこういう絵は描けないなぁ』って思うことがあるんだ。神絵師の腕を食べたい、ってのもそういうとこから来てるだろ。程度の差こそあれ、神絵師になりたい……神絵師のように、思ったことを何でも表現できる絵を描きたいって、思ったことはあるからさぁ」
「分かる。僕も小説で同じようなことがあるから」
「だろ?」
友人はそう言ってアイスコーヒーを飲んだ。ポーションミルクを入れたのに混ぜるのを忘れている。
「でも、それは自分で試行錯誤するっていう前提があるから、AIイラストやってる連中とは根本的に考え方が違うんだよな」
「そうだね。僕も冗談で『頭に浮かんだ話を自動的に出力できる機械がほしい』って言うことはあるけれど、その時に出力したいのは僕の文章であって、他人の文章ではないからね」
友人は頷きながらアイスコーヒーを混ぜた。普段のものよりやや白かった。
「そうそう。AI連中にはそういうのが分かっていない。絵は頑張ればうまくなるってことも、神絵師って呼ばれる人たちにも底辺だった時期があることも、絵が描けないからといって人の価値が下がるってこともない。そしてその人の特技に甲乙をつけること自体も野暮だ」
友人は再びアイスコーヒーを飲む。僕はちみちみとアイスティーを飲む。
「絵が描けることそのものはすごくても、だからといって絵が描けない人が全体の評価として劣るわけじゃないもんね」
「そうだ。それが言いたかった」
僕は知り合いの顔をあれこれ思い出した。科学方面の知識が凄まじい人がいる。中世ヨーロッパの歴史に詳しい友人もいる。絵が描ける人、足が速い人。英語がペラペラの人もいる。インターネットの世界に対象を広げれば、もっといろいろな人がいる。フィギュアを作る人、音楽を作る人。なぜか、絵だけが、良くも悪くも「特別」なものとして見られている気がする。この持論が正しいか間違っているかは分からないが、少なくとも僕の感性はそう捉えた。
「俺は思うんだ。AI絵師よ、お前は神絵師ではない。所詮お前は他人の努力の結晶を労せずパクったバカだ」
友人は頬を赤くしながら語る。「バカ」に全力のアクセントを乗せたので、近くの席に座ってパスタを食べていた女性二人が僕たちの方を見た。
僕は彼のこういうところがあまり好きになれなかった。彼はたまに絵描きの自分に酔うところがある。これは酒癖のようなものだ。彼は絵描きのあり方だとか絵の魂だとかについて語ると、まるでワインか何かを飲んだ時のようにふらふらとする。そうして強烈な言葉を使う。気をよくした彼が自身の感情を語るとき、これが最もふさわしい表現になるのだろう。僕はそれが嫌だった。明らかに人を傷つける類の罵倒は僕に向けられた矛先ではないはずだ。しかしその切っ先は間違いなく僕の心臓に向いていて、意味もなく僕を傷つけるのだった。
「どうして労せずに何かを成そうとするのか。いいか、絵でもなんでも何かを頑張るのは才能の一種だ。AI絵師たちには絵を頑張る才能がないんだ。だからといって嘆くことはない。絵を頑張る才能がないからといって絵が描けないわけでもなし、そもそも世の中には絵以外のなにかしらだってあるだろ。そっちを頑張ればすんなり生きられるかもしれないじゃないか」
僕はドリンクバーに退避しようかと思った。慌てて席を飛び出すことだってできた。だけどそうしなかった。僕はもう友人の言葉に疲れ切っていたのかもしれない。ファミレスの妙に硬いソファー席の上で、僕はぐったりと体を預けていた。このまま沈んでしまいたいとさえ思っていた。
「それでもあきらめないっていうのであれば頑張ればいいのに、AI絵師は本当に……」
「そうだよね。本当に。僕も今のAI技術が怖いよ。もしも小説でも同じことになったらって考えるとぞっとするよ」
僕はやや急いた口調でそう応えた。もう話題を変えたかった。だが、友人は豪快に笑った後、とんでもないことを言ってのけた。
「それについては大丈夫だって。小説なんて誰にでも書けるんだから、AI絵と同じようなことにはならないよ」
友人は「ははは」と笑った。
僕の視界が闇に落ちる。少し記憶を失った。
けだるさが僕の体からすうと引いていく。すれ違いざまに上ってきた熱は、友人の頬にそうしたのと同じようなことをした。頭頂部に取り付けられた糸がぐんぐん上っていく。僕の体は宙ぶらりんになった。つま先がかろうじて地面にくっついている。僕は空のグラスを手にもって、ぼんやりと友人を見つめる。
僕の憤怒を、友人はそうだと分からなかった。グラスを持って立ち上がった僕を見て、友人は「ドリンクバーか?」と言った。
「うん。行ってくるよ」
僕は、ものすごくひどい言葉を飲み込んで、友人の問いに答えた。
僕はずんずんと通路を進んだ。ドリンクバーで再びアイスティーを選んだ。茶葉が溶けたのではないかと錯覚する液体が順調に僕のコップを満たしていく。それは先ほどの怒りよりもずっと遅い速度であったが、僕が冷静さを取り戻すには足りなかった。
僕はコップの淵ギリギリにまで紅茶を注いでしまった。少し揺らせば中身がこぼれてしまう。僕はグラスをそっと自分の方に引き寄せて、慎重に唇をつけた。中身をすする。紅茶の香りも苦みも分からなかった。
なんとか運べる程度に量を減らせたので、僕は慎重に席に戻った。友人はへらへらしながら僕が注文したポテトをつまみ食いしていた。僕はこの程度では怒らない。こんなことでいちいち怒っていたら彼と付き合っていくことなどできないからだ。
「話を戻すけどさ。小説と違って絵ってのはスタート地点から相当な技術が必要だ。そういう意味では誰にでも描けないっていえる」
僕はアイスティーをテーブルに置いた。中身はこぼれなかった。よくやった、と言いたくなる。友人は僕の様子に気づくことなく、ペラペラと口を動かしている。
「だけど実際はそんなことないんだ。技術がなくてもなんとかなる。ちやほやはされないだろうけどな。そうだろ?」
……そうだね、とは言えなかった。僕が固まっていると、友人は僕の返事を待たずに言葉をつづけた。
「小説は誰にだって書けるんだから、AIを気にしなくて済むってのはいいよなぁ」
僕の中で、何かの液体が満ちていく。
誰かの唇が必要だ。
あふれ出る前に、僕が奴を壊す前に、これを啜ってくれ。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
